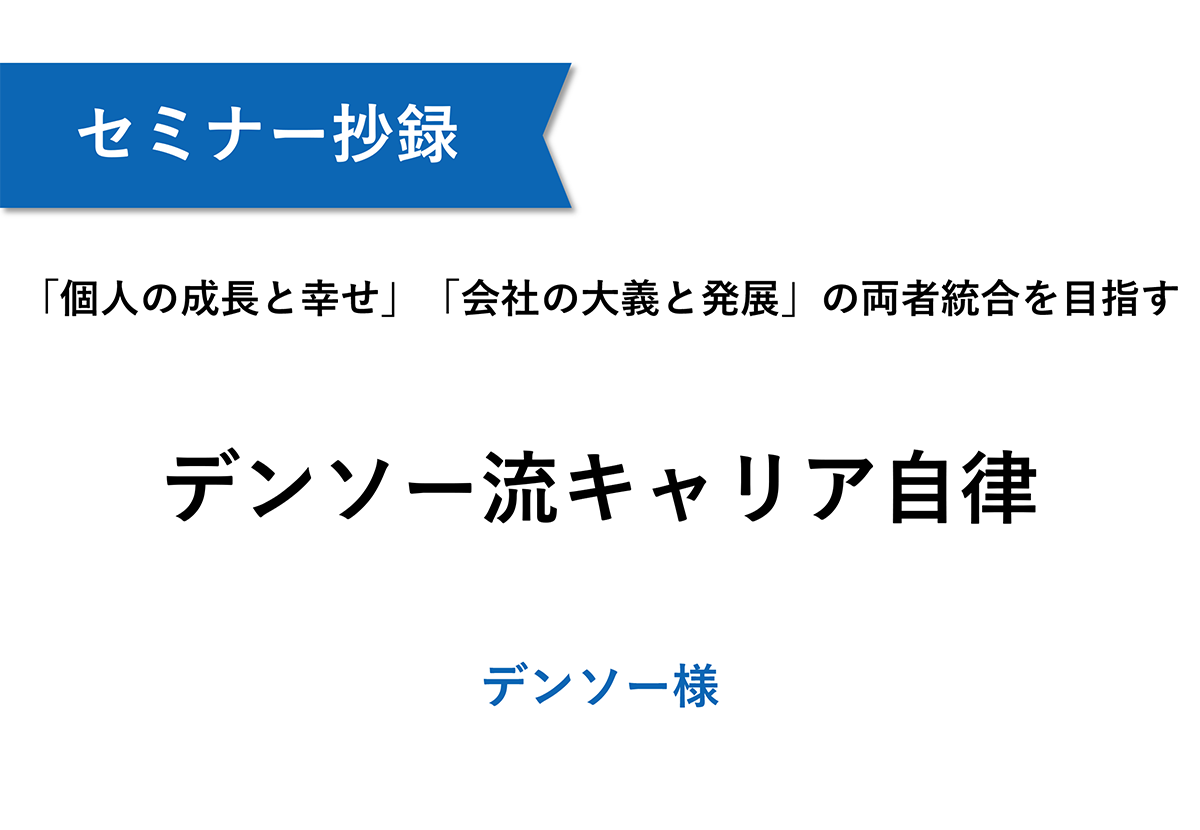- 公開日:2022/05/30
- 更新日:2026/02/19

これからの時代、主体的に自らのキャリアを選んでいく「キャリア自律」が求められます。しかし、個人主導のキャリア形成を行う企業は、まだ少ないのが現状です。2022年3月10日の組織行動研究所セミナーでは、「キャリア自律施策の展開〜なぜキャリア自律が進まないのか〜」と題し、働き手の自律性を重視したキャリア形成へ転換していくために、人事は何をすべきかについてお伝えしました。今回はそのセミナーの様子をレポートします。
- 目次
- 「自信・好奇心・関心・統制」がキャリア自律を考える際のキーワードになる
- 優秀な社員をリテンションしたいならキャリア自律と組織コミットメントの両方を高めるとよい
- 「キャリア自律を進めるサイクル」を回せばキャリア自律行動が増える
- 質疑応答
- おわりに
「自信・好奇心・関心・統制」がキャリア自律を考える際のキーワードになる
講師プロフィール
古野庸一 リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 所長

1987年株式会社リクルートに入社。キャリア開発に関する事業開発、NPOキャリアカウンセリング協会設立に参画する一方で、ワークス研究所にてリーダーシップ開発、キャリア開発研究に従事。2009年より現職。著書に『「働く」ことについての本当に大切なこと』(白桃書房)、『「いい会社」とは何か』(講談社現代新書)、『リーダーになる極意』(PHP研究所)、『日本型リーダーの研究』(日経ビジネス人文庫)、訳書に『ハイ・フライヤー 次世代リーダーの育成法』(プレジデント社)など。
最近は、社会やビジネス環境の変化が激しくなり、1つの仕事の寿命が短くなってきています。また、事業自体の寿命も短くなり、1つの会社で勤め上げることも難しくなってきました。その一方で、長寿化にともなって、個人はこれまで以上に長期間働く必要が出てきています。こうした背景のなか、企業は、社員一人ひとりが自分のキャリアを主体的にコントロールして、自分に合った仕事を自ら選んでいく「キャリア自律」を求めるようになってきました。例えば、日本経済団体連合会では、新たな社会「Society 5.0」を実現する人材育成の3つの取り組みの1つを「自律的なキャリア形成の支援」と考えています(図表1)。また、厚生労働省は、キャリア自律促進の具体的な企業施策として「セルフ・キャリアドック」を提唱しています。
<図表1>Society 5.0を実現する人材の育成――取り組みの3つの柱
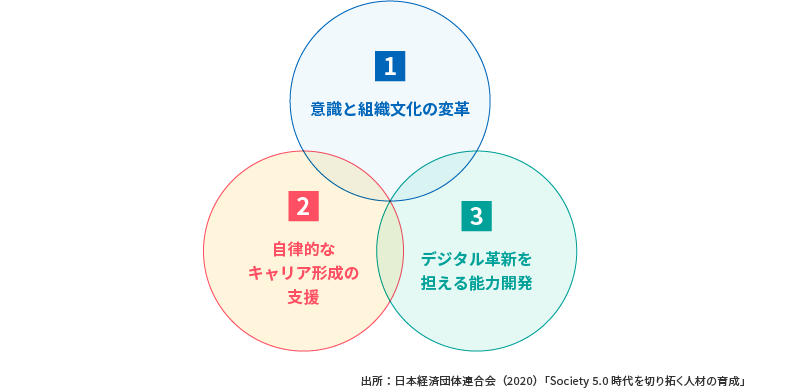
一方で、個人はどうしたらよいのでしょうか。マーク・サビカス氏は、「4つのCによるキャリア・アダプタビリティ」を提唱しています(図表2)。4つのCとは、「自信(Confidence)」 「好奇心(Curiosity)」「関心(Concern)」「統制(Control)」です。成功体験を積み自信を持っていること、好奇心を持って自分の可能性を周囲に探索すること、未来に関して関心があること、そして自分のキャリアは自分でコントロールしていくこと。サビカス氏は、個人がキャリア転機の多いビジネス環境を生き抜くには、この4つが必要だ、というのです。4Cは、個人がキャリア自律を考える際のキーワードとなります。
<図表2>マーク・サビカス氏の「キャリア・アダプタビリティ」
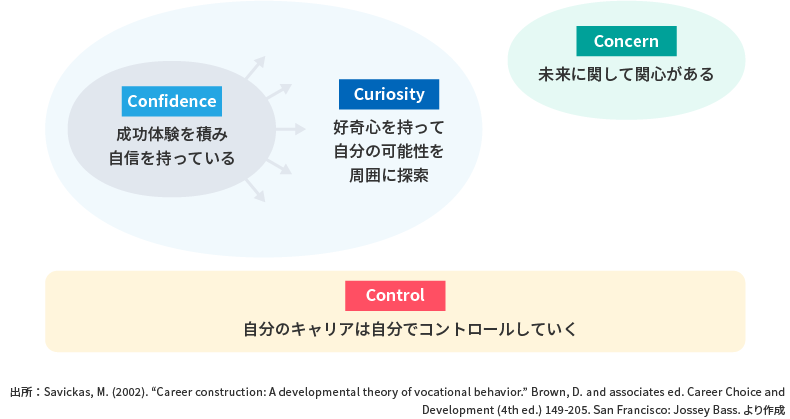
ここで、「関心(Concern)」について少し触れます。未来への関心が強く、将来展望がある程度明確になっている人の方が、キャリア自律をしやすいことは確かです。玄田有史氏は、「過去から現在にかけて、自分なりの物語があるとき、その物語を手がかりに、未来をどう生きるのかというヒントを得ることができます」(『希望のつくり方』岩波新書)と述べていますが、そのとおりです。自分なりの物語を得て、将来展望を明確にしたいと願う人が大多数でしょう。
しかし、自分なりの物語を描くのは決して簡単ではありません。うまく考えられない人、考えることをストレスに感じている人もたくさんいるのが実情です。国の発展、会社への貢献、経済的成功、出世といった分かりやすい物語が崩壊しつつあることが、事態をさらに難しくしています。また、多くの人が夢を持ちたい一方で、夢を持つことを強制されるのは嫌がります。例えば、就職活動で、将来の夢を何度も聞かれてうまく答えられず、悩んでいる学生が多くいます。高部大問氏は、そのことを「ドリーム・ハラスメント」と呼んでいます(『ドリーム・ハラスメント 「夢」で若者を追い詰める大人たち』イースト新書)。企業では、同様に「Willハラスメント」という言葉を耳にするようになってきました。Will(やりたいことや将来展望)を答えられない人が、何度もWillを問われるのは苦痛でしかないのです。
優秀な社員をリテンションしたいならキャリア自律と組織コミットメントの両方を高めるとよい
ここからは、「キャリア自律の実態」に関する私たちの調査結果をご紹介します。以下、図表3~11は、弊社が2021年に行った「若手・中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に関する意識調査」です。25~44歳の一般社員613名(男女均等・入社半年以上・正社員)にインターネット上で調査を行いました。
図表3によれば、キャリア自律(自律的・主体的なキャリア形成)が意味することは、10の選択肢のすべてにまんべんなく散らばっています。つまり、人によって、キャリア自律という言葉から喚起されるイメージが違うのです。多くの組織では、経営・人事・社員のあいだでキャリア自律のイメージが異なる可能性が高いでしょう。キャリア自律について話し合う際は、何を指しているかを明確にすると、コミュニケーションが進むはずです。
<図表3>自律的・主体的なキャリア形成が意味すること
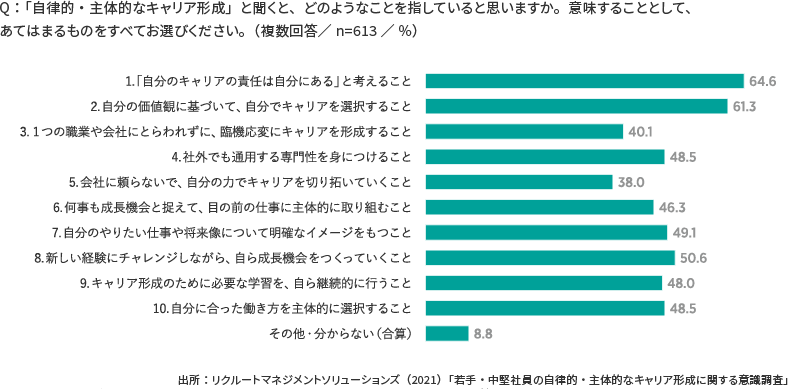
また、図表4のとおり、アンケート回答者の約半数が、やりたい仕事や将来像のイメージを持っていました。イメージを持っている人が1~2割しかいなかった時代もありますから、それに比べれば明らかに増えています。とはいえ、まだ半数がやりたい仕事や将来像をイメージできていないことも確かです。
<図表4>やりたい仕事や将来像のイメージ
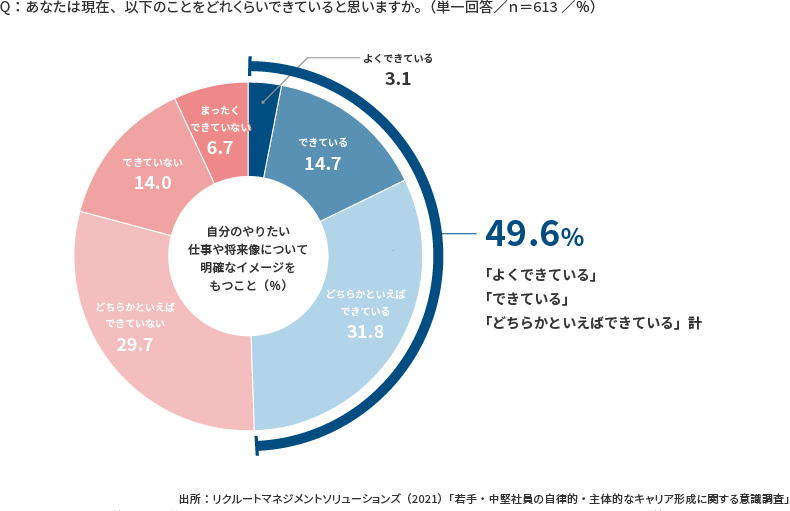
一方、65%ほどが、キャリア自律にストレスや息苦しさを感じています(図表5)。また、75%以上がキャリア自律は難しいものだと考えています(図表6)。キャリア形成についての悩みは、「このままの自分でいいのかと漠然とした不安がある」「自分のやりたいことが分からない」「自分の実力が分からない」が多くなっています(図表7)。キャリア自律にストレスや難しさ、不安などを感じている人が少なくないことがよく分かります。
<図表5>キャリア自律のストレスや息苦しさ
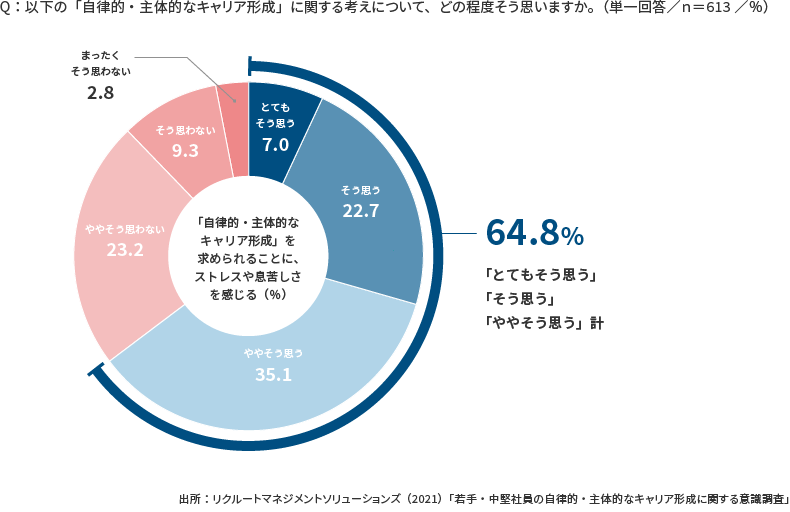
<図表6>自律的・主体的なキャリア形成の難しさ
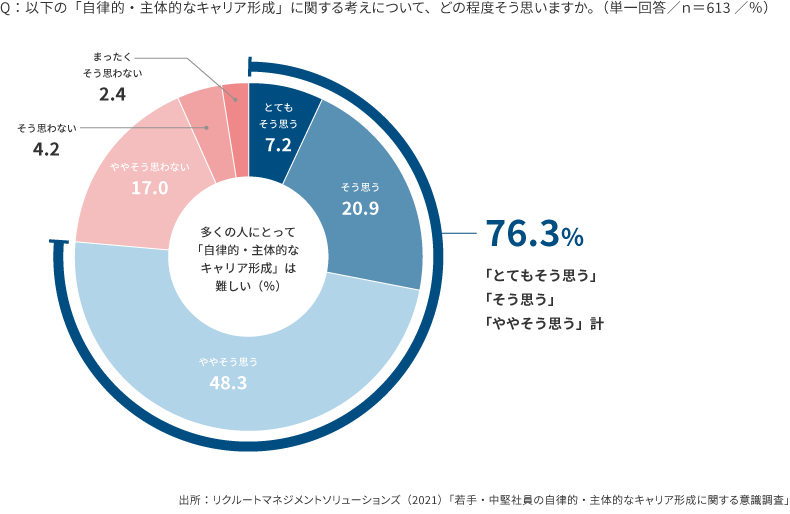
<図表7>キャリア形成について困っていること
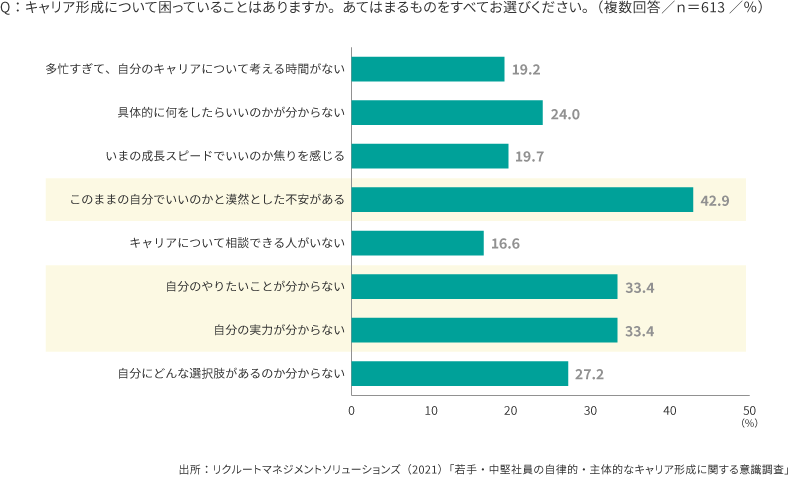
キャリア自律行動ができているほど、組織コミットメント、パフォーマンス発揮、職場適応のすべてが高いことも判明しました(図表8)。
キャリア自律行動が高まると、普通は転職意向が高まります(図表9)。これは多くの人事の方が心配していることですが、実際にそうなります。しかし、キャリア自律行動と組織コミットメントの両方が高い場合は、むしろ転職意向が弱まることも分かりました(図表9)。会社やチームのことが好きなら、キャリア自律していても必ずしも離職する必要はないのです。ですから、「優秀な社員をリテンションしたいなら、キャリア自律と組織コミットメントの両方を高めるとよい」のです。人事の皆さんが、このようなキャリア自律行動の特性を知れば、社員のキャリア自律促進に本気で取り組む企業が増えるのではないか、と考えています。
<図表8>キャリア自律行動と組織コミットメント・パフォーマンス発揮・職場適応との関係
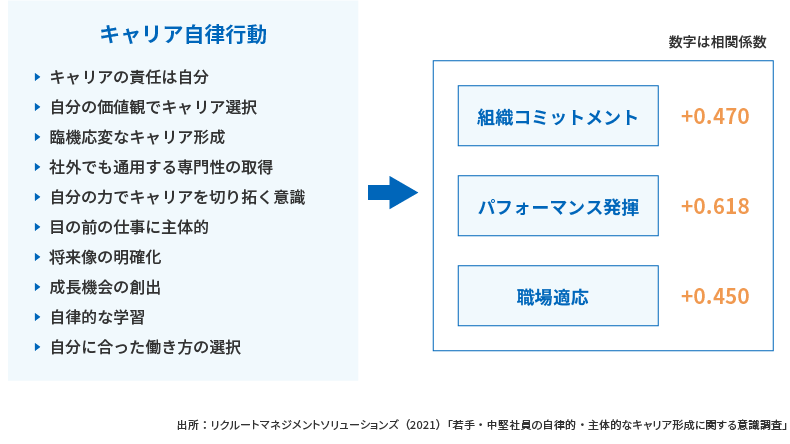
<図表9>キャリア自律行動が組織コミットメント目的愛着・転職意向に及ぼす影響
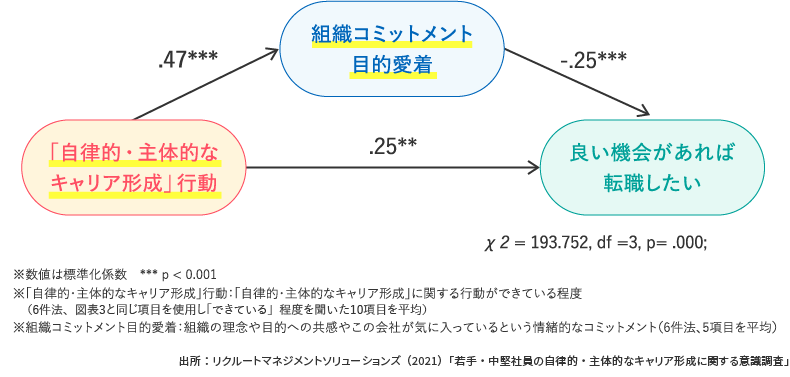
図表10から分かるのは、キャリア形成の役に立っているのは学習支援や柔軟な勤務体系だということです。また図表11で重要なのは、「資格取得や自己研鑽のための金銭的援助」「仕事に直接関係のない学びへの理解と時間」「副業の許可」「テレワークの制度化、フレキシブルな勤務時間の導入」を多くの人が求めていることです。ポイントは学習支援・副業・働き方の3つです。ただし、配置・異動や人事評価に関する要望も少なくありません。
<図表10>キャリア形成を支援する会社の仕組み・制度
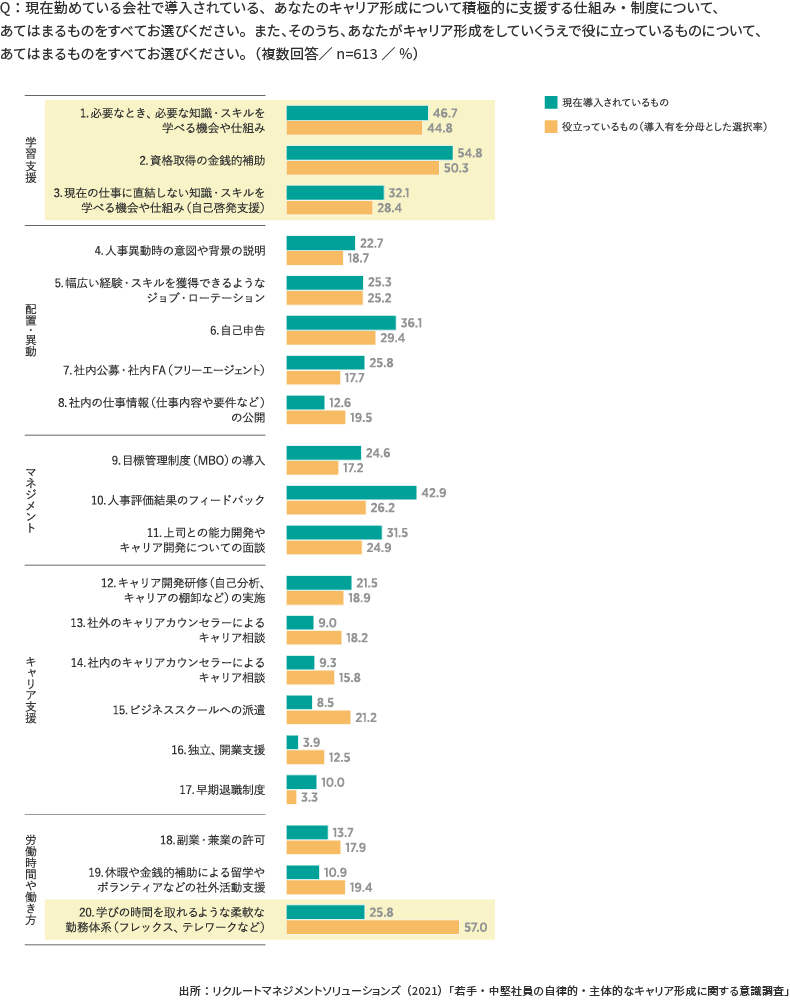
<図表11>会社・職場に要望する支援
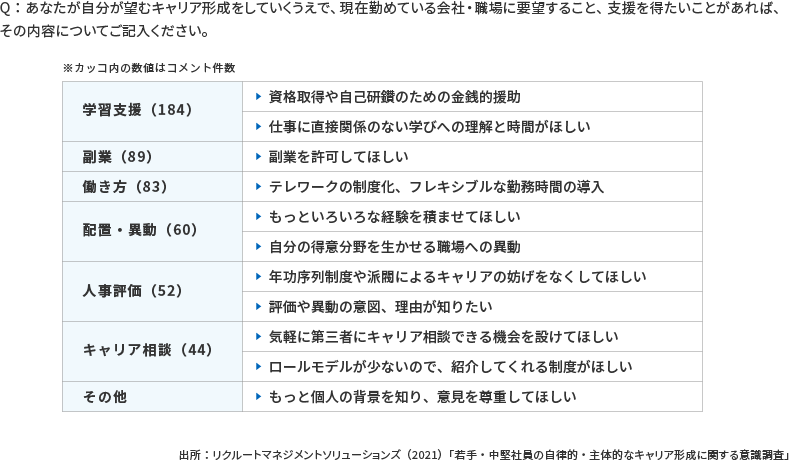
「キャリア自律を進めるサイクル」を回せばキャリア自律行動が増える
では、会社はどうしたら社員のキャリア自律行動を促せるのでしょうか。図表12は、前回セミナー(自律とエンゲージメントを促進するために 変わるマネジャーの役割)でもご紹介したものです。キャリア自律に必要なのは、図表右側の7つの要因です。特に、心理的要因の「職業的自己イメージの明確さ〈=自己理解〉」と「主体的キャリア形成意欲〈=将来展望〉」の2つを育むことが肝要です。自己理解と将来展望を促進させるのが、「仕事経験からの学び」とその背後にある「転機経験」です。
<図表12>キャリア自律の要素とキャリア自律促進の資源
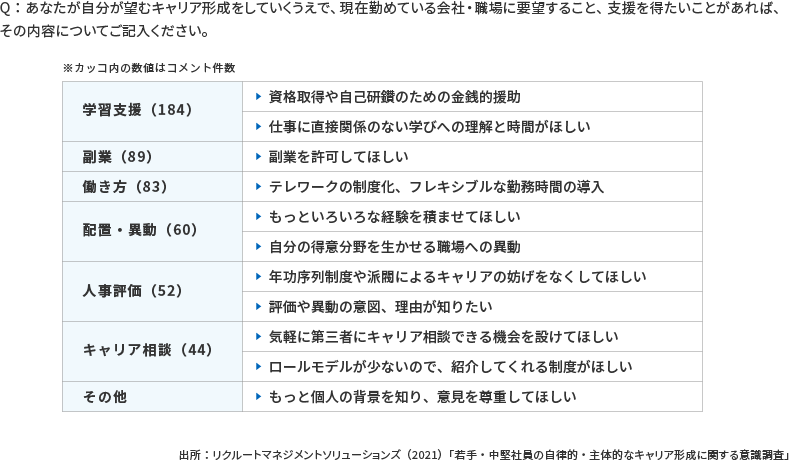
以上を踏まえて、私たちが考えた「キャリア自律を進めるサイクル」を紹介します(図表13)。このサイクルは、「自己理解を進める→気になる領域を調べる/他者に会う→将来を描いてみる→とりあえずやってみる……」を巡ります。「内省(自己理解と将来展望)」と「試行錯誤」を交互に繰り返すのです。試行錯誤では、これまでやらなかったことにトライすることが大事です。例えば、「社内でトライアルできるところを探す」「ロールモデルに会いにいく」「気になるセミナーに顔を出す」「資格を取る」「短期間、田舎に住んでみる」「ボランティアを(で)やってみる」「副業としてやってみる」といったことにチャレンジするのです。個人がこのサイクルを回していけば、そのうちに自己理解が進み、将来の方向性が見えてきて、キャリア自律行動が増えるはずです。
<図表13>キャリア自律を進めるサイクル
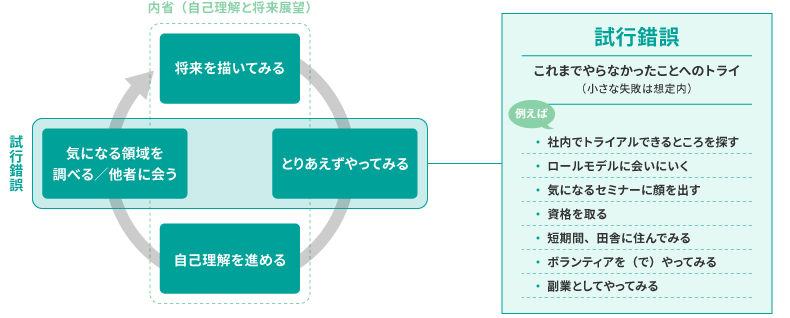
このサイクルは、図表2で紹介したマーク・サビカス氏の「4つのCによるキャリア・アダプタビリティ」とも呼応しています(図表14)。試行錯誤のときには好奇心があった方がよく、将来展望を描くときには未来への関心が欠かせません。また、このサイクル全体では自分のキャリアを自分でコントロールする統制の意志が必要です。
<図表14>将来を描く方法とキャリア・アダプタビリティ
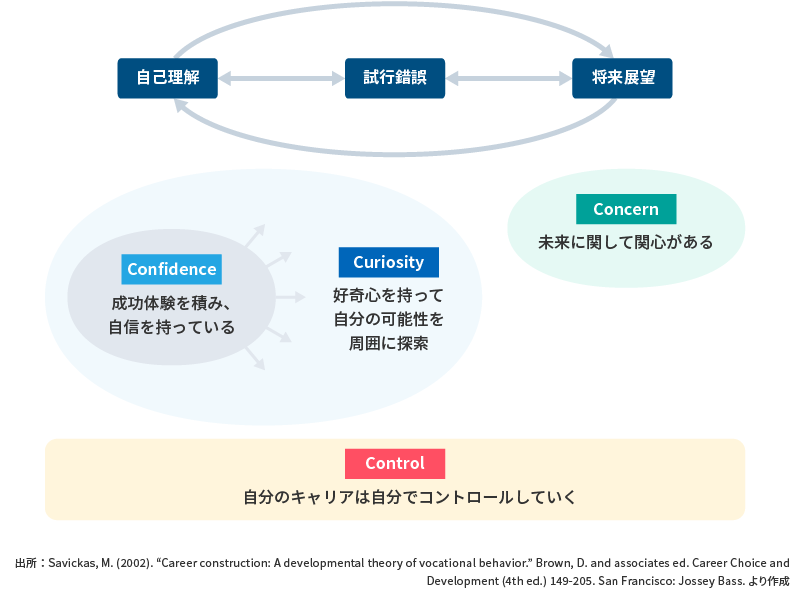
社員がキャリア自律を進めるサイクルを回すための具体的な支援策としては、次のようなことが考えられます。
〈日常〉
●過去の仕事経験から、個人の「持ち味」「価値観」「働き方」「将来」をふまえた対話を上司・部下間で行う【自己理解】
●そのうえで、パフォーマンスがあがる/意味がある/可能性を拓くようなジョブ・アサインメントやジョブ・クラフティングを行う【試行錯誤】
〈人事施策〉
● 仕事経験を内省する機会(研修、カウンセリングなど)を設ける【自己理解】【将来展望】
● 通常の仕事経験以外の経験を積む仕組みを整える【試行錯誤】
情報提供:他の仕事(プロジェクト)の情報、モデルになる人の情報
越境学習機会:副業、自己申告制度、自律的学習機会、各種休業制度、留学制度、働き方のI-deals、出戻り支援
一例として、「自分の仕事を引いて見直してみる」方法を具体的にご紹介します。次に示すのは中学生が考えた仕事のキャッチコピーです(辰巳哲子『たった17字でわかる あなたが「働く意味」』NIKKEI STYLEより)。
人生の先輩に恩返しをする仕事(介護施設職員)
日本人のために伝統をつないでいく仕事(和菓子職人)
お客様のために心の回復をはかる仕事(ケーキ職人)
どうでしょうか。たったの17字で、仕事の見え方が変わるのではないでしょうか。ぜひご自身の仕事のキャッチコピーも考えてみてください。ちなみに、私は自分の仕事を「働く人の幸福を高める仕事」と置いてみました。こうやって少し見方を変えてみるだけでも、自己理解や将来展望に影響があるはずです。
アイデンティティの概念を提唱した心理学者エリク・H・エリクソンは、自我の発達の最終段階において、うまく自己を統合できることを推奨しました。
例えば、60歳になったとき、65歳になったとき、70歳になったとき、あるいは死ぬときに、自分の人生をストーリーで語る人は、自分の人生に満足できている。しんどかったけれど楽しかった、充実していた、精一杯やったよな、と振り返ることができる。うまく統合できなければ、老いに絶望し、不安を抱えると思われます。自分の人生に満足する人を増やすため、社員の皆さんのキャリア自律を支援していただけたら幸いです。
質疑応答
Q:キャリア自律を進めるサイクルは、自己理解が起点になると考えてよいのでしょうか?
古野:そのとおりです。ただし、自己理解は1人でするよりも他者と進めることを推奨します。周囲の誰かに自分のイメージを話してもらったり、長所や短所を聞いたりすることで、自己理解は進みます。あるいは、他の誰かが大切にしていることを聞くことも、自分を相対化してみることに役立ちます。「自分は周りからはこう見えているのか」とか「私もこの人と同じように家族を大事にしている」とか「この人が大事にしていることは、自分は大事にしていない」といったことは、対話のなかで気づくことが多いのです。自己理解のために、社内外のさまざまな人と話してみることをお勧めします。
Q:年代によって会社からの支援の仕方は変えた方がよいですか?
古野:変えた方がよいです。年代によって共通する課題がありますから、その課題に働きかける施策が有効です。例えば、20代なら一人前になるための施策、40代はミッドライフクライシスに対する施策が、効果があるでしょう。50代・60代には、強みを棚卸してセカンドキャリアを考える施策などがお薦めです。
Q:Willハラスメントは、どのように気をつけたらよいでしょうか?
古野:肝心なのは、将来を考えることを強制しないことです。将来を描くことそのものは難しく、それなりの技術が必要です。なので、将来をうまく描けずに悩んでいる人には、キャリアカウンセラーやキャリアコンサルタントへの相談を薦めてみてはいかがでしょうか?
【text:米川 青馬】
おわりに
私たちは、日常の仕事に忙殺され、自分の仕事の意義を忘れがちです。俯瞰してみると、とても意味のあることをやっていると気がつくことも多いと思われます。ここでいう意味は、社会にとって意味があるという話もあれば、自分にとって意味があるということもあります。そのような意味づけがうまくできないときに、立ち止まり、自分ならではの物語をつくることがキャリアを考えるということにつながります。
つまり、自分らしさと今の仕事の関係を整理して、未来に希望を持たせ、人生に意味を持たせ、自分の物語の形成を促していくのがキャリア自律支援の根幹になると考えています。
【組織行動研究所 所長 古野庸一】
この記事で引用した調査
『若手・中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に関する意識調査』
バックナンバー
自律とエンゲージメントを促進するために 変わるマネジャーの役割(2021年12月開催)
コロナ禍で注目される自律的な働き方とエンゲージメント(2021年9月開催)
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)