連載・コラム
連続小説 真のリーダーへの道 第4回
「仕事を請けたのに、人がいないって!?」
- 公開日:2017/10/06
- 更新日:2024/03/27

リーダーの成長には、「仕事経験から学ぶこと」が最も重要であるといわれています。
企業は自社のリーダー育成のために、リーダーの成長に必要な経験を明らかにし、そしてその経験を網羅的に積めるよう、ポジションや仕事・役割を、意図的にローテーションさせていくことが有効です。私たちはこれを「成長経験デザイン」と呼んでいます。
リーダーに必要な経験は各社さまざまで、特定するのは至難の業です。そこで弊社では、先行研究やインタビュー、これまでの支援事例などから、リーダーの成長を促す8つの経験を抽出しました(下図参照)。
この連載小説では、架空のリーダー佐々木の成長ストーリーをたどりながら、それぞれが具体的にどのような経験で、それによって何を学び、どのようにリーダーシップを形成していくのか、1つずつ紹介していきます。
第4回は、「権限が及ばない人を動かす経験」です。
※「成長経験デザイン」について詳しく知りたい方は、>>>特設ページ<<<をご覧ください
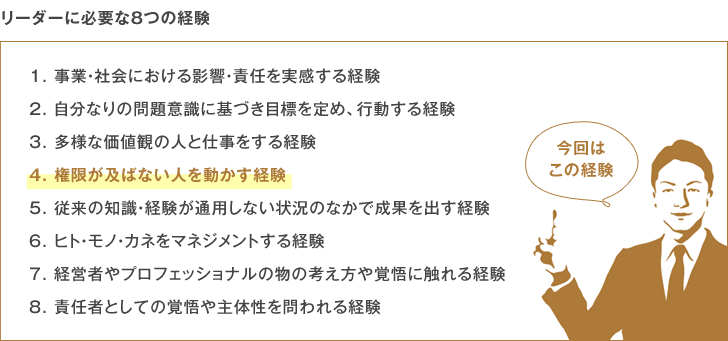
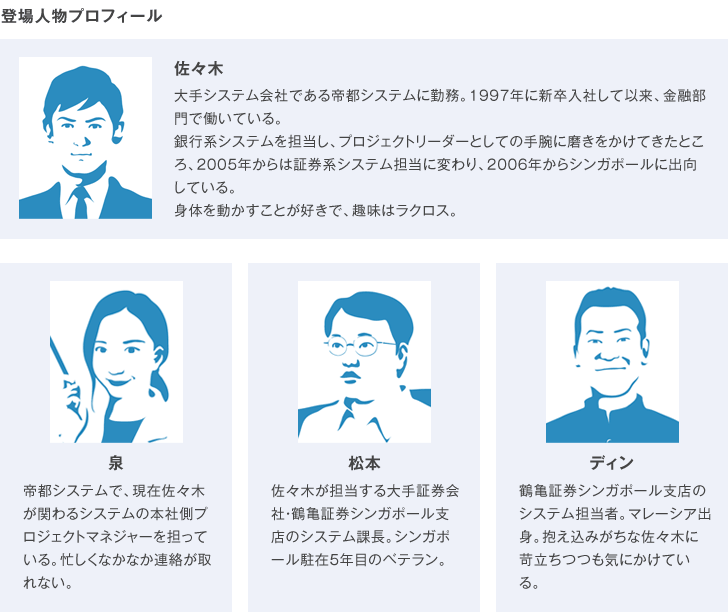
「案件を取れ、手は貸せない」の罠
「佐々木くん、正直しつこい。今、ちょうど開発の山場なのはあなたもよく分かっているでしょう? できるだけ自分で何とかしてもらえないかな」
ここでもう1回お願いしたら、多分泉はしばらく口を利いてくれなくなるだろう。佐々木はおとなしく引き下がることにした。
2007年2月、外はスコールの真っ最中だった。シンガポールの2月は雨季なのだ。
佐々木は、2006年4月に、日系大手証券会社・鶴亀証券の海外支店のシステム・サポートをするためにシンガポールに赴任した(第3回参照)。1年近く経って、シンガポールでの仕事や暮らしにもだいぶ慣れ、生活に支障のないレベルでシングリッシュも使えるようになった頃、新たな悩みが出てきていた。それは、「他社が作ったシステムのサポート」である。
帝都システムが構築した海外支店システムなどが抱えていた問題を解決していくうちに、佐々木は、鶴亀証券のシステム課長・松本や、ディンをはじめとする現地のシステム担当者たちから、ITの専門家としてかなりの信頼を得ることができた。
それはもちろん良いことなのだが、信頼の高さと比例して、新たな仕事が舞い込むようになったのだ。それは、鶴亀証券が使っている他社製システムのサポートだった。競合なら、契約外だと言って断るかもしれない。だが、そういうことをしないのが帝都システムの強みだと佐々木は考えた。帝都システムの日本本社で、鶴亀証券のシステムを一手に担当するプロジェクトマネジャー・泉も同じ意見で、「クライアントのために、ぜひ他社製品のサポートも頑張ってほしい」と励ましてくれた。
ただ、問題は、本社のエンジニアの工数が逼迫していることだった。本社では、鶴亀証券のグローバル基幹システムの入れ替えをちょうど行っている最中だった。他社製品のシステム改修となると柔軟な対応が必要になるため、中国・大連のオフショア開発に任せるのは難しい。とはいえ、佐々木一人の手には余った。何としても、日本本社の優れたシステムエンジニアの力を借りる必要がある。しかし、日本側は猫の手も借りたいくらいの忙しさで、救援を頼めそうなメンバーは皆無だった。そこで佐々木は、無理を承知で、プロジェクトマネジャーの泉に真正面から当たってみたのだ。しかし、にべもなく断られてしまった。
もはやどうすればよいのか。そもそも「ぜひ協力するように」「でも日本本社の手は貸せない」……この背反する言い分と、解をくれない泉の対応は何なのか。ただでさえ、日本で仕事をするよりは時間もかかるし気も使って疲れているのに。たまの休日も睡眠と生活に精一杯で、まったくリフレッシュできていないし……。
佐々木は自分の頭のなかを行き交うさまざまな感情を眺めるように、外のスコールを呆然と見つめていた。
率先し、仕事の意義を伝えて人を動かす
とはいえ、止めるわけにはいかない。佐々木は仕方なく、要件定義や詳細設計だけでなく、プログラミング設計・プログラミングから、テスト・導入に至るまで、システム改修の全工程を自分の手で行ってみることにした。依頼されているもののうち、一番小規模のシステム改修だったから何とかなったが、さすがに残業なしで終わらせることはできず、3週間は休日返上で取り組んだ。
しかし「やっぱり、自分1人で他社製システムをサポートするのは無理がある」と、佐々木はあらためて認識した。1人では小規模のサポートしか対応できないし、品質もベストとはいえない。1人というだけでさまざまなリスクもあるし、最悪、納期に間に合わないことだってあり得るからだ。
そんな頃、ディンがコーヒーを差し入れ、こんなことを言ってくれた。「佐々木さん、相変わらず忙しいですね。でもこれまでは時差のあるパートナーとメールでやり取りするしかなかったのが、佐々木さんがサポートしてくれるようになって、気軽に質問や相談ができるようになったし、スピーディに問題を解決してもらえて、とても助かっています。皆感謝してますよ」
また同じ頃、泉からフォローのメールが届いた。日本側も本当にギリギリなのだという。これまでいくつもの大規模プロジェクトを動かしてきた泉が言っているということ、そしてメールの送信時刻が日本時間のAM2:00であることが、その深刻さを物語っていた。
佐々木は、システム改修の1つくらいは自分でやらないと、と思い直した。日本にいる泉や仲間たちも、必死に働いている。自分だけが白旗を揚げるわけにはいかない。何より、せっかくこれまで積み上げた鶴亀証券からの信頼に応えるためにも、自分だけで何とかしなければと考えたのだ。
すると、グローバル基幹システムの開発が山場を越えつつあったこともあり、1週間のうち半日だけなら応援できるよ、週1日なら何か手伝おうか、と言ってくれる仲間が1人、2人と出てきた。

更に、佐々木はせっかく協力してくれているメンバーに、今ここでシンガポール支店のシステム改修に力を入れることが、回り回って本社のビジネスに良い影響があることを説明した。なぜなら、他社製システムの改修をすることで、鶴亀証券の新たな課題、新たに必要なシステムが見えてくるからだ。つまり、次の提案の種が見つかるのだ。そうしたことを話すことで、メンバーのモチベーションは少しずつ上がり、快く手を貸してくれるようになっていった。
佐々木は、更にこの話をあらためて泉にも伝えた。今回は、短期的には無理をしても投資をするメリットを具体的に伝えることにした。その上で、佐々木は強く念を押した。「この案件は、一見不利に見えるが、今後の鶴亀証券との関係性において重要な意味を持ってくるはずなんだ」。泉も、シンガポールでの佐々木の奮闘を耳にしていた。「分かったわ」と、今度は1人当たり週10時間までという条件付きで、プロジェクトメンバーに応援を要請すると約束した。こうして、このシステム改修は、厳しい条件を乗り越えて見事完了した。
このシステム改修がきっかけとなって、新たなシステムの開発も決まった。しかも、この案件で培った信頼関係により、帝都システムと鶴亀証券はその後も密な関係が続くことになったのである。
鶴亀証券シンガポール支店のシステム上の問題を一通り解決した上で、佐々木は2008年の末に任務を終了し、帰国することになった。シンガポール訛りの英語、オフショア開発のノウハウ、直接権限が及ばないメンバーへの協力要請のコミュニケーション、そしてシンガポールのたくさんの友人を得て、佐々木は再び日本に降り立った。最初はどうなることかと思ったし、途中何度も心が折れそうになったけれど、終わってみれば本当に実のある海外勤務だったと、佐々木は成田空港でコーヒーを飲みながら思い返した。
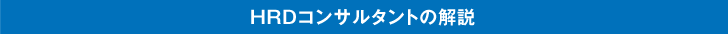

連載第4回の経験は「権限が及ばない人を動かす経験」です。
この経験は部門・機能・会社を超えて、もしくは上位者の協力を取り付けて動いてもらうことに取り組む経験です。“人を動かす”ということは、リーダーにとっては肝となる要素であり、実際に数々の実践を通して身につけられる力です。
本連載の主人公の佐々木は、顧客の要望に応えるべく他社システムのサポート業務を受けましたが、リソースが足りない現実に直面します。
そこで本社の泉に支援を要請しますが、本社のリソースも逼迫しており協力してもらえません。
そのような状況下で結果的に何とか支援を取り付けて無事仕事をやり遂げます。
佐々木はこの経験から何を学べるのでしょうか。実際に佐々木のとった行動から考えてみると人を動かすリーダーになるポイントが2つほど見えてきます。それは「自らの本気が伝わること」と「取り組む意義・方向性を示すこと」です。
■自らの本気が伝わること
合理的かつ納得できる説明だけが、人を動かすわけではありません。リーダー自身が本気で取り組もうとする姿勢によって、人は刺激を受けたり、感化されたりするものです。
佐々木は「白旗を揚げるわけにはいかない」ということを強く思い、システム改修に1人で果敢に取り組んだ結果、徐々に協力を名乗り出る仲間が現れてきます。佐々木の、「何とかしてやろう」という本気の姿勢が、周囲の人を動かしたといえます。
■取り組む意義・方向性を示すこと
本気が伝わっても、何を目指すのか、というビジョン・方向性が必要となります。
佐々木は、「この仕事を通じて鶴亀証券との信頼関係が強固になり、先々のビジネスにつながる」ことを訴えています。それが本社の泉に伝わり、泉は条件付きながらもオフィシャルな支援を承諾しました。佐々木の本気に加えて、なぜ今取り組むことが必要なのかが腹落ちしたことが結果につながっています。
以上2つのポイント以外にもリーダーに求められる要件はさまざま定義されていますが、佐々木がリーダーとして成長していく上で重要な教訓になり得るでしょう。ただし、佐々木自身は必死で何とかしようとした結果の行動です。意図してやっていたわけではありません。佐々木自身が2つのポイントに気づくには経験の内省が必要です。これまでの経験を振り返り教訓を言葉にすることを通じて、自身のリーダーシップスタイルを確立していくことにつながっていくでしょう。
次回は、「従来の知識・経験が通用しない状況のなかで成果を出す経験」です。日本に戻った佐々木に次は何が起こるでしょうか。
【イラスト:ノグチタロウ】
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

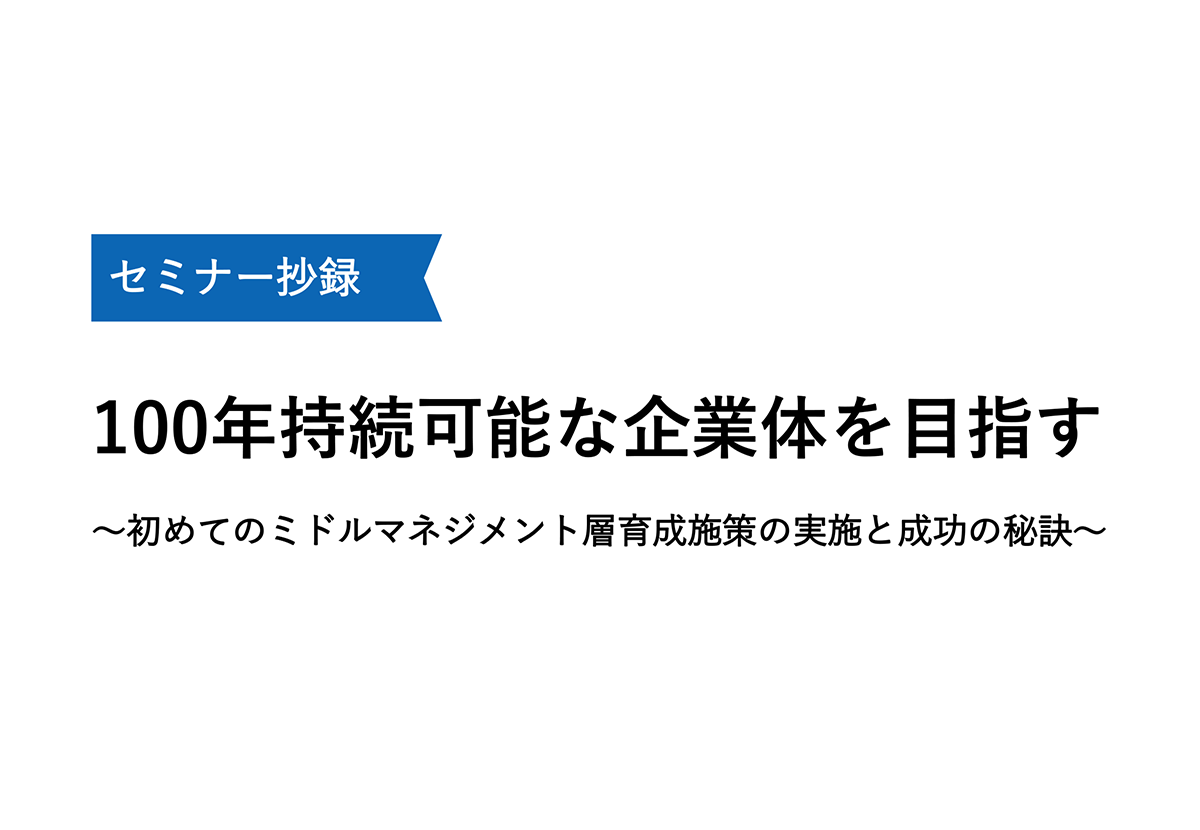









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての