- 公開日:2025/02/25
- 更新日:2025/02/25

eラーニングは低コストで運営でき、全社員の学習環境を把握できる便利な学習ツールである。一方で、それのみに安住すると、人間同士の生身の関係性を遮断し、人が人から学ぶ力を奪ってしまいかねない。今話題のLXP(Learning Experience Platform)はどのように活用されているのだろうか。旭化成株式会社 人事部 人財・組織開発室 室長の三木祐史氏と、同 担当課長 後藤麻美氏のお二人に伺った。
他者と学ぶ、他者から学ぶ、業務に生かす
2022年12月、旭化成は学習プラットフォーム「CLAP(Co-Learning Adventure Place:クラップ)」を始動させた。対象は国内グループ会社の従業員約2万4000人。その目的はCo-Learningとあるように、自律的キャリアと成長を目指し、「みんなで学ぶ」仕組みづくりにある。導入から3カ月後の状況はアクセス済みが81%、1つ以上のコンテンツを学習完了した割合は64.3%にのぼる。
同社は創業100年を超える総合化学メーカーだが、その特徴は事業ポートフォリオを常に変革してきたことだ。石油化学・住宅メーカーとしての印象が強いが、現在はヘルスケア、デジタル、環境事業にも取り組んでいる。CLAP立ち上げの責任者、人財・組織開発室室長の三木祐史氏が話す。「DXなどの大潮流は学ぶべきものとして分かりやすいが、見通しの立ちにくい未来に必要なすべての事柄を会社が設定し社員に学ばせるのは非常に難しい。そこで、学ぶべき内容は社員が自ら考えて決定することを尊重し、会社はその支援に回ることにしたのです。1人で学ぶのは大変だし続かないので、“みんなで学ぶ”をコンセプトにして学びを促したいと思いました」
コンテンツはキャリアの可能性を広げる学びの幅と、専門性を高める学びの深さの2軸から考えられている。前者としては、マネジメント、語学、プログラミングなどに関する外部提供のコンテンツが約1万本揃っている。「これらは対象者全員が見ることができます。職場で『あの人のお薦めなら見てみよう』という流れを起こしたいので、みんなが視聴できる環境にこだわりました」
後者は、比較的手軽に掲載可能な勉強会の録画、資料、確認テストなど約200本。専門力強化のカリキュラムを整備することもある。例えば購買物流部門では、初級から上級まで購買・物流について学べる9コースを内製し、受講を促すデジタルバッジも取り入れた。
CLAP活用促進の責任者、人財・組織開発室の後藤麻美氏が話す。「みんなで学ぶことには、他者と学ぶ、他者から学ぶ、業務に生かす、という3つの意味があります。階層別研修も『何かを学ばせる場』から、『学ぶ動機が湧く、つながりを作る場』へと見直しを進めています」
その代表例が2023年度に立ち上げたラーニングコミュニティ、新卒学部だ。
新入社員が全員参加する「新卒学部」
導入の背景について、三木氏が語る。「働き方改革が進行する半面、新入社員にとっては成長感を得にくい環境になっているともいえます。しかも新入社員といっても一枚岩ではなく、なかには学生時代起業していた、NPOで働いていた、いろいろな学会で発表していた、などさまざまな経験をもつ人がいて、これまでのような一律の教育では、一人ひとりの状況に対応することが難しくなっています。結果、職場に不満はないものの、キャリア不安を抱える新入社員が増えていました。そこで、同期のつながりを作り、同じような志向をもつ人が集まって、自分たちに合った学びができるようにしようと考えたのです。人事はそれをサポートしていく形です」
期間は6月から9月の第1クール、11月から2月の第2クールに分かれる。第1クールでは、キャリア診断の結果を参考に、管理職志向の強いアドベンチャーゼミ、専門職志向のプロフェッショナルゼミ、創造性を大切にするクリエイティブゼミ、安全や安心に親和性があるワークハックゼミのどれかに、すべての新入社員が所属する。
担当の入社7年目社員を学部長とし、手挙げ制で選ばれた約20名のゼミ長を中心に、事務局が並走しながら、各自が学んでいく。活動は主にオンライン上で、CLAP内のコンテンツの閲覧や月2回のワークショップ、Teamsへの投稿などだ。「集合学習や個人学習の成果を共有し、その学びや気づきを業務で実践できればまた共有するというサイクルを回しています」(後藤氏)
第2クールになると、より新入社員主体の活動となり、同期との関係や知見の拡大を目的とした「全体コミュニティ」と、学びたいテーマを提案してゼミを立ち上げ、自ら募集、運営する「個別学習ゼミ」に分かれる。前者は全員必須だが、後者は自由参加だ。316名の新入社員がいた2024年度は、約20のテーマを新人が提案し、学部長が7つのゼミに調整した。女性ならではのキャリアの悩みを取り扱う「女子相談塾」、見やすい資料の作成法を学ぶ「みやみん(見やすいをみんなで考える)ゼミ」、資産形成や会社制度の活用を学ぶ「大富豪ゼミ」などで、こちらは約5割の参加率だ。
リアル開催を企画したゼミには会場費を補助、福利厚生の仕組みを利用し外部講師を呼んだゼミもある。「こうした学び合いに興味がある新人もいれば、自分は仕事で勝負するという新人もいるでしょう。そう考えると5割というのはちょうどいい数字だと思います」(三木氏)
成果はどうだろうか。「新卒学部がなかった前年度の同時期の4カ月に比べ、新入社員のCLAP学習時間が3.5倍に増えました。また統計分析の結果、CLAPの利用と新卒学部を通じた学びの機会が彼らのキャリア不安の低減につながっていることも分かりました」(後藤氏)
なぜこんなに学習時間が伸びたのか。「CLAP利用時間のトップ30位と視聴時間を公開していたのも競争心を刺激したかもしれませんが、ゼミごとにお薦めコンテンツ一覧を用意し選択肢をある程度絞り込んだり、同期同士で職場や仕事での悩みを共有し、その解決につながる動画を紹介し合うなど、まさにみんなで学ぶことで学習時間の増加に結びついたのだと思います」(三木氏)
昨今よくあるように、AIが各自の学習履歴を参照し、次のお薦めコンテンツを知らせてくれるような機能は入れていないという。なぜか。「CLAPの導入前に若手社員の事務系、同技術系、シニア社員といったペルソナごとに学ぶ動機を調べたところ、他者から受ける影響が大きく、AIなどの機能を求める声は多くなかった。そのリアリティを大切にしたいんです。AIよりも、顔を見知った人が『面白かった』と言った、尊敬する先輩が薦めてくれた、上司が自分に選んでくれたら学びたくなる。そういうコミュニティならではのきっかけを大切にしたい」(三木氏)
テクノロジーの利点を活用しつつ、それに頼りすぎない。生身の人のつながりから学ぶ。人間味のある学びのシステムである。
【text:荻野 進介 photo:伊藤 誠】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.77 特集1「テクノロジーで変わる職場の学び」より抜粋・一部修正したものである。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



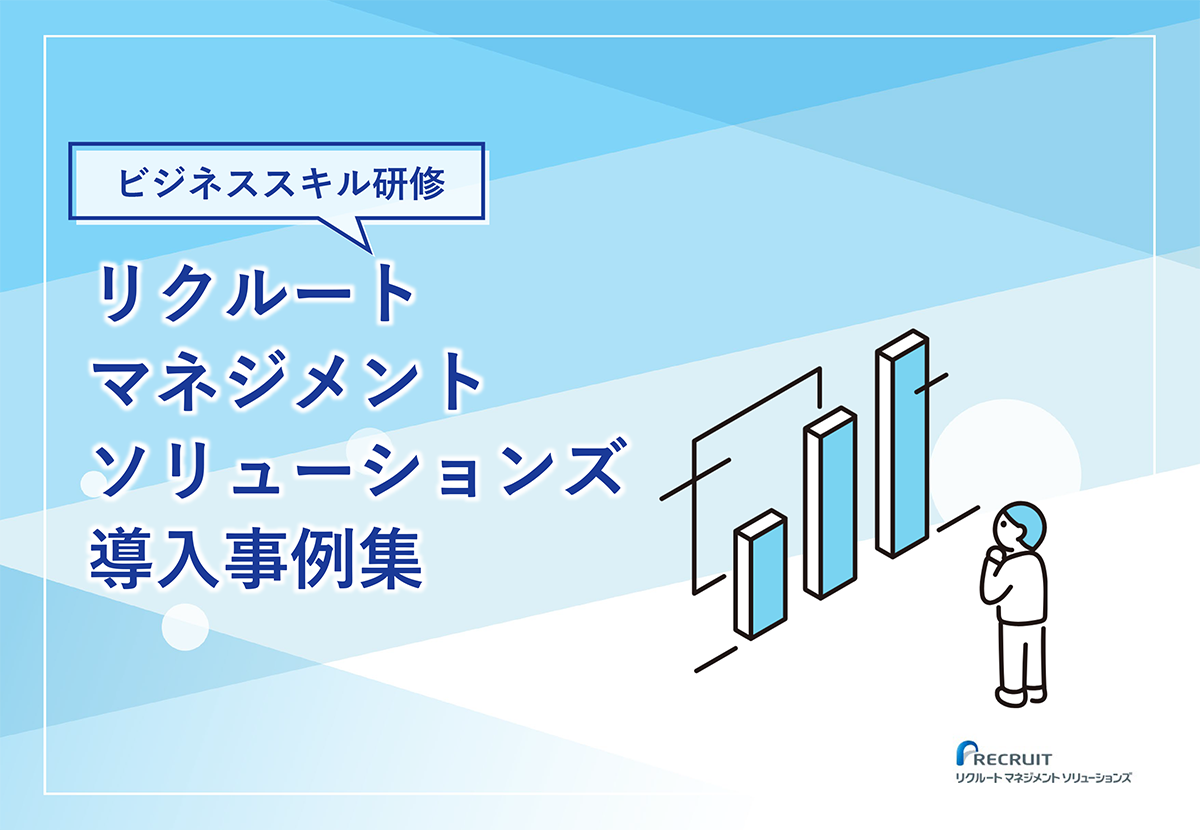










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての