企業事例
組織の状態を見極め、その時々に最適なマネジメントの在り方を追求する サイボウズ
マネジャー職の廃止は組織とメンバーにどんな影響を与えたか
- 公開日:2024/06/10
- 更新日:2024/06/10

オーバーマネジメントには、部下のモチベーションや業務効率の低下を引き起こす危険性がある。では、適切なマネジメントレベルとはどのようなものなのだろうか。ヒントをつかむため、過去にマネジャー職を廃止し、後に再び復活させたサイボウズ株式会社を取り上げる。開発本部副本部長の岡田勇樹氏に詳しく伺った。
プロダクト開発体制の変更がもたらしたマネジャー職廃止
グループウェアの「サイボウズ Office」や業務アプリ作成サービスの「kintone」などを手掛けるサイボウズの開発本部は2019年、大規模な組織変更を実施。このとき、マネジャー(部長職)を廃止したことで注目を集めた。この取り組みをリードした岡田勇樹氏は、プロダクトチームに所属するメンバーの足並みをそろえることが組織変更の最大の目的だったと、当時を振り返る。
「過去の当社では、まずプロダクトマーケティング部で製品デザインを固め、続いて開発部で製品を作り、最後に品質保証部でテストを行うというウォーターフォール型の流れで製品を仕上げていました。そのため、開発や品質保証といった職能別に部署を設け、そこからメンバーを各プロダクトチームにアサインするやり方が機能していたのです。ところが2016年から一部のチームでアジャイル型開発の手法が取り入れられると、旧来の組織に弊害が目立ってきました。例えば、開発部のメンバーが早期リリースを主張するのに対し、品質保証部のメンバーはじっくりテストしたいと望むなど、所属部署の理想やミッションに引きずられたことで生じる対立が増えたのです。プロダクトはフェーズによって素早く新しい価値を届けたいときもあれば、じっくりと品質を高めたいときもあります。そこで、職能別の組織からプロダクト別の組織へ切り替えることで、プロダクトの理想を追求しやすい開発体制を目指す決意をしました」
開発本部は、最初からマネジャー職を廃止するつもりではなかった。ただ、当時のマネジャーが担っていた役割を洗い出した結果、マネジャーがいなくても組織は成り立つと考えたという。
「出張の判断や休暇の承認などについては、権限を各チームに委譲しました。また、労務管理や人事評価、組織づくりといったチームではカバーしづらい分野は、元々マネジャーを務めていた人たちを集めた『組織運営チーム』が担当することにしました。このとき私たちは、マネジャーがいなくても組織が回ることに気づいたのです。そこでマネジャー職をいったん廃止し、ダメだったらまた対策を考えることにしました」
組織変更はメンバーの自律性を高める反面、弊害も生んだ
マネジャー職廃止後は、それまでマネジャーが担っていた役割の一部を複数のメンバーで分担していた。また、ほとんどのチームは合議制で運営するようになったという。
「従来は、各チームの課題をメンバーが職能別組織に持ち帰り、そこでの議論を経てチームにフィードバックすることがよくありました。でも、組織変更後はそうしたケースがなくなり、判断のスピードが高まったりチームの足並みがそろったりしたのは、期待どおりの成果でした。さらに、マネジャーの命令や判断を待つのではなく自分たちが何もかも決める仕組みになったことで、チームやメンバー一人ひとりの自律性は高まりました」
組織変更は大きな効果をもたらしたが、問題点もあった。その1つが人事評価である。2019年当時は8人の組織運営チームで約200人のメンバーを評価していたが、経営規模が拡大し従業員数が増えるのにともなって、組織運営チームの負担はどんどん増していった。また、時間が経つにしたがって組織運営チームと現場との距離が遠くなり、適切な人事評価を下すことが難しくなっていったという。
合議制になったことで「決まらないストレス」が発生したことも、意外な問題点だった。
「マネジャーがいた頃は、彼らがリーダーシップを発揮してものごとを決めるケースがよくありました。ところがリーダーの不在によって、メンバー同士が互いの顔色をうかがい合い、結論が出るまで時間がかかるケースが出てきたのです」
また、マネジャーがいなくなったことでメンバーの自律性は高まった反面、すべての人が自動的に、自ら動けたわけではなかった。
「5人程度の小さなチームなら、全メンバーが当事者意識をもち、役割分担しながら協力し合うことが期待できるでしょう。でも大規模なチームでは、強いリーダーシップをもつメンバーがいなければチーム運営はなかなか軌道に乗りません。そこで人数の多いチームの場合は、彼らが自律的に活動するためのサポート体制を用意したり、自律的に動くための研修を開いたりするなどの工夫が必要だったと、今振り返ると感じます」
管理と自由のバランスを上手にとる必要がある
組織変更から3年後の2022年、サイボウズ開発本部は再びマネジャー職を復活させた。
「人材マネジメントの担当者は4階層に分かれ、採用や育成、人員の配置、メンバーの健康管理、そして人事評価などを担当します。『職能×プロジェクト』のマトリックスでチームを組むのは2019年以前と同じなのですが、以前は職能別組織の方がウェイトが重くてメンバーはそちらに所属している雰囲気が強かったのに対し、今はプロジェクトの方がメインという感じです。これにより、チームメンバーが同じ方向を見ながら活動するという目的を果たしつつ、現場に近い人材マネジャーが適切な人事評価を下せるよう工夫しています。今後もより良い組織を目指し、常にチューンアップをしていくつもりです」
大企業になるほど、オーバーマネジメントの問題も深刻になるというのが岡田氏の実感だ。
「私が入社した頃の社員数は約180人でしたが、現在のサイボウズは1000人を超えています。こうした大組織を効率的に運営するためには、しっかりとしたマネジメント体制が欠かせません。一方、サイボウズでは『100人いたら100通りの働き方がある』とも考えています。さまざまなルールや制度を整備しつつ、メンバーの声を聞きながら個別対応を心掛ける。人によっては上司が細かいところまで指示をするが、時には大きな自由を与えたり合議制を取り入れたりして、メンバーの自律性を促す。そうしたバランスを上手にとることが、企業にとっても管理職にとっても、大切なのではないかと思います」
【text:白谷 輝英 photo:角田 貴美】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.74 特集1「オーバーマネジメント─管理しすぎを考える」より抜粋・一部修正したものである。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)




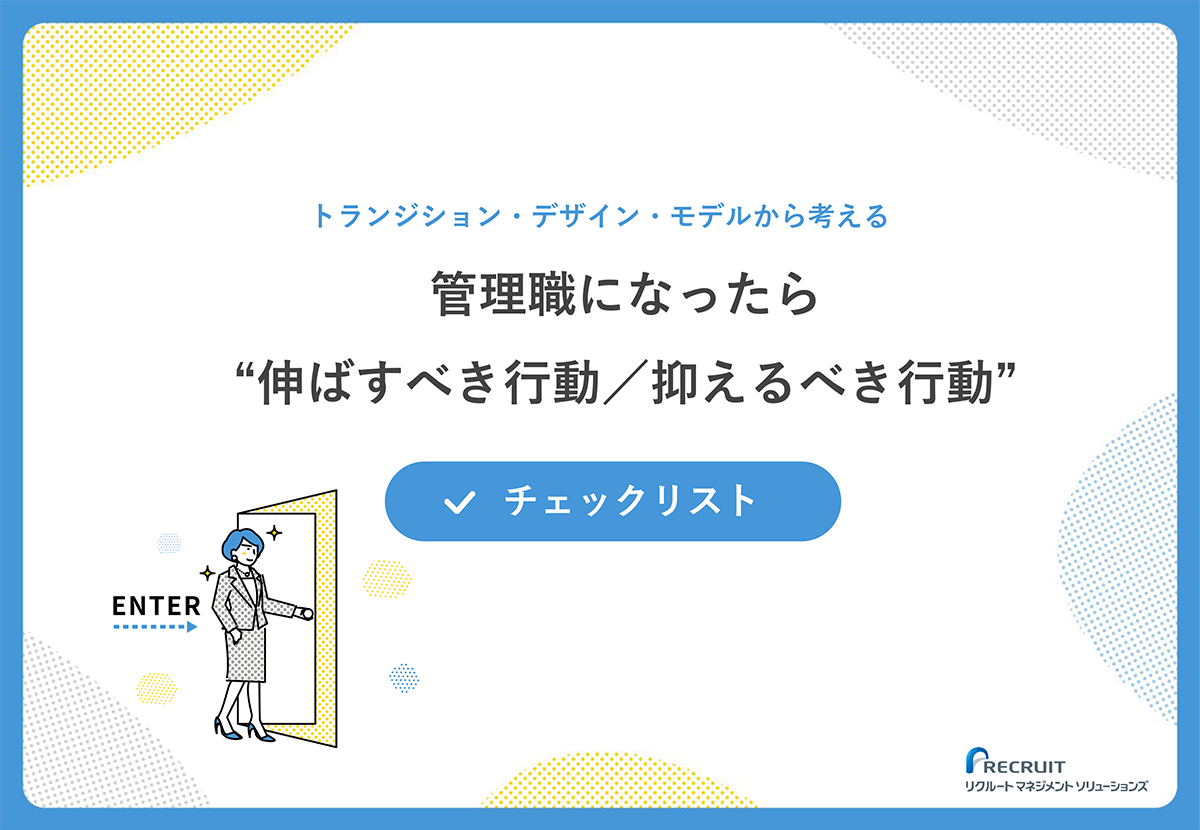









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての