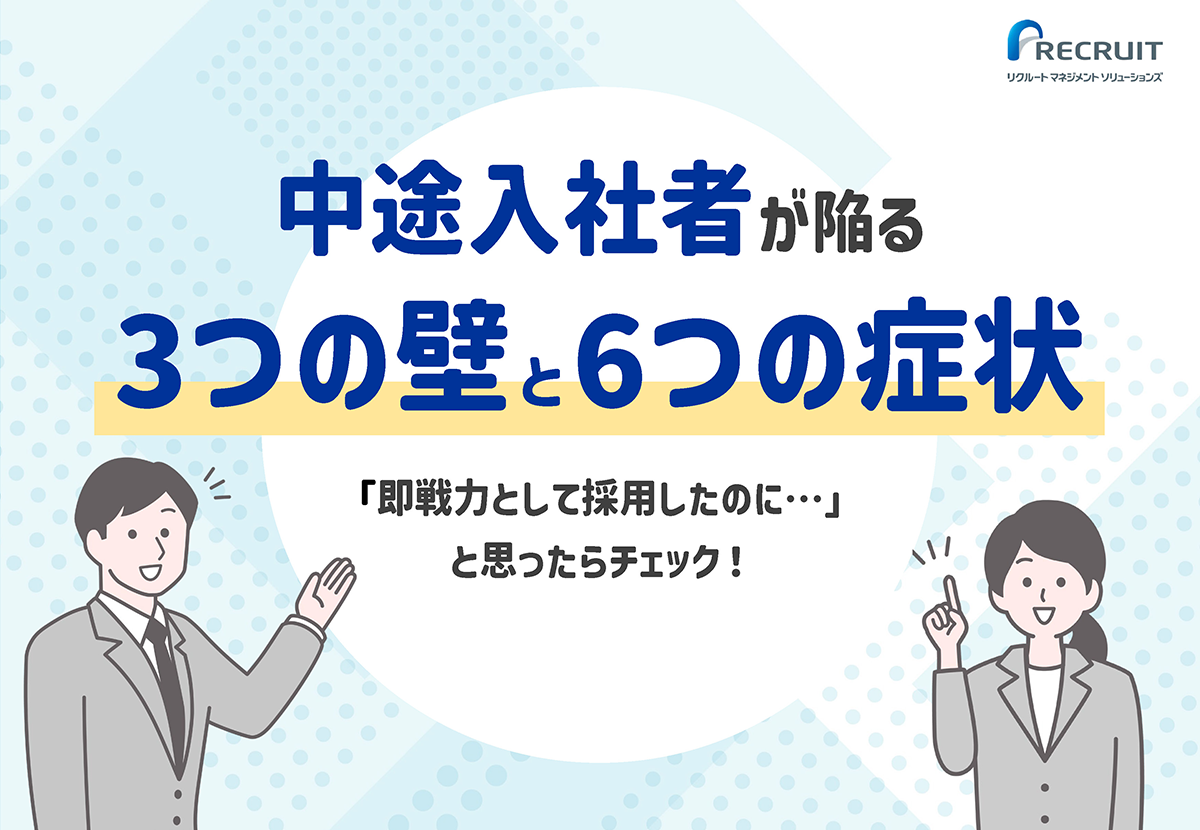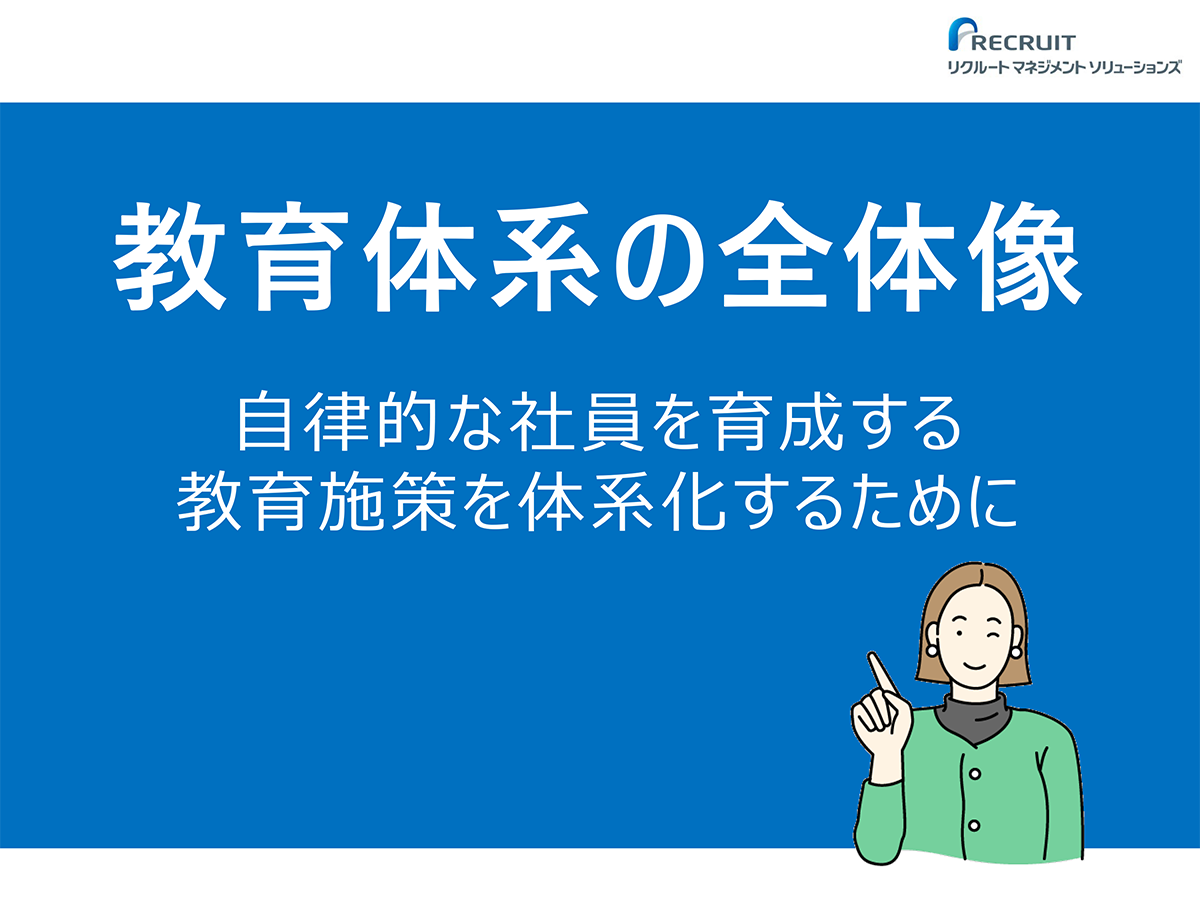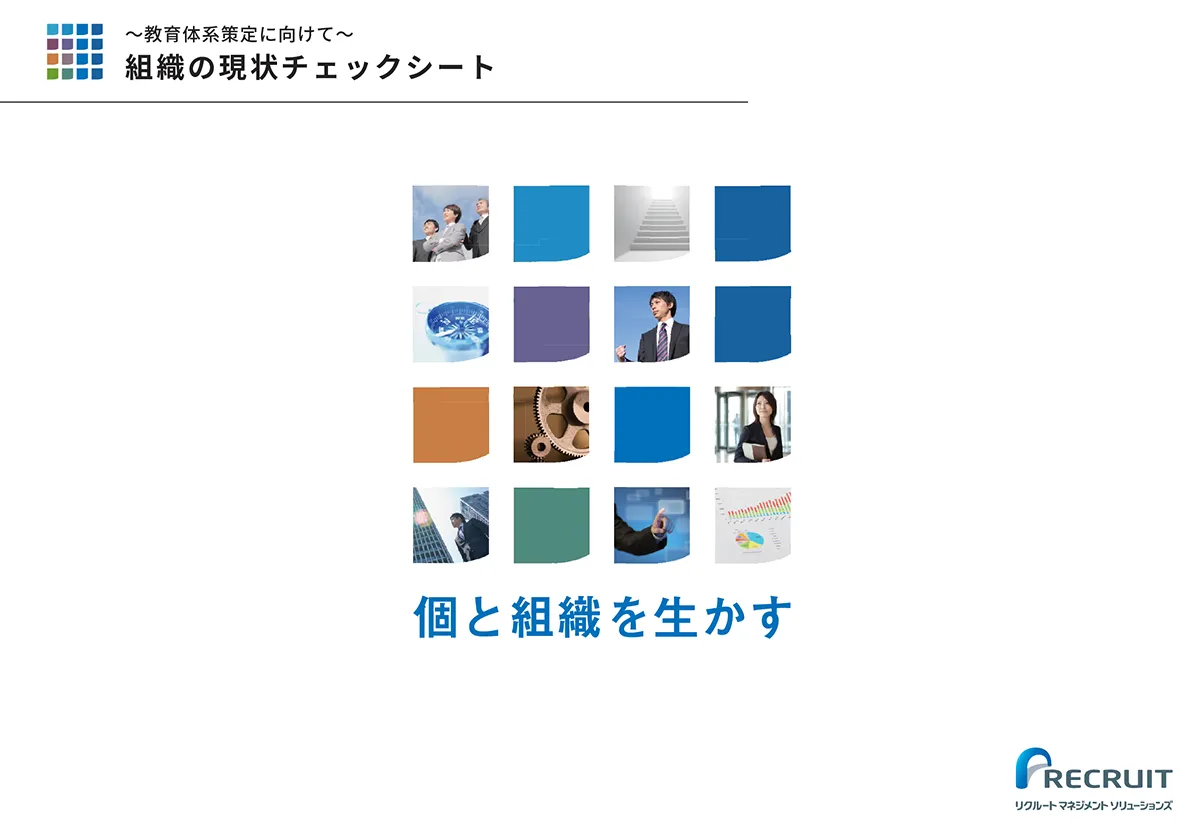特集
方針・戦略の推進を支えるリーダーシップ
組織の方針・戦略の推進の障害となる組織行動について考察
- 公開日:2005/01/01
- 更新日:2024/04/11

今日、多くの企業が変化する環境に適応するための新しい方針・戦略を策定し、その推進に取り組んでいます。しかし、そうした新方針、新戦略が必ずしもうまく浸透しない、言葉としては伝わっているがなかなか動きにつながらないといった声をよく聞くのも事実です。本稿では、組織の方針・戦略の推進の障害となる組織行動について考察するとともに、それらを回避し、効果的な推進を主導するリーダーシップのあり方についてご紹介します。また、その上で、組織開発、人材開発の領域からの推進支援策を探っていこうと思います。
新しい方針や戦略は、なぜ思うように浸透していかないのか?
新年度の方針や戦略が発信される時期となりました。IT化、グローバリゼーションの進展、規制緩和などビジネスの競争ルールを変更させるような今日の環境変化の中では、変化を敏感に捉えた方向性の発信とその実行、さらに実行を通じた軌道修正のサイクルを、組織としていかに速く回していくかが成否を分けるといえるでしょう。ここでは、優れた戦略はもとより、その実行力がより問われることになります。刻々と移り変わる状況の中では、従来と同様の方針・戦略が打ち出されることはむしろまれだと思われます。目指す方向性は変わらずとも、その実現方法や予定する早さが変わっていたり、また、企業として目指す方向性であるビジョンそのものが新しく発信される場合もあるでしょう。
リクルートでは、2003年に、方針や戦略を打ち出した大手企業20社にご協力をいただき、各社の方針戦略の推進度に関する調査を行いました。推進の現状に関する認識として、もっとも多かったのは「(方針・戦略の推進を)多くの人がやらなければならないと感じているが動けていない」というステータスでした。つまり、方針や戦略は経営活動の重要な指針として伝わってはいるものの、組織として動き始めており、現場が変わってきているという実感をもてていない組織が多いということです。また、その背景にあることとして尋ねた「方針・戦略のブレイクダウン度」では一般社員層と管理職層で大きな認識の差があることがわかります。
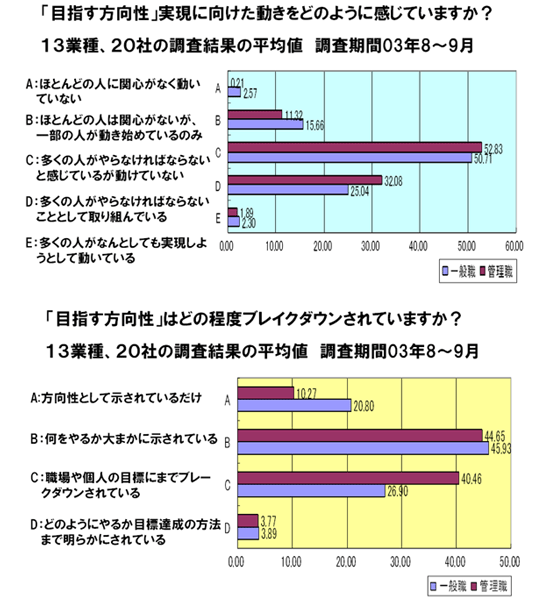
調査結果が示す背景要因
調査結果からは、この他にも次のような特徴を発見することができました。これらは、多くの企業で、方針・戦略が思うように実行されない背景にある要因と見ることができます。
・経営陣は方針・戦略を語っており、本気でそれを実現したいと発信しているものの、何に重点を置いて取り組むかについてわかりやすく発信していない。また、打ち出した方針・戦略をきちんとふりかえっていない
・経営陣による「前例や慣行にとらわれない意思決定」があまりなされていない。また、多くの企業で方針・戦略に向けて経営陣が「一枚岩」になっていないと感じられている
・方針・戦略の背景(なぜ、その方針・戦略なのか)の理解、またそれに向けて取り組むべきことの理解には、管理職(部課長)と一般層とでギャップが大きい
・「これまでのやり方ではまずい」という危機感において、管理職層と一般層で意識のギャップがある(一般層の危機感は弱い)
・「組織の情報公開性」についても管理職と一般層で認識のギャップがある(一般層ほど情報公開が不十分と認識している)
・方針・戦略の推進していくための組織としての「仕組み」や「制度」が不十分である(あるいは既存の「仕組み・制度」はうまく機能していない)。また、必要な資源が手当てされていないと感じている従業員が多い
・方針・戦略はやらなければならないことと認識されているが、方針・戦略の内容と外部環境との整合性に疑問を感じている従業員が多い
・ミドルマネジャー層が、現場の仕事と方針・戦略を結びつけて語っていない。また、メンバーの仕事を十分にモニタリングしていない。
・経営陣が現場に足を運んでいない、現場のことを理解していない(と多くの従業員が感じている)
・企業によって認識のギャップがある階層は異なる。経営陣と部長層にギャップが大きい場合もあれば、課長層とそれ以下でギャップが大きい場合もある
戦略・方針の推進に求められるリーダーシップ
どのような方針・戦略であれ、従来どおりの活動ややり方だけで達成できるようなものはむしろ少ないでしょう。新方針・戦略の推進が組織にとって意味するところは、「従来とは異なることを、多様な人々を巻き込んで進めていく」ことに他なりません。そこでは「組織の中で新しい変化を効果的に主導していく力」、すなわちチェンジ・リーダーシップが求められることになります。そして、こうしたリーダーシップはトップ層のみに求められるものではなく、すべてのレベルのリーダーに期待されるはたらきです。
では、組織の中で効果的に変化を主導するリーダーシップとはどのようなものでしょうか。
ここでは、ハーバードビジネススクールの「J.P.コッター」のモデルを活用して考えて見ます。
コッターは、数々の企業の変革推進プロセスの研究から推進プロセスに潜む「落とし穴」を発見しました。そして、変革のプロセスを成功させた企業はその落とし穴を注意深く時間をかけて克服していたことを見つけ出し、組織の変革推進モデルを提唱しました*。コッターが見つけた変革の落とし穴とは次のようなものです。(図表1)
* John P. Kotter , Leading Change: Why transformation efforts fail. HBR March1995
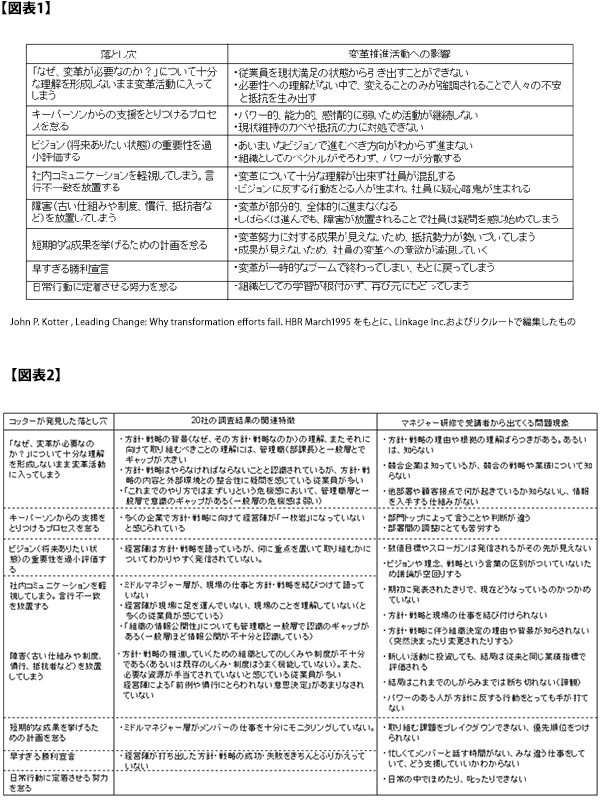
コッターが発見した組織における変革推進の落とし穴と、先の調査結果には多くの共通点を見つけることができます。加えて、弊社が実施しているマネジャー向けトレーニングのなかで受講者であるマネジャーの方々から出てくる問題現象も、新しい方針・戦略を組織で推進していく時の課題に示唆を与えるものと思います。(図表2)
コッターによる変革の8段階モデル
前出の変革推進の落とし穴を踏まえて、コッターは8段階の企業変革モデルを提唱しています。そしてこれらのステップを丁寧にたどり、各段階で陥りがちな失敗を最小化することが変革を成功に導くとしています。コッターの変革のモデルは今日的な環境の中で、組織に新しい方針や戦略を根付かせていく活動を効果的に主導するリーダーシップの原則を示しているといえるでしょう。
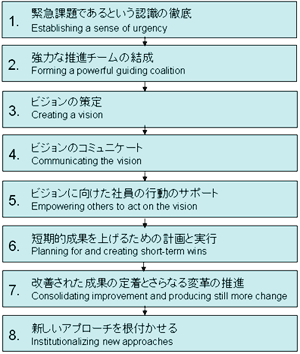
John P. Kotter , Leading Change: Why transformation efforts fail. ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー2002年10月号(黒田由貴子訳)をもとにリクルートマネジメントソリューションズで加工したもの
方針・戦略の推進を支援する
コッターの変革のモデルをベースに、新しい方針・戦略の効果的な推進を支援する組織開発、人材開発施策を列挙してみます。当然のことながら、これらの施策は個別組織の状況によって選択されるべきものです。また、選択された施策は有機的な連動を意図して組み合わされるべきでしょう。
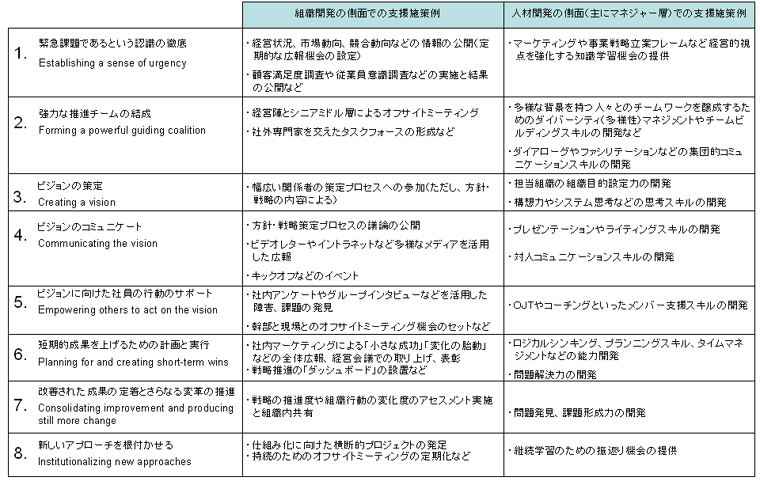
組織開発面、人材開発面のいずれの支援も、時間とパワーのかかるものです。また、こうした活動はいわゆる「組織の見えない資産」への投資活動であるため、なかなか成果が把握しにくいのも事実です。しかし、方針や戦略の推進の本質は、新しい方向性に向けて多様なバックグラウンドと価値観を持った人々を“その気にさせる”ことであり、そこでは一見、非効率的でまわり道と感じられるような活動が実は重要な意味を持つ場合もあります。
最後にコッターの言葉を引用しておきましょう。
「(変革のプロセスにおいて)踏むべき段階の一部を省略してしまうと、スピードアップに成功したという錯覚が生まれるが、けっして満足のいく成果を上げることはできない。」ジョン・P・コッター「リーダーシップ論-いま何をすべきか-」ダイヤモンド社 黒田由紀子監訳より
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)