特集
非組織長管理職の増加にあたり
これからの管理職に求められる能力・要件とは?
- 公開日:2008/12/17
- 更新日:2024/03/26

企業人の人生において大きな転換点でもある管理職への昇格。管理職の定義が変わる中、この転換点で求められることにはどのような変化が見られるのでしょうか?
管理職における組織長と非組織長のボーダーレス化
■非組織長管理職の増加
1960年代から普及を始めた職能資格制度の導入は、昇進と昇格を分離する、つまり職務と資格・賃金を切り離すことを可能にしました。その結果、団塊の世代には多くの部下をもたない非組織長の管理職、いわゆる部下無し管理職が存在していました。さらに2000年代初頭にバブル期入社世代のボリュームゾーンが昇格時期を迎えた上、組織のフラット化による役職・ポスト不足の影響で非組織長の管理職が増大したため、あらためて「新任管理職」に注目が集まりました。
企業におけるボリュームゾーンであるこの世代が活躍をしなければ、企業収益の達成、企業活動の存続は立ち行かない状況となります。これまでも創造性やイノベーション追及のために、専門性を磨き高めていくといった要素が求められていましたが、専門性だけでそれらの価値創造を実現することは難しくなりつつあります。多くの人との協働や後進の育成・活用により高い成果を上げることができなくては、求められる価値を生み出すことは困難であるという状況です。また、行き過ぎた成果主義の功罪として、極端な個人主義の増長による自己保身や、協働意識の欠如なども問題視されています。働く側の価値観の多様化も進む中で、職場のマネジメントを組織長だけに頼ることにも限界が来ているのが現状のようです。
■管理職に求められる要件の再定義の必要性
それゆえ、制度上では複線型の人事制度を取り入れ、職群別の枠組みがあったとしても、非組織長管理職は、専門プレイヤーとしての能力発揮だけを求められるのではなく、組織長の立場を理解し、うまく協働できるプレイヤーであることが求められています。さらに、職群間の柔軟な行き来を可能とする、職群をまたいだローテーションのできる人材が求められているともいえます。ここが、これまでのいわゆる部下無し管理職との大きな違いでもあります。
そのような状況において、非組織長管理職と組織長管理職のボーダーレス化が進んでおり、あらためて「管理職」を定義する必要性が増してきているのではないでしょうか。弊社では、組織長・非組織長にかかわらず管理職に求められる要件を、主任・係長との違いから、以下のようにまとめました。
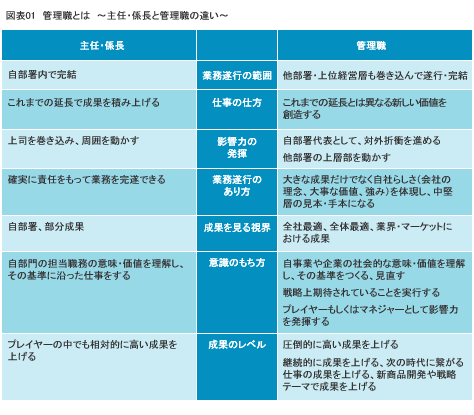
図表01の主任・係長と管理職の違いは、大きく3つの転換点に集約することができます。
・「経営資源として活用される」から「経営資源を責任をもって活用する」
・「与えられた仕事を完遂する」から「自ら仕事を創り出す」
・「環境の変化に適応している」から「自らを変え、環境を変える」
つまり、管理職とは「自らの意思と責任で、現場を改革・成長させて全社的な業績・価値創造に貢献する」存在だと定義することができます。
管理職昇格における実態
管理職昇格における実態を知るために、従業員規模5000名以上の企業10社の人事企画、人材開発部門の方とのディスカッションやインタビュー、管理職昇格者8名へのインタビューを実施しました。
■企業人事の課題認識
新任管理職について求めること、期待することについて企業の人事担当の皆様にインタビューしたところ、新任管理職における非組織長の割合が増えてきているという事実があらためて確認されました。また、組織長であれ、非組織長であれ、管理職となることは大きなトランジション(転換期)であると位置づけており、何らかの役割意識の転換の必要性を感じています。また、昇格時点というのは意識を変える絶好のチャンスで、これを逃すと役割意識の転換をさせることは難しく、昇格のタイミングで何かしらのマインドセットをさせたいと考えていることがうかがえました。
また、既任の管理職にも、経営的情報への関心、人を育てることへの関心の薄い人が増えてきているようです。彼/彼女たちに対して、自分の仕事をこなすだけの守りの立場では困るという問題意識はあるものの、それについて具体的に何をどうメッセージすればいいのかということに明確な答えをもてていないのが現状のようです。
■新任管理職の実態
実際の新任管理職に対し、現況に関するヒアリングをしたところ、組織長管理職については以下のような状況が見えてきました。
・部下育成をしなくてはならないが、自身もプレイヤーとしての業績を抱えており、その中に埋没してしまう
・部下育成は大事だと思っているものの、目先の業績に追われ後回しにせざるを得ない
・コンプライアンス、メンタルヘルスなどを意識して、部下をしかれない、要望できずに自分で仕事を抱えてしまい、仕事に忙殺され、自分自身が何を実現したかったのかを見失ってしまう
・働き方が多様化し、さまざまな部下がいるため一人ひとりへのフォローをしたいが、忙しくて手が回らない
また、非組織長管理職については、以下のような状況が見えてきました。
・仕事内容が変化せず、異動や配置換えもなく、そのまま以前と同じ仕事を続けている人が圧倒的に多く、組織長のように部下をもつ、評価権が与えられるなどの変化がほとんどない
・どこかで変わらなくてはいけないのではないかという漠然とした不安を抱えつつも、日常の仕事に忙殺され、いつの間にか時間ばかりが過ぎている
・制度上の役割定義を読んではみるものの、それが日常の場面で、何をどのようにすることなのか、何を大切にして何を実現することなのかということを実感できない
今求められる管理職への意識転換
先に述べましたとおり、非組織長管理職も組織長管理職と同様に管理職としての役割意識をもつことが求められています。よって、新任管理職という意識転換の絶好のタイミングにおいて、両者ともに「管理職になるとはどういうことか」ということをあらためて認識し、現在、もしくはこれから起こりうる自分の状況を自覚し、覚悟をもって今後の管理職としてのスタートを切ることが必要になっていると考えられます。それは管理職として、「自分の言動に伴い発生する影響範囲の大きさや責任の重さを認識・自覚するとともに、意思をもって決断し、やり遂げるためには自分なりの信念・覚悟を伴う」ということについて決意を新たにしなければ、「管理職」のステージに入ることが難しくなっているともいえるのではないでしょうか。
また、近年ではシニアの活躍に期待が集まっており、非組織長管理職についても育成や自身で成長していく人材開発の取り組みが始まっています。
弊社では、これまで見逃されがちであった非組織長管理職についても、組織長管理職同様に組織の存続を確実にするために「マネジメント」に責任をもつ存在であること、管理職としての責任や影響範囲の実感をもつことが必要だと考えており、この「管理職としての役割意識の変換」を支援するための研修を開発しています。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)




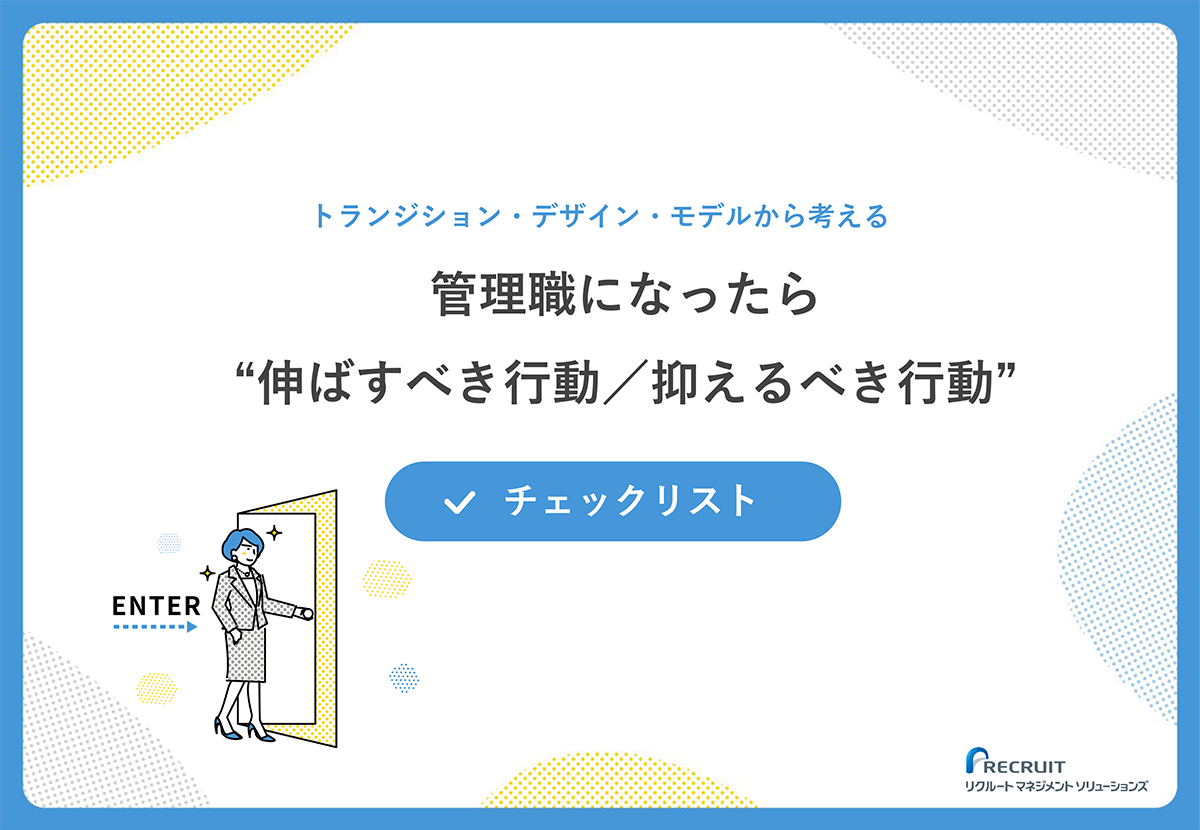









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての