特集
コミュニケーションのすれ違いを埋める
「伝える力」を磨きロジカルシンキングですれ違いを解消しよう
- 公開日:2008/03/10
- 更新日:2024/04/11
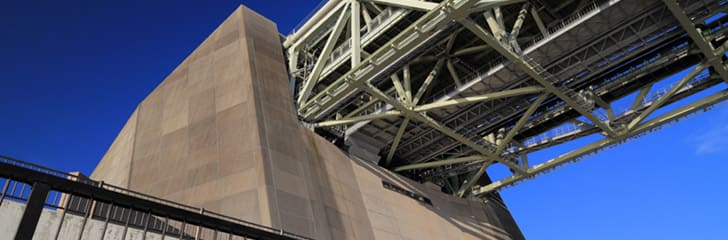
「若手のいっていることはよくわからない」「メールだけではなく対面で伝えることも覚えてほしい」など、若手のコミュニケーションを問題視する声が増えています。しかし、その原因は本当に若手だけにあるのでしょうか?
この20年の採用環境の激変は、ベテラン社員と若手社員ばかりで中堅社員がほとんどいない、いわゆる「ワイングラス型」の歪んだ人員構成という結果を企業にもたらしました。こうなると、特定の世代ではなく「世代間のギャップ」がコミュニケーションのすれ違いの原因の一つであることは容易に想像できます。
では、それを解消するためには、何が必要なのでしょうか? 解決の糸口となるのが「共通言語をもつ」「共通思考フレームをもつ」といったロジカルシンキングの思考法です。
本特集では、最近特にお客様にご支持をいただいている「ノウハウ・ドゥハウ(KD)」シリーズについて、講師としても人気の高い (株)HRインスティテュート副社長 稲増美佳子氏の視点で、昨今のビジネススキル系研修ニーズの実態とプログラムの特長 について語っていただきました。
時代が求める「伝える力」の重要性
リクルートマネジメントソリューションズ (以下RMS)
ここ数年、私たちを取りまく環境はグローバル化、スピード化と、めまぐるしく変化していますね。企業としては成長し続けること、成果を出し続けることが命題であり、所定の期間内に一定の、もしくは今まで以上の成果をあげよう!と生産性の向上に躍起です。このような環境要因の中で、なぜ今「ノウハウ・ドゥハウ」シリーズに注目が集まっているのでしょうか?
稲増さん
今の組織は、非正規社員・中途入社者が増え、コミュニケーションの環境として、国籍・文化圏すら異なることもあり得ます。こうした組織では、経営トップに限らず管理者以上であれば特に、相手に「伝える力」が求められます。
多くの組織においてこれまでの前提であった“トップダウン式の組織”、つまりヒエラルキーが明確で、同じ文化を共有し、「あうんの呼吸」で伝達・共有できる環境、というのはすでに崩壊しています。社員それぞれのバックグラウンドが異なる中で、仕事に携わるメンバー一人ひとりがその仕事の意味や背景を十分理解し、納得していないと、成果をあげることは難しくなってきています。
そうなると、正確に「伝える」ための共通した「思考法」や「言語」が必要になってきます。「ノウハウ・ドゥハウ」シリーズでは、こういった共通の思考法や言語、といったものを演習を通して身につけていただけます。伝えたい気持ちはあっても具体的なスキルがないとうまくいかないと感じている方は多いようです。この研修ではそういった実践的なスキルを学べるところにニーズの高まりがあるんでしょうね。
若手と管理職では身につける「伝える」レベルが違う
RMS
「伝える力」と一言でいっても、例えば、若手と管理職クラスでは「伝える」ことのレベル設定がそもそも違ってくると思うのですが、研修の現場では各階層について日々どんな問題を感じますか?
管理職クラスの「伝える」課題
稲増さん
管理職クラスの研修で感じるのは、“伝える力”が圧倒的に足りない、ということです。
何より自分の言葉で語ることができていないと感じる場面が多いです。伝えるとは“相手の心を動かす”ということですので、そこまで視野に入れて語ることが重要です。
基本的なスキルの一つである、ロジカルシンキングやマーケティングフレームは世界共通言語であり、いわば “論理語” “戦略語” ともいうべきものでしょう。これらはぜひ身につけておいてほしいですね。
論理語は、英語などの異国語よりも大事なスキルといえるでしょう。英語だけの問題なら、通訳がいれば事足ります。しかし、通訳するもとの日本語が論理的でなければおしまいです。なるべく早いうちに意識してこれらの“共通言語”ともいうべきフレームは理解しておくべきでしょう。
若手・中堅クラスの「伝える」課題
若手・中堅クラスに対しては、“課題解決力の向上”を要望されることも多いです。しかし、そもそも経験が少ない中で課題にうまく対処するには、経験不足を補うための仮説策定&検証する力が必要であり、“課題を因数分解していく力“も問われます。
なぜ因数分解が重要かというと、自分が対処しなければならないことを因数分解して“見える化”できれば、対処法も見えてきますし、何より、解決の糸口が見えない不安に捉われることなく、ポジティブに考えられるようになります。例えばロジカルシンキングのスキルを使って、問題を整理・分解し伝えることができれば、解決も早くなり、答えが導きだせるのです。
新入社員クラスの「伝える」課題
新入社員については、ソーシャルスキルの獲得が一つの基本的なテーマになります。学生時代と異なり、ビジネスの場では、かかわりたくない相手ともコミュニケーションをとっていかなくてはなりません。こうした場面で、ぜひロジカルシンキングの力を活用してほしいと思います。
例えばあらかじめ困難な状況・相手を想定したうえで、対処法について事前に整理しておく癖を身につければ、ずいぶんと違ってきます。新人向けにビジネスコミュニケーションの研修を実施させていただく場合は、こうした状況のシミュレーションとしての擬似体験につながるように意識しています。
ロジカルシンキングはシリーズの中でもベースとなるプログラムです。ある物事について、自分が理解したり、相手に伝えるためには、本来は“考える”→“(考えたことを)書いてみる”→“読んでみる”→“相手に話してみる”という一連のサイクルをまわす必要があります。
その土台になるのが、ロジカルシンキングであり、話してみて、内容が相手にしっかり伝わっているかどうか、ということがポイントです。重要なのは、シンプルであることです。本質がわかっていればシンプルに文章に落としたり、話をまとめることができます。「要は一言でいえば」がいえるかどうかです。
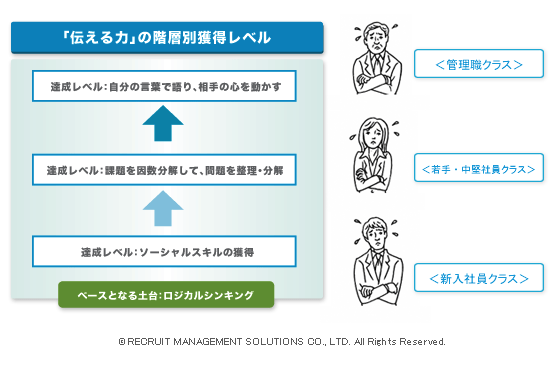
「ノウハウ・ドゥハウ」シリーズの特長とは
RMS
「ノウハウ・ドゥハウ」シリーズの紹介セミナーでは、「使ってナンボ!」「わかりやすく・楽しく!」といったキーワードでこのシリーズの特長を紹介することが多いですよね。実際に研修を導入していただいたお客様からは、実践を意識した演習豊富な内容やパワフルな講師への評価を多くいただいています。では、実際に研修を運営する講師の立場として、どんな意識で研修に臨んでいますか?
稲増さん
我々の企業理念である“主体性を挽きだす”というのがそのまま研修テーマなのです。
参加される受講者一人ひとりの意識を引き上げ、主体性を挽きだすことにフォーカスして運営するよう、心がけています。
研修内容をただ耳で聞くだけの研修とは異なり、あくまでも研修を通じて自分が体験・体感する中から、自分の強み・弱みなどを含め、実感を伴った様々な”気付き”を得ることが本人の主体性を挽きだすことにつながります。
主役は受講者です。講師の役割は受講者の力を挽きだすこと、と思って研修に臨んでいます。言葉には出しませんが「毎日が千秋楽!」という心意気で研修の場に臨んでいます。
さらに、研修では、講師対受講者、という関係だけにとどまらず、参加者同士、お互いを高めあう場であってほしい、と考えています。研修が飽きない、楽しい、というふうに思っていただけるとしたら、それは受講者同士がお互いの力を高められるような、ペアワーク、グループワークの機会を大切にしているからでしょう。
簡単なゲームであっても、チームとしての答えを導くにはフレームメソッドが必要、ということがまず実践を通して実感できますし、それが研修効果につながります。
研修効果を高めるために
RMS
どんなにいい研修の場であったとしても、研修後の実践を通じて、その効果を実感し、スキルをより高めていけることが望ましいと思うのですが、研修前・研修後、それぞれについて効果を高めるための工夫、留意点とはなんですか?
稲増さん
「ノウハウ・ドゥハウ」シリーズでは、どのプログラムにも副読本を用意しています。それぞれHRIの講師陣がチームを組んで執筆しているものですが、こうした副読本はできる限り事前に読んでおいていただけると、それだけでも違います。まず言葉に慣れることができます。
戦略やマーケティングといったテーマになれば、それだけ情報量も多いので、事前知識・情報としてある程度頭に入っていれば、より理解が深まり、実践的な取り組みを増やすことができます。
また、研修後の環境や取り組みもきわめて重要です。受講者が職場に戻っていきなり“ロジカルシンキング”のフレームを振りかざしても、職場によっては受講者だけが浮いてしまう結果にもなりかねません。ロジカルシンキングを活用するためには、組織全体が共通して理解していることが大切で、そのために組織全体がまとまって受講するなどの工夫が求められるでしょう。
あるいは、受講者が研修から戻ってきてすぐに実践しやすくするためにも、職場での報告会などはとても有効です。学んできた内容を具体的に職場のメンバーに報告し、実際の仕事で活用することを宣言するのです。
周囲のメンバーは、どれだけちゃんと使えているか、期待どおりの成果につながっているかなどを、随時、本人にフィードバックします(例えばプレゼン研修受講後であれば、どんな点でプレゼンスキルが上がったかなど)。それをさらに人事部にもフィードバックする仕組みがあれば、なお効果的です。人事部のサポートのもとで、本人の意識を高める、実践をより促すことがポイントになります。
効果的な導入事例
ここでは、具体的にどんなニーズがあり導入をしていただいているのか、簡単なポイントのみですが事例をご紹介いたします。
広告代理店 A社
「コンペでの勝率をさらに上げるプレゼンテーションスキルがほしい」
●導入背景
広告代理店営業では「プレゼンテーション」の機会も多く、必須のスキルとなっている。競合にコンペで負けない!勝率をあげる!などの明確な目的があり、「よりプレゼンテーションのスキルを磨く研修を実施したい」とご相談があった。
●受講対象者
入社3~4年目の営業担当者
●実施した研修
プレゼンテーションのノウハウ・ドゥハウ
●研修後の受講者の声
◆研修を受講する前までは、人前で話すのが苦手で、プレゼン当日は憂鬱になったりすることもあったが、研修を受講した今、少し自信が出てきた。まず実践してみようと思う。
◆提案される側の立場で、人のプレゼンを聞く機会は貴重だった。
◆自分が受けたことはもちろんよかったが、他の人にもぜひ受けてもらいたい。(特に、上司に受けてほしい……)
◆この研修受講後の翌日がまさにコンペだったのですが、学んだスキルを実践してコンペに勝ちました!
外資系メーカー B社
「引き継ぎ時のコミュニケーションに苦戦している」
●導入背景
外資系企業の場合、組織のリーダーは本国から赴任してくるケースが多い。またそのリーダが変わるタイミングも頻繁にある。そのような状況下でも現場担当者は言葉も文化も違うリーダーに間違いなく報告を行わなければならない。このような問題を解決するために、「世界でも通用する普遍的な思考法やフレーム」を短期間で身につけられる研修はないかとご相談いただいた。
●受講対象者
非管理職のスタッフ
●実施した研修
ロジカルシンキングのノウハウ・ドゥハウ
プレゼンテーションのノウハウ・ドゥハウ
●研修後の受講者の声
◆仕事の進め方、考え方、伝え方などスキルの部分はもちろん、気持ち的にも非常にやる気の出る研修でした。特に「考える人」と「悩む人」の話で、考えるとは“自分で決めて動くこと”という言葉が心に残りました。これから実践して「考える人」になります!
◆講師の話がわかりやすい。
しかも聞いているだけではなく、いつも双方向のやり取りがあったので楽しめました。
◆職場にもどって、本当にすぐに実践できました。
●その後
研修後アンケートでも受講者の満足度が高く好評だったため、この階層の上位階層にも導入が決定。広がりを見せている
最後に
いかがでしたか?
仕事は人と人とのやりとりで成り立っている以上、こういったコミュニケーションのベースは必須となってきます。むしろ変化の激しい昨今の環境下だからこそ、今回ご紹介したようなベースのスキルに立ち返ることが競争を勝ち抜く差別化ポイントにつながるのかもしれません。
誰しも「自分の思っていることを正しく相手に伝えたい」「コミュニケーションの齟齬をなくして、気持ちよく人と仕事を進めたい」という思いはあるはずです。そういう意味では、今回ご紹介した研修は企業や組織を離れても、一個人としても必ず役に立つのではないでしょうか。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


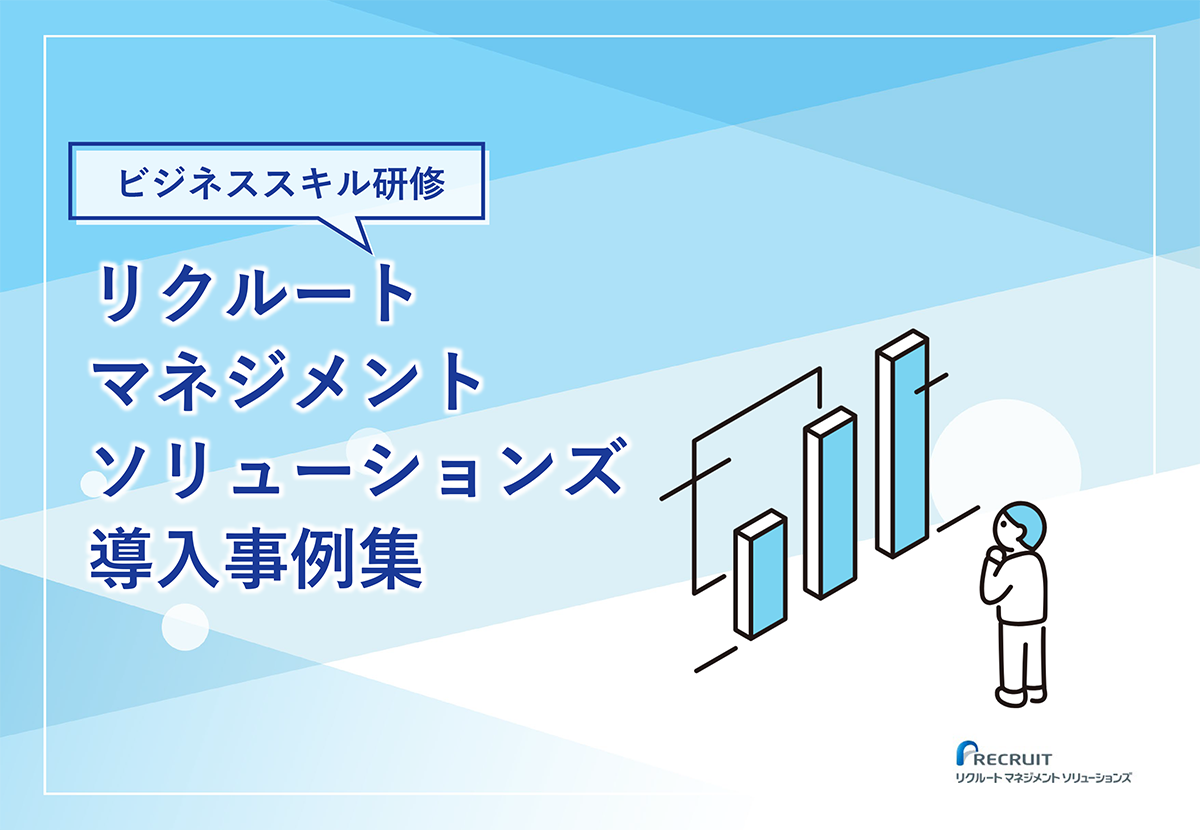
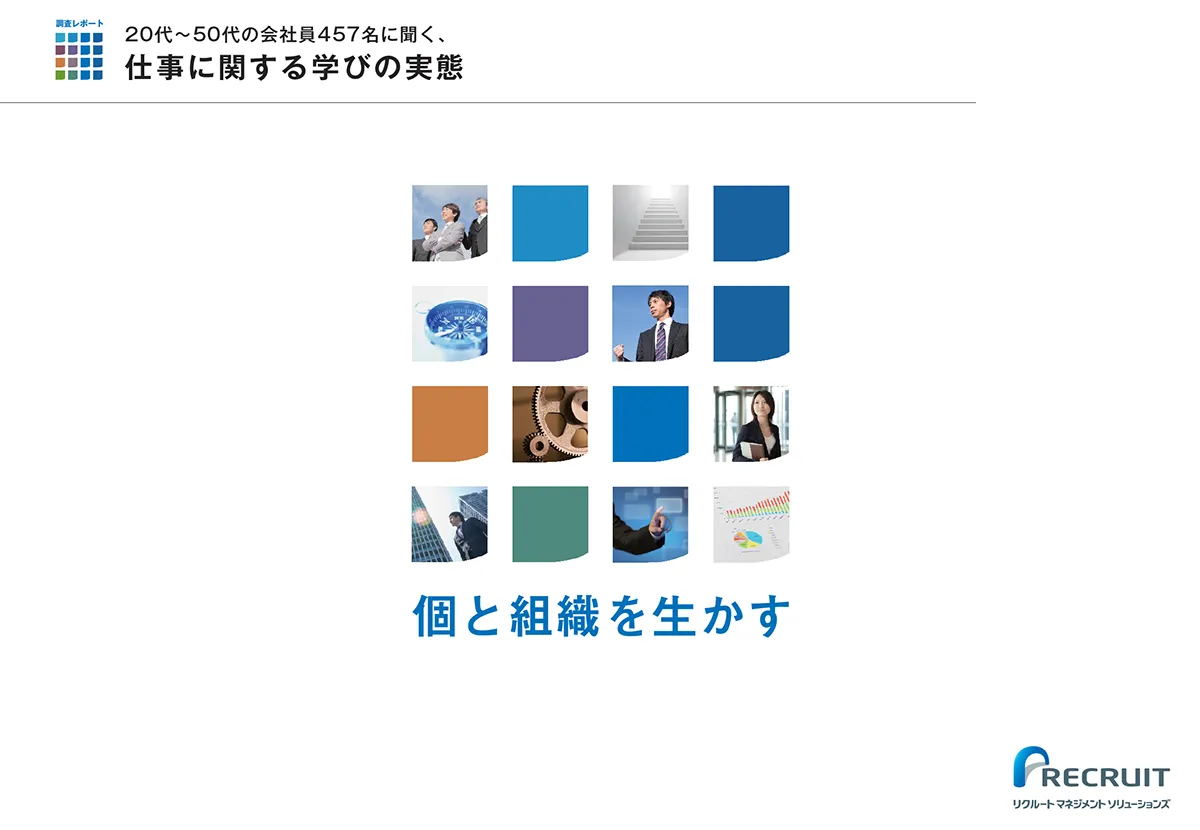
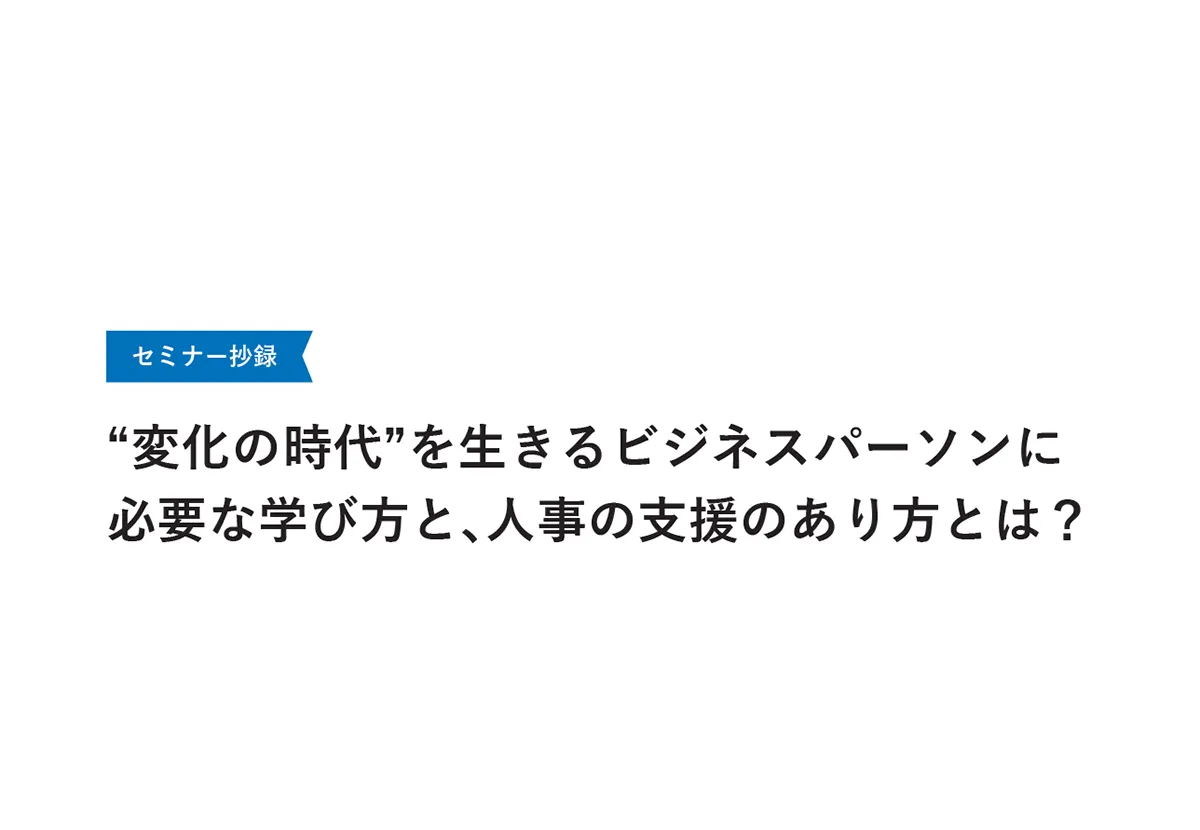









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての