特集
従業員満足度の把握から実践的な活用に向けて
従業員満足度(ES)の企業経営への活かし方
- 公開日:2007/12/01
- 更新日:2024/04/11

ある調査によると、従業員数1000名以上の企業における「従業員満足度調査」の実施率は38.2%と、約10社に4社が実施済みという結果が出ています(出典;労務行政研究所の「人事労務管理諸制度の実施状況調査」2006年度)。
また弊社が取引先に回答いただいた調査でも、「実施している」「実施計画がある」という取引先が50%を超えるなど、企業にとって、従業員満足度調査はもはやポピュラーな人事施策の1つとなったといえるでしょう。
しかし従業員満足度調査の結果を事業経営にいかせていると実感している経営者や人事部のスタッフが多いかというと、疑問を感じます。また従業員の方も、自分たちの声をしっかりと受け止め、有効に活用してくれていると感じているのは、むしろ少数派かもしれません。
本特集は、「把握」はできても、経営者、従業員ともに「取り組み実感」を感じにくい現状の背景を考察するとともに、「従業員満足度調査」を事業経営にいかすためのポイントを解説していきたいと思います。
- 目次
- もはや当たり前になりつつある従業員満足度の把握
- 「現状の把握」と「取り組み実感」の間にある大きな壁
- 従業員満足度を事業課題に照らして解釈する
- 組織全体のマネジメント能力を高め、ミドルの負荷をコントロールする
- 組織力向上の入口としての従業員満足度
もはや当たり前になりつつある従業員満足度の把握
労務行政研究所が3年に1度実施している「人事労務管理諸制度の実施状況調査」によると、2004年に14.2%であった「従業員満足度調査」の実施率は、2007年には20.1%に上昇しています。ちなみに2001年の調査には、この項目自体が存在せず、ここ数年で導入が急ピッチで進んだことがわかります。 従業員1000名以上の企業の実施率は38.2%ですが、この数字は業績連動型賞与(39.5%)や選択定年制・早期退職優遇制度(36.8%)などと同水準であり、いまや従業員満足度調査は一般的な人事制度の一つといえるでしょう。
弊社が取引先を対象に実施したアンケート調査でも、「実施済み」「実施予定あり」の合計が50%を超えており、その事実を裏付ける結果となっています。
従業員満足度が注目される理由は各社によりいろいろ異なる部分もあるでしょうが、その根底には知的資本としての従業員を重視するという考え方が定着してきたこと、また近年の業績回復を機に、希少な資本である「人材」にしっかりと投資しようとする意識が強まっていることがあると思われます。
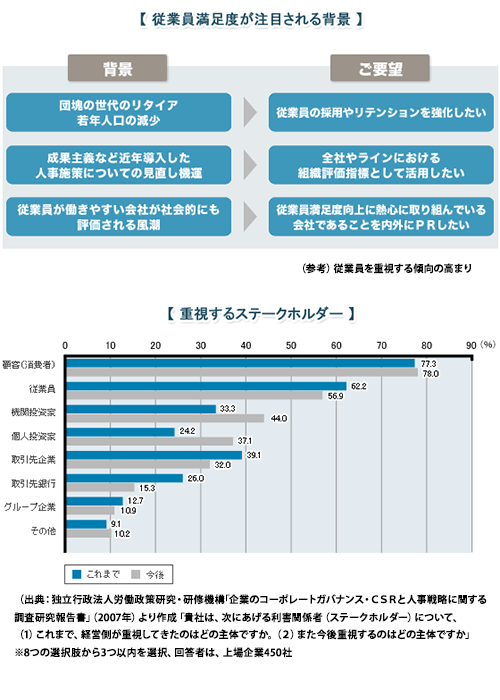
「現状の把握」と「取り組み実感」の間にある大きな壁
弊社が1119名の社会人を対象に行った、「従業員満足度の現状と期待」についてのアンケート結果(2005年6月)によると、「現在あなたが勤務している会社では、従業員に対する意識調査が行われていますか」という質問については、43%の方が「YES」と回答しており、この時点でも相当数の企業が、従業員満足度をはじめとした意識調査を実施している様子が窺えました。
しかしながら「従業員満足度を向上させる取り組みに熱心ですか」という問いかけに対しては、「YES」と回答した方が18%に留まり、45%の方が「NO」と回答しています。(「どちらでもない」が37%) このことからも、「従業員満足度の把握」と「従業員満足度の向上に向けた取り組み実感」の間には、大きなギャップが存在していることがわかります。
またこの調査では同時に、回答者一人ひとりの「従業員満足度」についても質問していますが、取り組み実感を感じている方と、そうでない方との間には、非常に大きな差が生じています(総合満足度で0.68)。 このことから分かるように、従業員一人ひとりに「従業員満足度向上における取り組み実感」を持ってもらうことは容易ではありませんが、それに成功した場合には、大きな成果が期待できるといえるでしょう。
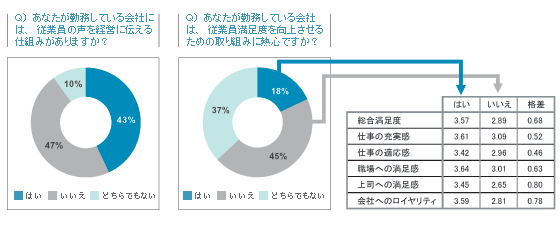
従業員満足度を事業経営にいかしきれていない現実
従業員一人ひとりに「従業員満足度の向上に、会社が熱心に取り組んでいる」と実感してもらうことが容易でないことを紹介しましたが、経営者サイドはどう感じているのでしょうか?
定量的なデータはありませんが、経営者サイドの声として、以下のような内容をよく耳にします。
「従業員満足度の現状は把握できたが、向上のための人事施策につながらない」
「ラインでの取り組みを促すために、ミドルマネジャーに結果をフィードバックしているが、具体的な動きがあまり感じられない」
「全社ではそんなに大きな変化はなく、毎年実施する必要はないのではないか」
実際、自社運用や弊社以外のコンサルタント会社や調査会社で従業員満足度調査を実施していたが、あまりその後の効果的な施策につながらないので、相談に乗ってほしいというご依頼をいただくことが増加しています。
どうやら従業員サイドだけでなく、経営者サイドにとっても「従業員満足度の向上に向けた実践」は、なかなか困難を伴う課題であるようです。
従業員満足度を事業課題に照らして解釈する
弊社では、現在年間約100社近い企業の従業員満足度調査の実施や分析、経営やラインへの報告会などの実施をサポートしており、お客様が自社の結果を分析するための一つのツールとして、2006年1月から12月までの1年間にご利用いただいた企業の平均値をリファレンスデータとして提供しています(提供可能なデータの種類などは、別途お問い合わせください)。
リファレンスデータでは、総合満足度が3点台の半ば、仕事の充実感が3点台の後半と、比較的高い水準になっています。「従業員満足度調査」を外部に委託して実施しようという企業であり、「従業員満足度」に対して比較的熱心な企業が多く含まれているという側面もありますが、これを見ても満足度の点数については、まずまずの結果となることが少なくありません。
従業員満足度の結果そのものに注目することは当然ですが、企業を取り巻くステークホルダーとして顧客や株主についても重視していることを勘案すれば、顧客満足度を高めることや会社業績を向上させることなど各社が直面している事業課題や組織課題に照らして解釈することが重要です。
またその企業の競争優位を支えている機能を強化するという観点から、何がその会社の組織・人事領域における優先度の高い課題なのかを十分に議論し、その上で従業員満足度調査の結果を解釈することが不可欠となります。 弊社が提供している「ESサーベイ2」では、従業員満足度に影響を与える諸要素(仕事、職場、上司、会社に関する合計30の要素)の現状と従業員の重視度についても集計し、報告しています。一見検討する要素が多くて分析が複雑になるように見えますが、より深い解釈を行うためにはこれら諸要素の結果が把握できることが重要です。
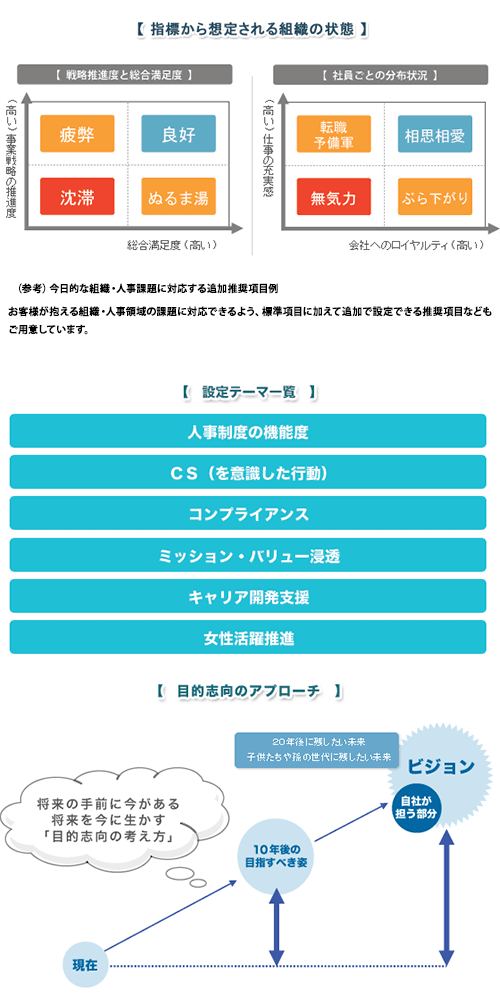
従業員満足度の向上に取り組んだ事例のご紹介
●通信販売会社A社のケース
ネットやマスメディアによる家電やPC、DVDなどの通信販売を主力とするA社。顧客接点を支えるコールセンターで働くテレコミュニケータの従業員満足を高めたいと考えていたが、ESサーベイ2の結果はコールセンター部門が全社で最も低いというショッキングな結果に。 経営TOP層へのヒアリング、センターのマネジャークラスとのブレストを行い、下記の原因を特定しました。
1.コールセンターの社内における位置付けが低く、他部署から異動してきたマネジャーのモチベーションも低下している
2.社長直轄の組織としていたものの、経営TOPはあまりセンターに足を運ばず、スタッフと直接話す機会が皆無
3.テレコミュニケータのマニュアルの校正が甘く、多くの修正が入り、現場において無用な混乱を引き起こしている
4.テレコミュニケータの評価・処遇制度があいまいであり、昇給も勤務して数年以内に頭打ちになる
打ち手と効果
まずは経営TOP自ら、コールセンターの社員全員にESサーベイ2の結果を説明し、今後の改善を約束しました。そしてコールセンターのマネジャーを対象としたセッションを開催。マネジメントにおける迷いや士気の低さが、センター全体に及ぼしている影響について直視してもらうとともに、今後の自分たちのマネジメントのあり方について議論し、方針を定めました。具体的にはセンターが効率的に運営されることの重要性を全社で確認し、マニュアルのミスを大幅に引き下げるプロジェクトを発足。テレコミュニケーターの評価基準を明確にし、昇給や賞与(寸志)の仕組みを整えました。
その結果、経営TOPやセンターの責任者と、コミュニケーターの皆さんとの心理的な距離感が縮まり、現場の問題点が早く吸い上げられ、対応が早まりました。導入した評価制度、昇給制度も概ね好評であり、単位時間あたりの対応数や制約率など目に見えて改善されるケースも出始めています。
●法人営業会社B社のケース
法人向けサービスを提供する会社の販社部門が分社化して設立されたB社。数多くの営業所を抱えており、上司のリーダーシップの巧拙、仕事の充実感の高低が、各営業所の業績と関係が深いのではと推測していたが、実際に業績と最も関係があったのは、「仕事の負荷の大きさ」であり、職場のバイタリティ、上司の課題形成にも業績との一定の関係が見られました。
各営業所のおかれた現実
1.各営業所の営業スタッフは経験の浅いメンバーが多く、営業所長との間に歴然とした経験、スキルの差がある
2.短期的な業績向上を重視するなかで、マネジャーによる徹底した行動マネジメントが行われている
3.どの業界を攻めるか、といった営業戦略も個々の営業所に任されている
調査の分析からわかったこと
1.単純化された営業スタイルなので、当面はメンバーの行動量=業績という関係が成り立つ
2.徹底した行動マネジメントの副作用として、メンバーの疲弊感につながり、定着率が悪化することもある
3.営業所長が適切な業界への営業を指示している営業所では、結果につながりメンバーの充実感が向上しやすい
打ち手と効果
ともすれば単調になりがちな営業スタイルに配慮し、結果を個人単位や組織単位でゲーム感覚で競いあうなどメンバーが興味を持てるような工夫をしました。またどの業界を攻めるのかは、本社の営業企画がシナリオを描き、標準企画書や営業ツールなども全社で用意し、営業メンバーの工数を軽減しました。 営業のステップとして、顧客である企業に対して一社一社ソリューション提案を仕掛けるスタイルの組織も立ち上げ、ベテランの営業を配置するとともに、若手メンバーにも将来のキャリアとして示せるように工夫しました。
これらの取り組みにより、営業社員の仕事における負荷は低減されるとともに、若手社員の定着も向上しました。
組織全体のマネジメント能力を高め、ミドルの負荷をコントロールする
弊社のESサーベイ2をご利用いただいた企業の結果分析から、各社において総合満足度との相関が高い要素の多くが、上司に関する要素となり、中でも対人マネジメントに関する要素となる可能性が高いことがわかっています。上司の対人マネジメントは、部下一人ひとりに対するマネジメントであり、上司と部下との関係を決定します。また個別マネジメントを通じて、職場の雰囲気にも大きな影響を与えることは容易に想像がつきます。
さらに、会社に関する側面には、経営トップ層のリーダーシップが含まれますが、これが機能するかどうかは、現場と経営をつなぐミドルマネジャーの役割が極めて重要です。
総合満足度は、仕事・職場・上司・会社というそれぞれの側面における総合結果なので、幅広い側面に直接、間接に影響を与える上司のリーダーシップが、全体の鍵を握ることは当然ともいえます。
一方、現在のミドルマネジャーは、ラインのマネジメントのみならず、プレーイングマネジャーとしての役割も担い、仕事における負担感は総じて高くなっています。また非正規従業員の増加や、メンバーの年齢構成のゆがみ(自分よりもキャリアの長い部下の存在や、ミドルを支える係長層の人材不足など)からマネジメントの難しさはかってなく高度化しています。
従業員満足度を支えるキーファクターではありますが、ミドルの頑張りにのみ期待するのはむしろ危険であり、ベテランメンバーの組織貢献意識を高め、若手社員のOJTに積極的にかかわらせること、若手メンバーにも組織の一員であるという意識を持たせ、主体的な仕事の進め方を促すことなど、組織全体としてのマネジメント力を高めることが重要です。
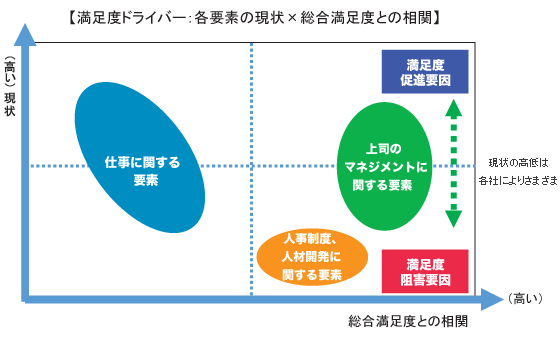
組織力向上の入口としての従業員満足度
「従業員満足度を向上させたい」という表現は同じでも、その背景にある経営層や人事部のニーズは、会社のミッション、ビジョンや事業戦略を浸透させ全社に徹底させたい、顧客第一主義に立ち返りCS向上を意識した行動を徹底したい、会社の将来の基盤強化に向けて若手社員が成長できる組織運営を行いたいなど各社によりさまざまです。
また仮に漠然と従業員にとっていい会社にしたいというニーズであっても、従業員満足度の向上のためには、ミドルのリーダーシップや経営層とラインとの心理的距離感を縮めることなど、全社レベル、部門レベルの組織・人事課題に議論が集約されていくことになります。そういう意味では、従業員満足度は、組織として達成すべきゴールでもあり、組織力向上に向けた入口でもあるといえます。
「組織全体として自分たちはどうありたいのか」。従業員満足度をマネジメントするということは、組織本来が問い続けなくてはいけない本質的な取り組みであり、まさに目的志向でのアプローチそのものといえます。目的志向において、経営幹部が取り組むべき課題は、「将来のために緊急度は低いが、重要性が高い仕事」であり、これを怠ると、組織の活力が失われ、優秀な社員が離れていく原因となります。従業員満足度の議論は、いろんな立ち場の方が、いろんなレベル感や時間軸で議論することが可能です。それだけに、経営を担うトップや企画セクションのスタッフは、「今の問題をどうする」という原因志向の議論に終始することなく、継続的な事業成長を意図した目的志向での議論をしっかりと行うことが重要だといえるでしょう。
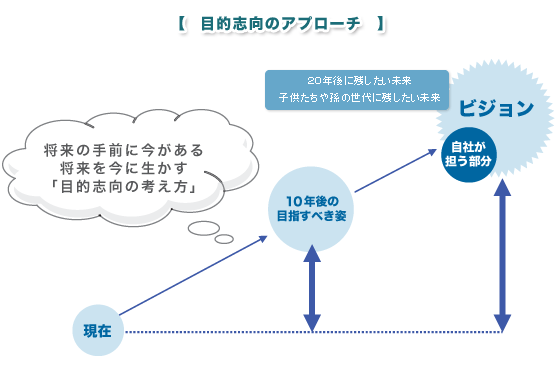
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


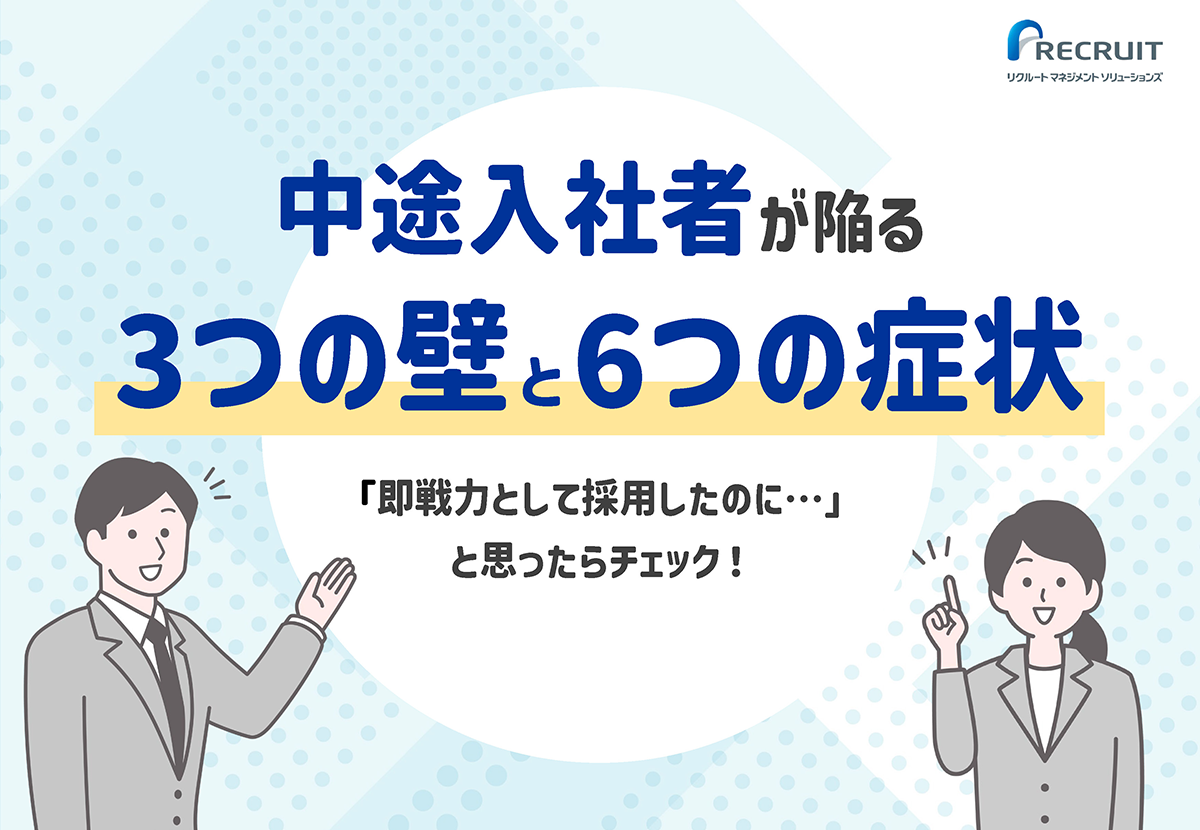
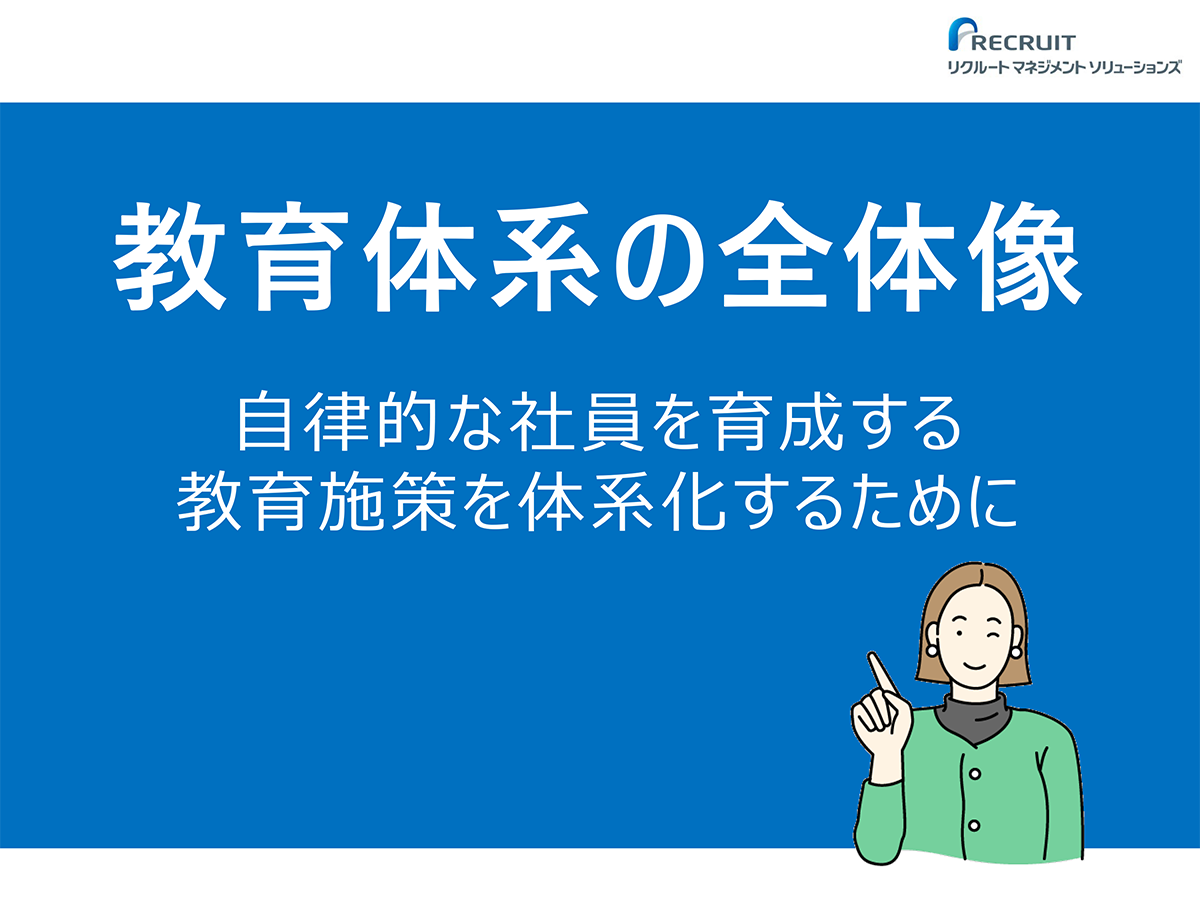
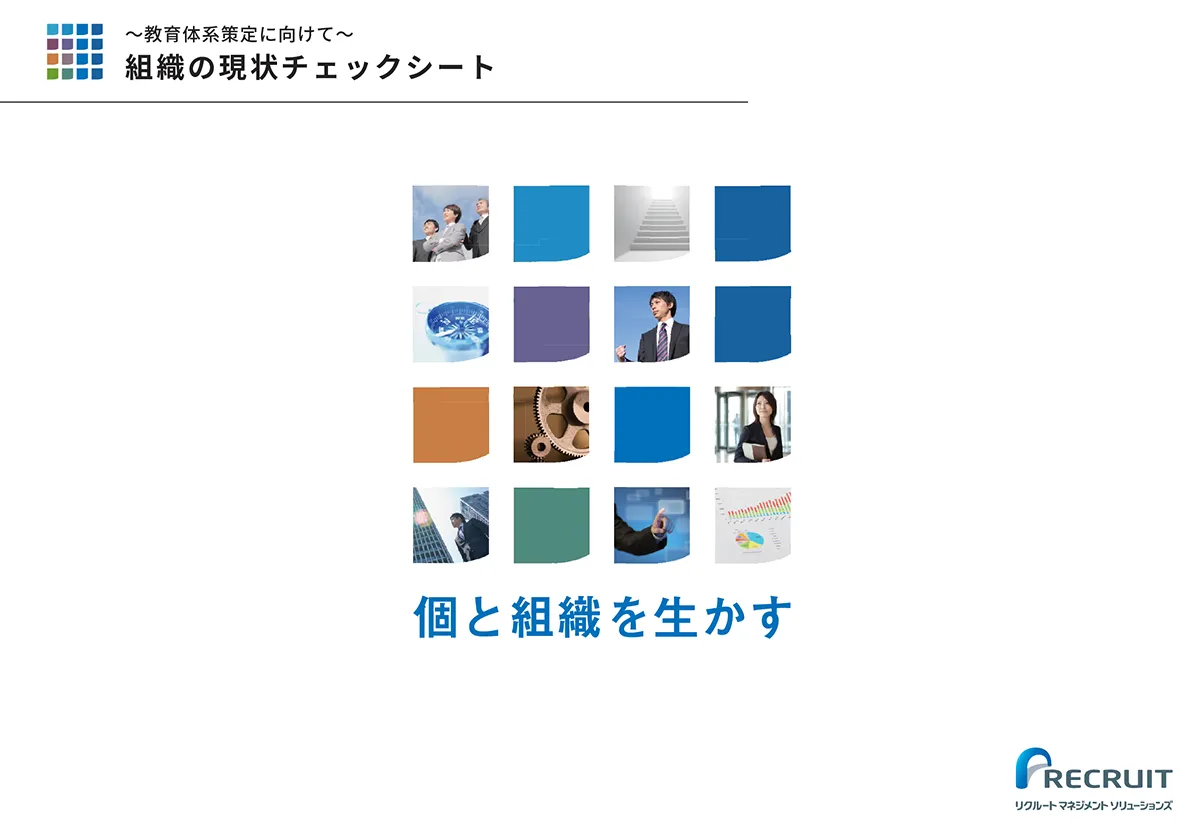









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての