特集
キーワードは「女性」「若手」「50代」
データが語るキャリアデザインの可能性
- 公開日:2007/05/01
- 更新日:2024/05/16

弊社がキャリアデザイン研修にキャリアカウンセリングを加えたトータルのキャリア自律支援サービスを提供し始めて2年になります。ここ数年、企業が従業員のキャリア自律支援、キャリアデザイン支援を行うのは30代、40代のミドル・中堅層が中心でしたが、最近の傾向としてさまざまな対象者にキャリア自律支援サービスが求められてきています。本特集ではこの2年間、弊社で提供したキャリア自律支援サービスの受講者の分析※を通じて、どのような傾向がみられるのか、その背景、今後予想されるトレンドをみていきたいと思います。
※今回のデータ分析の対象としたデータは、2005年4月から2007年3月末日までの2年間で弊社のキャリア自律支援サービスを受けられた方を対象としています。なお数字の表記につきましては、1万未満の数値は上2桁表示(未満は切り捨て)、1万以上の数値は上3桁表示(未満は切り捨て)とさせていただいております。
- 目次
- キャリア自律支援サービスの受講者の推移と傾向
- どのようなテーマが寄せられているか
- 今後の方向性を探る
- さまざまなニーズに応えられるキャリア自律支援サービス
- キャリア自律支援施策を成功させるポイント
キャリア自律支援サービスの受講者の推移と傾向
1.この2年で延べ2万5000名が受けられたキャリア自律支援サービス
サービス受講者の推移
まず下記の表1をご覧ください。この2年間で取引社数が120社から160社、延べサービス受講者数が1万500名から1万5100名に増加しています。この伸び率からも、多くの企業の関心が高くなっていることがお分かりいただけると思います。
キャリアカウンセリングについては以前の特集でご紹介していますが(「人材開発におけるカウンセリングの活用」)、対前年比150%と大きく伸びていることが見て取れると思います。キャリアカウンセリングについては、カウンセリング単独で導入していただいている例がもともと多かったのですが、この2年の傾向ではキャリアデザイン研修と組み合わせて導入されるケースも増えております(表2)。この背景は後述いたします。
今回は、弊社のキャリア自律支援サービスの受講者のデータに基づき、具体的にどのような業種や規模の企業がどのようなテーマで施策を講じているのか、また、なぜ今キャリア自律支援施策が求められているのかを考えていきたいと思います。
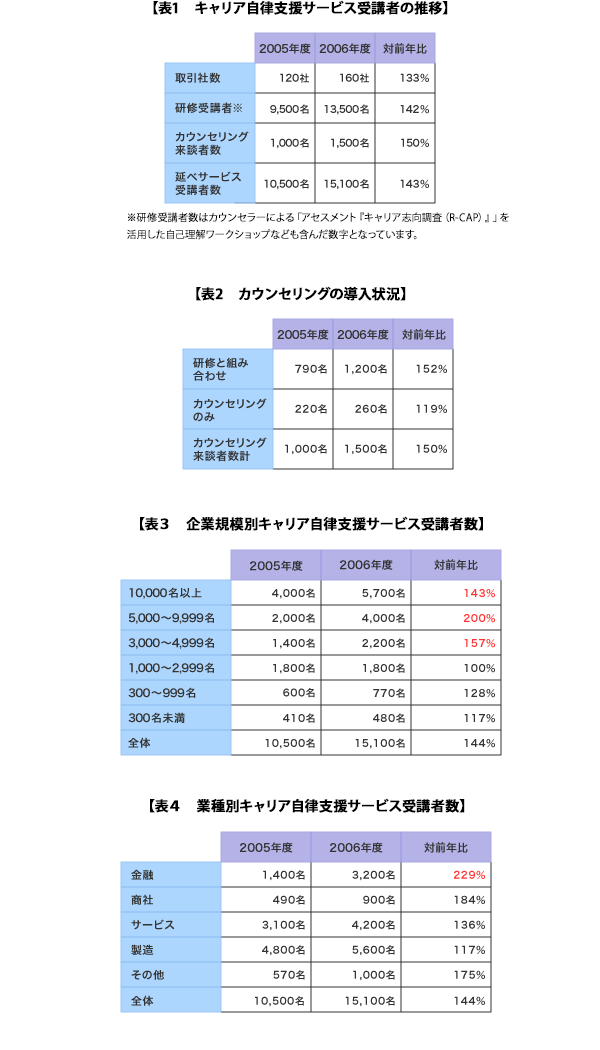
2.従業員規模別・業種別にみた傾向
3,000名以上の企業・金融業界での導入が伸張
まず企業規模別の特徴を見ていきましょう。表3は企業規模別のサービス受講者数です。
特徴としては3,000名以上の企業の伸び率が高いことから、従業員にキャリア自律支援施策の展開を実施している企業は、ある程度の規模の企業が中心となっていることが分かります。中でも5,000名以上の大手企業がこの2年間では特にキャリア自律支援施策を推進させていることが見て取れると思います。
では、より詳しく状況を整理するために、続いて、業種別に傾向を見ていくことにします。対前年比(伸び率)の高い順に業種を並べると以下のとおりになります。(表4)
業種別にみてみると、最大の特徴は金融業界での受講者数が急増していることです。銀行、証券、生命保険、損害保険など業態は分かれますが、業態を問わずここ数年の大きな統合、それに伴う人事制度の変更など大きな変化を経たあと、従業員に求められてきているのがまさにキャリア自律の意識の醸成です。これまで金融機関というと一般的には企業主導で配属が決められ、キャリアパスが設定されていくというイメージが強かったところですが、グローバル化が進行し、サービスが高度化するといったこれまでの環境と大きく変わっていくなかで、従業員が働くことの意味を問い直し、主体性を発揮し、プロフェッショナルとして活躍することを考えてもらいたいという狙いのもとに、従業員が自らのキャリアをデザインしていくことが強く求められています。受講者数の絶対数で多い製造業やサービス業に次いで、いよいよ金融機関も動き出したという状況が見て取れると思います。
どのようなテーマが寄せられているか
1.テーマ別の傾向
弊社では企業からサービスの導入をご相談いただく際に、どのようなテーマで施策を導入したいかをお聞きした上でサービスを提供していますが、そのいただいたテーマに基づいて伸び率が著しい研修の受講者数を集計したのが下の表(表5)になります。今回便宜的に分類をしましたが、多少重なるテーマの場合(50代女性など)は、いずれか重きを置いているテーマに分類をしています。
グラフ1をご覧いただいてお分かりのように、受講者の数でいえば、「30~40代」がボリュームゾーンとなりますが、「女性(対前年比:267%)」、「中高年(50代)(同:210%)」 、「若手(同:200%)」、 「有期雇用(同:189%)」、「管理職(同:180%)」の伸び率が著しい状況を示しています。以下、その各テーマの特徴をみていきたいと思います。
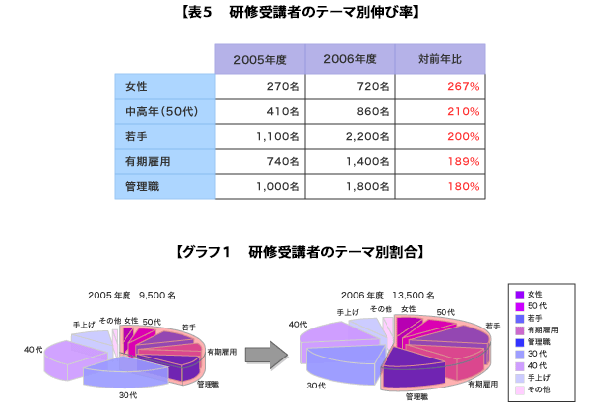
2.伸び率が著しいテーマ
【女性】
以前の特集(「女性活躍推進の先にあるもの」)でもご紹介していますが、昨今多くの企業が、女性の活躍できる環境づくりに取り組んでいます。
施策を整える一方、女性従業員の意識醸成が重要だという認識が広がっています。
しかし一方で、女性従業員からは「制度が変わったからといわれて、急にこれから先のことを考えろといわれても、何を手がかりにどう考えてよいか分からない」、「ロールモデルとなる先輩と接する機会がないのでこれからどう取り組んでいけば良いのか見えない」「これまでの働き方を変えるのは怖さがある」などの声があります。
このような状況下、会社としても支援のための施策(昇進の可能性の拡大や先輩社員との交流会など)を展開するので、個人側の意識の醸成のための手立てとしてキャリアデザイン研修が位置づけられてきています。
「これまで以外の選択肢を考えるのも悪くなさそう」と考え始めたり、「改めて自分らしい働き方をはっきりさせて前向きに仕事に取り組みたい」などといった自分の可能性を広げるような意識を醸成する方策として、キャリアデザイン研修に期待が寄せられています。
【50代】
50代を対象とした研修は、これまでは年金・保険などのファイナンシャルプランニングなども含んだ、退職後の生活を考えるライフデザイン色の強い研修がほとんどでした。
この層が増えた背景には、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、企業ごとに定年制度の変更、再雇用・継続雇用の制度を整えつつあることがあります。それに加え、団塊の世代の引退が企業の労働力や技術伝承の観点からも大きな影響を与えることが予測されているなかで、従業員に再雇用や継続雇用も含めた60歳以降の働き方・生活を考えてもらう必要性が高まってきています。
そのため、多くの企業がこれまで50歳代に提供していたライフデザイン的な研修とは趣を変えて、その人自身が自分の60歳以降の働き方を含めたキャリアについて考える研修が望まれるようになってきています。
【有期雇用】
雇用形態の多様化に伴い、終身雇用の従業員以外の契約社員の形態で働く従業員も増えています。
あえて契約社員を選択している従業員は、その限られた期間の中でどのような力を身につけたいかを考え、それを意識した上でどのようなパフォーマンスを示していくかを考えることが重要となります。ある意味、その期限の限られた期間のなかで有期雇用の従業員側がその会社や組織をどう有効に活用できそうかを考えることが重要となってきます。
そういった関係性の中で、企業側も有期雇用の従業員を単なる労働力としてみるのではなく、限られた期間にどれほど充実した職業生活を送ってもらうかが施策を継続する上でも重要となっています。
その意味合いからも企業側でもそれをサポートする必要性がめばえてきています。
【若手】
以前より若手社員の離職問題が人事上の課題として多くの企業で取りざたされていますが、若手社員に対してのキャリアデザイン研修を導入し、「改めて自分らしい働き方とは何だろうか」、「今の仕事を見直してみると将来につながりそうなことがありそうか」などを考え、働くことの意味をとらえ直すことによって、結果としての離職を防ぐことを意図して実施されている企業もあります。
また最近の特徴として挙げられるのが、いったん全社的にキャリアデザイン施策を各節目となる世代(30歳前後、40代半ば、50歳など)に導入している企業の中で、それら節目の世代に加えて若手に実施されることも増えてきています。前述のように自分の仕事の意味をとらえ直すためもありますが、そこで中心となるテーマは、『なぜキャリアを考えることが会社で求められているのか』、『キャリアを考えることの重要性』といったテーマへの意識付けを行うことを主眼に置く企業も出てきています。
早い段階からキャリアを考えることの必要性を喚起することにより、今後の節目節目でのキャリアデザインについての意識を高めていくことも、重要な施策となってきていると思われます。
3.管理職のキャリアデザイン
【多様な人材を支援する管理職のキャリアデザイン】
以上述べてきたようなテーマの層とともに増えているのが、管理職対象のキャリアデザイン研修です。
その背景の一つはこれまでの流れをご覧いただいてお分かりの通り、女性従業員であったり、若手社員がキャリア自律支援施策の一環としてキャリアデザイン研修を受講した後に、そのメンバーが『今後このような方向性で自分自身のことを考えていきたい』と考えていたとしても、上司自身が『メンバーはどのような研修を受けてきているのか』『なぜキャリアを考えることが必要なのか』などをしっかり押さえた上でないと、これまでの旧来の価値観・パラダイムで対応してしまい、せっかく研修でメンバーが考えてきたキャリアプランを「無理だ」とか「これまでの経験から君はこうなるはずだ」など、メンバー個人のプランを簡単に否定してしまったりすることもあり得ます。
メンバーの直接の支援を行うのは、やはり職場の上司といえます。そのために上司自身が自分のキャリアも考え、そこで得られた視点をメンバーとの面談に生かしたり、さまざまなメンバーの支援に携わることを期待して、管理職向けのキャリアデザイン研修の数が増えている状況です。
また、管理職である上司がリーダーシップを発揮する上でも、自分自身のビジョンを物語り、人をひきつけていくことも求められます。そのときにもベースとなるのは個人の「どうありたいか」、「何をしたいか」の想いだったりします。そのためにも、管理職である上司が自分自身のキャリアをしっかり考える必要性も高まってきています。
今後の方向性を探る
キャリアが中軸となる制度設計をする企業も増えていく
以上、弊社のサービスの状況から最近の流れを見てきましたが、キャリアのテーマは企業で働く従業員のさまざまな層に対して求められてくる様子がうかがえます。このような多様な層への支援はますます必要性が高まってくると思われます。
多様な価値観をもつさまざまなメンバーが仕事へのモチベーションを高め、コミットメントを高める上で、改めて自分自身を理解し、主体的な動き方を考えていくことは企業で働く従業員にとっての基盤的な研修となってくることが予想されます。事実、いくつかの企業では、人事施策の中心を「キャリア」において研修体系を再構築することも起こり始めています。
そのような状況の中で、雇用形態も年齢も性別もばらばらなメンバーを管理職が支援をするにあたって、自らのキャリアを自分自身が考えることも引き続き大きなテーマになっていくと思われます。管理職であるリーダー自身が自分のことを「内省」することは、管理職のリーダーシップに寄与するところは大きくなると思われます。
個別性の高い問題を扱うカウンセリングも重要なファクターに
一方で、そのメンバーの支援すべてを一人の管理職に任せることは相当高い負荷を与えることにもなります。キャリアの問題は個別性が強く、また場合によってはキャリアデザイン研修の限られた時間・空間の中では解決できない問題が含まれていることも往々にしてあります。
そのような個別性が高く研修の中で解決できない問題に対処するために、また、研修で立てた目標の実効性を高める方策の一つとして、キャリアカウンセリングが導入されることも増えています。キャリアをテーマにした研修とカウンセリングの利点と課題をまとめたのが下記の表6になります。
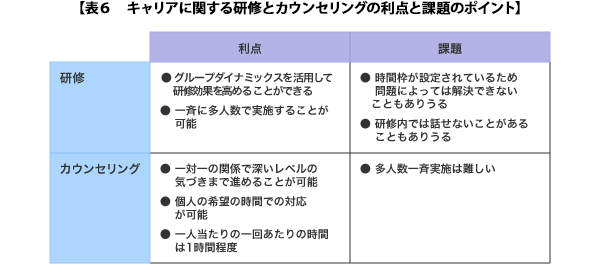
さまざまなニーズに応えられるキャリア自律支援サービス
以上のようなさまざまなテーマで個別性の高いキャリアに関する問題に対応するために、弊社では以下のようなコンセプトでサービスを提供しています。
個別のニーズに応える最適な組み合わせ
企業ごとに立てたい狙い、従業員の層・状況の違いを考慮した場合、一律のキャリアデザイン研修を導入していくことは効果が不十分になってしまうことも起こり得ます。そのために、研修の狙い、従業員の状況に即して研修のセッションやツールを組み合わせることが重要となってきます。
そのために、弊社のキャリアデザイン研修ではセッションやツールをモジュール化し、各企業ごとのならい・求めたい状態に合わせて最適な形で組み合わせた提供が可能です。(図1)
研修に加えたキャリアカウンセリング
またキャリアデザイン研修だけで解決できない問題を解決したり、研修の効果を高める上では、個人-個人の関係性の中で細かなフォローアップを行うことも重要になってきます。(図2)
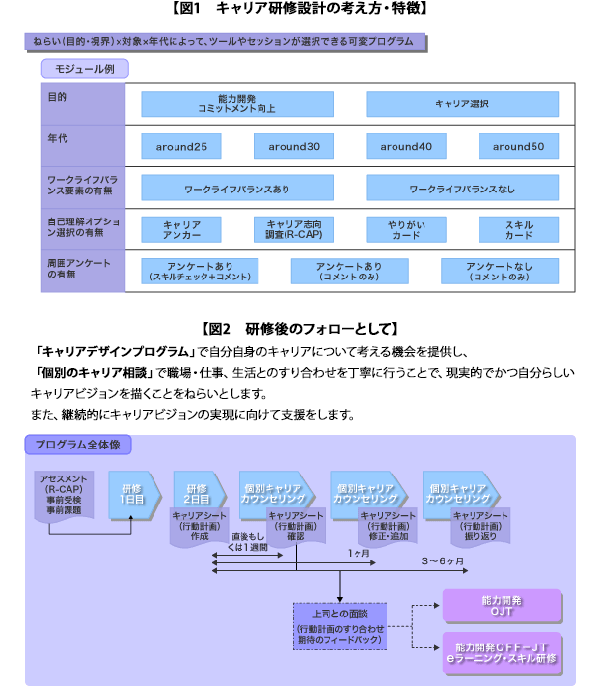
キャリア自律支援施策を成功させるポイント
キャリアデザインを促進する風土の醸成が重要
最後にもう一つキャリアデザイン施策に特徴的なデータをご紹介します。弊社の研修が終わった際に受講者の方にアンケートをお願いしていますが、そこにキャリアデザイン施策を効果的に進めるためのヒントがあります。
このデータを見てみると、他の研修に比べキャリアデザイン研修は、1)研修目的に対する理解、2)参加への期待をどう高めるかが各企業の抱える問題点といえます。ただ実際に参加してみると非常に良かったと満足していただける方も多く、目的理解と満足度のギャップ、参加への期待の満足度のギャップが大きいのが特徴といえます。
やはり個人の問題でもあるキャリアをなぜ企業が支援するのか、その必要性をいかに従業員に伝えていくのかが、今後キャリア自律支援策を推進する上では重要だと思われます。
下記E社のように研修目的に対する理解がある程度伝わり、参加への期待が高まった状態で受講すれば、それだけ持ち帰るものも多くなることが予想されます。
制度が整ってきた今、経営層からもキャリアを考えることの重要性をアナウンスしつつ、管理職もキャリアの問題を自分の問題としてとらえ、メンバーも主体的にキャリアを考えて日々の仕事に取り組める『キャリアデザインを促進する風土・カルチャー』をいかにつくっていくかが、今後の課題になっていくと思われます。
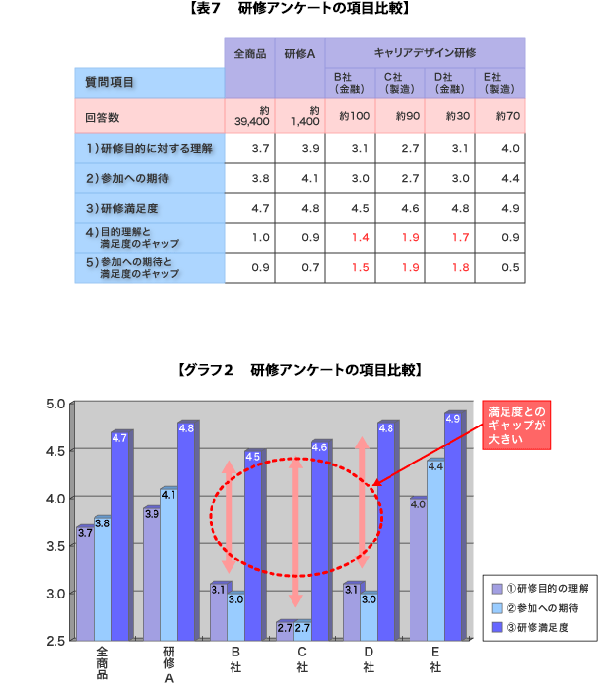
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



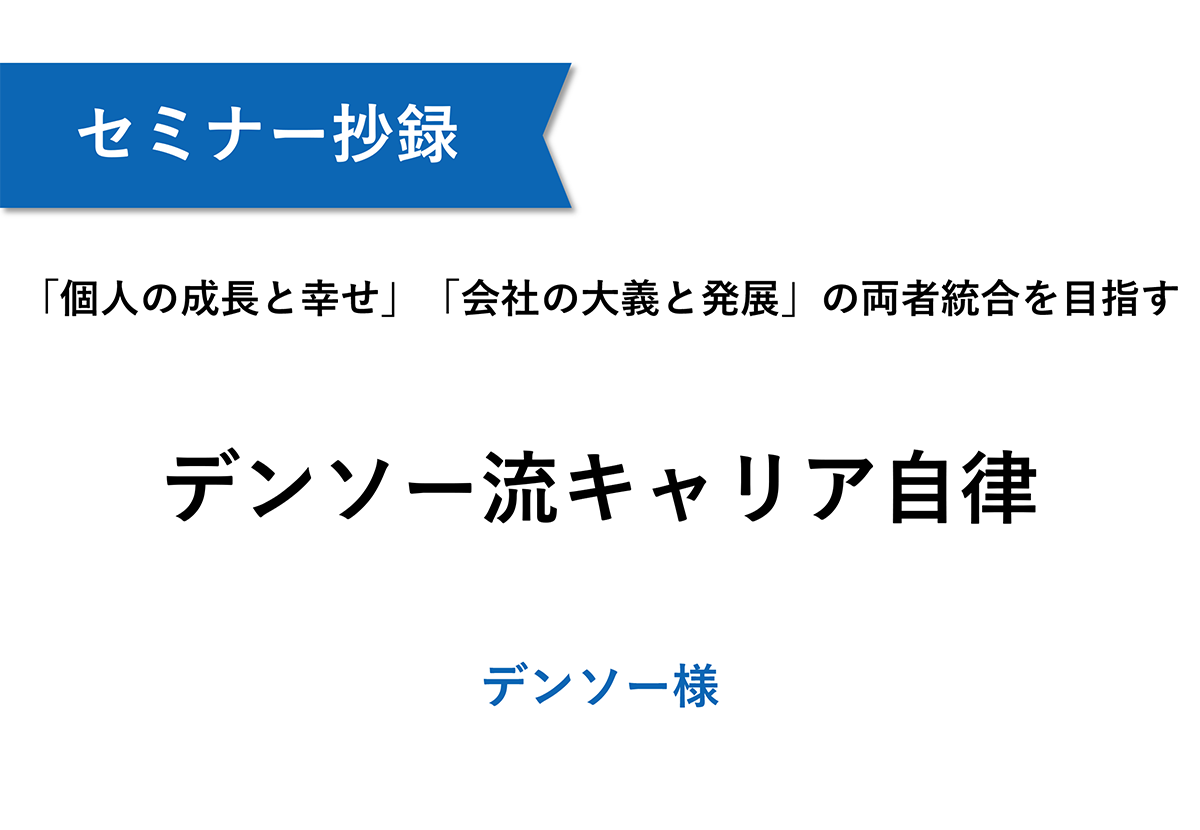









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で