特集
“自分ごと”を引き出すマネジメントのポイントとは
今改めて、「目標によるマネジメントの実践」を考える
- 公開日:2009/05/11
- 更新日:2024/04/11

成果主義の象徴的な仕組みでもある目標管理制度。導入率は80%を超えたともいわれます。企業で働く人に「目標とは?」と尋ねると、「必ず達成すべきもの(≒ノルマ)」「会社・上司との契約・約束」「達成度に応じて評価が変動し、賃金などの報酬を左右するもの」「上位組織からブレイクダウンされてくるもの」などと答える人が多いようです。
高い業績圧力のもと、マネジャーとメンバーの間で目標をめぐって交わされる会話も「目標を達成できるかどうか」だけを中心に据えたものとなり、ともすると育成的観点でのかかわりが希薄になりがちです。
また、今後ますます業績へのプレッシャーが高まるにつれ、業績への責任感が強いマネジャーであればあるほど、自然と「目標を達成できるかどうか」に関心が集中する傾向は強まると思われます。
しかし、「目標の達成」をめぐる会話に終始するマネジャーのかかわりだけで、「これは、何としてでも取り組むんだ!」と本気になって仕事に向かえるメンバーは限られています。
では、メンバーが「目標」を“自分ごと”と捉えて取り組み、前に進むことを支援するマネジメントのポイントとは何でしょうか
今回の特集では、目標をめぐるコミュニケーションに焦点をあて、「メンバーが『目標』を“自分ごと”と捉えて取り組み、前に進むことを支援するマネジメントのポイント」をご紹介します。
- 目次
- メンバーが目標を“自分ごと”と捉えて前に進む3+1のポイント
- 目標を意味づける2つのアプローチ
- 取り組むこと自体へ動機づける ~陥りやすい罠~
- チームをつくり、チームの力で動機づける
- 事例:ある企業で起きた、小さくも大きな変化
メンバーが目標を“自分ごと”と捉えて前に進む3+1のポイント
メンバーが「これは自分の目標」と思って、本気で取り組むのはどんなときでしょうか。
弊社では、以下の3つのパターンと、その前提として「マネジャー自身の目標の捉え方」があると考えています。
【図表1 目標を“自分ごと”と捉えて前に進む3つのパターン】

まず、前提である「マネジャー自身の目標の捉え方」については、「目標=必ず達成すべきもの(ノルマ)」とだけ捉えるのか、「目標=組織の目標達成につながるものであると同時に、メンバーにとっての意味、育成・成長視点を込められるもの」と捉えるのかで大きく違ってきます。業績圧力が高まるほど前者に偏りがちですが、マネジャーの目標の捉え方が広がることで、目標に込める意味、メンバーとの会話やかかわり方が随分と変わります。
この前提を押さえた上で、上記3つのパターンを、各メンバーに合わせて使いこなすことが、「目標」を“自分ごと”と捉えて前に進むことを促すマネジメントのポイントです。
次のページからは、事例も交えながら、各パターンのポイントを見ていきたいと思います。
目標を意味づける2つのアプローチ
1. メンバーの成長ステージから考える
「Aさんに取り組んでほしいこの目標は、事業の次の中核商品が育つかどうかを決める大事な目標。大変だがこれに取り組むことはきっと君のためにもなる!」Bマネジャーが一生懸命語っています。しかし……。
目標の背景や意味を伝えようと、このような会話をすることがあるでしょう。Bマネジャーは「会社・事業にとっての意義」の視点から目標を意味づけ、会話をしています。
メンバーによってはこの視点からの意味づけだけで目標にコミットできる人もいます。しかし、「会社・事業にとっての意義」の視点だけで、“自分ごと”として「この目標に取り組もう!」と動ける人ばかりではないのが現実です。
では、ほかにどんな視点があるのでしょうか。ここでは2つのアプローチをご紹介しましょう。
【1】「メンバーの成長ステージ」に合わせて目標を設定し、意味づける
【2】「仕事の意味・価値」の視点から目標を設定し、意味づける
●「メンバーの成長ステージ」に合わせて目標を設定し、意味づける
次のようなメンバーがいたら、どんな意味を込めた目標を設定しますか?
Cさん
仕事もわかってきて意欲的に取り組むのはいいのだが、いろいろ手を出しすぎて中途半端で終わっている
このメンバーには、例えば次のような意味を込めた目標が考えられます。
【図表2 メンバーの成長ステージ】

「メンバーの成長ステージ」とは、「新入社員から管理職直前までにたどる幾段階かの状態」をいい、一般的には8段階程度あります。最初の段階は「入社して間もない頃、業務に必要な知識や技術もほとんどなく何をどうしていいかわからず戸惑うことが多い」、そんな状態が最初の段階です。これを乗り越え幾つかのステージを経ると、上記のCさんの状態に陥ったり、それを突破してもまた次の段階があり……と成長の過程には幾つかのステージがあります。
各メンバーが今どのステージにいるのか、次のステージに進むためにこの目標を通じて何を掴んでほしいのか、メンバーを「成長ステージ」という視点から見て適切な目標を設定し意味づけます。
2. 仕事の意味・価値から考える
●「仕事の意味・価値」の視点から目標を設定し、意味づける
初めて仕事の意味や価値、面白さ、やりがいを感じたのは、どんな場面だったでしょうか。
ある会社の研修では、こんな場面が紹介されていました。
・「社会人2年目。社内の数人から『あのシステムのおかげで仕事が楽になった、ありがとう』という言葉をもらった。使う人のことを考えて工夫するって面白い。今から思うと、スタッフの仕事の面白さを実感した場面だった」
・「公園で、お客様が家族で自社の商品を『美味しい!』と笑顔でほお張っている場面を見て。家族団らんの時間に少し貢献できている気がして嬉しかった」
「この仕事ってこういう価値があるんだ!」と発見してからより仕事が面白くなったというだけでなく、「何のためにこの仕事をしているのだろう」と迷った時に立ち戻る先になっているという方もいました。
その仕事の面白さや価値を感じられる場面は企業・職種などによりさまざまですが、「これらを経験できる確率が高いテーマや領域」に目標を設定し、メンバーが仕事の意味や価値、面白さ、やりがいを自ら発見して仕事にのめり込んでいくことを支援します。
●マネジャーが意図的に機会をつくり、かかわることが必要
しかし最近は、環境の変化が速く、仕事の意味や価値を実感しないまま、どんどん次の仕事に進む傾向が強くなっています。また、仕事の意味や価値を実感しうる経験をしていても、一人で自覚するのが難しくそのまま次の仕事に紛れてしまうことも多々あります。
ゆえにマネジャーが意図的に機会をつくることが必要です。機会をつくるとともに、メンバーがその場面を経験したら、それを見逃さずかかわり、自覚化を手伝うことがポイントです。
ここまで目標を意味づける2つのアプローチをご紹介してきました。とはいえ、すべての目標に何かしらの意味づけを行うのは難しく、時には目標に意味を感じられないこともあります。しかし、目標そのものに意味を感じなくても、「取り組むこと自体に動機づけられて前に進めること」も多くあります。それはどんなときなのでしょうか。
取り組むこと自体へ動機づける ~陥りやすい罠~
目標そのものには意味を感じなくても、取り組むこと自体には動機づけられて前に進めるときがあります。挑戦的で難しい目標であっても、「このお客様に認められたい」「信頼しているこの上司から言われたら」などが動機となって、不安があっても乗り越えられるときがあります。
●取り組むこと自体へ動機づける際のポイント ~陥りがちな罠~
では、取り組むこと自体へ動機づける際のポイントは何でしょうか。陥りがちな罠がいくつかあります。
例えば、
「“できない理由・動けない理由”に着目、それをつぶそうと“もぐらたたき”」
などは、ついやってしまいがちなことです。
しかし、メンバーの立場に立って「できない理由」を挙げるとどうでしょう。「忙しい」「うまくいくイメージが持てない」「不安」など、きりがありません。それを“もぐらたたき”のようにつぶそうとしてもなかなか「できない理由」はなくなりません。でもメンバーの中には「このお客様に認められたい、期待に応えたい」「ほかに取り組めそうな人がいない、自分しかいない」など「動く・動ける理由」もあります。メンバーの「動く理由」に着目することがポイントです。
【図表3 動けない理由-動く理由】

ほかにもマネジャーが陥りがちな罠はいろいろありますが、動く理由は人によってさまざまです。一人ひとりのメンバーの「動く理由」を探し、取り組んでほしい目標との接点をつくり、動機づける。これが取り組むこと自体へ動機づける際のポイントです。
ここまで2つのパターンを見てきましたが、メンバー一人ひとりにかかわること以外にマネジャーができることがあります。
チームをつくり、チームの力で動機づける
「成長ステージや仕事の意味・価値の視点から目標に意味を込める」「メンバーの『動く理由』を知り相手に合わせて動機づける」といった一人ひとりにかかわること以外に、マネジャーができることがあります。それが「チームをつくり、チームの力で動機づける」ことです。
あるマネジャーが語った、こんなエピソードがあります。
・「12時に鳴った1本の電話。それが期末最終日のミラクルの始まりでした。 『競合が強い新規エリアを新人~3年目の10名で攻める』という無謀な組織。商品知識もおぼつかないメンバーが全員、自分の目標に半年間必死に取り組んだ。その甲斐あり、9名は全指標目標達成。中には個人表彰を狙えそうな人もいる。最終日朝には課も売上目標達成。しかしあと1指標『件数目標100件』に2件足りない。その2件はAさんの数字。彼も必死で動いたが、昨日全ての見込みを当たり尽くしてしまっていた。それでも『皆に申し訳ない!』と早朝から飛び出していく。だが飛び込みで当日2件の受注は諸手続もあり高い壁。私は内心、未達成を覚悟していました」
・「ところがこれを、メンバーは見事な連携プレーで乗り越えた。Bさんは自分が受けた新規商談の電話を、Cさんは自分の顧客が紹介してくれた商談に、自分の表彰が懸かった数字を捨てて、Aさんを向かわせた。残りのメンバーはそれぞれ審査の手続役、契約書の運搬役、現況の報告役……と手分けして動き、“Aさんの目標達成による課の目標達成”を実現させた。この時のメンバーの半数は若くしてマネジャーになり、今もいいマネジャーとして活躍しています」
このチームは自然に形成されたのでしょうか? 詳しく話を伺うと、マネジャーは個々人に対する意味づけ・動機づけ以外に、意識してチームの成長を促す施策を講じられていました。
・期初、組織発令されたばかりの時には仕事以外の面も含めてお互いを知る機会をつくる
・ある程度の関係性ができたところで仕事上の悩みや相談をし合える場を定期的に設ける ……etc
このマネジャーは、チームの成長段階を把握して適切な手を打ちチームを育て、チームの力でメンバーが動機づいて、目標の達成に向けて一丸となって前に進める状態を、意図的につくっていたのです。
このように人と同様、チームにも「成長ステージ」があり、そのステージに合わせたマネジャーのふさわしいかかわり方があります。
しかし、ステージに応じたふさわしいかかわり方がある一方で、マネジャーがしてしまいがちな対応もあります。
例えば「せっかくメンバー同士で動き始めているのに、すべての報告を求めて自分に目を向けさせてしまい、マネジャーがチームの成長を邪魔してしまう」などは、ついやってしまいがちなことでしょう。マネジャーだけを見て動いているチームであれば、先のミラクルにつながるようなメンバーの動きは起きなかったかもしれません。
では、このようなメンバー・チームへと成長していくきっかけとなる最初の一歩はどのようなものでしょうか?
事例:ある企業で起きた、小さくも大きな変化
ここまで、「目標をめぐるコミュニケーション場面に焦点をあて、メンバーが『目標』を“自分ごと”と捉えて取り組み、目標達成に向けて前に進むことを支援するマネジメント」のポイントを紹介してきました。 最後に、このテーマでミドルマネジャーを対象に研修を実施された企業で起きた「小さくも大きな変化」を、「受講者のコメント」という形で紹介したいと思います。
この企業では、業績圧力や強烈な効率化の推進、行き過ぎた成果主義の中で、弱体化した現場のマネジメント力・育成力を立て直したいという課題を抱えておられます。
そんな企業で、目標をめぐるメンバーとの会話・かかわり方が変わり、現場のマネジメントが好転していく、小さくも大きな変化が起きつつある事例です。
【ある企業で起きた、小さくも大きな変化】
●自分にとって、新人メンバー=宇宙人。彼・彼女らのことを理解しようとした時期もあったが、いくら歩み寄ろうとしても噛み合わない。組織に大きな支障が出ている訳でもなく、もういいかと最近は半ばサジを投げかけていた。だが、改めて、彼・彼女らは今の目標や仕事をどう感じているのだろう? 楽しいのだろうか? 何に仕事の意味を感じているのだろう? 果たして感じているのだろうか? 気になって仕方がない。目標や仕事をめぐって、彼・彼女らとこんな会話をしたことはなかった。一体どう思っているのか、聞いてみたい、話してみたい。
●普段から目標の意味などはメンバーと話をしているし、メンバーのことはある程度わかっていると思っていた。だが、その自負心は木端微塵に吹っ飛んだ。メンバーが何で動くのか、動く理由に確信が持てない、いや持てないというよりわからない。一体自分はメンバーの何を見て動機づけた気になっていたのか、改めて一人ひとりの動く理由を考え、メンバーの本気を引き出していく。
●いくら「君の成長のため」と言って難しい目標にチャレンジさせようとしても尻込みしているメンバー。サボっているわけではないし、無理に取り組ませなくてもいいかと思っていた。無理強いして嫌われたくないという思いもどこかにあった。しかし、本気でそのメンバーの成長を考えるなら、時には「業務命令」と言って要望し取り組ませることも必要。これはマネジャーだからできること。自分もそうやって育ててもらった。メンバーを小粒で終わらせるか否かの責任は自分にかかっている。
●同時に、メンバーに本気で取り組むことを求めるのであれば、自分自身も目標に本気であることが問われる。そうでないと、できるメンバーほど見透かされる。改めて自分自身が、目標を“自分ごと”として捉えることにも合わせて取り組もうと思っている。
●組織でこれまでやってきた目標共有の浅さがわかった。何を目指すか、何に取り組むか、「コト」を伝えてきただけだった。組織は回っているけれど、自分を中心に回っている。それで何の問題もないと思っていた。だが、自分がいなければ動けない組織をつくっていた。今のメンバーのステージやチームのレベルを考えると、メンバーが自走する力をつけることを自分が奪っていたと気づき愕然とした。最高レベルのチームをつくるには時間がかかりそうだが、目標に込めた思いを共有するところから一歩一歩積み上げていこうと思う
さいごに ~厳しい経営環境だからこそ~
「これは、自分として、何としてでも取り組むんだ!」と本気になって仕事に向かい合っている時ほど人は力を発揮し、結果としてこのような時には成果も上がる確率が高く、取り組んだことを通じて本人も成長します。
つまり、マネジャーから見ると業績達成と人材育成とを両立できる状態に近づくといえます。
厳しい経営環境のもと、限られた人材で成果を上げていくことが今後ますます求められることが予想される中、「目標」を核にして、一人ひとりの力を最大限に引き出し、チームの力で支え合い・高め合うマネジメントがより一層重要になると思われます。
本特集が、マネジメントに携わる方々が目標によるマネジメントを実践される際の一助となれば幸いです。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)




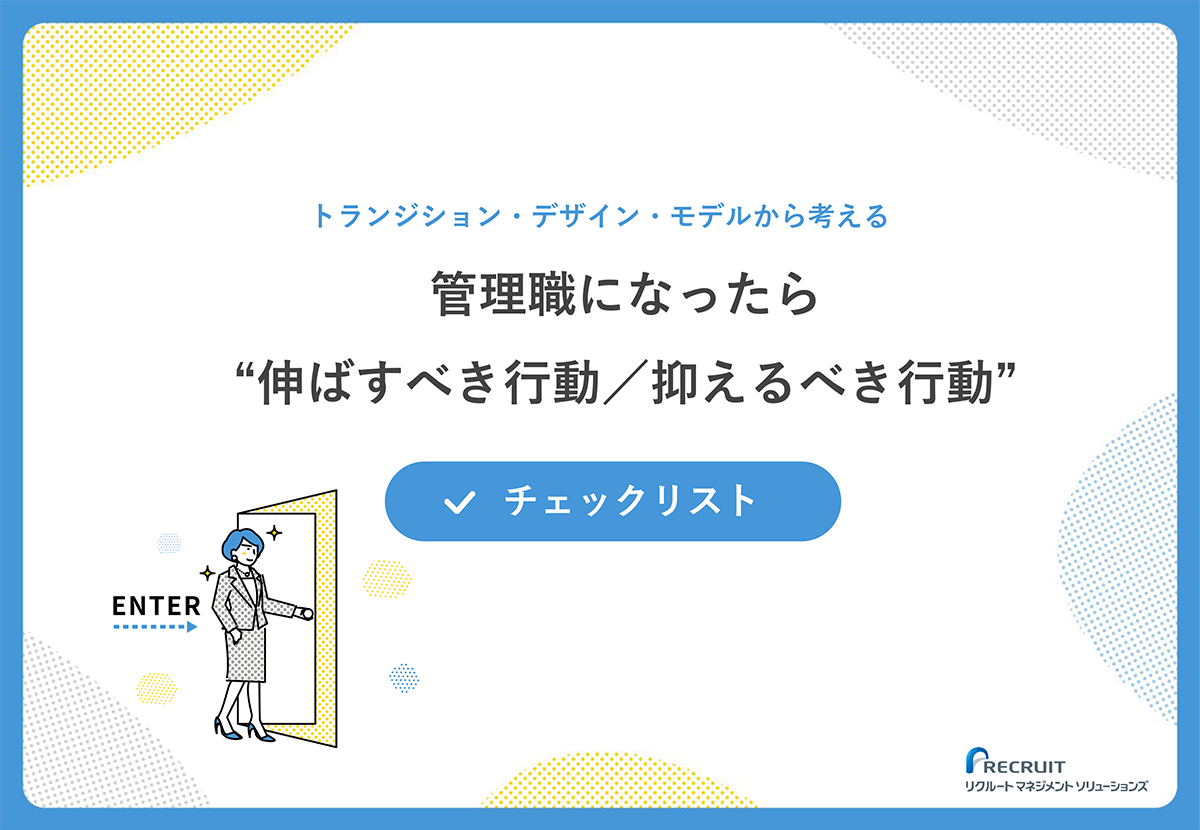









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての