特集
人事担当者必見!昇進・昇格のいま
RMS Research'09昇進・昇格実態調査から
- 公開日:2010/01/08
- 更新日:2024/04/11

人事制度上の要となる昇進・昇格制度。中でも管理職層の登用となると、選考審査の重要性が一層高くなります。貴社の管理職ポストに理想的な人材が継続的に配置され、その結果として、この階層が事業推進の原動力になっていくために、昇進・昇格という制度をどのように設計していくとよいのでしょうか?
昨今の昇進・昇格制度は、「いびつな人員構成」「低成長によるポスト不足」「高度専門職の処遇」など、運用を難しくする要因が複数絡み合っており、その運用上の問題解決を一層困難なものにしています。
「他社はどのような状況ですか?」「同じような問題を抱えている企業の事例が欲しい」「何か斬新な提案はありませんか?」、最近よく耳にする人事担当者の声です。多くの人事担当者にとって、この領域における情報が不足している様子がうかがえます。
今回の特集では、2009年7月から9月にかけて、各社にご協力いただき実施した「RMS Research’09昇進・昇格実態調査」の報告の一部をご紹介させていただきながら、昇進・昇格について考えてみたいと思います。
人事が抱える管理職層の問題とは?
まず、各社の管理職層の問題について見てみます。
調査結果からは、管理職層の問題が多岐にわたっている状況がうかがえます。
「上位階層に昇進・昇格しても、実務も行う管理職が多く(プレイングマネジャー)、職務意識が変わらない」という問題を、課長職に対しては3社に2社が感じています。実際に、私たちが人事制度設計支援の際に管理職層に対するインタビューをすると、業務の大半が、昇格前から現在も引き続き担当しているお客さまへの営業活動であり、仕事にはほとんど変化がないなどという話が出たりします。
これらの現象は、専門職(部下のいない管理職)に昇格する場合には、一層顕著に見られます。中には、「仕事内容も特に変更がなく、昇格前と何一つ変わっていません」という方もいらっしゃいます。部下なし管理職という役割の中で、管理職層としての責任感や役割意識を醸成することの難しさを感じる瞬間です。
一方、部長職に対しての問題は、「短期的な成果に注力するあまり、長期的な視点での取り組みができていない」が最も多く、次に「現状にとらわれず、広い視野や高い視点から課題を設定していく力が不足している」という回答が続きます。短期成果が求められる状況下で、大きく全体を俯瞰したり、長期的に取り組む弱さが目立つようです。
【図表1 現在の管理職層に関する問題】

意外と多い?3社に1社が降格運用
厳格に審査され昇格したにもかかわらず、その後、さきほどのような問題をいくつか抱え、期待される成果を出せずにいる管理職層もいます。では、技術や知識、能力が劣る管理職に対して各社はどのような対応をしているのでしょうか。降格運用を行っているという企業は、ほぼ3社に1社(部長30.4%、課長33.5%)あり、数字だけ見ると、6社に1社だった91年の調査と比べると約2倍に増えています。
3社に1社という結果は、降格実施の有無だけを質問しているので、対象者が毎年複数人いたり、毎年必ず発生するわけではないという企業も含まれている可能性があります。従って、結果は慎重に見る必要がありますが、91年の調査からは増加していると見てよさそうです。この18年の間に成果主義へ移行する過程で、多くの企業は、昇格・降格が大胆に行える人事制度に改定しており、その運用が現在も継続されていることなどが、増加理由の一つとして考えられます。
従業員規模別に見ると、大手企業ほど、降格運用をしています。従業員5000名以上の企業では、部長は36.2%、課長が38.3%という割合で実施しているという結果でした。また、導入している人事制度のタイプ別にみると、職務等級制度を導入している企業は、職能資格制度やその他の制度を導入している企業に比べて、降格運用を行っている比率が高く、職務等級制度の合理的な運用部分が見てとれる結果となりました。
【図表2 能力・技術・知識が劣る管理職の対応】

万能薬にはならない昇進・昇格
続いて、昇格前の候補者の状況について見てみます。
昇進・昇格に関する問題意識では、「昇進・昇格そのものに魅力を感じない者が増えている」という項目が上位にあります。社内外におけるキャリアが多様化してきた結果、従業員にとって昇進・昇格は、もはや無条件に動機付けられる魅力ある人事イベントではなくなり、「昇格したい(した)から頑張る」という構図は、昔のようには成立しなくなってきているようです。
また、「後輩や若手育成の経験のない層が、管理者となることに不安を感じる」といった声も、ほぼ同数ありました。人員構成上の問題や、仕事の進め方の変化などにより、従来なら管理者になる手前の段階で経験しておくべきことがしづらくなってきている状況が、各社に共通して起こっているようです。
ちなみに最も問題に感じているのは「女性の管理職登用が進まない」ことであり、女性活躍推進への関心の高さと、現状とのギャップが大きいことが示唆されます。
【図表3 昇進・昇格に関する各社の問題意識】

選考見直しにとどまらない人事の取り組み
では、このような状況にある各社の人事は、今後の取り組みをどのような方向性で考えているのでしょうか?
単に選考方法や基準の見直しだけではなく、早期選抜や専門職処遇の見直しなど、関連するいくつかの領域を視野に入れて改定を検討している様子がうかがえます。
改定の方向性としては、過半数の企業で「昇進・昇格選考に新たな基準・考え方を設ける」ことを検討するという結果でしたが、ほかにも「経営幹部候補者の早期発見・育成を図る」ことや、「複線型人事管理の徹底(専門職などの処遇方法の見直し)」、また「女性管理職比率の目標値設定や女性の能力開発」などを検討する予定の企業も多くありました。
昇進・昇格は、「人材の適正な配置」だけでなく、「新たな役割が付与されることによる育成機会の提供」や、「従業員モラールの影響」といった性質を持っていますし、また「中長期にわたる各階層ごとの人員構成比を形作る」といった性質も持ち合わせていることもあり、自社にとってもっとも効果の高い改定案を、各社ともに模索しているようです。
【図表4 昇進・昇格に関する施策の方向性】

昇進・昇格の動線を作る4つの点検領域
本特集でご紹介した結果を元に昇進・昇格を再設計する際のポイントについて整理してみたいと思います。
各社がおかれている状況や今後の取り組み施策を見ていると、 「入り口(昇格選考):領域(1)」「出口(降格ルール):領域(2)」「候補者育成:領域(3)」と「昇格後教育:領域(4)」の4領域の制度の整合性をとりながら再設計することの必要性が見えてきます。
例えば、厳格な昇格基準づくりに限界があり、「一度、機会を与えてやらせてみよう」という昇格運用(領域(1))をせざるをえない企業であれば、昇格後の教育機会の提供(領域(4))を充実させる必要があります。それでも適合しなかった場合には、現在のポジションから「健全に退くためのルール」や「風土づくり」(領域(2))をしっかりと行うことで、昇格前から降格までの動線(パス)に納得感がうまれ、実効性の高い制度として描くことができます。
昇進・昇格というと、 「入り口(昇格選考):領域(1)」を想起される方が多いのではないでしょうか。 冒頭の「昇進・昇格をどのように設計すれば理想的な管理職が継続的に配置されるか?」という問いに対し、「これさえやれば大丈夫!」という特効薬はありません。しかし、この4つの視界で見た時に、自社の実態に合わせ、整合性・連続性を丁寧に調節していくことが、昇進・昇格運用の精度を高めることにつながっていきます。
【図表5 昇進・昇格制度点検の視界図】

さいごに
さて、今回の特集では、先般実施した昇進・昇格調査報告の一部を紹介させていただきながら、昇進・昇格について考えてみました。人事制度上の要となるこの制度を4つの視界で見ることで、「適正な人材配置」と「継続的な人材成長」がなされ、その結果、貴社の管理職層が事業推進の原動力になっていくことを心より願っております。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


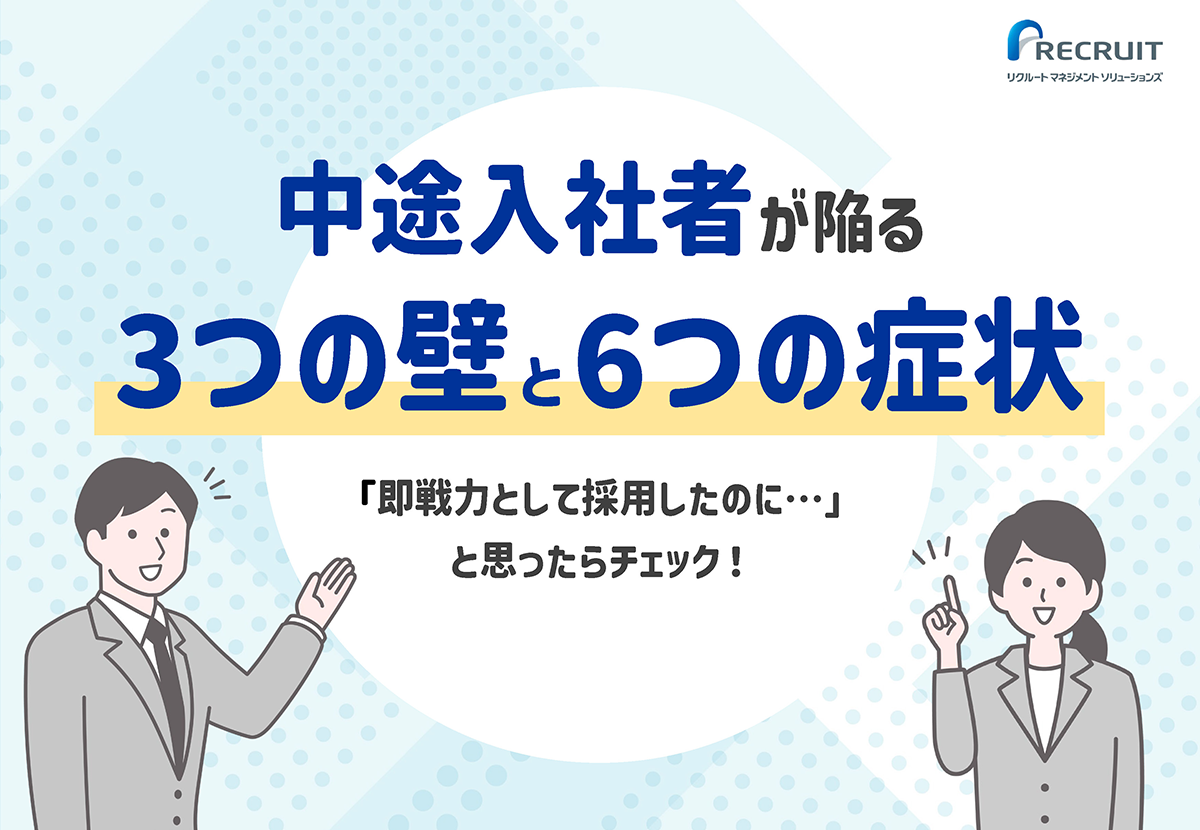
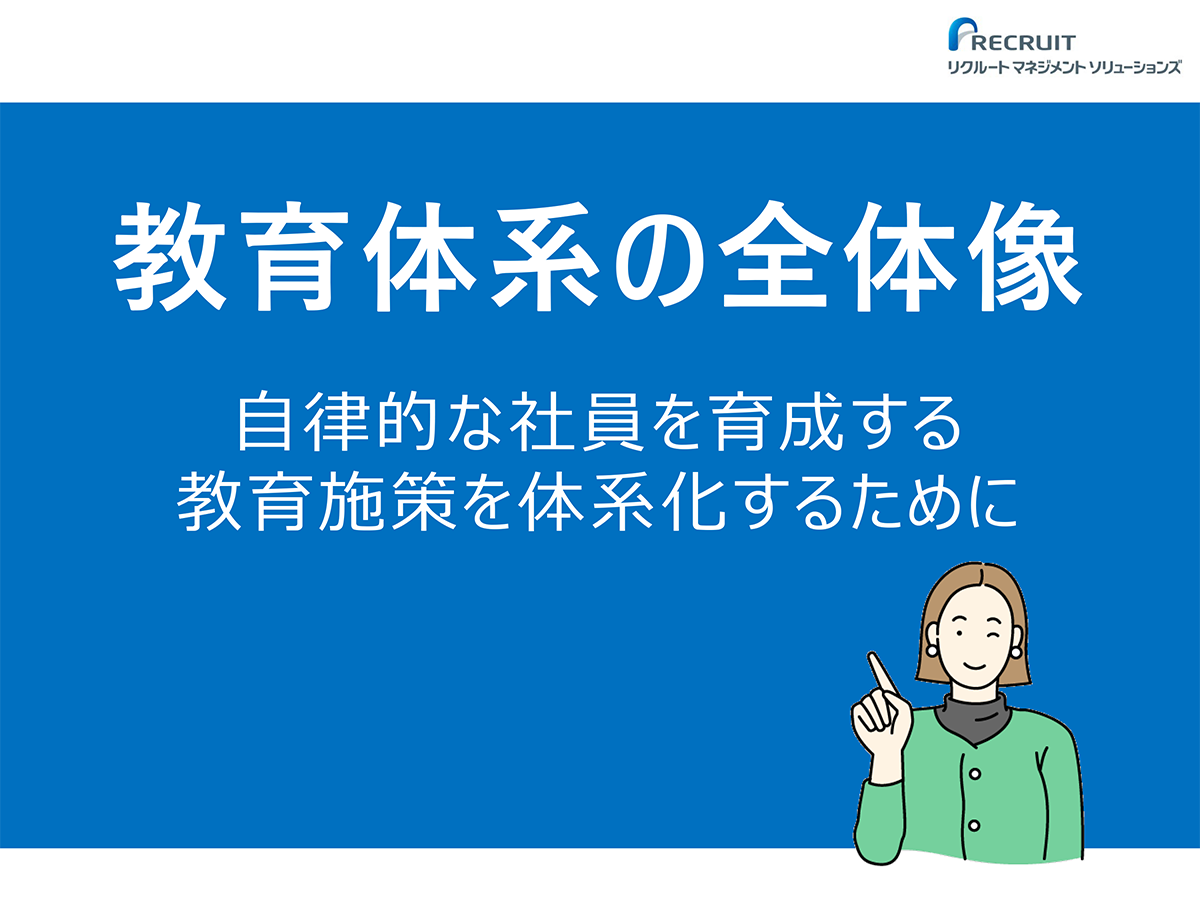
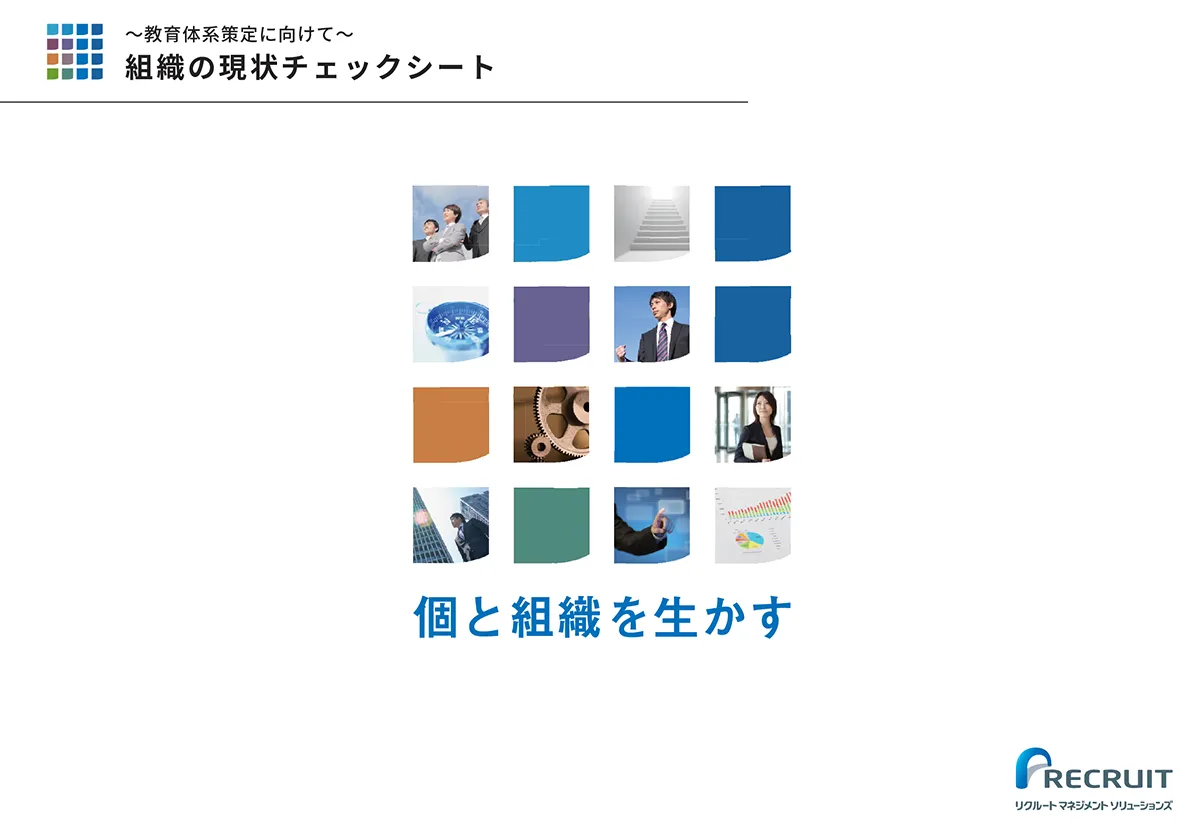









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての