特集
潜在的な能力・可能性を「見える情報」へ
人的資源活用に向けた今日的な人材アセスメント活用術
- 公開日:2007/01/01
- 更新日:2024/04/11

昨今、経営環境が大きく急速に変化する中、社員一人ひとりには、過去の実績やこれまでの発揮行動の延長線上では対処しきれない、新しい役割や変化への対応そして成長が求められています。
このような環境においては、事業戦略はもちろんのこと、企業と個人の成長・業績を支える人的資源の活用は「待ったなし」の状態です。その人的資源の活用においては、
1.企業が個々人の力を最大限に発揮するために適材適所の配置を行い、育成していくこと
2.個人が自らの特性に応じたキャリアを主体的に選択し、自己啓発していくこと
この2つがバランスよく機能している必要があります。
そのためには、目に見えやすい職務・職場行動を評価するコンピテンシーモデルや業績評価の導入に加えて、目に見えにくい潜在的な能力・可能性を「見える情報」として提供する、人材アセスメントデータの活用が効果的です。
さらに今日では人材アセスメントデータを人材発掘や選抜目的で用いるだけでなく、キャリア開発・能力開発と連動させることで、効果的な人的資源マネジメントを実現している企業が増えています。
本特集では、各企業での人的資源活用に向けた人材アセスメント・サーベイの活用事例を中心に、その位置づけと、活用のポイントをご紹介いたします。
- 目次
- 効果的な人材アセスメント手法とは
- 活用事例1 昇進昇格場面
- 活用事例2 全社人材の棚卸/埋もれた人材の発掘・動機づけ
- 活用事例3 人材の定期健康診断+能力開発
- アセスメント・サーベイを選ぶポイント ~リクルートマネジメントソリューションズが大事にしていること~
効果的な人材アセスメント手法とは
企業側にとっても個人にとっても、まずは「現状の立ち位置」を知ることが、効果的な人的資源活用や、自発的な能力開発には欠かせません。
この章では、その第一歩となる効果的な人材アセスメント手法について整理していきます。
個々人の実際の職務・職場行動は、汎用的な知識やスキルに支えられています。それらの獲得や発揮にはパーソナリティ・基礎能力などの特性が深く関わっていることを示しているのが、図表1の「企業人の能力構造モデル」です。この中で、業績評価やコンピテンシー評価は、主に発揮行動領域を測定していることになります。各層の間には、「Aという特性があれば、Bという能力が高まる」というほど強い関連性はありません。
それゆえ、現在の仕事の延長線上ではない、新たな役割付与や昇進・昇格時には、業績評価・コンピテンシー評価のみならず、知識・スキルや特性部分も踏まえた、多面的な人材アセスメントを行う必要があるといえます。
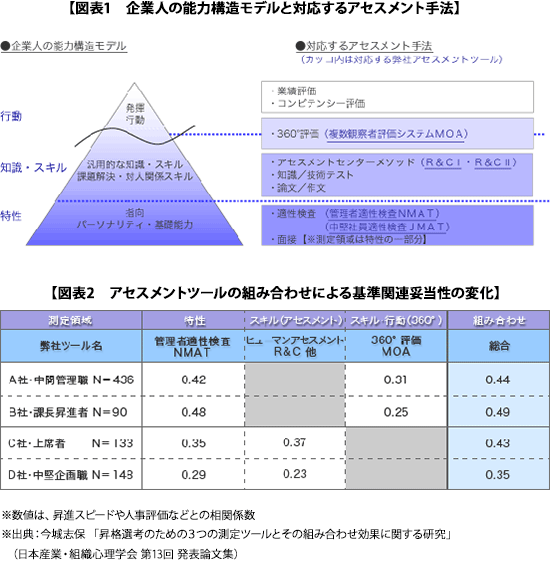
弊社では実際に、人材アセスメントの多角的な利用による有効性の高まりを検証するために、発揮行動/知識・スキル/特性の各領域を測定するアセスメントツールを組み合わせた場合に、人事評価や昇進スピードといった基準情報との関係性がどの程度強くなるのか、という研究を行いました。
まず、特性領域を測定する管理者適性検査NMATと、スキル領域を360°評価手法で測定する複数観察者評価システムMOAを組み合わせることで、その後の昇進スピードや人事考課を単体で用いる場合よりも、高いレベルで予測できることが示されました。
次に、前述したNMATと、スキル領域を測定するアセスメントセンター手法であるR&CI、R&CIIなどを組み合わせると、同じく昇進スピードや人事考課結果を、より高く予測できることが示されました。これらの具体的なデータについては、図表2のとおりです。
総括すると、目的に応じてさまざまなアセスメント手法を使い分け、組み合わせることが有効である、ということです。
活用事例1 昇進昇格場面
ここからは、アセスメント手法の多面的な組み合わせによる活用イメージについて、各企業の事例を具体的にご紹介させていただきます。
■ メーカーA社: 課長職昇進場面におけるアセスメントデータ活用事例
・導入目的:カンパニー制の導入に伴い、社内人材を共通の枠組みで捉える機会が減少している。そのため、能力評価・業績評価のみならず全社共通の基準として、課長職昇進選考時に世間標準と比較可能なアセスメントデータを用い、公平性・客観性を確保した昇進・昇格制度を運用したい。
・概要:選考は2段階に分かれており、適性検査NMATと各種人事考課をウエイト付けし総合点を算出する「選考1」を行い、通過した候補者に対して「選考2」でスキル領域を測定するアセスメントセンター手法である研修R&CIを実施している。具体的なフローは図表3のとおり。
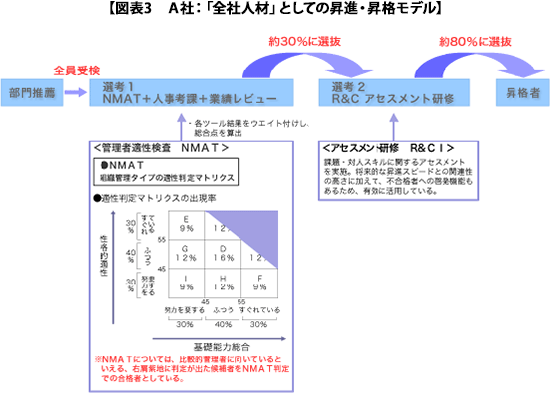
活用事例2 全社人材の棚卸/埋もれた人材の発掘・動機づけ
■ITシステム/サービスB社: マネジメント人材発掘を目的としたアセスメントデータ活用事例
・導入目的:新規事業発足に伴い、プロジェクトマネジャー・マネジメント層が不足し始める。そもそもマネジメント指向が強くない技術者が社員の大半を占めるため、マネジャー適性の高い人材を発掘・動機付けし、同時にマネジメント能力の開発にもつなげたい。
・概要:適性検査NMAT、360°評価MOA、そして人事考課からマネジメントに対する適応性・指向の高い人材を抜擢・抽出(図表4)。さらに、個々人の能力発揮状況(MOA結果)に見合った能力開発プログラムを用意した(360°評価MOAの結果から能力開発プログラムへの連動パターン)
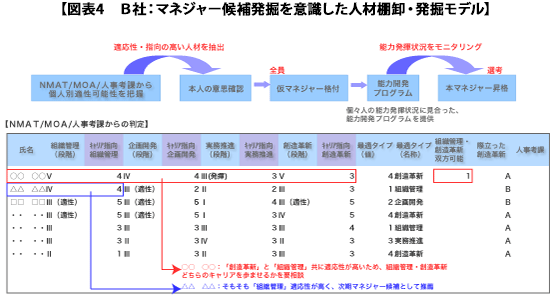
活用事例3 人材の定期健康診断+能力開発
■ 建設設備C社: マネジメント人材の棚卸と能力開発を目的としたアセスメントデータ活用事例
・導入目的:ソリューション事業へ転換する事業フェーズにおいて、従来型の課題解決型マネジメントから、より現場の力を引き出すマネジメントが求められるようになってきた。それに伴い、社員全体の能力の棚卸と360°評価を基軸とした能力開発計画をつくりたい。特に、自己の現状認識と周囲からの期待のギャップが大きい管理職には、360°評価の結果をベースに今後のキャリア開発につながるような機会にしていきたい。
・概要:360°評価MOAの実施から、MOA結果の適切な受容・能力開発計画立案を進めるためのフィードバックガイダンス、キャリアカウンセリングも交えたMOA個別フォローアップセッション、そして能力開発の第一歩として取り組みやすいeラーニングを一連の流れとして実施している。具体的なフローは図表5の通り。
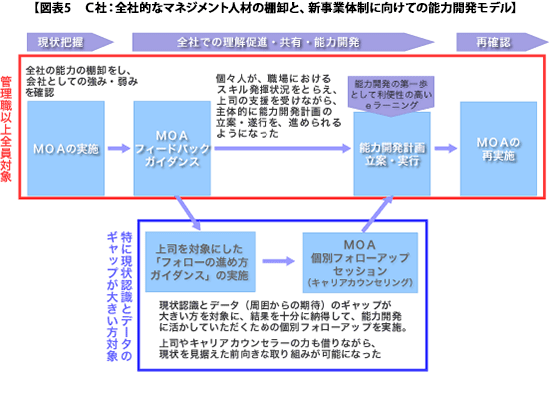
アセスメント・サーベイを選ぶポイント ~リクルートマネジメントソリューションズが大事にしていること~
時代や環境に応じて、さまざまな人材アセスメント・サーベイの手法やツールが開発されています。
目新しさや利便性、価格などそれぞれのツールには特色があり、選択に迷われることもあるのではないでしょうか。
ここでは、人的資源活用に効果的かつ公平で納得感のあるアセスメント・サーベイを選ぶための、4つのポイントをご紹介いたします。
これらのポイントは同時に、弊社が人材アセスメントを開発する上で最も大事にしている考え方でもあります。弊社では常に高い精度でのご提供を目指し、継続的な統計データ検証と改善を重ねております。
【 POINT1 標準性 = 結果の客観性と一貫性(ぶれの少なさ)】
・世間水準との比較をベースにした、将来の可能性も含めた適性や能力の客観的な把握
・統計的に検証された測定尺度により、他社平均との比較や自社の経年変化の比較が可能
【 POINT2 妥当性 = 将来の成功度の予測】
・期待される職務遂行能力を発揮し、十分な成果をあげられるかの予測力
・職場や上司とのミスマッチによる埋もれた人材の発掘
【 POINT3 信頼性 = 公平感、納得感の確保】
・職種や部門、キャリアの違いに影響されない、「同じ土俵での勝負」
・「客観的データ」が加わることによる納得感
・測定尺度が正しくその内容を捉えている(統計的な信頼性)
【 POINT4 啓発性 = 自己理解の促進】
・評価結果のフィードバックによる自己理解の促進
・適性をふまえた上でのキャリアプランニング支援
最後に
従来より、「アセスメントデータの活用」というと、昇進・昇格などの選抜目的の印象が強いかもしれません。
しかし、先にご紹介したような人材マネジメントに先進的な各企業では、単に選抜目的にとどまることなく、個人の持ち味をいかした適材適所の配置・キャリア開発、能力開発まで連動し、人的資源活用に幅広く利用されています。
本特集が、これから人材アセスメントデータの導入・利用をお考えの企業だけでなく、既に各種アセスメント・サーベイを実施されている企業におかれましても、人材アセスメントデータの更なる有効活用のご参考になれば幸いです。
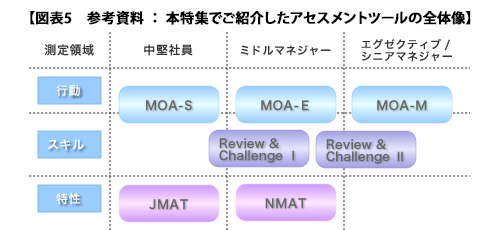
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

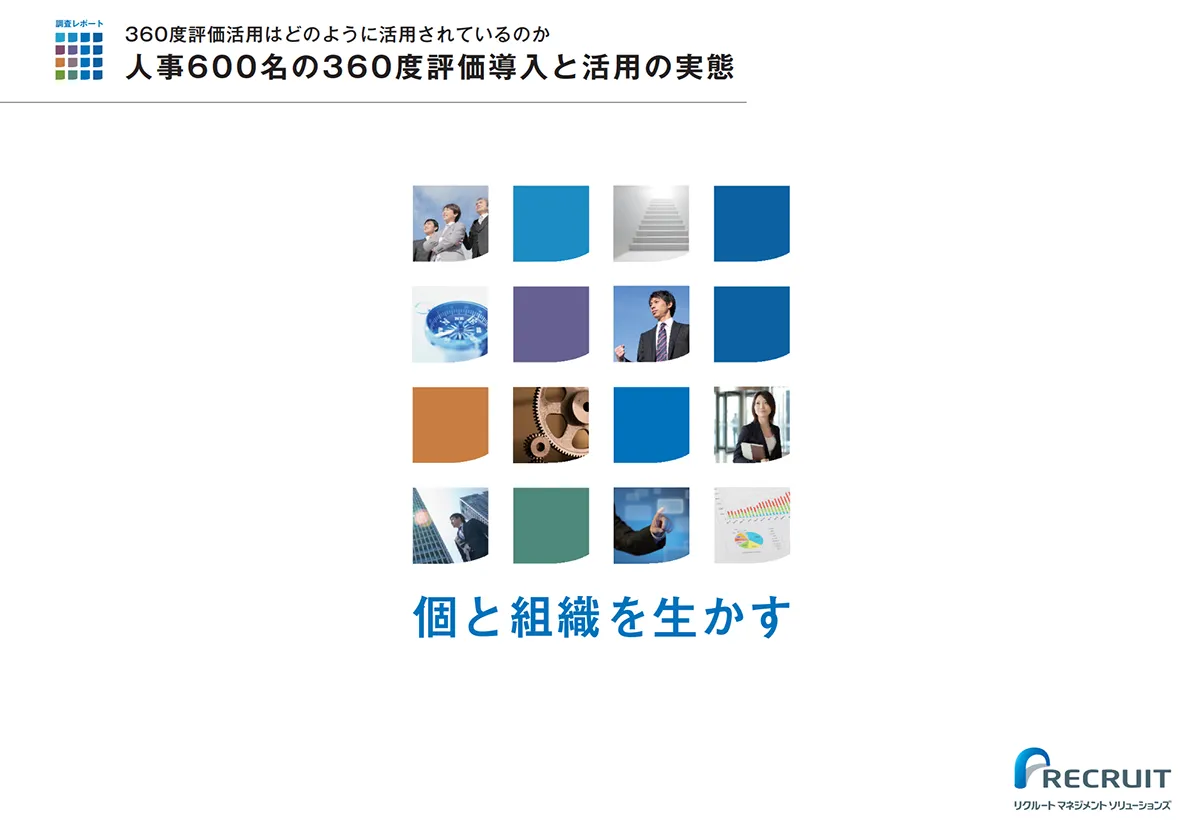









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての