特集
資源ベース戦略の側面から考察
事業戦略実現における人材マネジメント 〜知的資本の観点から〜
- 公開日:2005/11/01
- 更新日:2024/05/04
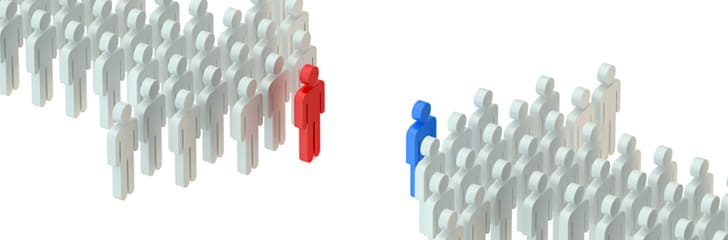
ある人事部門の声
我々は声を大にして言いたい。
人材採用、人材育成、従業員満足、マネジメント、これらのダイナミズムこそが、企業の持続的競争優位性の源泉である。技術、製品そのものが、競争優位の源泉ではない。しかし現実は、企業業績が下がれば一番先に採用、教育、人件費が削られる。
この、ある人事部門の声に、わが意を得たりと感じた方も多いと思います。
何故、このようなことがおきるのでしょうか。それは、
人材、組織文化、マネジメントなどの「見えざる資本」(=以下、知的資本)が、
(1)企業のビジネスモデルにどう影響するのかという観点から、人事施策が考えられていないこと
(2)そもそも、その成果を具体的に示すことができていないこと
が、大きな要因と考えられます。
そこで、今月の特集では、資源ベース戦略(resource based view)の側面から、事業戦略実現における人材マネジメントについて考えてみたいと思います。
- 目次
- 自社の強みを視野に入れた人事施策になっているか
- 競争優位となる経営資源の特徴を把握しているか
- 模倣困難性を高める人事戦略になっているか
- 人事戦略を通じて競争優位を高める3つのポイント
- 自社の現状を把握し、要因と施策を検討する方法
自社の強みを視野に入れた人事施策になっているか
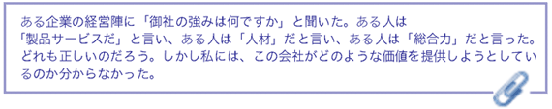
自社の儲けの構造、コアとなる経営資源を明確にし、それが競争力を持たなくなったら、経営資源を組み直して新たな価値を生み出すこと。これを「コンピタンス経営(知的資本経営)」といいます。
自社の強みを明確に認識できるのであれば、環境変化があっても経営資源を組み直して生き延びることができます。
環境の変化に即して自分たちの市場におけるポジションを変える企業もあります。
最近では、環境が変化したら、自社のコアとなる経営資源だけを残して、他は自由に外部にある経営資源と組み合わせる企業も出てきています。
つまり企業の儲けの構造は絶えず変化しており、それに合わせた経営資源の組み合わせと活用が必要になります。
何故新卒採用、中途採用をするのでしょうか。何故従業員教育をするのでしょうか。それは自社の事業戦略とどのように関係するのでしょうか。「人が足りないから採用、人を育てることが大事だから教育」だとすると、事業戦略と人事施策の関係は不明確です。自社の儲けの構造(コアの経営資源)との関係で人事戦略を考えることが重要です。
競争優位となる経営資源の特徴を把握しているか
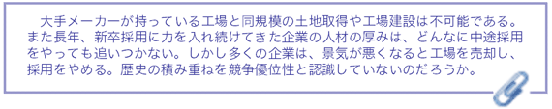
競争優位となる経営資源には4つの特徴があります。(J.B. Barney 1997)
1)価値(Value)
企業の経営資源や能力は、環境の変化、脅威に対応できるものか。
2)希少性(Rareness)
競合と比べて、特定の価値ある経営資源や能力をどの程度保有しているか。
3)模倣困難性(Imitability)
特定の経営資源や能力のない企業が、その経営資源などを獲得しようとした時、コスト上の不利となるか。また代替の手段は存在するか。
4)組織化
企業は、組織的に経営資源や競争する上での能力を十分に開発しているか。
これらの特徴は、重要な経営資源である「人と組織」にもあてはまることです。
仮に人・組織・組織文化という経営資源が自社のコアとなる経営資源であるとすれば、自社の従業員が、環境変化に対応できる、他社にない価値ある能力を持っている、模倣困難な組織文化を持っている、人や組織が十分にマネジメントされていることが、競争優位性となります。
人と組織という経営資源の有効活用が人事の役割だとすれば、これらの特徴を把握すること、さらに高める施策を打つこと、その成果を検証することが重要です。
模倣困難性を高める人事戦略になっているか
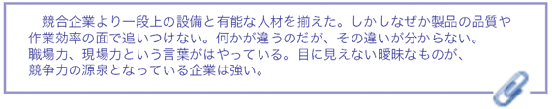
4つの特徴の中では、模倣困難性が特に重要です。ではどのような時に、経営資源は模倣困難なものになるのでしょうか。(内田恭彦 2004)
1)固有の歴史的条件
歴史的条件のもと、低コストで経営資源の獲得もしくは開発ができた場合、その歴史的条件のない企業が同様の経営資源を獲得もしくは開発しようとすると相対的にコスト高になる。
2)因果関係の曖昧性
模倣しようとしている企業が、経営資源と競争優位の因果関係を理解できない。
3)社会的複雑性
社会的に複雑な現象により経営資源(社会的評価、組織文化)が成り立っている。
新卒採用や教育は、経営資源の価値がわからない時期に、その獲得や開発を行うことにあてはまります。その時のコストは低いですが、価値が明らかになれば、その獲得や開発費用は高まります。競合が、自社と同じ設備やルールを導入しても同じ価値の製品サービスは提供できません。そこには、組織文化や価値観という因果関係が曖昧なものの存在があるからです。
まさに人事戦略のゴールは、企業の模倣困難性を高めることといえます。
これらは短期間では獲得できません。よって中長期的視点で採用、教育を考え、組織文化、価値観の醸成を進める具体的な施策とその成果を検証する方法の開発が重要です。
人事戦略を通じて競争優位を高める3つのポイント
事業戦略は、自社のコアを生かす経営資源の組み合わせであり、そのダイナミズムこそが持続的競争の源泉となります。とすれば、経営資源のマネジメント、コントロールこそが重要であり、技術や製品サービスそのものが持続的競争優位の源泉ではないということになります。
人材マネジメントは、自社の経営資源をマネジメントし、コントロールする人・組織という経営資源の有効活用であり、この観点から人事施策やその成果検証を行うことが必要です。
今後、事業戦略を実現するためにさらに強化すべきことは、
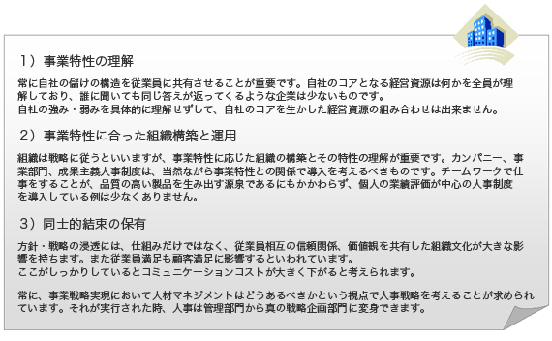
自社の現状を把握し、要因と施策を検討する方法
すべての戦略や施策のスタートは、現状把握とその共有です。現状把握をしてもその結果の解釈や施策がばらばらでは成果に結びつきません。
現状把握と共有の上で、真の要因が明らかになり、的確な施策を立案することができます。
最後に、2つの簡便で効果的な方法をご紹介します。ぜひ、ご参照ください。
1)従業員意識調査
定期的に従業員の声を聞く仕組みを持つことは、事業戦略の理解度・浸透度、また人事施策の定量的な成果を測定する上で効果的です。
最近では従業員満足度調査が盛んに行われています。弊社でも年間40社強でお手伝いをしています。
意識調査により、現状とその要因、今後に向けての打ち手を検討する材料が得られます。
2)知的資本実態調査
自社のビジネスのコアとなる経営資源の実態とその活用状況をアンケート方式で明らかにする方法です。定量的なデータの他に自社のビジネスを可視化するチャート図もアウトプットされ、経営陣をはじめ、従業員との間で事業の現状と今後を共有する効果的な資料となります。(詳細は以下の参考資料1~3を参照してください)
【引用文献】
-内田恭彦(2004) 「持続的競争優位を構築するために」研究会資料
-野中郁次郎、竹内弘高 (1995) 『知識創造企業』東洋経済新報社
-釘崎広光(2002) 「知的資本経営における戦略の立案、実行と評価・検証」 HRRメッセージNO.50、10-21
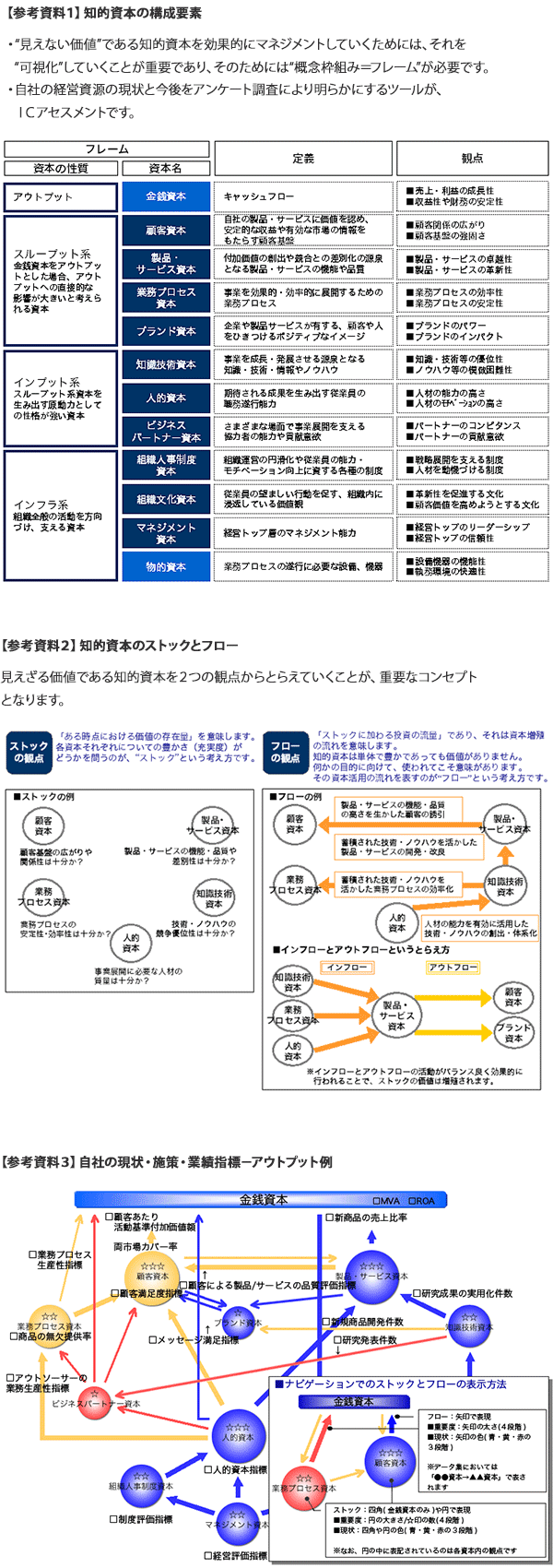
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)




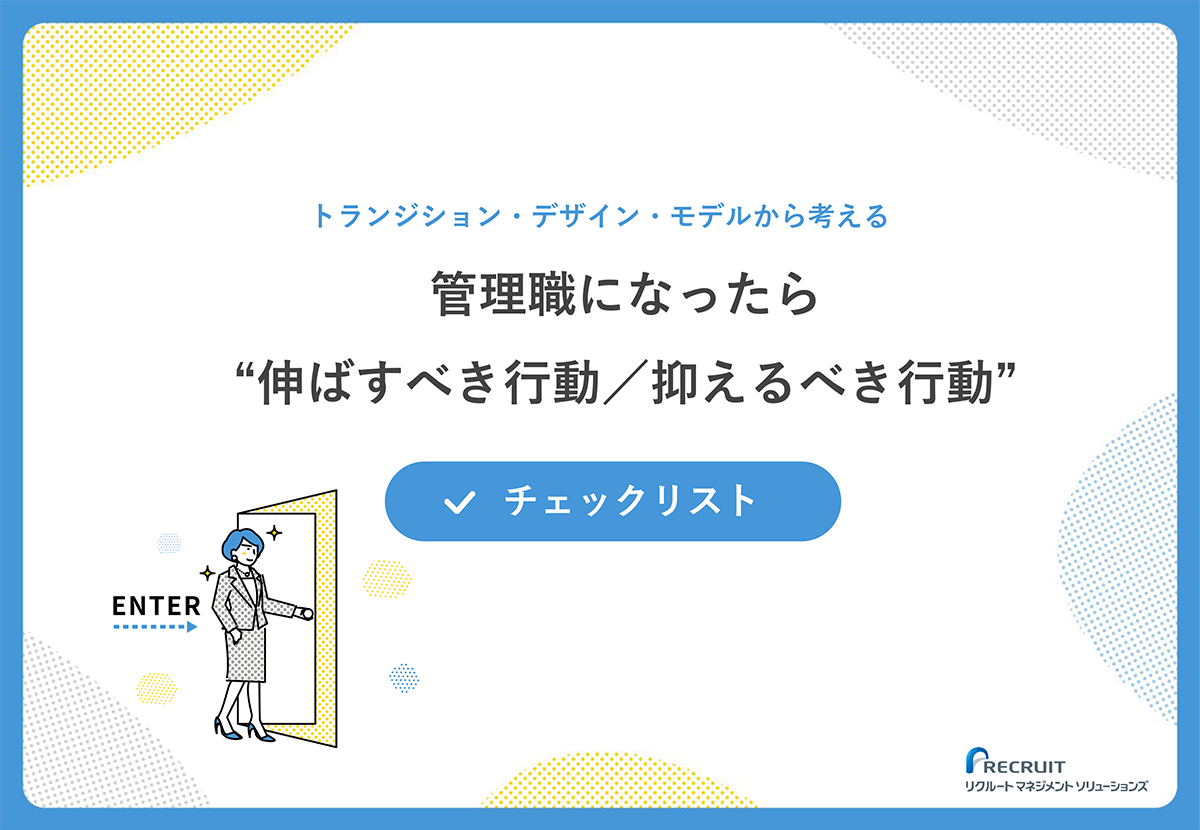









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての