特集
これからの基軸となる
人材アセスメントデータの効果的な活用法
- 公開日:2005/07/01
- 更新日:2024/04/11
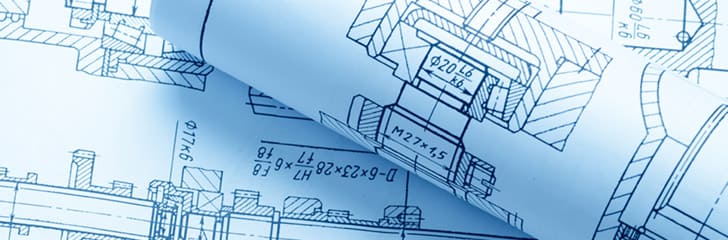
リクルートワークス研究所発行の「ワークス」70号(最新刊)には、「人材マネジメント これまでの10年 これからの10年」という特集記事が掲載されています。そこには、企業へのアンケート結果から、ここ10年間で人材マネジメント思想に起こった、大きな変化について記されています。
具体的には、人材マネジメントを支えるポリシーが
・年齢や勤続年数によらず、個人の「能力」や「業績」によって昇進・昇格を決定
・賃金や処遇が下がることもあり得る人事制度
へと、大きくシフトしたことがデータで示されています。これは、読者の皆様の実感値に近いものではないでしょうか。この変化は、「個人の能力や業績の評価に格差をつける」「賃金が下がる根拠を明示する」ために、個々の社員にとっても、納得感の高い人材アセスメントの必要性を高めることに繋がります。
本特集では、今日的な人的資源管理場面における「人材アセスメントデータの位置づけ」と「活用方法」について、具体的な事例を交えながら論を進めていきます。
- 目次
- これからの人材マネジメントの基軸となるアセスメントデータ
- 「企業人の能力構造モデル」と対応するアセスメント手法
- アセスメントツールの効果的な組み合わせについて
- アセスメントデータの活用
- アセスメントツールの全体像
これからの人材マネジメントの基軸となるアセスメントデータ
ここ十数年、日本では職務主義・成果基軸の人事処遇制度の導入が進められ、日本流のアレンジが加えられてきました。各企業では、制度や運用の修正をしながら、より自社にフィットした人事処遇制度を構築していきました。
その構築過程において、職務(役割・職責)と報酬の関係については意識的に設計を行ってきましたが、図表1の赤矢印の部分(職務・役割 / 適性・能力・指向 / の関係性)には、あまり注意が払われてこなかったといえます。
このように記述すると、「いいえ、当社は各職種別のハイパフォーマを抽出し、コンピテンシーモデルを作成しおり、上司評定のレベルと職務側の要件をマッチングした上で、職務任用を行っているので、全く問題はありません」 との回答が返ってきそうです。
また、別の方からは「うちは業績評価のみなので、細かい適性は関係ないね」という返答が返ってくるかもしれません。確かに、職種別のコンピテンシーモデルや業績評価各々は有用なものですが、新たな役割付与や昇進・昇格を伴う人材アセスメント場面でも、十分な情報を提供することができるでしょうか?
【図表1 人材マネジメントの基本構造】
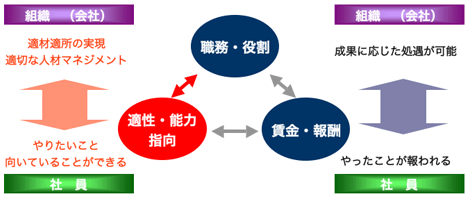
「企業人の能力構造モデル」と対応するアセスメント手法
では、どのようなアセスメントが効果的なのでしょうか?
図表2をご覧ください。
個々人の実際の職務・職場行動は、汎用的な知識やスキルに支えられており、それらの獲得や発揮にはパーソナリティ・基礎能力などの特性が深く関わっていることを示すモデルです。その中で、業績評価やコンピテンシー評価は、主に発揮行動領域を測定していることになります。各層の間には、「Aという特性があれば、Bという能力が高まる」というほど強い関連性はありません。
それゆえ、現在の仕事の延長線上の職務任用ではない、新たな役割付与や昇進・昇格時には、業績評価・コンピテンシー評価のみならず、知識・スキルや特性部分も踏まえた多面的な人材アセスメントを行う必要があるといえます。
総括すると、目的に応じてさまざまなアセスメント手法を使い分け、組み合わせることが重要だということです。
図表2では、各層に対応する有効なアセスメント手法も併せてまとめています。
貴社にて実施されている、人材アセスメント手法と対比・整理されてはいかがでしょうか?
【図表2 企業人の能力構造モデルと対応するアセスメント手法】
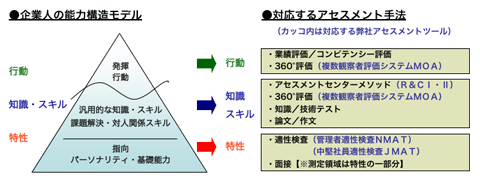
アセスメントツールの効果的な組み合わせについて
「効果性の高い人材アセスメント」とは、目的に応じて、発揮行動/知識・スキル/特性の各階層をバランス良く把握することが有効であることは既に述べた通りです。しかし、複数のアセスメントを組み合わせると、どの程度有効性が高まるのかについては、これまで不明確なままでした。そこで、弊社では発揮行動/知識・スキル/特性の各領域を測定するアセスメントツールを組み合わせると、人事評価や昇進スピードといった基準情報との関係性がどの程度強くなるのか、といった研究を行いました。
まず、特性領域を測定する管理者適性検査NMATと、スキル領域を360°評価手法で測定する複数観察者評価システムMOAの指標を組み合わせることで、その後の昇進スピードや人事考課を単体で用いる場合よりも、高いレベルで予測できることが示されました(図表3、A社・B社)。
次に、前述したNMATと、スキル領域を測定するアセスメントセンター手法であるR&CⅠ、R&CⅡなどを組み合わせると、同じく昇進スピードや人事考課結果を、より高く予測できることが示されています(図表3、C社・D社)。
この結果は、複数のアセスメント手法を組み合わせたことによる有効性を示唆しているといえます。
【図表3 アセスメントツールの組み合わせによる基準関連妥当性の変化】
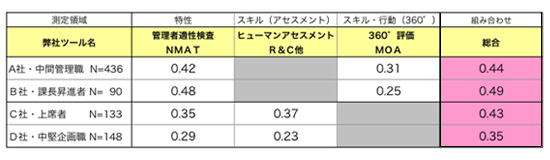
※数値は、昇進スピードや人事評価などとの相関係数
※出典:今城志保 「昇格選考のための3つの測定ツールとその組み合わせ効果に関する研究」(日本産業・組織心理学会 第13回 発表論文集)
アセスメントデータの活用
さて、ここまでは人材アセスメントついて、「考慮すべき領域」や「組み合わせ実施の有効性」について整理してきました。以降は、具体的な活用イメージについて「活用例」をご紹介させていただきます。
アセスメントデータの活用~異動/昇進・昇格場面での活用~
■事例1
メーカーA社 課長職昇進場面でのアセスメントデータの活用(図表4)
・概要:ライン課長・専門課長選抜時に、能力評価・業績評価のみならず全社で設定した基準を確認するために、下記のようなステップを踏んで世間標準と比較可能なアセスメントデータを用い、公平性・客観性を確保した昇進・昇格制度を運用している。
・選考は2段階に分かれており、適性検査と各種人事考課をウエイト付けし総合点を算出する「選考1」を行い、通過した候補者に対して「選考2」でアセスメント研修を実施している。
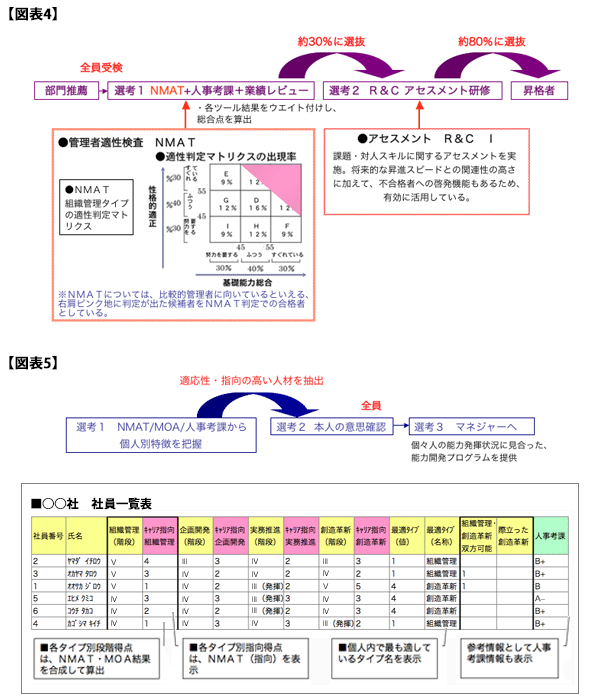
アセスメントツールの活用~全社人材の棚卸/埋もれた人材の発掘・動機付け~
■事例2
SI業界B社 「マネジャーのなり手がいない!」全社人材の棚卸し/埋もれた人材の発掘・動機付け(図表5)
・概要:自己申告面談においてプロフェッショナル指向が強く、プロジェクトマネジャ-・ラインマネジャーへの指向が強くない方が多かった。会社側は、業容拡大に伴いプロジェクトマネジャー・マネジャーが求められる状況下、NMAT・MOA・人事考課データを組み合わせて候補者を抽出し、それらの中からNMATの組織管理・創造革新指向の強い人材を抽出し、個別に動機付けを行った。
アセスメントツールの全体像
時代や環境に応じて、人材アセスメント手法やアセスメントツールは進化していきます。
ただし、人材アセスメントを行う際に、多面的な情報を基に行う方が効果的であること、アセスメントツ-ルを用いる場合は信頼性や妥当性の高いツールを用いる必要があることなど、ベースとなる考え方は共通です。
本特集が、各企業での“人材アセスメント”領域での課題解決にあたって、多少なりともご参考になれば幸いです。
【図表6 本特集でご紹介したアセスメントツールの全体像】
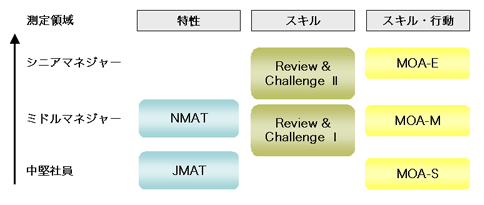
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

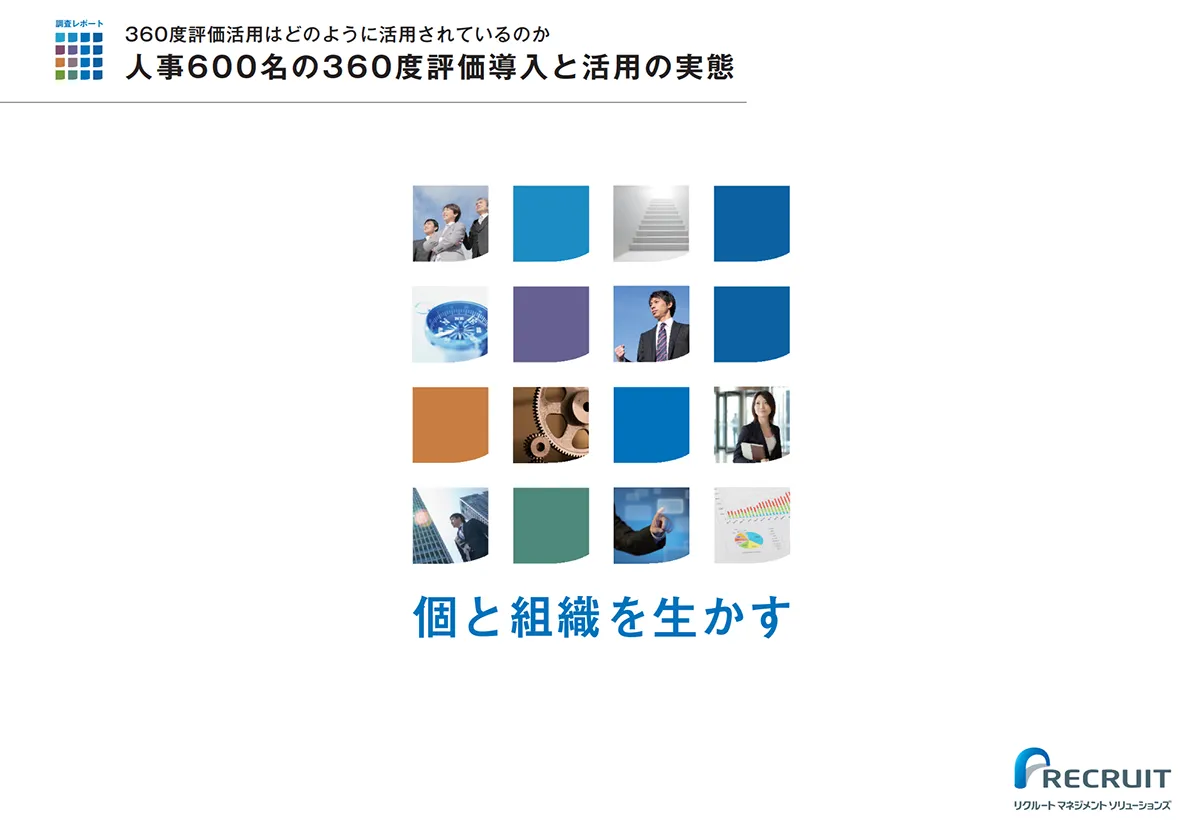









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての