特集
マネジャーの部下育成スキルを高める
部下育成には「伸ばす」だけでなく「抑える」働きかけも必要
- 公開日:2012/02/13
- 更新日:2024/04/11
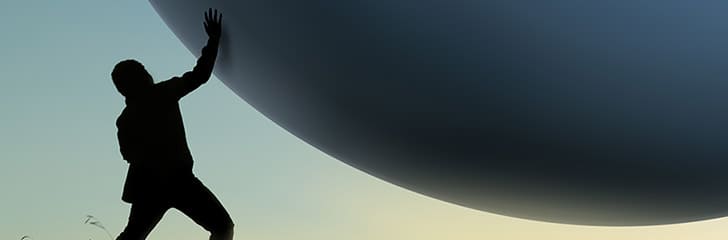
企業人の役割転換不全(周囲から期待されている本来の役割を果たせていない状態)が顕著に見られる昨今、この問題を解決するための人材育成モデル「トランジション・デザイン・モデル」を2010年8月の特集記事にてご紹介しました。
モデルをご紹介してから、企業人事の方のみならず現場のマネジャー・メンバーの方からも、非常に高い関心を寄せていただいており、モデルの詳細をご紹介する場面が増えてきています。これは、階層構造が曖昧になる中、ビジネスパーソンとしての自分の「立ち位置」を世間一般水準から客観的に知っておきたいという思いの現れだと受け止めています。
そこで今月の特集では、「トランジション・デザイン・モデル」を各種の人事施策や現場での人材育成、特にマネジャーの部下育成に具体的に活用していただくために、各役割ステージごとの詳細の説明と、モデルの活用方法についてご紹介します。
今回ご紹介するのは、現場のミドルマネジャーの育成対象となる一般社員層、「Starter」「Player」「Main Player」「Leading Player」の4つのステージです。
- 目次
- 一般社員層の4つのステージ
- 「Starter(社会人)」・「Player(ひとり立ち)」のステージ
- 「Main Player(一人前)」・「Leading Player(主力)」のステージ
- 育成で活用するポイント
- 順調にステージを登っていくための仕掛け
一般社員層の4つのステージ
一般社員層は、「Starter」=社会人、「Player」=ひとり立ち、「Main Player」=一人前、「Leading Player」=主力の4つのステージで定義しています。一般的な企業の新入社員であれば、全員が「Starter」からビジネスキャリアをスタートさせ、さまざまな経験を経てステージを登っていきます。ステージは基本的には、1段ずつ登っていきます。また、入社年次とは必ずしも関係せず、おかれた環境や与えられている業務内容によってステージは変わります。例えば、5年目ですでに「Leading Player」ということもあれば、やっと「Player」という場合もあるでしょう。
【一般社員層の4つのステージ】
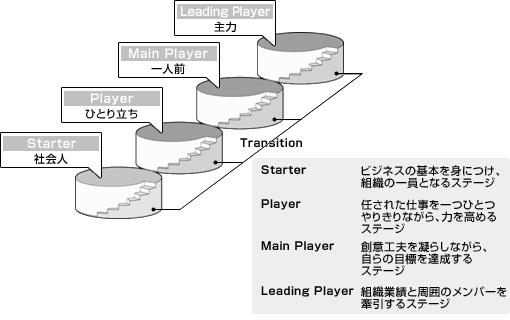
上記の図は、それぞれのステージの定義と期待される役割を示しています。読者のみなさんは、「自社ではどの階層が順調に成長しているだろうか?」「このステージにはあまり着目してこなかった」など、さまざまな感想をもたれることでしょう。一般的には、 「Starter(社会人)」や「Player(ひとり立ち)」のステージでは新入社員教育から始まる、比較的手厚い育成施策がとられています。一方で、「Main Player(一人前)」・「Leading Player(主力)」のステージの教育はどうしても手薄になりがちです。
各社ごとに、どのステージへの教育機会が不足しているのかは、バラツキがあるでしょう。そこで、各種の教育施策と連携して、特に手薄になりがちな階層には現場のマネジャーの意図的な関わりが必要になってきます。でなければ、ある一定のステージまでは成長するものの、そこで滞留するリスクが生じることになります。ここからは、各ステージの部下にマネジャーが関わるための指針となる「伸ばす」働きかけと「抑える」働きかけを、具体的にご紹介していきましょう。
「Starter(社会人)」・「Player(ひとり立ち)」のステージ
まず、「Starter(社会人)」・「Player(ひとり立ち)」についてご紹介します。
「Starter」は学生からビジネスパーソンへと転換するステージです。新入社員にとって、意識を切り替えるのは簡単なことではありません。
「自分でコントロールできない時間が増える(出社・退社時間、勤務日など)」「社会人としての言葉遣いや身だしなみを守ることを求められる」「名刺をもつ」などです。このような出来事を通じて、学生とは違う、社会や会社の一員であるという意識をもち始めます。
新人が職場に配属になると、えてして2年目社員は「お前ももう先輩になったんだから、ひとり立ちしないとな」などと周囲からハッパをかけられるのではないでしょうか。
どの時期から「Player」としての役割を期待されるかは、企業や職場によって異なりますが、次のような状態になれば、「Player」になり始めているといえます。「後輩が入り、一番下の立場ではなくなる」「自分の担当業務をもつ」「先輩の仕事を引き継ぐ」「関係者が増える」などが代表例です。
【「Starter(社会人)」・「Player(ひとり立ち)」のステージ】
」・「Player(ひとり立ち)」のステージ】.gif)
「Main Player(一人前)」・「Leading Player(主力)」のステージ
次に中堅社員と呼ばれる方々、「Main Player(一人前)」と「Leading Player(主力)」についてご紹介します。
「Main Player」 は創意工夫を凝らしながら、自らの目標を達成するステージであり、「Leading Player」 は、組織業績と周囲のメンバーを牽引するステージです。 一般的に、これらの役割ステージは企業の中で最も人数が多いといわれています。この人たちが、現場の最前線で業務を支え推進しているといっても過言ではないでしょう。
充分に役割を果たしてもらうことが求められます。
この役割ステージは年齢の幅が広いのも特徴です。一通りの仕事をこなす力や経験も身についています。それゆえ、いつ何を変えなくてはいけないのか、つまりトランジションのタイミングや内容があいまいになりがちなのです。
では、それぞれのトランジションとそれをどう乗り越えればよいのか、そして先輩や上司など周囲はどのように関わることが育成のポイントなのかを見ていきましょう。
【「Main Player(一人前)」・「Leading Player(主力)」のステージ】
」・「Leading Player(主力)」のステージ】.gif)
育成で活用するポイント
では具体的に、現場のマネジャーはこのトランジション・デザイン・モデルを、どのように育成に活用すればよいのでしょうか?
弊社では、以下の3つの場面で、効果を発揮すると考えています。
(1)タイミングをとらえた指導育成
(2)仕事の割り当て
(3)評価
ここからは、それぞれの場面についてご説明します。
(1)タイミングを捉えた指導育成
4つのステージという部下を捉える「ものさし」がなければ、新入社員以外の部下には、ほぼ同じような指導をしてしまっている可能性もあります。それを、ステージにあわせて関わりを変える指導へと変化させることができるでしょう。また、特に次のステージへの転換が始まるときこそ、「伸ばす」「抑える」意識・行動を部下が身につけられるように、マネジャーは丁寧に関わっていく必要があります。
(2)仕事の割り当て
通常、部下に仕事を割り当てる際には、現在の実力を見て、十分任せられる部下に割り当てることが多いでしょう。しかし、そうしてばかりいては、いつまでたっても部下の実力が高まりません。「もう次のステージを要望してもいい頃だな」と感じている部下には、敢えて次のステージに求められるレベルの仕事を割り当て、成長を促しましょう。
(3)評価
通常、評価をする際には業績・成果をいかにあげたか? ということが主になると思います。しかし、その観点だけだと若手よりも経験豊かなベテランの評価が常に高いという結果になることもあるでしょう。業績だけではなく、「今、その部下にどのステージの役割を期待しているか?」ということも考慮に入れる必要があるでしょう。例えば、「Leading Player」の役割を要望している部下が、業績はあげているもののチームへの貢献が低い場合などは、業種のみで評価してよいものか検討が必要です。
順調にステージを登っていくための仕掛け
さて、今回は「現場のマネジャーがトランジション・デザイン・モデルを部下育成に生かすためのヒントを提示する」という主旨で、一般社員層に着目して詳細をご紹介してまいりました。社員一人ひとりが、ビジネスパーソンとして成長し、事業を前に進める人材になるかどうかは、人事施策と現場のマネジメントの両輪が必要不可欠です。トランジション・デザイン・モデルをぜひ、人事と現場の共通言語として活躍し、「次世代を担う人づくり」を推進していく一助としていただければ幸いです。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)




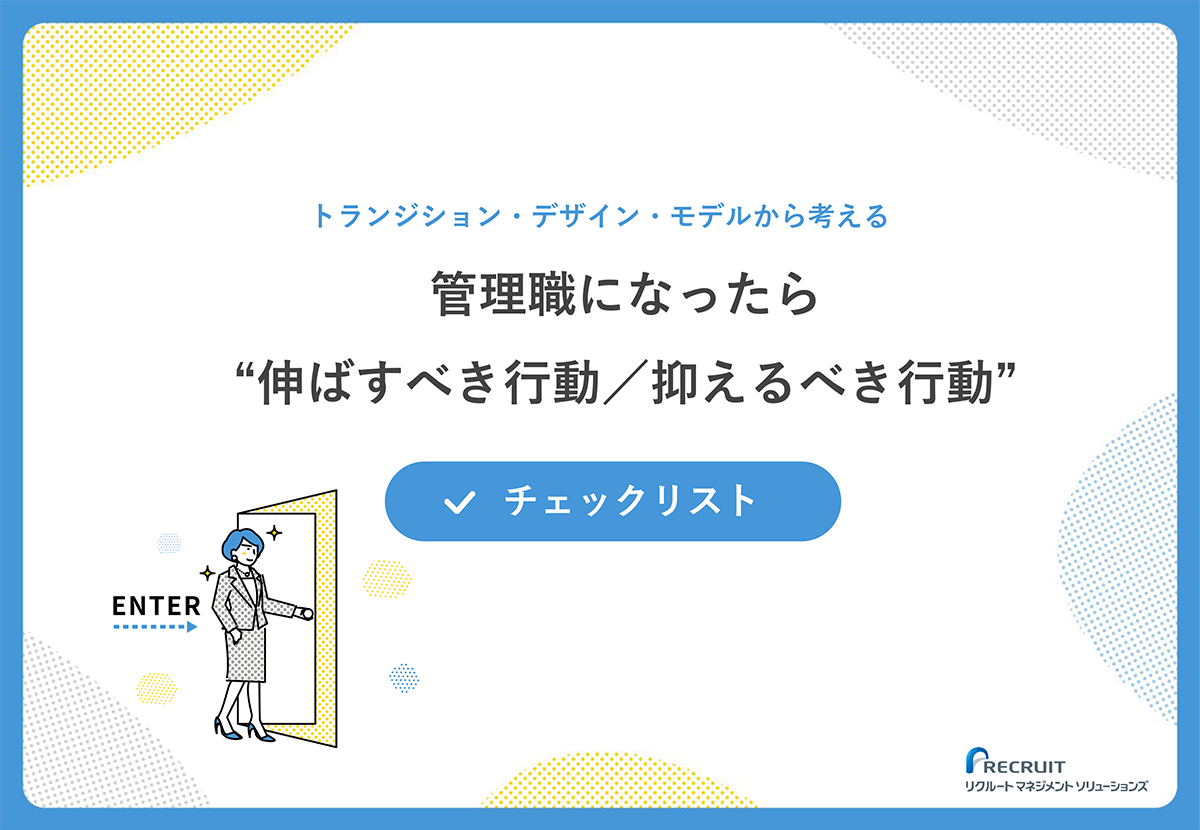









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての