特集
人材開発とマネジメントに関わるウソ・ホント
ようこそ人材開発部へ 〜異動者むけ演習〜
- 公開日:2005/04/01
- 更新日:2024/04/11

4月の人事異動で研修部・人材開発部に配属になった方も多いと思います。今回の特集は、そんな方々をターゲットとして導入演習を企画しました。肩の力を抜いて取り組んでいただければと思います。
人材開発や人材マネジメントに関わる理論や原則は、職場で起こっていることを観察・調査して体系化されたものです。研究室の中で発明されたものではありません。ですから、経営学や心理学の学者よりも、現場の実務家のほうが実践的な知恵や見識を持っていることもあります。しかし、現場で、「当たり前だ」と信じられていることが必ずしも正しいとは限りません。科学的な調査や研究からするとウソであったり、根拠が乏しいことがあります。それらの調査・研究結果をあらかじめ分かっていれば、皆さんが、研修や人材開発施策を展開するにあたり、「他山の石」として失敗を回避することに役立つかもしれません。
研修部・人材開発部に異動になった方、あるいは異動して1年未満の方むけに「導入演習」を企画しました。あなたの常識や感性で挑戦してみてください。正誤を判断するだけではなく、誤っている場合には、なぜ誤っているのか、考えてみてください。では、さっそくスタート!
演習設問(1~3)
次の設問1から10までについて正誤を判定してください。もし、間違っている場合は、その理由もあげてください。
設問1.
ある業務を教える場合、その分野で高い業績を上げている人が教えるのが効果的である。たとえば営業研修なら、トップの営業担当を講師としたほうがよい。
解答と解説
ある業務研修を企画する場合、手っ取り早い方法として社内のその道の「達人」、高業績者を考える。彼らに内容を企画させたり、講師にすることがある。高業績者や熟練者の行動を学ぶ場合には、次のような点に留意すべきだとされている(Clark&Estes1996)。
(1)高業績者や熟練者は各行動のステップを無意識に行っていることが多く、自分の行動を言葉で語ることができない傾向がある。とくに複雑な状況下、どの時点で、なぜそのように判断したのか、説明できない場合が多い。
(2)高業績者や熟練者は、技術やスキルが高いために基本的なステップを飛ばしたり、簡便にしても成果を上げることができる傾向がある。
たとえば、トップセールスの場合には、その人だからできる行動や発想を持っていたりする。彼らの方法を真似させようとしても「生兵法は怪我のもと」といった結果になりかねない。
誰が教えるかというよりも、何をどのような方法で教えるかが、研修効果を大きく左右する。したがってこの答えは、『誤り』。
熟練者、高業績者の行動の学習をさせるには、第三者が彼らの行動を観察・分析し、特殊要因と普遍的な要因に分け、他の者が学習可能なものを切り出す必要がある。また、若手の営業パーソン教育であれば、トップではなく、中堅で、オーソドックスな営業を行い業績を上げている人を選んで行動のモデルをつくることが効果的である。
設問2.
グループ単位で業績を評価・フィードバックをするほうが、個人別に評価・フィードバックした場合に比べ、個人の業績は高まる傾向がある。
解答と解説
同じ個人の生産性を比べた場合、個人単位で評価した場合よりも、グループ単位で評価したほうが生産性は低下することが調査から明らかになっている(Williams and Karau 1991,Karau and Williams 1993 )。
これは、social loafing(ぶらさがり)といわれる現象である。各メンバーは、グループで評価されるとなると、多少手を抜いても自分の評価は下がらないだろうと考え、努力の度合いを緩めるからだといわれる。また、チームで行っている業務のアウトプットを上げようとして、メンバーの数を増やすと、個人の貢献度合いに対する評価が行われにくくなると考え、個人レベルのパフォーマンスは下がっていく傾向があると報告されている。したがって、『誤り』。
しかし、この事実は、チームで業務を行うことを否定することではない。チームで一つの仕事をする上では、チーム全体の業績における個人の貢献や業績をより精緻に評価・フィードバックしないと、本来持っている個人の力を十分に引き出しにくいということである。チームで仕事をしているから、「チームの業績=各個人の業績」とするのは、安易すぎるといえる。
設問3.
エンパワーメント(権限委譲)されると、その職場の業績は向上する傾向がある。したがって仕事は、できるだけ個人の裁量にまかせるのがよい。
解答と解説
自分たちで決定できたり、裁量範囲が広がると、従業員の満足度は高まる。これは職務充実といわれる。自主的な活動を行うQCサークルなどがその例である。
業績については、従業員満足度と相関が見られるという一貫した調査結果はない。また、組織文化によって権限委譲した場合、生産性が著しく落ちたり、離職率が高くなる場合もあった(Clark 1998) 。
権限委譲される相手によっても異なる。新人や経験が不足している部下が自分の行動目標を設定したり、仕事の進め方を決めたりすることは難しい。メンバーの成熟度や能力に応じて、統制や権限委譲の度合いを変えていくことが効果的だとされている(Hersey & Blanchard 1996 )。したがってこれも『誤り』。
権限委譲を行うかどうか判断する時には、職場環境、相手の熟練のレベルなどを考慮する必要がある。人は、まかせられるとやる気になって仕事の成果が上がるものだ、と考えるのは短絡的であり、一歩間違えると、「ほったらかし」につながるのである。
演習設問(4~6)
設問4.
従業員満足度と業績は相関が高い。したがって従業員満足度が高い職場は、業績が高くなる傾向がある。
解答と解説
これまでの多くの研究によると、職務満足と個人の業績は相関関係が見られない。また業績が高い組織だからといって従業員満足が高まるともいえない (Smitter,J.W.&Collins,H 1989)
業績を上げる上では、職場環境、モチベーションもそれぞれ一つの要素であるが、それ以外に能力や必要な情報へのアクセス、ツールなどの他の要因も重要であるからである(Gilbert 1978 ,1996)。したがってこれも『誤り』。
ただし、組織全体の長期的な業績で考えると、職務満足度の低い職場は定着率が悪くなり、有能な人材の流出をもたらし、採用と訓練のコストが余計にかかると考えられる。とくに個人の熟練やスキルに依存する業務では、熟練した従業員から新人に置き換わると業績は明らかに下がるといえる。
設問5.
マネジャーは、職場の要である。したがってマネジャーの行動は、チームの業績に直接影響を与えているといえる。
解答と解説
下の図表は、56人の営業マネジャーおよびその部下263名への調査結果である。部署の風土、マネジャーの行動、部下の情報共有意欲、情報共有行動、業績との因果関連を表している。それぞれの要素の因果関係の強さは数字で表される(-1から1まで。正の数字になるほど因果関係が強い)。図から読み取れるように業績に直接影響を与えているのは、マネジャーの行動ではなく、部署の風土であった。マネジャーの行動は、組織風土を作ることに直接影響を与えるが、業績には直接影響せず、間接的に影響を与える。(高橋.2004)他の営業組織で行った調査でも同様の結果が得られた。
したがって、マネジャーの行動が直接業績に影響を与えるとするのは『誤り』である。この調査のメッセージは、組織の業績を高めるためには、マネジャーは優れた組織風土をつくることに注力しなければならないということである。
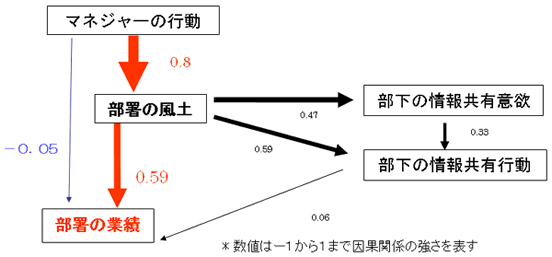
設問6.
協力的な風土になればなるほど、知識の創造が促進される傾向にある。したがって個人間で仕事の進め方で意見が食い違ったり、競争しあう風土よりも、協調型の組織風土をつくることがポイントになる。
解答と解説
組織の持っている知識が競争優位をもたらす知識競争時代を迎え、知識の共有やナレッジマネジメントは重要な経営テーマとなっている。組織内で知識が共有されるためには、メンバー間に協力的な関係が必要とされている。しかし、仲良しクラブだけでは新しい知識やイノベーションは創造されない。個人的な感情の対立や資源の奪い合いは、知識創造を阻害するが、仕事の進め方をめぐっての対立はむしろイノベーションが促進される、とくに顧客志向の強い組織ほどその傾向が強くなると報告されている(松尾.2002)。
どんな方法がいいのか、侃々諤々(かんかんがくがく)と議論していたり、お互いが優れた方法をめぐって切磋琢磨している様子を思い浮かべれば、納得しやすいだろう。協調的な風土は前提であるが、それだけではイノベーションは起こりにくい。したがってこの設問も『誤り』である。
知識が創造され、イノベーションが起こる組織にするためには、適度な緊張感・生産的な衝突が必要なのである。あえてタイプの異なるメンバーや異論を提起するようなメンバーを加えたほうが、議論が深まることは、多くの人が経験しているとおりである。
演習設問(7~10)
設問7.
人は、読んで理解する、図表や映像などのビジュアルで理解するなど、それぞれ得意な学び方がある。その人の学習スタイルに合わせて教え方や研修の仕方を変えたときに教育効果は高くなる。
解答と解説
人には、読んで理解するのが得意であったり、ビジュアルをより好む、耳から入ってくるとよく覚える、など知識を習得する上で好みがある。しかし、その人の好む、どれか一つの方法を使ってメッセージを伝えるよりも、刺激の方法を組み合わせてメッセージを提供したほうが、より知識を吸収しやすくなる(Snow, R.1998)。
したがって文章を読むのが苦手だからといって話すだけの研修ではなく、テキストを読ませたり、ビデオを見せたり、と他の五感と組み合わせて提供することで学習効果を高めることができる。したがって、設問の記述は『誤り』である。
学習効果を上げるためには、メッセージの伝え方を限定せず、学習意欲が起こるような演習や手法を組み合わせることがより重要である。研修の企画では、対象者の属性と伝える手段(メディア)を選んで終わりというのではなく、伝え方・学習のプロセスを設計することが必要である。
設問8.
本来、受講者が楽しいと思える研修であればあるほど、学習効果は高くなる。したがって研修直後のアンケートでは、受講者の満足度が高いほど研修内容がその後の業務で実践されやすくなる。
解答と解説
研修の満足度は高いに越したことはない。だからといって、満足度が高ければ、職場にもどって研修で学んだことを実践するとは限らない。これはベテランの研修担当者であればいやというほど経験していることであろう。研修の満足度は、学んでいる内容もさることながらトレーナーと受講者の相性、研修環境などに影響される(Bers,T.H.1975 )。たとえば休日をつぶしての研修は概して満足度が低くなる。
また、受講者が心理的に受け入れにくいメッセージを伝えたり、理解させる研修は、受講者の心に中に葛藤を引き起こし、終了直後のアンケートでの満足度は逆に低くなる。(Clark,R.E.1980)
良薬は口に苦しということもあるわけだ。つまり、研修直後の受講者の満足度は、研修が受講者から受け入れられたかどうかを示す。しかし、職場での態度や行動の変化を保証するものではない。したがって、この設問の記述も『誤り』である。
研修内容の実践を期待するのであれば、研修直後の受講者の満足度に一喜一憂するのはあまり意味が無いといえる。現場で実践されるかどうかは、実践する上での阻害要因を取り除いたり、上司からのサポートといった研修以外の要因にも手を打つことが必要なのである。
設問9.
業績に対して報酬を支払うことで、より高い業績を引き出すようになる。したがって業績を上るためには企業の成果主義の人事制度・報酬制度を導入することをまず考えたほうがよい。
解答と解説
これは、昨今議論されている成果主義人事制度に関連してくる内容である。結論からいうと、業績と報酬をリンクさせることでは業績をさらに向上させることはできないということが多くの研究・調査によって明らかになっている。具体的な弊害として個人が短期の業績のみしか考えなくなり、長期的なチャレンジをしないといった事態も起こる。さらに自己の業績のみに執着することでメンバー間の協働が損なわれるなどといった弊害も持っている(Nulty,P.1995,Woods,S. 1996)。したがって、設問の記述は『誤り』である。
成果主義人事は、総人件費のコントロールや利益の分配の論理など、業績追求以外のねらいで導入されているケースも多い。成果主義人事にともなう弊害を回避するためには、目標設定、評価、チームワークの醸成など、さまざまな人事施策、マネジメントの強化を行う必要があるということである。たとえば、人材開発部としては考課者訓練や人事考課のフィードバックスキルを向上させる研修によって予想される弊害を防ぐことも考えられる。扱いを間違えると、むしろ全体の業績を損なう恐れがある。
設問10.
コーチングは、本人の自発性を引き出す普遍的なOJTの手法である。したがって部下育成では、まずはコーチングから行うことが効果的である。
解答と解説
4、5年ほど前からブームになっているコーチング、ともするとコーチング万能主義の感がある。
さて本論にもどろう。これは、設問3と同じように考える。部下の成熟度によって育成の方法を変える( Hersey &Blanchard 1996 ) ことがポイントである。これは、したがって『誤り』である。
新人や経験不足の人間には、教え込むというティーチングが有効な場合が多い。
ベテランには、権限委譲が効果的である。
人材開発に絶対的な原則はない
10問とも実は『誤り』というちょっと意地の悪い演習だったかもしれません。
当たった、外れたと一喜一憂しても仕方がありません。それよりも重要なのは、なぜ正しいといえないのだろうか、どんな条件があれば正しいといえるのか、を考えることです。まず自分で考えることで知識を鵜呑みにすることが減ってきます。
研修ひとつを取り上げても、昨今は、研修が業績向上の手段や戦略・業務の推進の一環として位置づけられるケースが増えています。たんに研修だけでなく、会社の戦略や職場での環境改善まで踏み込んで、いかに目的を実現するか、考える必要があります。
人材開発は人を相手にする仕事であり、絶対的な原則はありません。また原則には必ず例外が存在します。
しかし、リサーチや研究で明らかになっている考えや原則をわかっていると、失敗やつまずきをあらかじめ回避することが可能になります。失敗しないように、少なくとも注意を向けるでしょう。
ここで紹介したこと以外にも一見するともっともらしいことでも、実はウソである、あるいは他の条件がそろわないと成り立たない原則がたくさんあります。新たに研修部・人材開発部に配属された方は、「現場感覚」を大切にしながらも、人材開発・マネジメントの奥行きの深さを「味わって」いただきたいと思います。
そしてアイディアに行き詰まったり、よりよい具体策が気になったときに、リクルートマネジメントソリューションズが皆さんのパートナーとしてお役に立てると思っています。 気楽に私どもにお声をおかけください。
参考文献のご紹介
Bers,T.H.(1975) The leadership and enjoyment : a study of student perceptions of teaching techniques. Morton Grove ,IL:
Clark,R.E.and F.Este.(1996) Cognitive task and analysis for training. International journal of Educational Research 25,no 5
Clark,R.E.(1998) Motivating performance . Performance Improvement,37(8)
Clark,R.E.(1980) Do students enjoy the instructional method from which they learn least ? Proceeding of perceptions of the annual meetings of the American Educational Reasearch Association, Chicago ,March
Gilbert ,T.F.(1978,1996) Human Competence . International Society for performance Improvement
Hersey,P.,K.Blanchard and D.Jhonson(1996) ”Management of Organizational Behavior”(7th ed) ,Prentice Hall,Inc.(山本成二・山本あずさ訳『行動科学の展開』 生産性出版,2000)
Karau ,S J and Williams,K.D.(1993) Social loafing : a meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social psychology 61:
松尾睦(2002)『内部競争のマネジメント-営業組織のイノベーション-』白桃書房
Nulty,P.(1995,November 13) Incentive pay crippling. Fotune,235
Smitter,J.W., Collins,H. and Buda,R.(1989) When ratee satisfaction influence performance evaluations: a case of illusory correlation. Journal of applied psychology,74
Snow ,R.(1989) Aptitude-treatment interaction as framework for research on individual difference in learning. Learning and individual differences. New York Freeman
高橋勝浩(2004)「営業組織における知識共有の要因に関する研究」筑波大学大学院経営・政策科学研究科修士(経営学)論文
田辺秀俊(2002)「実践 ビジネスコーチング」 PHP研究所
Williams,K.D, S J.Karau.(1991) Social loafing and social compensation: The effects of expectations coworker performance. Journal of Personality and Social psychology 61:
Woods,S.(1996)High commitment management and payment systems. Journal of management studies.33,55.
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



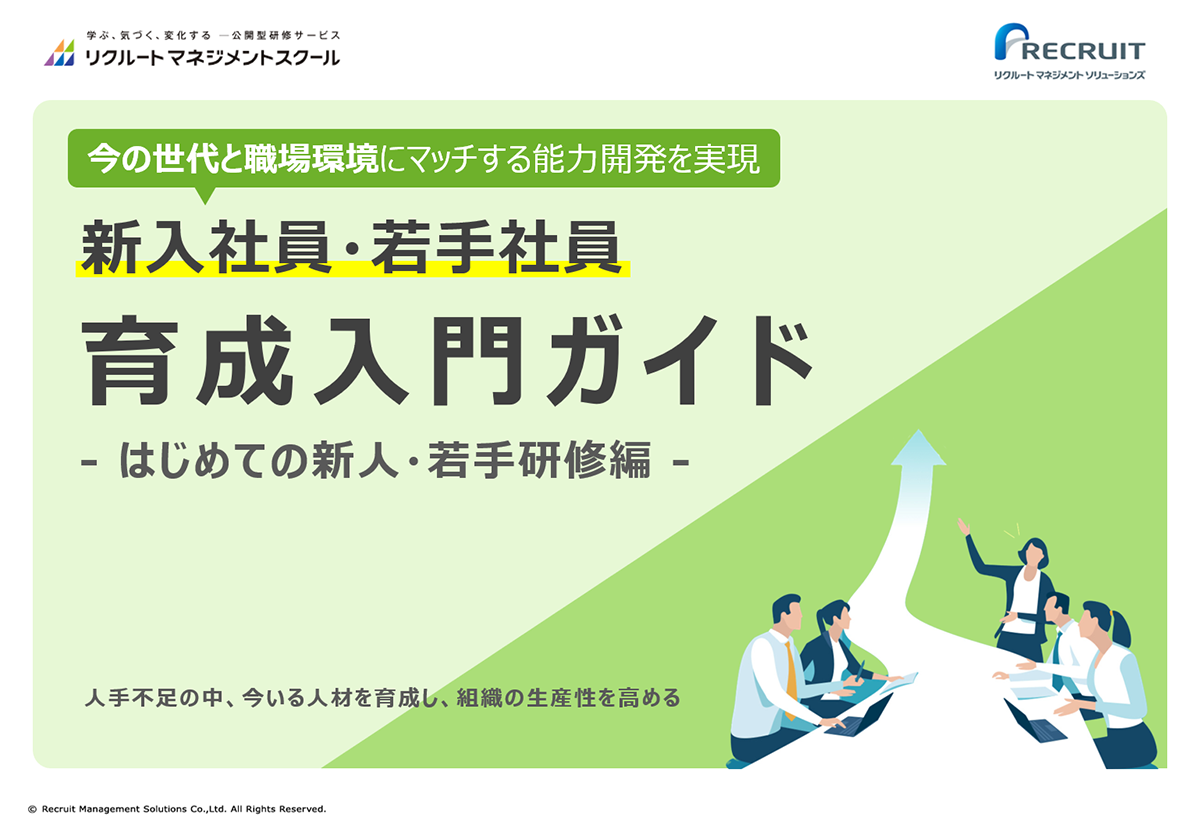
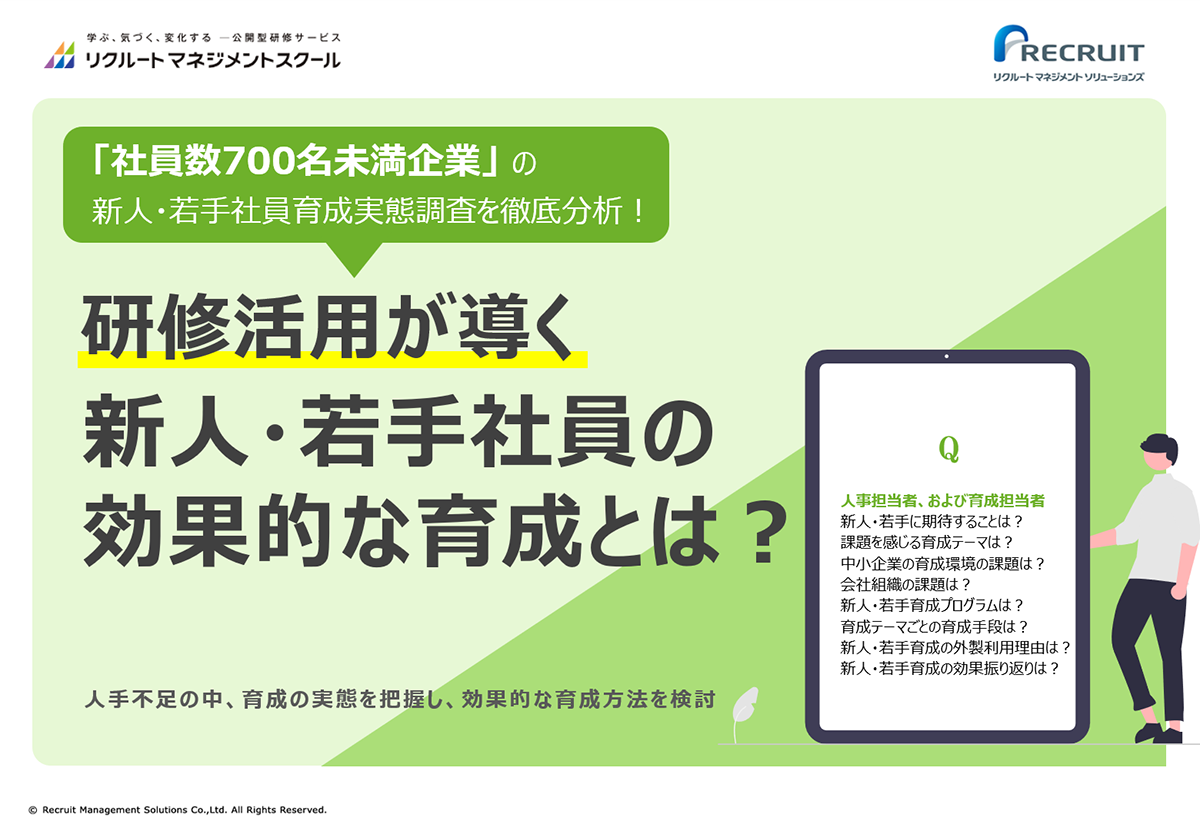









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての