特集
「現場」視点から捉えた成果主義人事
マネジャーを取り巻く“現状の壁”をどう突破するか
- 公開日:2004/10/01
- 更新日:2024/04/11

この時期、新しい期を迎えられて「今期の目標をどうしよう」と考えられている方は多いと思います。
今回の特集では「メンバーに組織の方針を浸透させたいマネジャー」と「納得感のある目標設定をしたいメンバー」の両者の現場視点から、成果主義人事について考えてみたいと思います。
「人事制度の定着」ってどんな状態?
今期のテーマをどう掲げていますか
「人事制度の定着が今期の人事部のテーマです」などとよくお聞きします。そんな時、意地悪に「『人事制度の定着』というのは、悪い目標の書き方の典型例ですよね」とお答えすることがあります。
「目標」とは一定の期間において、「何を(指標)」「どこまで高めるか(水準)」の二つが込められたものです。しかし、「人事制度の定着」という言葉にはどちらも含まれていません。その結果、その意味するところが社内の中でもすりあっていないことが多いようです。
ここで、比較的よくある「人事制度の定着」という状態を表す表現をご紹介します。
「人事制度の定着」って、どんな状態?
1)ルールがしっかり守られている
2)総額人件費の管理が実現した
3)従業員の評価への不満が減った
4)上司との会話が増え、職場運営がスムーズになった
5)人材の競争力が高まっている
6)業績が向上した
いかがでしょう。上記の中で、どれがイメージがつきやすいですか?
例えば、方針としては「5)人材の競争力が高まっている」を掲げるものの、実態としては1)~3)を目指している企業も多いと思います。
「人事制度の定着」の注意点
目的をどう置くかで検討する視界が変わる
前ページの「人事制度の定着」という状態を表す表現において、「どれが正解」というものはありませんが、ひとつ言えるのは目的をどのレベルに置くかにより、思考の範囲が変わることです。
例えば、「1)ルールがしっかり守られている」のみをゴールに置くと、次のような展開が予想されます。
ルールを徹底させる → 守ること(守らせること)が目的化する → 形骸化する → 何かのきっかけで消滅する → 人事は困るが現場は困らない
では「2)総額人件費の管理が実現した」をゴールに置いた場合はどうでしょうか。
人件費を左右する人事評価に公正さが求められる → 評価に完全はないし、賃金が下がる人は必ず出る → 不満が出る → さらに評価の公正さを追求する → 迷宮入り
このように、狭い視界だけで考えると、打ち手がどんどん対症療法になってしまいます。広い視界で捉える必要がありそうです。
すると、やはり「5)人材の競争力が高まっている」ぐらいを目的に置くべきかな……となりますが、そうすると実はまた厄介な問題が立ちはだかることが多いのです。
思考停止ワードに要注意
目的を高く掲げると、議論が抽象的になる恐れがあります。例えば、次のような方針を掲げている企業は多いと思います。
1)人材育成に向けたコンピテンシーの導入
2)評価のフィードバックを通じた能力開発の実現
3)人事制度改革を通じた組織風土の変革
4)業績連動型賞与によるモチベーションの向上
これらが悪いと言っているのではありません。現実を踏まえ、現場で具体論に展開されていればOKです。しかし、これらの「聞き心地のよい」方針のみでは、従業員には実は何も伝わりません。例えば、「4)業績連動型賞与によるモチベーションの向上」というのも、現場には「業績悪いと下がるのね」と聞こえているかもしれません。
思考停止ワードとは「何か最もらしいことを言っているようで、実は何も語っていない言葉」です。上記の方針はまさに思考停止ワードと言えます。人事の言葉で完結するのではなく、現場の状況を踏まえて語らないと何も伝わりません。
では、一方で現場のマネジャーを取り巻く現状はどうなっているのでしょうか。
評価を行うマネジャーの心境
現状の壁に直面するマネジャー
よく評価の問題は「評価される部下の不満」がクローズアップされます。しかし、評価する上司の心境はどうでしょうか。
<評価を行うマネージャーの心境>
・低い評価をフィードバックするのは嫌だし、本人もやる気が下がるだろうから、標準にしておこう。
・高い評価をつけておこう。結局は後で調整されるんだから。
・部下の行動なんて、日々見ていられない。
・一人一人やっていることが違うから、評価基準なんてもってない。
面倒だ。評価で時間を使うぐらいなら、別の仕事をしたい。
・低い評価をどう返却しよう。
・会話がもたない。1対1で話すのは怖い。
・「育成につなげる」よりも、とにかく穏やかに返却したい。
一言でいうと「勘弁してくれ」「人事の言いたいことは分かるけど、実態はそうはいかない」といったところでしょうか。このような”現状の壁“に直面しているマネジャーに、「目標とはそもそも…」と投げかけても、聞く耳を持ってもらえそうにありません。
評価に満足しているメンバーのコメント
ある会社で、評価に満足しているメンバーを抽出しインタビューする機会がありました。彼らの目標管理シートを見ても、特にしっかり書かれているわけではありません。インタビューで聞かれた声は以下のようなものでした。
~評価のフィードバックを受けて納得したメンバーの声~
・評価面談時には徹底的に自分の考えを聞いてくれた。それを理解したうえでの上司の判断であれば、受け止めるしかない。
・1時間の評価面談が3時間にもなってしまった。上司も忙しい中だろうが、時間を惜しむことは一切無かった。
・上司は、自分のプロジェクトでの仕事ぶりについては、わざわざプロジェクトリーダーに聞きにいっているそうだ。かなり細かく聞かれたと、リーダーは言っていた。
・低い評価ではあったが、営業同行時に毎回のように「今後はこうすべき」とフィードバックを受けた。改善できなかった自分が悪い。
・上司はいつも自分の先のキャリアのことを考えてくれている。先のことを考えると、今の一時の評価に必要以上にこだわっていても意味はない。
面白いのは、「評価基準」「客観性」といった言葉はあまり出てこないことです。もちろん、彼らの上司が評価の客観性を求めていないわけではないのでしょう。
しかし、その限界を心得ており、評価をしっかり行うと共に、「長い目で成長を支援しよう」「日頃の会話を大切にしよう」「気がついたことはすぐにフィードバックしよう」「部下の成果はちゃんとみよう」という意識を強く持っているのではないでしょうか。
人事評価の納得感を高めるヒント
評価の納得感を高める方程式
以下は筆者が各社の評価制度設計・運用の経験から生み出したモデルですが、評価に対する納得感というのは次のような要素で構成されるのではないでしょうか。
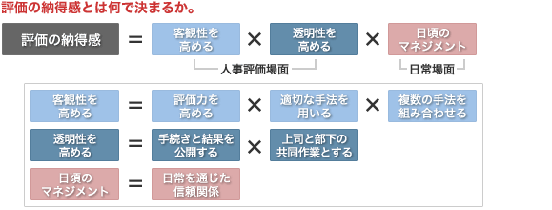
客観性と透明性は人事評価を通じて高めていくものです。無論、評価力とは目標を設定し、その結果とプロセスを把握する力なので、これらすべてが人事評価時のみに発揮する力ではありません。
そして、ポイントは最後の「日頃のマネジメント=日常を通じた信頼関係」です。先ほどの評価に満足しているメンバーへのインタビューを見ても、ここのウエイトは高いようです。
最後は上司の主観を受け入れられるか
評価基準がきわめて明確で、客観性が完全に確保されるのであれば、わざわざマネジャーが評価する必要はありません。表計算のソフトに任せておけばよいでしょう。しかし「評価」とは単なる「測定」ではありません。あくまでマネジャーの主観が混じった価値判断なのです。
すると、上司の主観が信じられるかどうか、がポイントになるわけですが、それはやはり日頃のマネジメントにかかってくるといえるでしょう。
逆に言えば、「評価への不満」=「Mgrへの不満」であることが多いのではないでしょうか。
客観性を追求するとともに、日常的なマネジメント力を強化すること
しかし、客観性を放棄してよい、と言っている訳ではありません。客観性を高める努力は必要です。目標の設定方法、面談の実施、調整会議、賞与への反映方法……すべて整っていることが前提です。ここを疎かにし、日常のマネジメントだけで納得感の高い評価を実現するのは無理でしょう。
しかし、客観性を追求しすぎるのも無理があります。プロジェクト単位での業務遂行、各業務の専門性の高まり、プレイング比率も高く部下を日々ウォッチできない……部下の成果や日々の行動を明確に把握することは、難しい現状になっているのです。
成果主義人事を進めるにあたっては、「人事制度をまずは整備する」「マネジャーが基本的&実践的な評価スキルを獲得する」に加えて、「マネジャーの日常のマネジメントを強化する」にヒントがありそうです。
さいごに
リクルートマネジメントソリューションズが提供するサービス
この10月をもって、リクルートでトレーニング事業を営んできたHRD事業部と、SPI 2をはじめとしたアセスメントや経営人事コンサルティングサービスを提供してきたHRRは事業統合いたしました。今後は、トレーニング、アセスメント、コンサルティングという手段を幅広く有することで、人と組織に関する問題に対して、これまで以上に最適なソリューション手法を提供していくことができるようになります。
今回のテーマである成果主義人事の推進に関しても、成果主義人事制度の設計、各社の制度に沿った考課者研修はもちろんのこと、
・成果創出に向けて力強く組織をリードするマネジメント強化研修の提供
・コンピテンシー評価の運用支援(多面評価)及びそのアセスメント結果を用いた能力開発
・そもそも組織があげるべき成果や重視したいバリューの明確化とその浸透支援
など、幅広いサービスを一貫したコンセプトでご提供することができます。
また、この特集コーナーでも様々なメッセージをお客様に向けて発していきたいと思っております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


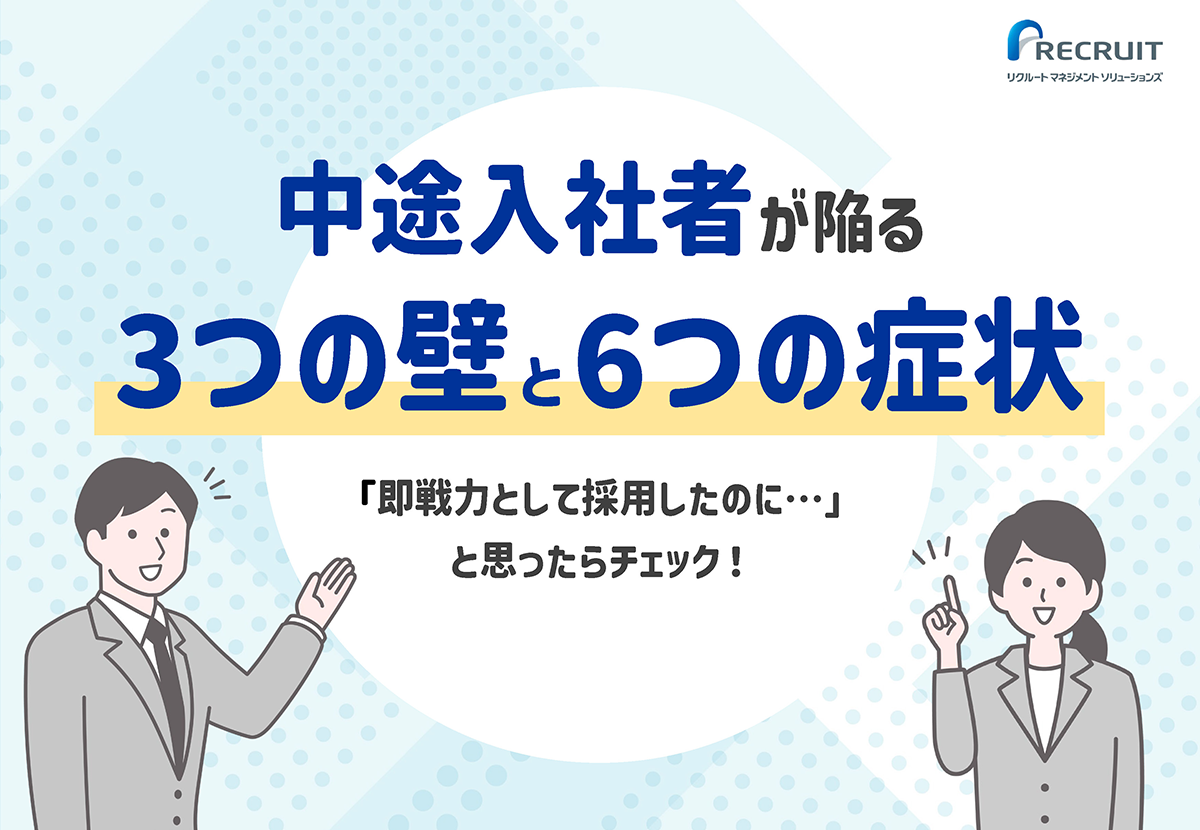
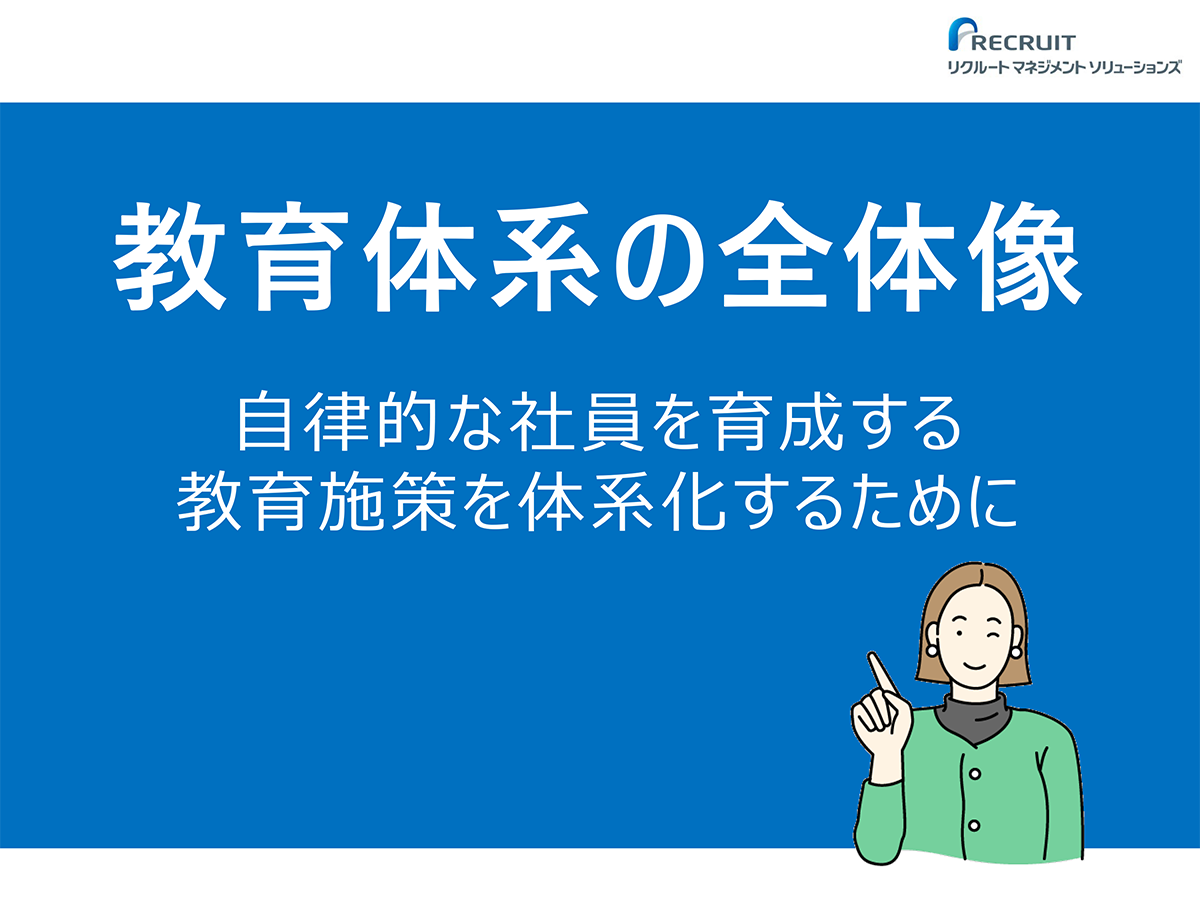
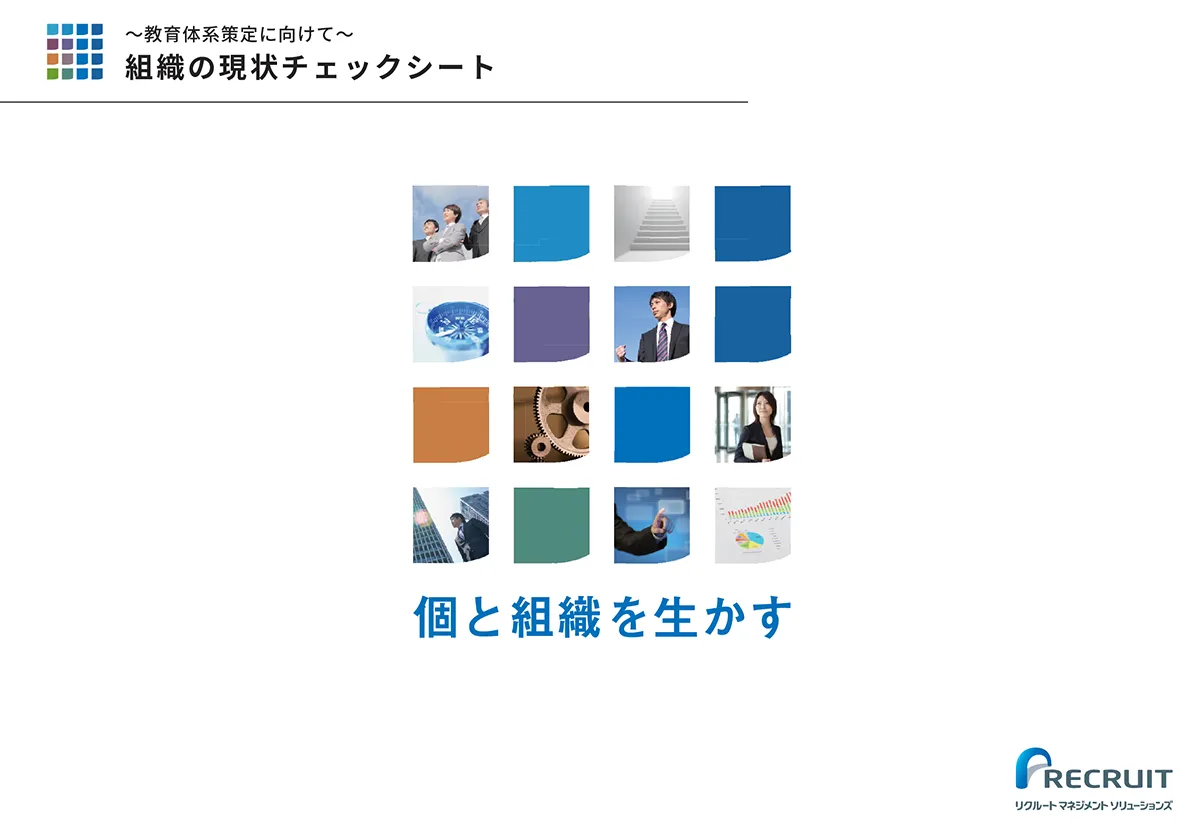









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての