特集
一時のイベントで終わらせないために
次世代リーダー育成は早期から行うべきか?
- 公開日:2012/06/11
- 更新日:2024/04/11

多くの企業で、「次世代リーダー育成」や「次期経営者育成」と銘打ち、今後の会社・事業の舵取りを任せられる人材を早期から、そして計画的に育てようという取り組みが行われています。
グローバル化の進展をはじめとして、日本企業を取り巻く環境が変化していることにより、経営者が直面する経営課題の難易度は上がっています。それに伴い、経営人材候補にも、より高い能力とバイタリティが求められるようになり、次世代リーダー(次期経営人材)を育成することの経営的な重要性も増しています。
一方、弊社が毎年開催している『RMS Forum』のアンケートでは、「関心が高い人事テーマ」として、「次世代リーダー育成」が2年連続で第1位となっており(2010年、2011年)、多くの企業が課題を感じていたり、安易に着手できるテーマではないと感じているようです。
今月の特集では、この次世代リーダー育成の取り組みの現状と考え方を確認した上で、効果的な育成を行う上でのポイントを考えてみたいと思います。
「次世代リーダー育成」の実態
「選抜型の経営幹部育成に関する実態調査」(出典:『企業と人材』 2012年3月号)によると、2012年で制度を導入しているのは37.7%、1,000人以上規模の企業に限ると導入率は55.6%となっています。次世代リーダーの選抜対象としては、課長層が62.2%、次いで次長・部長層が54.1%となっており、ある程度マネジメント経験を積んだミドル層を対象とするケースが多くなっています。
つまり多くの企業が、教育研修後に経営層としてすぐに登用するより、将来、経営を担える人材のプール群を豊かにすることを主目的として実施されていることになります。
一口に「次世代リーダー育成」といっても、その中身は各社様々です。特に課長層を対象とした育成施策においては、「集合研修を中心とした教育研修プログラムの付与」と「ローテーションや異動・配置による、実務経験の機会提供」の2つに大別されます。
【図表1.「次世代リーダー育成」の全体像】

●集合研修を中心とした教育研修プログラムの付与
経営戦略論やマーケティング、会計といった「経営幹部として必要な知識(経営リテラシー)付与のための集合研修」と、「学んだ知識・スキルを使った、事業変革課題の提言とその実践活動(アクションラーニング)」を組み合わせ、半年から1年間の比較的長い期間をかけて実施するケースが多くなっています。
●ローテーションや異動・配置による、実務経験の機会提供
「人は仕事経験を通じての学びが最も大きい」といわれています。選抜した人材に、たとえば企画業務や新規事業担当を担わせることで、経営スキルを磨き事業観を養っていただきます。
弊社がお手伝いをさせていただいているある企業では、約半年間のトレーニングを終えた対象者に、「戦略推進に寄与する、新たなKPIの設定と、人事制度への反映」という、これまで役員の方が担っていた経営テーマの推進を任せることに決めました。役員の方いわく、「これまでは素振りをさせていたが、今回はバッターボックスに立たせる」。言い得て妙ですね。
成長を促す「6つの刺激」
どのような経験がリーダーとしての成長を促すのかについては諸説ありますが、弊社では以下の「6つの刺激」を伴った良質な経験が、経営人材として求められる能力・スキルの獲得を促すと考えています。
【図表2.次世代リーダーの成長を促す「6つの刺激」】

しかしながら、「社内に修羅場となるような、良い経験の機会がない」「タイミングよく現在の部署から異動させることは簡単ではない」というご相談をよくいただきます。確かに、不振事業の立て直しや、海外赴任、子会社でのマネジメントなどは大きく成長するための良質なチャレンジとなります。ただし、こういった機会がなければ現場で次世代リーダーの育成ができない、というわけではありません。
弊社の特集『効果的な次世代リーダーの育成法』(2011年5月)では、リーダーとしての成長を促す経験として、仕事の割り当てや、成長を促す人間関係を紹介しています。この中では、同僚が不在の期間、その職責を引き受けるという仕事を割り当てたり、「対話の相手」として、異なる見解や観点を提供する、といったことを挙げています。これらは上司や周囲の裁量で実施が可能なものであり、改めて機会を探せば、日々の仕事の中にも次世代リーダーを育てるチャレンジはいろいろと見つかるのではないでしょうか。
早期育成に潜む「落とし穴」
これまで見てきたように、「経営リテラシー教育」と「事業上の課題設定、実践活動」をセットにし、できるだけ現実環境に近い状況でインプットとアウトプットを行う機会の提供が増えています。しかしながら、必ずしも「うまくいっている」と満足されている企業ばかりではないようです。それはなぜでしょうか。
その一番の要因として、育成施策全体の絵が描けておらず、教育研修プログラムがイベント化していることが挙げられます。
先の「次世代リーダー育成の実態」で見たように、早期に候補者を選抜して育成する場合、課長層が対象となることが多く、実際に経営の職責を担うまでに、10年、場合によっては20年ほどの準備期間があることになります。その間は経営層ではない立場で仕事をしつつ、チャレンジを伴う経験をくり返し、経営者になるべく鍛錬を積み重ねる必要があります。
しかし、教育研修プログラムを実施した後、個人別にどのように育成するのか、という計画がなされないままにスタートしているケースが見られます。そのため、学んだことは使われることなく「無用の長物」となり、スキルが磨かれません。本人も、「何のために自分は選ばれて、あのような大変な取り組みをやらされたのか」がわからないままです。結局、受講者に目に見えた変化が見られず、教育研修プログラムが「イベント」と化してしまうのです。
早くから育成に着手すべき、と考えていたはずなのに、早期にスタートしたがために仕事上の実践に生かされず、その投資効果に疑問符がつく……というのは皮肉なことです。
では、この“早期育成の落とし穴”にはまらないようにするには、どうすればいいのでしょうか。
教育研修プログラムで実現すべき2つのこと
次世代リーダー育成における教育研修プログラムは、その後の日常(職場)における継続的な育成につながってはじめて意味を持ちます。プログラムはあくまで育成構想全体の一部であり、この位置づけをぶらさないことが重要です。
つまり、早期から次世代リーダー育成を始めるのであれば、実務を通した次世代リーダー育成まで視野を広げた上でプログラム設計をする必要があります。
このことを踏まえた上で、改めて、「教育研修プログラムで実現すべきこと」を考えてみましょう。
1.受講者の主体性や意欲を引き出す
期間限定の教育研修プログラムの中では、最後に経営へのプレゼンテーションを設けるなど、半ば強制的に学習に取り組ませることは可能です。しかしプログラム後の日々の仕事の中で、経営者となるための学習を続けるのはよほど強い意志がないと難しいでしょう。そう考えると、受講者が学び続けることへの主体性や意欲を持つことが必要になります。
受講者の主体性や意欲を引き出すには、以下の3つの方法が考えられます。
(1)そもそも意欲の高い社員を、手挙げ・自薦で選ぶ
(2)現在の経営者・事業責任者が、自ら後継者として期待していることを受講者に伝える
(3)プログラムを通して、自分が学んだこと、気づいたことやできるようになったことをふり返ることで、自分の可能性や影響力が広がることに面白み感じる
2.一人ひとりの、次世代リーダーとしての強みと弱みを明らかにする
対象者のリーダーとしての成長には、プログラム終了後も、上司あるいは経営者自らが継続的に関わり、個々の仕事や役割を設計し、チャレンジする場の提供やフィードバックを行うことが必要になります。
適切な機会付与やフィードバックのためには、対象者を集団としてではなく「個人」として捉え、一人ひとりの強みと弱みを明らかにすることが必要です。
半年から1年間の取り組みは、対象者一人ひとりの特徴を観察する良い機会となります。必要であれば行動観察のプロフェッショナルの力を借りて、対象者の特徴を観察・記録し、それを上司や経営者と共有することが望ましいでしょう。
また、経営者自らが対象者の取り組みを自らの眼で見ることで、対象者の可能性を直に把握し、選抜・登用する際の材料とすることもできます。
さらには、人材データベースを整備し、受講者の観察結果を蓄積していくことで、会社全体でその情報を共有し、次世代リーダー候補者の選抜・育成を計画的、組織的に進めるために活用することも可能になります。
さいごに
せっかくの教育投資を無駄にしないためにも、自社にとって最適な選抜育成の対象を設定することが重要です。とにかく早期から着手することが大事だと思いがちですが、必ずしもそうとは限りません。
事業をとりまく環境変化の速さとそれに応じたリーダー像の変化や、現在の次世代リーダー群の充足度によっても、必要となる育成スピードや最適な育成対象層は異なります。
自社を取り巻く環境や戦略を踏まえ、そのために必要となる経営人材像と、その育成対象や方法を検討することが重要となります。
次世代リーダーの育成には長い時間がかかり、そこに近道はありません。結局、育成を成功させるには、どれだけ丁寧に一人ひとりの思考や行動をつぶさに観察し(アセスメント)、現実の仕事の中で主体性を持って困難な課題に取り組み(チャレンジ)、周囲や経営者からの支援やフィードバック(サポート)を、一人ひとりに合った形で提供できるか、に尽きるといえるでしょう。
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

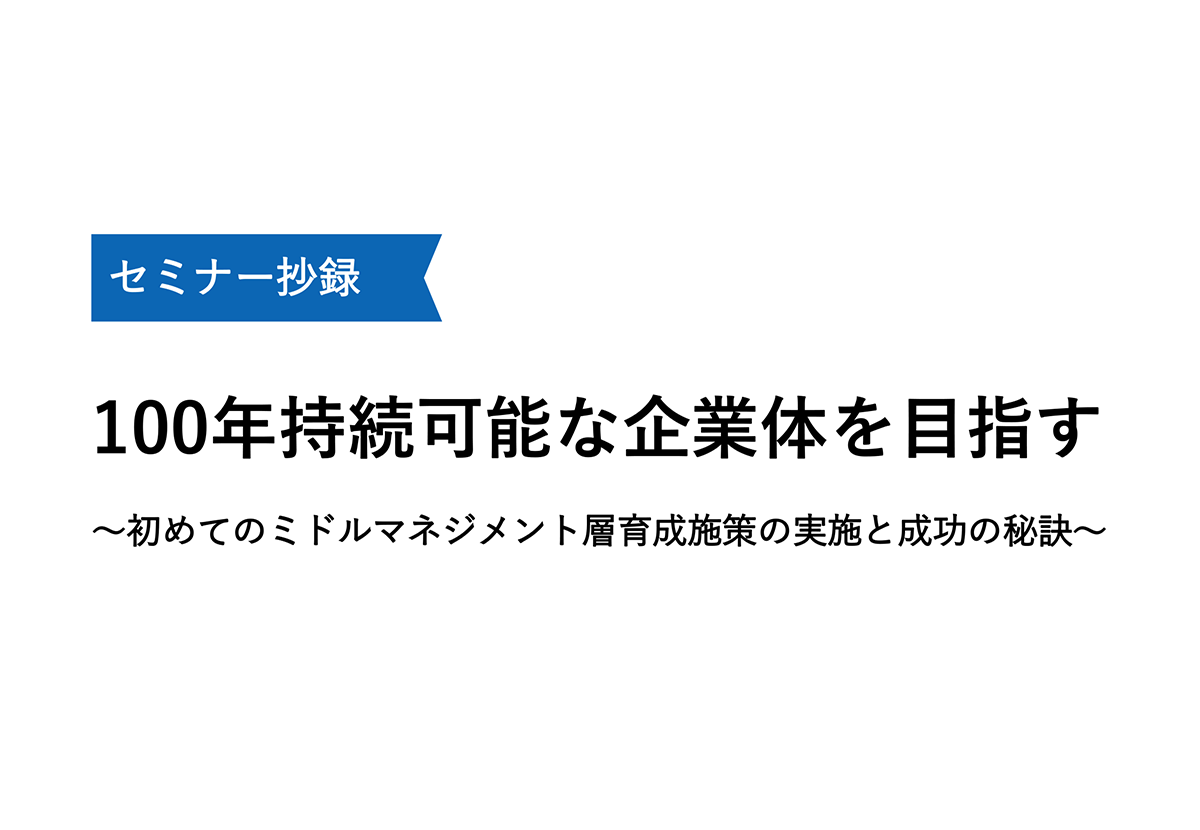









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての