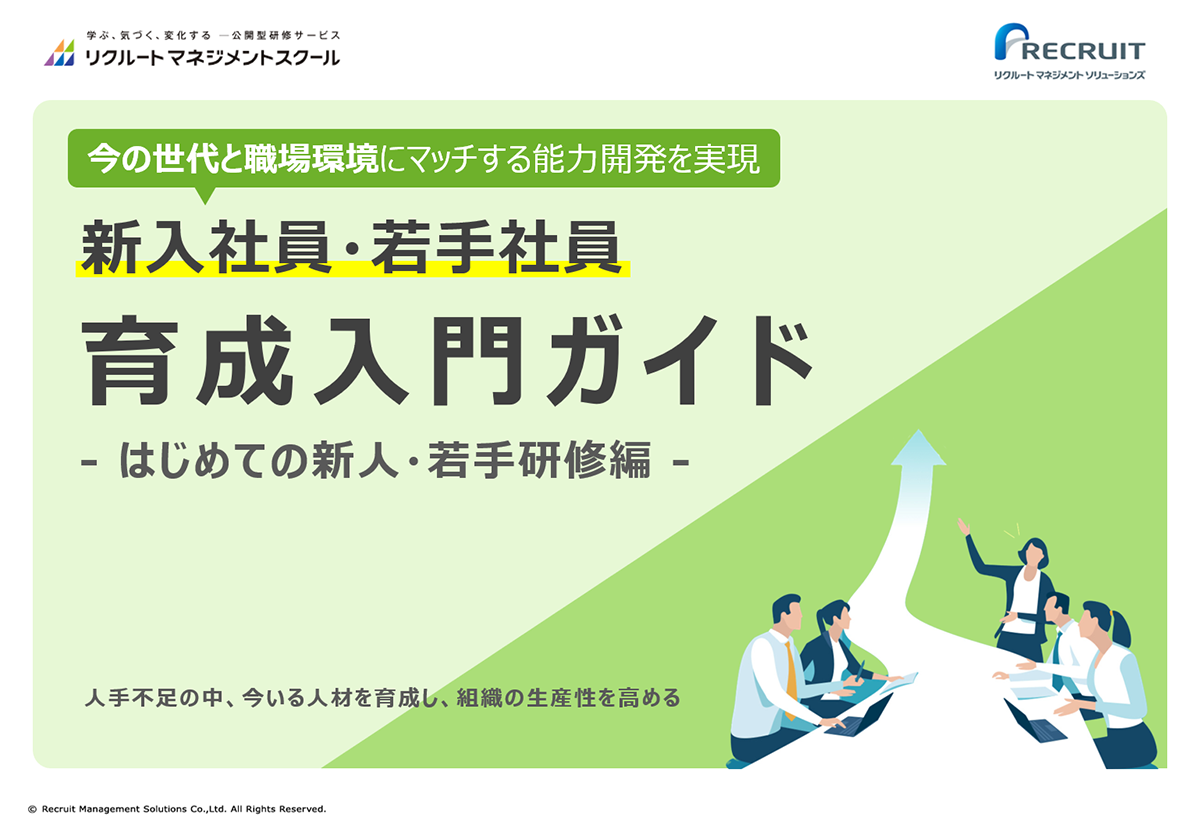連載・コラム
【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【後編】
AIがコーチングできる時代。“生身の対話やコーチング”に宿る価値とは?
- 公開日:2025/06/16
- 更新日:2025/07/21

コーチングのパイオニアとして知られる鈴木義幸氏をお招きし、対話の価値と可能性を探る鼎談シリーズ第3弾。最終回となる本記事のテーマは、「DXと人材育成」です。オンラインでいつでも話すことができる昨今において、あえて対面で話す意味とは何なのか。AIコーチングが登場している時代において、あえて人が人を育てる意味とは何なのか。実際にオンラインでのコーチングや、AIコーチングサービスを提供している鈴木氏ならではの視点を伺いました。
鼎談メンバー
●鈴木 義幸氏(株式会社 コーチ・エィ 取締役 会長)
●桑原 正義(リクルートマネジメントソリューションズ サービス統括部 主任研究員)
●武石 美有紀(リクルートマネジメントソリューションズ サービス統括部 研究員)
- 【専門家に聞く】第3回 希望学と新人・若手社員育成
- 若手社員が壁にぶつかったときにどう関わる?~逃げずに“ウロウロ”する考え方~
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【後編】
- AIがコーチングできる時代。“生身の対話やコーチング”に宿る価値とは?
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【中編】
- 部下とのコミュニケーションを円滑にする、“本音”と“ご機嫌”のススメ
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【前編】
- コーチングのパイオニアに聞いた、“考えさせる対話”のコツ
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【後編】
- 「業務の進捗どう?」で終わらない、若手社員とのコミュニケーションのコツとは?
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【前編】
- ダイバーシティ実現を目指すなかで、若手をどう育てる?―― “ダイバーシティ”との向き合い方を考える
デジタル時代の今、“生身の人間同士”の対話の強みとは?
武石:昨今はオンライン技術の発達によって、リモート会議などの「対面ではない対話」が増えています。育成の現場からは「オンラインでは部下との関係性がなかなか育たない」という声も多くいただくのですが、オンラインでの育成や関係性づくりというのは、やはり難しいものなのでしょうか。

鈴木:育成も関係性づくりも、リモートだと難しく感じることは多いです。
前回も対話のコツについて触れましたが、対話をする時は、「自分と相手が何を感じているか」を擦り合わせることが重要になります。対面なら相手の機微にも気づきやすいので、「何か話していないことはない?」や「どうしたの? 焦っていない?」など、いろんな言葉が出てくるんですよね。
ですがリモートだと、相手の反応を感じ取ることが難しくなります。「相手が今、何を感じているのか」を察するにあたって、一番ものをいうパーツって目なのです。そのため、オンラインで目の表情が読み取りにくく、身振りも分からないなかで、「関係性をつくりましょう」というのは、やはり難しいと思います。
リモートで会話する時に画面をオフにするとなると、コミュニケーションの難度は増します。上司の立場としても、社員に配慮する気持ちから「画面をオンにしてほしい」と伝えにくいとは思うのですが、せめてコミュニケーションを取る時は相手の顔を見るようにしたいですね。
桑原:DXに関連するホットトピックとして、AIを使った育成についてもお伺いさせてください。鈴木様が会長を務めているコーチ・エィでは、さまざまなコーチングサービスを提供されています。AIによるコーチングがどんどん発達していくなかで、人間によるコーチングの価値とは何なのでしょうか。
鈴木:AIコーチングと対面コーチングは、一長一短なのです。AIコーチングの方が優れているところは、ユーザーが何でも言えてしまうことにあります。人間相手だと「こんなことを言ってしまっていいのだろうか」とブレーキがかかるところを、すんなり言えるんですよね。抑制がかからない分、クリエイティビティの発揮にも繋がります。ブレインストーミングをしたい時は、むしろAIコーチングの方がいいのかもしれません。
一方で対面コーチングの方が優れているところは、誰かに聞いてもらった実感があることと、約束というパワーをもらえることです。人間のコーチに「絶対に実現してみせます」と誓ったことって、「やってやろう」という心理的な拘束力がはたらくんですよ。

武石:確かに、自分の誓いを受け止めてくれた人がそばにいると、底力が湧いてくることもありますね。そういった面は対面コーチングならではの強みといえそうです。
鈴木:ただ、「人の感情を受け止める」という機能も、ゆくゆくはAIが実現できてしまう可能性はあります。今のAIコーチングは文章が主流ですが、ユーザーの声や表情を分析して、適切な感情でコーチングしてくれるアバターがいたら、人は心地いいと思うかもしれません。そうなった時に、対面コーチングの価値が残るのか、残らないのか、蓋を開けてみないと分からない面はありますね。
ただ、生身の人間のコーチを受けたいというニーズはきっとなくならないと思います。AIコーチングと対面コーチングのそれぞれの強みを生かしながら、人々の成長を支えていけるようになればいいですね。
即戦力を採用できるコーチングのパイオニアが、あえて若手を採用し育てる意味
桑原:御社はコーチングのパイオニア企業ですが、10年ほど前から新卒採用もされているそうですね。御社ほどの企業ブランドがあれば即戦力となる人材も獲得しやすいと思うのですが、新卒の方を育成されているねらいは何でしょうか。

鈴木:たとえ社会人経験がある方でも、コーチとしてすぐに活躍できるわけではありません。新卒・既卒にかかわらず、全員に育成期間は必要です。ですので、私たちは採用において「即戦力かどうか」ではなく、「コーチとしての素養があるかどうか」を重視しています。
そしてこの素養は、社会人経験の有無とは必ずしも関係ありません。むしろ、新卒の方であっても、コーチに必要な素養をしっかりと持っている方は確実に存在します。ですから、「即戦力でない新卒より、既卒が良い」という考えは、私たちにはありません。
また、会社としても常にフレッシュな視点を持ち続けたいとも思っています。組織の平均年齢が上がり、人の流動性が低くなると、どうしても視野が固定的になりがちです。物事を新鮮に捉える視点を持ち続けるという意味でも、新卒の方の存在はとても魅力的だと感じています。
あとは、自分が歳を重ねたからこその意見かもしれませんが、若い方がいると場のエネルギーが明らかに違うんですよ。もちろん年齢が高くても元気な方はたくさんいますが、場のムードをつくる時に、若さは大きな力になります。若手はデジタルを扱う技量も非常に高いですし、彼らの力を生かせる場面も多いと思いますよ。
桑原:弊社としても、組織と若手が相乗効果を生むような環境づくりをサポートできればと思っています。昨今はVUCA時代の慌ただしさもあって、育成の時間を確保すること自体が課題になるケースも多いのですが、やはり若手と前向きに対することが、組織の可能性を広げることに繋がると伝えていきたいですね。
鈴木:そもそも次世代を育てることは、人類の発展のために必要なんですよね。会社の新人の育成がどうこうではなく、次世代が育たなかったら、そこで人類の進化は止まってしまうのです。極論、次世代を育てないことは進化を放棄することと同じですから(笑)。
人里離れた山奥ではなく、あえて社会という輪の中で生活していくなら、次世代を育てることは何も特別な任務ではありません。先に生まれた人間として、次を育てる責任があると思えるようになったら、育成への向き合い方も変わっていくのではないでしょうか。

桑原:若手と接して自分にはない発想をもらうことで、育成に対して新しい視点を持てるようになる方もきっといらっしゃると思います。本日はありがとうございました。
本コラムでは、対話を軸にした新人・若手育成の重要性について、鈴木義幸氏に3回にわたりお話を伺いました。
弊社では、新人・若手のオンボーディング支援や、対話力を強化する研修プログラムなど、さまざまなソリューションを提供しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
関連するサービス
管理職向けコーチング研修
新人・若手育成ソリューション 新入社員研修・若手社員研修
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
- 【専門家に聞く】第3回 希望学と新人・若手社員育成
- 若手社員が壁にぶつかったときにどう関わる?~逃げずに“ウロウロ”する考え方~
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【後編】
- AIがコーチングできる時代。“生身の対話やコーチング”に宿る価値とは?
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【中編】
- 部下とのコミュニケーションを円滑にする、“本音”と“ご機嫌”のススメ
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【前編】
- コーチングのパイオニアに聞いた、“考えさせる対話”のコツ
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【後編】
- 「業務の進捗どう?」で終わらない、若手社員とのコミュニケーションのコツとは?
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【前編】
- ダイバーシティ実現を目指すなかで、若手をどう育てる?―― “ダイバーシティ”との向き合い方を考える
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)