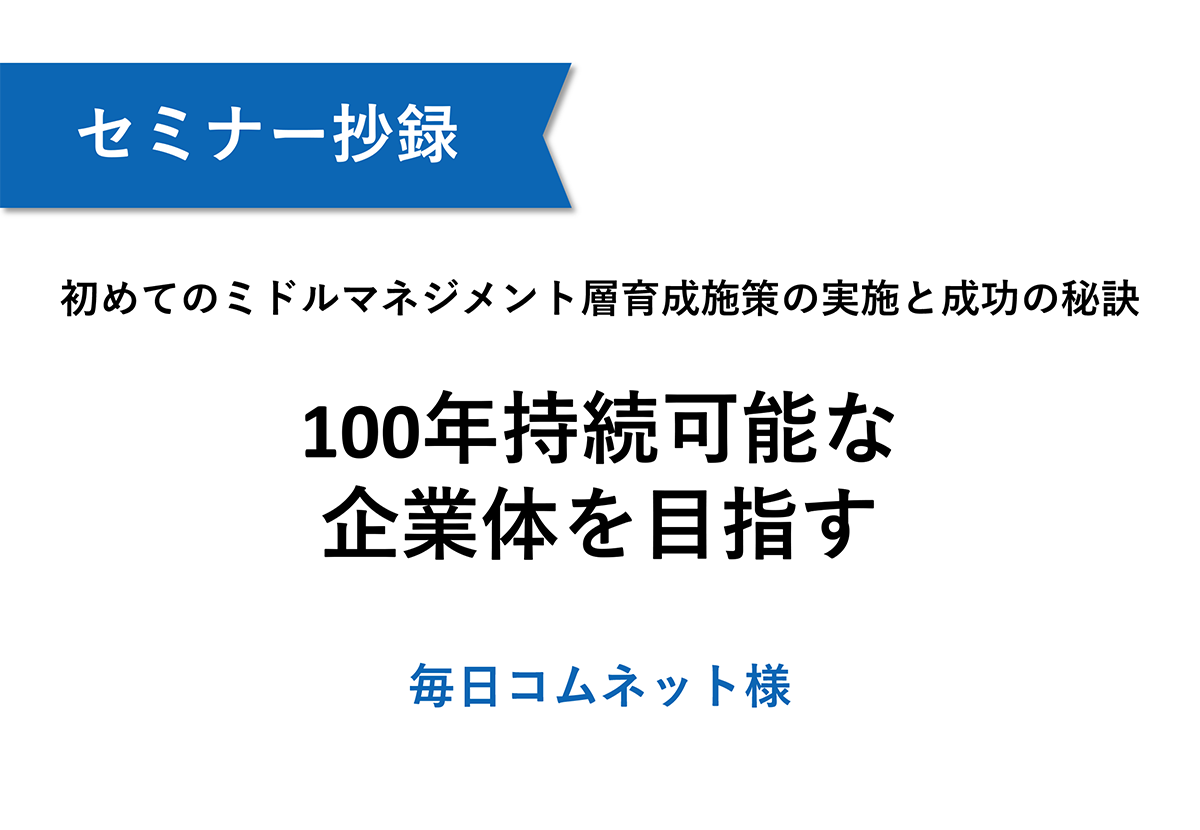連載・コラム
さあ、扉をひらこう。Jammin’2024 Jammin’ Award Report
2024年のグランプリは逆転の発想で「日本の資産」を世界に届けるアイディア!〈Jammin’ Award〉
- 公開日:2025/04/14
- 更新日:2025/07/21

異業種・越境による共創型リーダーシップ開発プログラム「Jammin’」、6年目のJammin’2024が終了した。44社247名の次世代リーダーたちが、「不」を基点に新価値を生み出すプロセスに取り組んだ。2024年9月6日の第1回リーダーセッションから始まり、2025年2月14日のJammin’ Awardでゴールを迎えた。Jammin’ Awardでは、社会課題テーマごとに分かれた15のコースから1チームずつ選出された代表15チームが、約5カ月にわたって作り上げてきた事業案をプレゼンテーションした。最後には、グランプリがリアル参加者・オンライン視聴者の投票によって選ばれ、審査員特別賞がゲスト審査員によって選ばれた。2024 Jammin’ Awardの模様を紹介する。
- 目次
- 2024 Jammin’ Awardは会場に発表者63名が集まり、オンラインでは約300名が視聴!
- 「このビジネスは伸びます。人と人をつなげる発想がすばらしいと思いました」(鈴木氏)
- 「圧倒的なバリューがあるか、参入障壁をつくれるか、差別化ができているかが問われます」(高津氏)
- 「いくつかの案には財務的な持続可能性に課題を感じました」(高津氏)
- 「皆さんはJammin’を通して『人生の使い方』を学んだのでは」(鈴木氏)
2024 Jammin’ Awardは会場に発表者63名が集まり、オンラインでは約300名が視聴!
2024 Jammin’ Awardは、代表15チームの発表者63名が新橋の新虎安田ビル NIKAIの会場に集まり、プレゼンテーションを行った。オンライン視聴もできるハイブリッド形式で、発表者以外のリーダー、オーナー含め、約300名がオンラインで視聴した。司会は、海津秀剛と内田怜七(共にリクルートマネジメントソリューションズ)である。

13時、オープニングムービーが華やかにスタートした。司会がJammin’の取り組みやJammin’ Awardの位置づけを説明した後、ゲスト審査員を紹介した。1人は、スイスを本拠に世界に展開するビジネススクール・IMDの北東アジア代表・高津尚志氏である。もう1人は、多くの社会起業家の育成に尽力している株式会社ボーダレス・ジャパン代表取締役副社長の鈴木雅剛氏だ。昨年の2023 Jammin’ Awardと同じ審査員タッグである。

Awardでは、全15コースの代表チームが舞台に上がってプレゼンテーションを行い、その様子はオンラインでも配信された。各チームの発表時間は8分。全チームの発表後に、審査員特別賞とグランプリが選出された。グランプリは、会場の参加者とオンラインの視聴者の投票で決定した。
「このビジネスは伸びます。人と人をつなげる発想がすばらしいと思いました」(鈴木氏)
前半5チームのプレゼンテーションが始まった。最初に各コースと発表チームを紹介するムービーが流れ、次に司会が各コースの専門家のコメントを読み上げた。専門家は発表チームを選んだキーパーソンであり、発表チームへの思い入れは深い。その後に、各チームが8分間のプレゼンテーションを行った。5コースのプレゼンテーションが終わったところで、高津氏・鈴木氏が5つの事業案にまとめてコメントした。(※この記事では、分かりやすいように各コースの事業案と専門家・審査員のコメントをセットでごく簡単に紹介する)
1番手は「インバウンドコース」。美容×インバウンドをテーマにした事業案で、専門家は「完成度が高く手触り感のあるビジネスモデルで、プレゼンテーションも分かりやすかった。他が真似できない独自のポイントをさらに磨いてもらえたら」とコメントした。
高津氏は「野心あるパートナーを見つけることが大事ではないかと思いました。海外進出も視野に入れてはどうでしょうか」、鈴木氏は「完成度が非常に高かったのですが、社会課題にもう一歩踏み込むと、より良いビジネスモデルになると思いました」とそれぞれの見方でアドバイスした。

インバウンドコースBチーム
Beauty Voyage 美容院バウンド!!
2番手は「グローバルコース」。このチームは、ある国の国家的問題となっている「肥満」の解決を目指した事業案を提案した。専門家は「事業コンセプトとサービスが理解しやすく、顧客の行動変容を容易にイメージできた」と評価し、代表チームに選定した。
鈴木氏は「想定顧客を会社にしていましたが、個人で買いたい人もいるのでは。デリバリーモデルをもっと深めてください」、高津氏は「目の付けどころが良いです。その国の社会全体の肥満リテラシー向上が大事ではないかと感じました」とそれぞれ次の一歩を促した。

グローバルコースCチーム
Itadaki mas! お菓子で始める、ダイエット!オフィスで1本、いや2本!
3番手は「食料コース」。代表チームは、栄養精神医学に着目した新たな飲料の事業アイディアを提出し、すでにプロトタイプ開発まで進めていた。専門家は「合理的な判断が積み上げられ、問いへの応答も的確だった。身体感覚に訴えるプロダクト開発をしてもらいたい」と要望した。
実際にプロトタイプの飲料を飲んだ審査員の2人は、高津氏が「栄養精神医学を初めて知りました。ぜひ日本をその中心地にしてください」と応援した一方で、鈴木氏は「味は良かったのですが、この甘さなら僕は飲みません。それから説得力を持たせるためのファクトが欲しいです。必要な人にどう届けるかも深めてください」と叱咤激励した。

食料コースAチーム
Vivaresil 全ての人の心に、レジリエンスを
4番手は「介護コース」。代表チームは、要介護者同士の会話を促すAIサービスの事業案を提出した。専門家の選定理由は「私たちは最期のその瞬間まで笑顔で過ごせるのだろうか、という始まりの問いがすばらしい。フィールドワークを経て皆さんが出した結論は、自分にとっても新たな気づきになった。見たことのないサービスでワクワクした」と高評価だった。
両審査員も「このビジネスは伸びます。人と人をつなげる発想がすばらしいと思いました。概念の定義をさらに深めていくと、より良いビジネスになるはずです」(鈴木氏)、「AIの使い方が斬新で、可能性のある事業案だと感じました」(高津氏)と賞賛した。

介護コースCチーム
コンチェルト~AIファシリテーターで助ける介護から良くする介護へ~
5番手は「地方創生@上勝コース」。代表チームは、上勝で実施する教育パッケージを提案した。専門家は「人的リソースの限られている上勝で起きているイノベーションが、なぜリソースが豊富にあるはずの日本企業で起きないのか、という疑問を起点に、日本企業の『不』を捉える逆転の発想に魅力を感じました」とコメントした。
「教える人材をどう育成するのかがポイントだと思います。大企業を巻き込む戦略を練るとよいのでは」(鈴木氏)、「この種の教育プログラムを開発するのは簡単ではありません。どうやって壁を越えるのか、ぜひ知恵を絞ってください」(高津氏)と、審査員はどちらも着目点を評価する一方で実現の難しさに触れていた。

地方創生@上勝コースDチーム
探求DOJOー教育から日本を変えるー
「圧倒的なバリューがあるか、参入障壁をつくれるか、差別化ができているかが問われます」(高津氏)
休憩後、次の5チームの発表が始まった。6番手は「エネルギーコース」。日本の脱炭素社会の実現に向けて、一人ひとりの行動変容を促す事業案である。専門家は「ソーシャルインパクトが明確で、すでに提携先企業とも話をしており、新しい価値提供に踏み込んでいる点に可能性を感じた」とコメントした。
鈴木氏は「これからの日本の地域に欠かせないソリューションになり得ると思いました」と賞賛する一方で、「地域にどう還元するかという観点が加わるとさらに面白くなるでしょう」とさらなる一歩を求めた。高津氏は「内容はすばらしいのですが、プレゼンテーションがもったいなかったです。何を伝えたいのか再検証してください」と注文を付けた。

エネルギーコースCチーム
家庭のエネルギーマネジメント
7番手は「働き方コース」。代表チームは、AIを活用して、職場のコミュニケーションを改善する新たなサービスを考え出した。専門家は「充実したフィールドワーク、プレマーケティングを行い、ステップを踏んで『不』を解決する事業案になっていた。チーム全員でよく考え抜いていた」と高く評価した。
両審査員は高評価をしたうえで、事業案の差別化を求めた。「この事業案はAIのプロンプト設計そのもので、その点で優れていました。ただ、より分かりやすい差別化も可能ではないかと感じました」(鈴木氏)。「ポテンシャルの高い事業案ですが、手元の生成AIだけで実現できる部分もありそうです。差別化ポイントや用途をさらに追求してみてください」(高津氏)。

働き方コースDチーム
AI com~愛のあるコミュニケーションが未来を変える~
8番手は「教育コース」。代表チームは、非認知能力の教育支援プログラムを提案した。専門家は「皆で根気よく話し合った結果、ビジネスとして立ち上がるイメージが十分にできる事業案が完成した」と取り組みを讃えた。
ただ、2人の審査員は、共に非認知能力というテーマの難しさに触れた。「教育では、どうしても受験のために認知能力を向上させなくてはなりません。そのなかで、なぜ非認知能力が大切なのかという説得力をより高める必要があると感じました」(鈴木氏)。「このテーマは難しいと思います。1つの考え方として、週末の親子の遊びのようなライトな入口を提示する方法もあると思いました」(高津氏)。

教育コースCチーム
CO-GROW-これからの時代を自分らしく生き抜く力を育むー
9番手は「地方創生@中能登コース」。代表チームは、中能登の農業を守るための新価値創造にチャレンジした。専門家は「中能登の『不』の解決とビジネスの実現可能性のバランスが取れていた。多くの利害関係者と接点を持ち、現実を確認していたのも良かった。何よりこのチームのアイディアに驚いた」と述べた。
両審査員ともに事業案をポジティブに捉えていたが、集客に弱点があると見抜いていた。「中能登への愛情と敬意に満ちたプレゼンテーションでした。ただ事業案としては、現実的にどうやって集客するかをもう一段深く詰めてほしいと思いました」(高津氏)。「メインターゲットは個人よりも企業ではないでしょうか。越境や団体利用の文脈を上手につくれれば、企業にアピールできるはずです」(鈴木氏)。

地方創生@中能登コースBチーム
のとのたねまき~能登の大地と海が、こころをほどく~
10番手は「ヘルスケアコース」。代表チームは、親子関係を中心に据え、一人ひとりの健康と人生に寄り添うサービスを構築した。専門家は「これからの日本社会を見据えた、時流を捉えたソリューションになっていた。マーケット理解の解像度も高く、メッセージも共感を得やすい」と取り組みを評価した。
審査員はそれぞれの見方でより詳細に踏み込んだ。「このサービスは、必ず保険会社との関係性が問われます。保険会社とどう関わるかを考えてもらうとよいでしょう」(高津氏)。「現状のアイディアだと、利用するのはマジメな人に限られそうです。違う切り口もあり得るのではないでしょうか」(鈴木氏)。
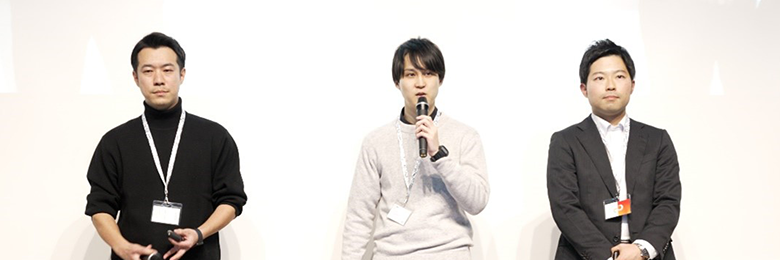
ヘルスケアコースBチーム
あいろぐ 親子で紡ぐ健康のバトン
講評の際、高津氏は「正しく美しい事業案ばかりでしたが、それが本当に成り立つかどうかは別の話です。実際のビジネスでは、圧倒的なバリューがあるか、参入障壁をつくれるか、競合との差別化ができているかが問われます。ですから、そうした観点を大事にしてお話ししました」と述べた。
「いくつかの案には財務的な持続可能性に課題を感じました」(高津氏)
休憩後、最後の5チームが発表した。11番手は「防災コース」。代表チームはインバウンドと防災を組み合わせた事業案を提案した。100名以上にインタビューし、ある地域の観光連盟と手を組んで事業案を磨いてきた。専門家は「これまで防災では扱われていないテーマを選定し、過去最大のフィールドワークを経て、協働者の心をがっちり掴んだ。他の地域も後押ししてくれる可能性の高い事業案だ」と賞賛した。
審査員も「視点がナイスで逆転の発想がすばらしい。実現に向けてはいかに面を取るかがポイントとなるでしょう」(鈴木氏)、「目の付けどころがすばらしく、ものすごく大きな可能性を感じました。日本を理解するうえで必要なコンテンツになるはずです。これこそ日本が世界に貢献できる分野でしょう」(高津氏)と高評価だった。

防災コースBチーム
いのちを守る旅に出よう インバウンド防災
12番手は「格差コース」。代表チームは、患者と家族が共に病に立ち向かうためのアプリを考えた。専門家は「患者、家族、医者などのステークホルダーの総合的課題を具現化し、解像度を上げて解決策を創出した。競争優位性が明確で、先行者利益も得やすい」と選考理由を語った。
審査員たちは事業案を評価しながらも鋭い指摘を入れた。「これは有料でも使う人がいるサービスです。ただし、利用時の解像度をさらに高める必要があると思います」(鈴木氏)。「日本の社会インフラとして開発したほうがよいサービスだと感じました。ぜひ厚生労働省やデジタル庁と話してみてください。予算が出る可能性がありますから」(高津氏)。

格差コースDチーム
患者と家族がともに病に立ち向かうためのアプリ「かけはし」
13番手は「文化コース」。代表チームは、家庭料理にまつわる「不」を解決する事業アイディアを発表した。専門家は、「レシピサイトやフードデリバリーが百花繚乱のなか、ぬくもりがテーマのユニークな事業案を生み出した」と選定理由を語った。
両審査員は、温かくほっこりするコンセプトを褒めた一方で、「むしろBtoBに強いニーズがあるのではないでしょうか」(高津氏)、「想い出を残すことを大事にするなら、WEBサイトではなく、本にするのもいいかもしれません」(鈴木氏)と、ターゲットやアウトプットに関して再考を促した。

文化コースBチーム
なごめるレシピ~和めし~
14番手は「地方創生@雄勝コース」。代表チームは、フィールドワークから始まる地方創生を掲げ、関係人口創出を目指した独自の事業案を提出した。専門家は「自分たちがワクワクするか、自分たちがやってみたいと思えるかにこだわり、高みを目指したチーム。実現可能性の高い事業案を創り上げてくれた」と選定理由を語った。
審査員はそれぞれ異なる観点から、アイディアのブラッシュアップを求めた。「皆さんが想定している顧客ターゲットは、どうしても予算が限られています。本当に売上や利益が出るのか、ビジネスモデルの再検証が必要だと思います」(高津氏)。「すばらしい取り組みですが、関係人口という概念はアップデートが必要です。どんなまちを創るのかをあらためて深掘りしてみるとよいかもしれません」(鈴木氏)。

地方創生@雄勝コースDチーム
マナビバ!ツナギバ!~フィールドワークから始める地方創生~
15番手は「ジェンダーコース」。代表チームは、働く人たちの睡眠時間を増やすための事業アイディアを提出した。専門家は「着眼点が秀逸で、日本に新しい文化を広められる可能性を感じた。多くのステークホルダーを巻き込み、大きなうねりをつくっていくという現代的な考え方もすばらしい」と評価した。
鈴木氏は「キャッチフレーズはパワーワードだと思いました。ただ、このサービスの利用にはハードルがあります。コアバリューを見定めると、サービス内容が変わってくるのではないでしょうか」、高津氏は「社外スペースではなく、社内スペースの活用から始めてみてはどうでしょうか」と指摘した。

ジェンダーコースCチーム
ちょこっと眠る ちょこね シェアリングスペースを活用したパワーナップの提供
「皆さんはJammin’を通して『人生の使い方』を学んだのでは」(鈴木氏)
全チームの発表が終了した。休憩を挟んで、いよいよ審査員特別賞とグランプリが発表された。なお、グランプリは全チームのプレゼンテーションを視聴したリアル参加者・オンライン視聴者の投票で選ばれた。
審査員特別賞・鈴木賞は「エネルギーコース」! 鈴木氏は「この賞を条件つきで授与します。絶対に事業化してください。私たちは地球環境が危ういことを知っているにもかかわらず、いまだに従来どおりの電気を使っています。この状況を変えるには、再生エネルギー電源を増やして蓄電しなくてはなりません。さらに利用しやすいサービスを開発しなくてはなりません。皆さんはまさにそうした事業案を考えたわけです。皆さんのビジネスはきっと日本の必須ソリューションになります。やるしかありません。絶対に事業化してください」と強く求めていた。チーム代表者は「絶対にやります!」と力強く返していた。

審査員特別賞・鈴木賞の「エネルギーコース」
審査員特別賞・高津賞は「介護コース」! 高津氏は「AIをファシリテーターにして、人と人をつなぎ、コミュニケーションを豊かにしてウェルビーイングを高めるという考え方がすばらしいと思いました。これは、私たちがAIと共存する有力な方法の1つだと思います。高齢化で世界最先端を行く日本発のソリューションとしてふさわしいのではないでしょうか」と高く評価した。チーム代表者は「5カ月間、青春を味わうことができました。協力してくれた施設の皆さんに、感謝を伝えに行きたいと思います」と嬉しそうに語った。

審査員特別賞・高津賞の「介護コース」
そして、グランプリは「防災コース」! プレゼンターとして壇上に上がったJammin’ファウンダーの井上功(リクルートマネジメントソリューションズ)は「被災というネガティブな話をポジティブに昇華して世界に届ける発想と行動量に感動しました!」と述べた。次に、鈴木氏が「防災に関するビジネスは収益モデルをつくりにくく、実は多くの組織が壁にぶつかっています。皆さんは逆転の発想で新価値を生み出し、その壁を軽々と乗り越えました。このビジネスも絶対に実現してください!」とエールを送った。高津氏は「皆さんのプレゼンテーションを聞いて、数々の災害に立ち向かってきた日本人の知恵や工夫は、日本の資産なのだ、誇りなのだと感じました。勇気をもらいました。私も何かできることがあれば協力したいと思います」と語った。
チーム代表者は「実は防災コースの参加者全員が、私たちのプレゼンテーションをブラッシュアップしてくれました。皆さん、ありがとうございました。日本の防災のすごさを世界が評価してくれる社会にできたらと思っています」と感謝の弁を述べた。

グランプリの「防災コース」
最後は審査員の2人が総括した。「8分でプレゼンテーション、は過酷です。それで審査をするのも残酷です。しかし私は、15組のプレゼンテーションを通して、皆さんが多くを学んだことを確認し、同時に私自身がおおいに学びました。私は今、若い皆さんのメンターでありながら、同時に若い人たちからインターンのように学ぶ『メンターン』でありたいと思っているのですが、今日はまさにメンターンとして存在することができました」(高津氏)。
「皆さんはJammin’を通して、『人生の使い方』を学んだのではないかと感じています。皆さんはJammin’のなかで、新たな可能性を切り拓こうと仲間同士で壁を乗り越えました。これからも人類の可能性を信じ、自分たちが切り拓けることを信じ、仲間がいれば何でもできると信じて、前に進んでいってください。明日からまた、皆で力を合わせて頑張りましょう」(鈴木氏)。
これにてJammin’2024の全プログラムが終了した。発表終了後、参加者・視聴者からは、「鈴木さん・高津さんからのFBがめちゃくちゃ学びになりました」「この場に居られて幸せでした」「OBになっても聞きたいです」「もっと詳しく話を聞いてみたいと思った事業案が数多くありました」など、興奮冷めやらぬ様子のコメントが寄せられた。

おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)