連載・コラム
一流になるための「10年ルール」
「一流」と「二流」を分かつものは何か?
- 公開日:2012/08/06
- 更新日:2024/03/26

恩師が費やした「集中の5000時間」
先日、大学時代の恩師が、退官することになり、最終講義を聞きに行った。
講義開始の15分前に着いたにもかかわらず、200名ほど入る会場はすでに満席に近い状態で、かろうじて後ろのほうに座ることができた。講義が始まると、会場には入りきれないほど人が集まった。
先生は、つい自分の功績を自慢してしまうが、憎めない性格で、学生はもちろんのこと、多くの人から愛されていることを、このイベントを通じて、あらためて感じた。

先生の専門は船のデザインである。2000年のアメリカズカップの技術とデザインの責任者を務めていた。その先生の自慢は、恩賜賞の受賞である。日本の学術賞としては最も権威ある賞であり、長年の研究成果が認められたと喜んでおられた。
最終講義は、先生のキャリアの歩みについてのお話であったが、その中で、最も印象に残ったのは、「集中の5000時間」という話であった。先生は、大学を卒業した後、民間企業に勤められたが、その後、大学の修士課程に戻った。その最初の1年、5000時間もの時間を研究に費やしたそうだ。一日平均14時間弱、それこそ研究に没頭する毎日。先行文献を読み、実験を行い、思考し、論文を書き上げた。その論文で、その領域のエキスパートになり、その後のキャリアを方向づけた。
「何かに秀でようと思えば、それなりの努力が必要なことはわかっているが、単に日々、努力を重ねるだけではなく、人生のどこかのタイミングで勝負の時があり、そのタイミングに集中できることが大事である」という話であった。
その話を聞いて、「私が学生だった時にこの話を聞いていれば、私の人生は変わったかもしれない」と思った。
一流になるための「10年ルール」
何かで突き抜けるためには、短期の集中も大事だが、長期にわたる鍛練も必要である。熟達研究の第一人者である、フロリダ州立大学のアンダース・エリクソン氏は、高いレベルのスキル、知識を身につけるためには、10年以上にわたる長期的な学習が必要だと述べている。
エリクソン氏をはじめとする熟達研究者は、チェス、ピアノ、バイオリン、水泳、テニスなどの世界的な一流プレイヤーを対象として、彼らの学習プロセスの研究を行なってきた。

単に10年以上の時間をかければいいというわけではなく、上達につながるような鍛練でなければ、一流には届かない。10年以上、趣味でゴルフやテニスを続けている人はたくさんいるが、多くの人はあるレベルに到達したら、そのレベルを保つように最低限の練習しかしない。趣味だからある程度のレベルで楽しめればよく、忙しいにもかかわらず、余分な時間を使って楽しくない練習をわざわざ行う動機が起きない。しかし、それではなかなか上達はしないのも事実である。
エリクソン氏は、ベルリンの音楽学校で、さまざまなレベルのバイオリニストの研究を行なった。定量調査、インタビュー、日記を使った調査などを行ない、そのレベルの差がどこから生まれるのかを調査した。世界レベルで活躍できそうな「最優秀グループ」から、卒業して普通の学校の音楽の先生になる「普通グループ」まで、3つのグループに分けて研究を行っていった。換言すれば、「最優秀」と「優秀」と「普通」を分かつものが何かという研究である。
最も明確にレベル差を説明するものは、18歳になるまでの累積の練習量であった。「最優秀グループ」は8,000時間を費やし、「優秀グループ」は5,000時間、「普通グループ」は3,000時間の練習量であった。バイオリンを7~8歳で始め、10年かけて8,000時間練習をする。一日に換算すると2時間強である。遊びたい気持ちを抑えて、日々、バイオリンを弾き続けなければ、スタートラインに着けないということである。
「最優秀」と「優秀」は、入学する時点で、3,000時間の違いがあることになる。とすれば、「優秀」は、「最優秀」に追いつくためには、3,000時間を埋める練習量が必要になる。
実際、三つのレベルのバイオリニストたちの音楽活動時間を日記によって調べていくと、すべてのレベルで、週に50時間程度の活動を行っていた。土日も含めて、1日7時間。年間2,500時間。「優秀」も「普通」も練習しているが、「最優秀」も同じように練習している。
「最優秀」が毎日7時間練習しているなら、「優秀」は10時間練習すれば、3年で追いつくこともできる。それこそ、恩師が行なったように「集中の5000時間」を行うことができれば、「優秀」から「最優秀」へレベルを変えることができるかもしれない。ただ、身になる練習は、一日に何時間もできるものではない。集中力が持たない。せいぜい数時間であるということも知られている。
一流が行う「熟考された鍛練(deliberate practice)」
エリクソン氏は練習の量だけではなく、練習の質にも言及しており、むしろこちらのほうが大事であると述べている。レベルを上げる練習は、単なる練習ではなく、「熟考された鍛練(deliberate practice)」である。
バイオリニストの場合、マスターしなければならない練習に特化した、一人での練習である。できないところをできるようになるという、最も苦痛な練習である。二流はできることを繰り返して練習するが、一流はできないことをできるようになるための練習をする。
練習は一人で行うが、何ができて何ができていないのか、というフィードバックを先生やコーチからもらいながら、力量を高めているというのが、一流が行っていることである。

「素人の歌手は、練習を自己実現やストレス解消とみなしていたが、プロの歌手は、練習中、集中力を高め、力量を高めることに力点をおいていた」という歌手の研究もある。
一流になるためには、練習の量だけでなく、練習の質も大事だということである。当たり前のことであるが、普通の人はなかなかそれができない。
そこにはいくつかの理由がありそうである。
単純に「絶対にうまくなってやる」という信念がなかったり、「うまくなれる」という自信がないということも考えられる。信念や自信がなければ、苦しいと思える鍛練を行うことは難しい。
あるいは、趣味の分野であれば、「そこそこできて楽しめる」し、仕事の分野であれば、「そこそこやれていて、仕事になっている」ということかもしれない。
あるいは、努力そのものが怖いということもあるだろう。
私が、バスケットボールのコーチをしていた時の話である。
チームのエースが突然、練習に来なくなった。しばらく放っておいたのだが、3カ月しても来なかったので家を訪ね、なぜ突然来なくなったのか問いただしてみた。はじめは、他にやりたいことがあるからだと言っていたが、よくよく聞いてみると、バスケットそのものが怖くなったという。もっと詳しく聞くと、バスケットそのものより、「思いっきり努力したにもかかわらず、それが報われなかったらと思うと、怖くて怖くて仕方がない」ということだった。
練習しなくてできなければ、「練習していればできたはずだ」と言い訳ができるが、懸命に練習してできなかったときは、その言い訳ができなくなってしまう。
その後チームメートの説得により、そのエースは帰ってきて事なきを得たが、彼の気持ちはよくわかる。
自らの有能感は、アイデンティティーにつながっている。何かがうまいという感覚によって、自分の存在価値が確かめられる。しかし、うまいことばっかりやっていても上達しない。上達は、下手なことと向き合い、それを克服するところにあるのだから。
そこにジレンマがある。
有能感を味わうためには、上達していなければならないが、上達するためには、苦手な部分と向き合い、克服することが求められる。
熟達していくということは、ある意味、高度なマインドセットが必要だ。そういう意味で、道を究めるのは、精神修行でもあるといえそうだ。
日々の仕事を振り返ったとき、昨日より今日、何かがうまくなっただろうか。今日より明日、何かがうまくなりそうだろうか。たいていの仕事は、そこそこやっていてもそこそこ成り立つ。しかし、その仕事は、やはりそこそこの仕事にしかならないということだ。
≪参考文献≫
The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (Cambridge Handbooks in Psychology)
Neil Charness (著), Paul J. Feltovich (著), Robert R. Hoffman (著), K. Anders Ericsson(著)
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)












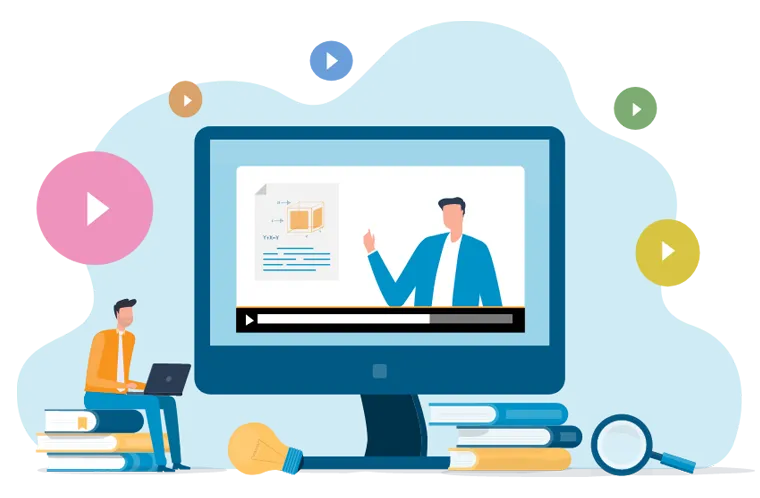 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で