連載・コラム
「助け合う」「協働する」風土が生まれる背景
人はなぜ他人を助けるのか?
- 公開日:2015/08/03
- 更新日:2024/03/26

激しい環境変化に立ち向かい、新たな価値を生み出すために、「組織開発」が叫ばれるようになって久しい。しかし日本企業においては、組織開発を専門に担当する組織があることは稀であり、各社、試行錯誤しているのが実態だ。
では組織開発の根底にある「助け合う」「協働する」風土とはどのようにして生まれるのか。
実は不思議な「通りすがりの人に道を教える」という行動
誰しも、見知らぬ人から道を尋ねられたことがあるだろう。
逆に、あなたが道を尋ねたこともあると思う。
多くの場合、人から道を尋ねられたら、快く教えてあげるのではないだろうか。私も、 仕事で知らない街を訪れたときや、旅行で外国の街に行ったときなど、地元の人に道を聞いて助けられた経験が少なからずある。もちろん、自分が教えてあげた経験も同様だ。

このような、見知らぬ人を助ける行動は社会において少なからず見られる。朝の満員電車で体の具合が悪くなった人を介抱する、歩いていてハンカチを落とした人に「落としましたよ」と声をかける、行楽先でバッテリーが上がってしまった車のエンジンをかけるのを手伝う、といったことだ。
しかし、これは冷静に考えると不思議な行動である。通りすがりの見知らぬ人を助けても、おそらくその人に二度と会うことはない。その行為に対して、なんらかの見返りを得られることもないのだ。せいぜい、「ありがとうございます」の一言くらいである。しかし、こうした行為が、社会をわれわれにとって住みやすい場所にしていることは間違いない。誰もこうした行為をしなければ、社会はギスギスしたものになってしまうだろう。
このような、他人を助ける行動は、職場でも見られる。特に日本の職場では、目に見える自分への見返りがなくても後輩や同僚を助けることは、伝統的に広く見られる行動である。例えば、新入社員を先輩たちがみんなで面倒を見る、などというのはその最たるものだ。 本コラムでは、こうした職場における「助ける」「協働する」行動 を科学してみたい。
「助け合い」とは、リスクのある「交換」 である
古くは1970年代から、職場での柔軟な協働は「日本の組織」の大きな特徴であり、強みと言われてきた。日本の多くの組織では、ジョブディスクリプション(職務記述書)がないことに代表されるように、あまり個人の責任範囲を明確に定義にしない。むしろ、「三遊間のゴロを拾いに行け」「上司の視点で仕事をしろ」といった言葉に見られるように、自分の本来の役割を超えることが奨励される。そして、互いに調整し合い、すりあわせ、仕事を回していくことが評価される。

しかし、日本においても、「それは僕/私の仕事ですか?」と部下から聞かれて困った(あるいは怒りを覚えた)経験をおもちの管理職の方もいるだろう。個人の業務上の目標を明確にし、目標の達成度を評価や報酬に反映させる、いわゆる「成果主義」の結果として、「職場での協働の風土が弱まった」といった嘆きの声も、一時はよく耳にした。
一方、同じ日本企業でも、海外拠点に目を向けると、様相は大きく異なる。
「彼らは自分の目標、担当業務のことばっかり見ていて、他の社員を助けたり、互いに融通し合ったりということをしないんですよ。情報も自分だけで抱え込むし。なぜあんなに自分の目線だけで仕事をしようとするのか、理解に苦しみます」
これは、とある日本企業の中国拠点に赴任している日本人幹部の方からうかがった、現地の人材に対するコメントである。このような問題意識は、この企業に限られたものではない。同様のコメントを、業界を超えてさまざまな企業の方から聞く。また、違う国、例えばイギリスにおいても、協働の不足は、比較的よくうかがう話である。 もちろん、海外拠点においても、互いに助け合い、協働する組織を作り上げている組織は存在する。しかし、それは日本におけるよりもどうやら難しいようである。
では、そもそも、なぜ人は他の人を助けるのだろうか。
この問いに対して、さまざまな視点から考えることができるが、今回は「交換」という視点から考えてみたい。
職場で他の人を助ける、あるいは協働するためには、自分の資源を投資する必要がある。例えば、自分の仕事の手を止めて、同僚や後輩の仕事にアドバイスをする、自分がもっている情報を同僚に共有する、あるいは、周りの人が仕事をしやすいように、自分の仕事のやり方を少し調整する。このいずれも、自分のもっている、時間も含めた資源を、他の人のメリットのために使っていることになる。一方、他の人からの助けを受ける、というのは、 相手が資源を自分のために使ってくれている、ということになる。
この投資の悩ましい点は、必ずしもリターンがあるとは限らないことだ。もちろん、自分が相手に対して協働的に振る舞ったことに対して、相手が恩を感じて、後々なんらかの形で恩を返してくれればなんの問題もない。しかし、それがいつ、どのような形で行われるかは分からない。自分が相手を助けてあげても、相手が何かをしてくれるとは限らない。フリーライド(ただ乗り)されてしまう可能性もあるのだ。そう考えると、協働という行為はリスクを含んだ「交換」だと捉えられる。
ただ乗りされない3つのアプローチ
では、こうしたリスクをコントロールするためには、どうすればいいだろうか?
まず1つ目のアプローチは、「事前に交渉する」ことだ。例えば、緊急を要する案件に同僚の手を借りる際に、「ちょっと手伝ってくれないか。お礼に、今度一杯おごるよ」といった具合である。もちろん、「一杯おごる」以外にも、交渉の材料はあるだろう。同僚の他の案件を手伝うのもよいかもしれない。
このアプローチは、相手にとってはただ乗りが防げるため、安心である。この仕事を助けたら、後々何が得られるか、事前に分かっているからだ。
ただし、このアプローチは柔軟性に欠ける。いちいち交渉しなければならないし、また、ちょうどよい「お返し」のネタがいつも手近にあるとは限らない。そのため、日常での円滑な協業という点では、このアプローチには限界がある。

2つ目のアプローチは、「相手に合わせて行動する」ことだ。相手がいつも自分を助けてくれるなら、自分も助ける。逆に、相手がただ乗りするような人であれば、自分は何もしない。相手に対する信頼のレベルをもとに、態度を変えるのである。これまでの付き合いにおいて、「この人を助ければ、いずれ何かきちんと返してくれる」と分かっていれば、わざわざ交渉する必要はない。
このアプローチは1つ目の交渉型の交換と比べて柔軟性が高い。毎回、「ちょうどよいお返し」を約束する必要はなく、中長期的に貸し借りのバランスが大体合っていればいいのである。互いが相手から受けた恩を返すことで成り立つことから、これは「報恩型」の交換といえる。
しかし、このアプローチの場合、見ず知らずの人との間では協働は成り立ちにくい。職場で、いつも一緒に仕事をしている同じチームの同僚や、普段から接点がある他部署の人との協働であれば、このアプローチはぴったりである。しかし、日頃からあまり接点がなく、信頼関係がない人に対しては、「彼・彼女を助けたところで、自分になんのメリットがあるのか」となり、協働にはつながりにくい。
これらに対する3つ目のアプローチが「集団型の交換」である。冒頭の、見ず知らずの人を助ける行為は、まさにこれに当てはまる。ここで大事なロジックは、 「情けは 人のためならず」である。他の人を助けておけば、巡り巡って自分に返ってくる、という考え方だ。面白いことに、これに似たことわざは英語にもあり、“Kindness is never lost”という。
見ず知らずの人に道案内をしてあげる人は、おそらくその相手が自分に何か返してくれることは期待していないだろう。まず確実に、その相手に二度と出会うことはないからだ。しかし、社会を構成する多くの人がそのように振る舞ったら何が起きるだろうか。今日は自分が道を案内してあげるかもしれないが、明日は自分がどこかで道に迷って誰かに助けてもらう立場になるかもしれない。つまり、直接目の前の相手から帰ってこなくても、個人としての 貸し借りの計算は 、間接的にバランスがとれる。
これは組織においても同じである。組織を構成する一人ひとりが、直接相手から見返りが期待できない場合であっても、協働的に振る舞う。そして、全員がそのように振る舞うことで、結果的にみな、人を助けると同時に、人から助けられ、帳尻が合うというわけである。この交換スタイルは、2つ目のアプローチよりもさらにフレキシブルである。組織内のメンバー同士であれば、誰とでも協働できるからだ。
どうすれば「協働する組織」をつくれるのか?
このような、「みんなが協働的に振る舞うことで、目の前での直接的なリターンがなくても、結果的・間接的に全員がリターンを得る」というのは、理想的に見える。なんといっても柔軟だからだ。しかし、こうした組織を実現することはそう簡単なことではない。最大の課題は、やはりフリーライドである。「自分は知見を出し渋るが、他の人の知見はもらう」というような人が増えていったら、この集団型の交換の仕組みは崩壊してしまう。お互いが、「みんなも自分と同じように振る舞うだろう」と思えないと、この仕組みは持続しない。

では、集団型の交換を支えるものとはなんだろうか。もちろん、個人の性格特性や価値観の違いも、交換に対する姿勢には影響しそうである。また個人主義や集団主義といった、社会としての文化の違いも影響があるのかもしれない。しかし、ここでは組織レベルでの特徴に注目してみたい。
まず着目すべきは「組織内における規範」である。組織内に「周囲を助けるのは当然のことであり、それをしないような人はうちにふさわしくない」という規範が一度出来上がってしまえば、フリーライドはしにくくなる。 採用や入社後の育成、評価や登用の基準にそうした要素を盛り込むのも、こうした規範を作り、維持していく上では重要だと考えられる。また、組織のリーダーが率先してこうした行動をとることも、組織の規範を作る上では大きな役割を果たすだろう。
次に、組織構造としては、密度の高い人的ネットワークが、部門の壁を超えて存在することが考えられる。個人同士が縦横ななめにつながっている状態だと、規範から外れた行動をとった人材に対するネガティブな評判は、すぐに組織内で共有されることになる。つまり、「あいつはただ乗りする」という悪評が立つということだ。こうしたネットワークが上述のような規範と組み合わさることで、個人のフリーライドを防止し、協働的な行動を促す役割をもつ。
そして最後が、メンバーシップの安定性である。組織に自分がいつまでいるか分からない、というような状況では、「集団型」の交換を選ぶのは合理的ではない。逆に、周りの人がいつ転職するか分からない、という状況も同様であろう。
このように考えると、個人の目標を明確にし、その達成度を報酬に反映する、いわゆる「成果主義」型の人事制度や、 拠点間や職種間の異動のない「限定型」の雇用契約、有期雇用といった仕組みは、どちらかといえば柔軟な協働を阻害する方向に働くのではないかと思われる。集団としての規範を緩め、人的ネットワークが分断されるからだ。また、人材流動性が高く、専門性が高いキャリアパスが好まれる(ローテーションが行われにくい)労働市場を持つ国では、 人的ネットワークが形成されにくく、また、上述のような規範も作りにくい。そうした環境では、身近な同僚同士での、個人のつながりをベースにした報恩型の協働は起きるかもしれないが、部門を超えた柔軟な協働は起こりにくくなりそうである。
日本企業の組織の特徴の1つが、「組織の壁を超えた柔軟な協働」だとすれば、それを制度や雇用の変化を超えて維持していくためにはどうすればいいだろうか。また、海外拠点においても同じような組織行動を促進するためには、どのような人事・組織施策をとっていけばいいのだろうか。
私は、1つのヒントは、「面倒見」にあるのではないかと考えている。最近、このテーマで日本および中国で様々な方にインタビューをしているのだが、「この会社のいろいろな人たちからとても世話になった」 という気持ちを感じている人は、あまり自分の損得の計算なく、周りを助ける傾向が強い。
「交換」の観点から言えば、誰かがまずgiveしなければ、彼・彼女らから周囲へのgiveを引き出すことは難しいのかもしれない。社会の違い、また、人事制度や雇用形態に関わらず、面倒を見る=上司や先輩、そして組織や会社がまずgiveをする。それが「協働する組織」をつくる第一歩になるのではないだろうか。
PROFILE
吉川 克彦(よしかわ かつひこ)氏
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 客員研究員
1998年リクルート入社。
コンサルタントとして、経営理念浸透、ダイバーシティ推進、戦略的HRM等の領域で、国内大手企業の課題解決の支援に従事。
英London School of Economicsにて修士(マネジメント)取得。
現在は同校にて博士課程に所属する傍ら、リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所客員研究員を務める。
※記事の内容および所属は掲載時点のものとなります。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)














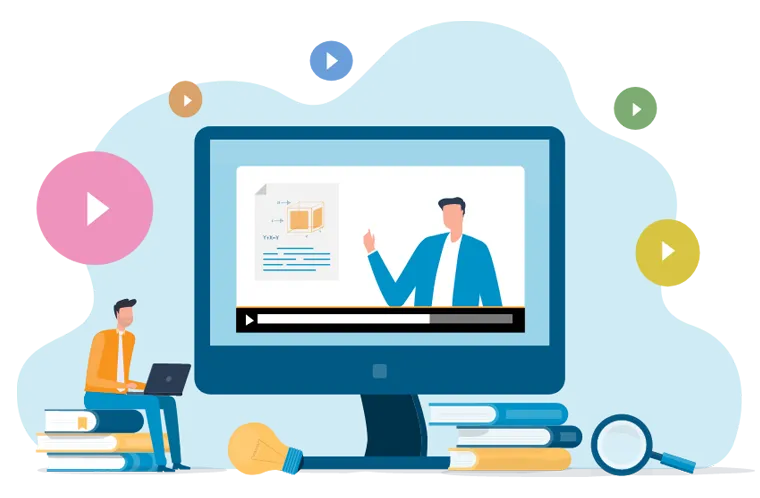 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての