連載・コラム
海外拠点の人材マネジメントのあり方について
海外駐在員を「捨て石」にするな
- 公開日:2013/05/07
- 更新日:2024/03/19

今回のコンサルタントコラムは、2000年代半ば以来、中国をはじめとした海外の日系企業の人材マネジメントに関する研究やコンサルティングに携わってきた田浦が担当します。2006年から4年間、駐在員として中国現地法人に勤務した田浦自身の経験や、周囲の人々を観察する中で感じた駐在員の本音の一端をもとに、海外拠点の人材マネジメントのあり方について掘り下げます。
駐在員が赴任後に直面する疑念
「中国事業の主役は現地社員の皆さんです。当社は『現地化』を進めていきます」
と、総経理(中国企業での社長)が社員を集めて演説をする。本社から社長や役員が来て、同じような演説をし、日本からの出張者も業務の合間に現地社員に対して同じようなことを語りかける。

このような場面が繰り返されるうちに、駐在員は赴任先での自らの存在意義についてある疑念を持つようになる。
「マネジャーとして派遣された駐在員の自分は、本来、この地に存在してはいけない人間なのだろうか?」
昨今、日本人の内向き志向が盛んに指摘されているが、成長著しい新興国などへ赴き、第一線で体を張って活躍したいと考える人は多い。
しかし、意欲に燃えて赴任した社員は早晩、「現地化」というスローガンにぶつかって立ち止まり、当惑するだろう。
経営層のポストについては、日系企業である以上、本社から派遣されるのは自然なことだという暗黙の了解が、現地社員の間にもなくはない。
悩ましいのは中間管理職である。設立後、一定の年数を経た拠点であれば、現地採用のベテラン社員がいる。管理職に登用するに足る器量の人材がベテラン社員の中にいなくても、外部から即戦力を採用することはできる。にもかかわらず駐在員を送り込んでくるということは、この会社には現地の人材を積極的に活用する意志がないのだろう、と現地社員は考える。
そして、駐在員の心の中に「自分は現地社員から、現地化を阻害する張本人として白眼視されているのではないか」という疑念が頭をもたげてくる。
実際、古い世代の現地社員の中に、「中国のことは中国人にしか分かるはずがない」と言って、新任駐在員をはなから相手にしようとしない人を、時おり見かけることがある。こうなると遠慮が先に立ってしまって、議論をするにも部下を指導するにも、駐在員は腰が引けてしまうのだ。
自分の使命や存在意義を「現地社員の成長を支援すること」などと自分なりに見定め、自分の主張として譲れないことと現地社員の考えを尊重すべきこととの境界線を見極めて、自信を持って職務に当たることができるようになるまでに、短くて数ヵ月、長くて数年かかってしまう。
OKY(おまえが、きて、やってみろ)の裏側
日本では、海外勤務は本社に比べて気楽なものだと思われているが、決してそのようなことはない。海外では、刺激的で充実した駐在生活を体験できる一方、さまざまな苦悩や失意に苛まれる場面もある。しかし駐在員は、弱音を吐いていると思われたくないし、また「話したところで、どうせ本社には理解してもらえない」という諦めがあるため、本音は黙して語らない。

業務指導や人材育成を例にみてみよう。海外拠点の現地社員は、日本と異なる文化的背景を持っていることに加え、中途採用者が多いので、過去の職場でさまざまな癖を身につけている。一方、日本企業の業務は企業内特殊能力によって進められることが多い。それらを現地社員に習得してもらうためには、多大な労力と時間を要する。日本では言わなくても伝わるようなことにまで気を配って指示を出し、きめ細かく指導しなければ、期待する結果は出てこない。
言葉の壁の問題も馬鹿にできない。会議中、議論が白熱してくると、現地社員が現地語で議論をはじめて、駐在員は蚊帳の外に置かれてしまう。現地化の方針が出ている以上、「日本語で話してください」とお願いするのは憚られる。現地語を学習している駐在員は多いが、ビジネスで使いこなすレベルには程遠い。管理職としてリーダーシップを発揮するどころではなくなってしまうのだ。
日常のコミュニケーションも一苦労である。勇気を出して昼食に誘っても、現地社員はどことなくよそよそしい態度を崩さず、現地語でひそひそと会話している。こうした時に駐在員が覚える疎外感は大変なものだ。現地社員は、いつも日本人だけで集まって食事することに対して批判的であるし、現地社員にとけ込もうとする駐在員の努力をもちろん評価してくれるだろう。しかし同時に、上司に気を使いながら外国語を使って食事するのは疲れるから、休憩時間は現地社員同士で気楽に過ごしたいとも、心の中では思っている。
「現地社員の育成のスピードを上げろ」「言葉を習得して現地社会に入り込め」「日本人だけで固まらず現地社員と積極的に交流しろ」など、日本から駐在員に突きつけられる改善要求は目白押しであるが、現地での実践は、日本で考えられているほど容易ではない。
ビジネスに目を向けると、新興国への日本企業の進出ラッシュが続いているが、順風満帆の企業は少ない。
「現地市場に十分に入り込めていないのは、駐在員による市場の読みや打ち手が拙いからではないか」との批判が本社で巻き起こり、「駐在員頼りではいけない、現地化を急げ」との号令が一段と声高に叫ばれる。駐在員の派遣を決めたはずの本社が、駐在員を支援するどころか戦犯視し、梯子を外しにかかるのである。
「OKY(おまえが、きて、やってみろ)」という駐在員のつぶやきは、本社に理解されえない苦労や苦悩が積み重った末に漏れる、鬱屈した憤嘆なのである。
奮闘の後に残るもの
こうした疑念や苦悩に苛まれながらも、苦楽を共にして一緒に任務を成し遂げる経験を重ねるうちに、現地社員との間に戦友のような仲間意識や信頼感が育まれてくる。熱気溢れる海外でこそ味わえる刺激や達成感に加えて、現地社員との精神的な絆を実感できれば、海外勤務は極めてやりがいのあるものとなる。
活躍する駐在員の口からしばしば、「本社には自分の後任になりうる人材はいない」、「現地社員の中に自分の後任になりうる人材はまだ育っていない」、「現地の労働市場には自分のポストを務められるレベルの人材は少ない」などといった発言が飛び出す。その真偽はともかく、「できるだけ長く海外拠点で働き続けたい」という心理が働いているのは確かだろう。

しかし3年から5年経つと、多くの場合、日本への帰任命令がやってくる。ようやく現地社員との間に信頼関係が築かれ、現地市場について土地勘が働くようになり、方々に人脈ができてきた矢先での、帰国命令である。後ろ髪を引かれる思いで帰国の途に就く人が多いはずだ。
もし自分の後任に現地社員が登用されるならば、「自分の人材育成の努力が実を結んだ」と手応えを感じるかもしれない。しかし、たいていの場合は、本社から日本人が後任として派遣される。その日本人が、これまで当該国の事業に全く関わったことがない社員であったりすると、「自分が駐在しつづけたほうが、会社にとっても自分にとってもハッピーなはずなのに」との思いを禁じえず、駐在期間中の自分の努力が御破算にされたような徒労感に襲われる。
それでも帰国後に、駐在期間中に培った知見を生かせる職務に就くならば、こうした徒労感を免れることができるだろう。しかし、駐在経験を生かせないどころか、自分のキャリアの発展に寄与するとは思えない職務に配属され、失意の底に突き落とされるケースも少なからずある。
ある消費財メーカーの人事担当者は、「本人は海外から凱旋してきたつもりでいるが、業務レベルが低い海外拠点で数年間過ごした人は、成長が止まっていて、本社に戻っても使い道がない。帰任する頃には中高年になっていて、能力開発にお金をかける年齢は過ぎている」と語っていた。
「駐在員と現地社員」という二元論からの脱却を
日本企業の担当者に海外拠点の人材マネジメントの方針を尋ねれば、ほぼすべての方が「さらなる現地化を推進する」と答えるに違いない。学者やコンサルタントも、いかにして現地の人材の意欲と能力を引き出し、経営層・管理層のポストへの登用を進めるべきかについて、多くの研究や提言を行ってきた。しかし現地人材の育成・登用と表裏一体のものとして取り組むべき駐在員の活用のあり方については、ほとんど目が向けられてこなかった。

最近は、駐在員に求められる人材要件を定めたり、そうした要件を満たす人材の採用や育成に力を入れたりする企業が増えてきている。だが、駐在員に対する赴任期間中の支援、特に精神面でのサポートや、帰任後のキャリア形成への配慮については、企業の関心は驚くほど薄い。
その背景には、「本社で育った社員である以上、手厚い支援など期待せず、自分の力で任務遂行に努めよ」という、日本社会特有の根性論があるのではないかと感じている。
これでは、海外の戦場の前線に送り込んだ駐在員を「捨て石」にしているのと同じである。
現地で生活してこそ得られる知見は豊かで深く、頻繁に出張しても到底手に入れることはできない。駐在経験者の知見と本社社員のスキルとを組み合わせて組織能力の最大化を図るのが、マネジメントである。
先に紹介した消費財メーカーのように、お膝元である本社の社員を社命によって海外に派遣しておきながら、帰任後にその知見を生かさないどころか「生かすことは不可能だ」と、こともあろうに人事担当者が断言するような企業には、海の向こうにいる現地人材の活用などおぼつかないし、海外事業が成功する望みはないだろう。
「現地化」を、海外拠点の組織や人材ポートフォリオの具体的な将来構想が伴わない、漠然としたスローガンとして掲げる限り、現地人材の登用が遅々として進まないのみならず、多額の費用をかけて派遣する駐在員を戦力として生かすことはできない。そもそも本社派遣の駐在員か現地社員かという二元論の是非も、再考すべき時期に来ているのではないだろうか。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










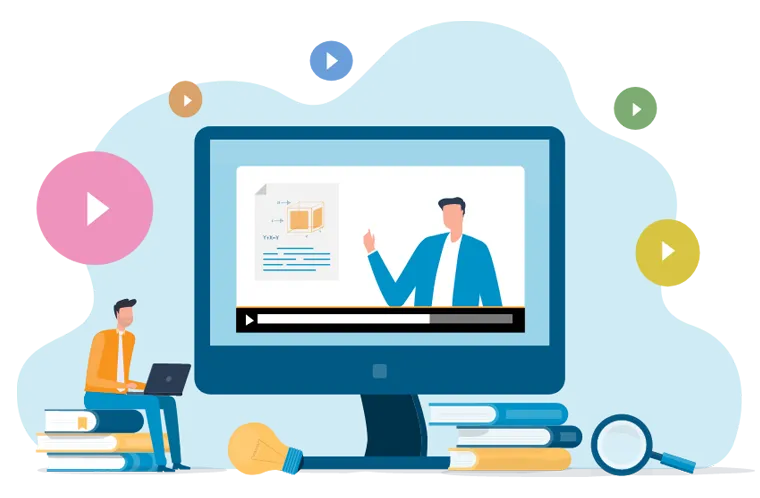 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての