連載・コラム
国際経営研究の現場から 第1回
なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
- 公開日:2014/01/22
- 更新日:2025/04/15

武田薬品工業が次期社長に外国人社長を起用する——ちょうど筆者が本稿を書き始めた日に速報として届いたニュースである。“グローバルな事業運営の経験”(日経産業新聞ウェブ版11月30日)が登用のポイントになった、とのことだが、“日本の主要製造業で外国人トップを同業から招くのは異例”(同)ということで、読者の皆さんも、驚きをもってこのニュースをご覧になった方が多いのではないだろうか。
筆者は現在、ロンドンのLondon School of Economicsの博士課程に所属し、国際経営、特に人材マネジメントの領域の研究に取り組んでいる。本連載では、その研究のなかで考えたこと、また、国際経営研究の現場で新たに議論されつつあることを、定期的に報告していく予定である。第1回は、武田薬品工業の例にも見られるような、幹部ポジションに外国人を登用していく、という動きについて、考えたい。
「国籍にかかわらず、最適な人材を登用する」「本社においても自国の人材だけでなく、海外からも含めて人材を配置する」ことがグローバル化を進める上では重要である、という議論は古くて新しい議論である。国際経営研究の世界では、古くは1970年代に遡ることができる。しかしながら、日系企業においては、本社や海外法人における中核的なポストを日本人が占める一方で、外国人は周辺的なポジションを占めるにとどまるという、所謂“ethnocentrism(本国指向)”に関する指摘が継続的に行われてきた(例えば、白木, 2006)。本稿では、この事象について異文化経営論および、制度論の観点から考察する。
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
国際経営における本国指向
“ethnocentrism(本国指向)”という概念は、Perlmutterによって1969年に提唱されたもので、実は国際経営論においても非常に歴史のあるものだ。Perlmutterは、国際経営のスタイルは、ethnocentrism、polycentrism(現地指向)、geocentrism(世界指向)の 大きく3つに分類されるとした(後にregiocentrism(地域指向)という4つ目の類型が追加された(Heenan & Perlmutter, 1979)) 。本国指向の核となるのは、本社が存在する母国 の人材を中心に国際経営を行うということであり、海外拠点の経営も母国人材が担い、本社の考え方が各国に展開されていく、というものだ。それに対して、世界指向では、国籍はもはや関係なく、能力に応じて最適な人材を登用し、配置することが指向される。
昨今の多国籍企業を巡る議論においては、世界指向こそ経営の進むべき方向である、という風潮が強い。当初のPerlmutterの主張は、あくまでも類型は類型であり、異なるタイプがある、ということを指摘しているにすぎず、絶対的にどれが優れているということではない。しかし、研究者の間でも本国指向から世界指向を、企業の国際化進化の過程として捉える例が多い(De Cieri, Cox, & Fenwick, 2007) 。ビジネス誌などにおいても、海外の現地市場に入り込み、海外拠点発のイノベーションを起こしていくためには、現地法人の人材を登用していくべきだ、といった主張が見られることも少なくない。
また、企業においても、海外拠点の人材を育成、登用することへの関心は高い。日本人を送るのではなく、現地人材をトップに登用する、という意味での「現地化」を重要課題として挙げる経営層の声を、2010年頃から盛んに耳にするようになった。実際、リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所が実施した、「人材マネジメント実態調査2013」において、「グローバル人材の採用・育成の強化」を課題として挙げる企業が2010年度調査と比較して大幅に増加している。また、同社実施の「中国における多国籍企業の人材マネジメント調査2013」においても、「現地法人のキーポジションへの現地人材の登用」が欧米企業だけでなく、日本企業の現地法人においてもトップ課題として認知されている。このように、「これからはグローバルに人材を登用すべきだ」という認識は広くビジネス界に広まっているといえるだろう。
このような、多くの企業や研究者、ビジネス誌が異口同音に「これからはこうだ」と主張するものに聞き覚えはないだろうか?人事領域の経験が長い方には思い当たる節があるかもしれない。そう、「成果主義」である。多くの企業が導入したものの、「よくよく考えてみると、日本企業の文化や組織のあり方には合わなかった」という反省が何年も経ってから、多くの企業や識者から指摘された。筆者は、ここで成果主義の成否を語るつもりはないし、一律に語れるほど単純なものでもないということを重々承知している。しかし一方で、海外の成功している企業の例を見て、それを「正しい」「こうあるべきだ」と主張することにも、少なからず疑問を感じるのである。その考えを踏まえ、本稿では、「こうあるべきだ」「今の状態は問題だ」という姿勢で現状を見るのではなく、あくまでも中立的な立場で、現状がそうであるにはそれなりの合理的な理由があるのではないか?という視点で考察を続けていきたい。
実態はどうなのか
日本企業の国際経営が海外赴任者に強く依存していることは、過去何度も指摘されてきた。このテーマについては、古沢(2008)が国内外の代表的な調査を整理しており、参考になる。同研究によれば、(1)日本企業の海外拠点における現地人社長比率は、時間が経過しても大きく変化しておらず、一般的に欧米の先行研究で見られる時間と共に現地化が進むという見解が日系企業には当てはまらない、(2)欧米企業との比較においても、1980年頃の調査から2000年代の調査まで一貫して、本国人社長比率が日系企業では75%を超えるのに対して、欧米企業では50%を下回るという結果が出ている、ということだ。
では、果たして、その後状況は変化したのだろうか。最近のデータとしては、Harzigら(2013)が行った調査がある。彼らによれば、海外法人において本国人が海外法人の社長を占める割合が最も高かったのは日系および韓国系企業で(64.5%)、全体平均(24.9%)よりも大幅に高い(残念ながら日系と韓国系を分けたデータは公表されていない)。ちなみに、最も低いのは北欧企業であり、海外法人の社長を本国からの赴任者が占める割合は7.5%にすぎない。欧米企業のなかで最も高いフランスでも31.7%である。また、社長に限らず何らかのポジションで本国からの赴任者が存在する企業の比率は、日本企業、韓国企業では86%に達しており、北欧企業の46%と比較して、かなり高いことが指摘されている。
過去の調査とこの調査を厳密な意味で時系列比較することはできないが、2000年代の調査では日本人社長比率が75%を超えていたということを考えると、日本企業においても、現地人材の現地法人トップへの登用は進んでいるのかもしれない。しかし反面、10%を切るような北欧企業とは大きく状況が異なるのもまた事実である。そう考えれば、日本企業の国際経営は「本国指向的である」という主張は正しい、といえるだろう。
しかし一方で、このことをイコール、日本企業が遅れている、問題だ、と捉えるべきなのかについては、上述のとおり、少々疑問でもある。欧米企業が大きく世界指向への変遷を果たしたからといって日本企業が世界の市場から存在感をなくしただろうか? 韓国企業が台頭したものの、彼らも上述のデータを見る限り、非常に自国中心的な人材配置を行っている。このことを考えると、自国中心的な人材配置ではグローバル競争に勝てない、という主張を改めて考察する必要性を感じるのである。
日本企業における本国指向の背景にある要因
では、日本企業が本国指向から転換しにくい、あるいは、転換しないことにメリットがあるとすれば、どのような要因が考えられるであろうか? 筆者は、日本企業を取り巻く制度的環境と文化に要因があるのではないかと考えている。
(1)雇用システム
まず、日本の制度的環境として挙げられるのが、長期雇用と社内労働市場を核とした雇用システムである(Aoki, 2001; P. Hall & Soskice, 2001) 。労働市場全体を見れば、派遣労働者の増加など、さまざまな変化が起きているものの、大企業を中心に、新卒で入社し、数十年をその企業で過ごした人材が経営の中核を占めることは、現在においても一般的である。
こうした雇用システムのもとでは、社内固有の文脈に依存した知識がきわめて重要な役割を担う(Marsden, 1999) 。 中核人材は、ローテーションなどを通じて、社内のさまざまな部門を経験し、多様な人々と関わるなかで、社内特殊な知識を蓄積していくのである。こうした知識の蓄積は、改善活動(Koike, 2002)や、研究開発(Lam, 1997)、サプライヤーとの関係(Sako, 2004)など、社内にとどまらないさまざまな領域で、重要な役割を担っていることが指摘されている。こうした特徴は、日本企業においてビジネススクールなどの外部での学びへのニーズが低いことにも表れている。MBAなどで学ぶような標準化された知識やスキルは、社内の文脈に当てはめて翻訳しない限り、価値が生まれにくい、というのが日本企業における一般的な特徴なのである。
このことは、社内特殊な知識を分かち合った人たちだけで仕事をしている限りにおいては、非常にスムーズに仕事が進む、ということでもある。そして、それは社内に限らず、長期的な関係を保っている取引先との関係においても当てはまると考えられる。自社も担当者も、取引の担当者も、互いに長い期間その企業に勤めており、その間を通じて会社同士の関係も続いているのである (長期の信頼関係と知識共有でつながった企業間関係、というのも日本の制度の特徴である(P. Hall & Soskice, 2001))。
こうした状況においては、 社内特殊な知識を備えていることが、中核人材として機能する上での重要な要素となる。それは、本社との関係が深い現地法人のポジションにおいても同様であろう。本社と切り離され、かなりの自立性をもって運営される場合であれば別だろうが、本社との相互依存性が高い限り、共通の社内特殊知識を備えていない人を登用することは、コミュニケーションの効率や一貫した意思決定を阻害し、パフォーマンスにネガティブな影響があると考えられる。もちろん、現地の人材を登用することによる、 従業員のモチベーションや採用に与える好影響を無視してよい、というわけではない。しかし、ネガティブな影響がありえるし、それは日本企業の本質的な特徴に関わることなのだ、ということも押さえておきたい、というのが筆者の主張である。
(2)ハイコンテクストコミュニケーション
さらに、こうした雇用システム上の特徴に加えて、日本の文化的特徴である”high-context communication(ハイコンテクストコミュニケーション)” の影響を考えたい。こうした文化をもつ社会におけるコミュニケーションには、言葉で語られたものが必ずしも伝えたいことのすべてを表すわけではない、という特徴がある(E. T. Hall & Hall, 2001)。 語られなかったことから行間や文脈を踏まえて情報を解釈する、また、語る側も皆まで語らない、ということが日常的に行われている社会なのである。「あうん」で伝わる、ことが当たり前であり、逆に、それを察することができない人は、「なんで全部言わないと分からないんだ!」と言われがちな社会である(個人的な話だが、筆者はこの点は非常に苦手なため、長年、諸先輩達から「吉川は空気が読めない」と指導をいただいてきた。しかし、先輩達には非常に申し訳ないことに、未だにあまり変わらないと自覚している)。
一方、low-context communication(ローコンテクストコミュニケーション)の社会においては、語ったこと=伝えたいことである。逆にいえば、語られなかったことは理解されない、というのが(多少極端な表現ではあるが)こうした社会の特徴である。面白いことに、ハイコンテクスト文化の出身者は、ローコンテクスト社会のコミュニケーションを理解することにはそれほど苦労しない。一方で、ローコンテクスト社会の人々が、ハイコンテクスト文化の人々のコミュニケーションを理解することは非常に難しい、とされている。
上記の特徴に、こうした文化が加わると、何が起きるだろうか。 国内で長く勤める中核人材の間では広く共有されている当たり前の考え方、手順、基準などを、言葉で明示して説明することが非常に難しい、ということだ。新入社員として入社してから、何十年もかけて理解してきたことは、すでに体の一部となっており、なおかつ、周りにいる人々も、基本的にそれを理解している人々ばかりであれば、それを言葉で説明する機会も必要もほとんどない。外部から 入社してくる人材も、空気を読むのに慣れた日本人であり、長い期間をかけてそうした文脈を理解し、一人前として認められていく、というステップを受けいれてくれやすい。
しかし、海外との関わりとなると、話は別である。海外の拠点が置かれる環境は当然のことながら、国内と大きく異なる。そして、“海外”としてひとくくりにできないほど、国によってその環境は互いに違うのである (Kostova, Roth, & Dacin, 2008) 。そして、日本のように長期雇用でもなく、ハイコンテクスト文化に属してもいない人たちも多い。そうなると、そうした環境下で育ち、生きている人々に、本社の当たり前を理解してもらおうとしても非常に難しい。そもそも、日本人がそれを言葉で説明できないのである。逆に、本社の人材にとっても、現地の社員の語ることは文脈が違いすぎて理解に苦しむことが多いはずだ。なぜ、自分たちにとって当たり前のことを踏まえずに、こんな無茶なことを言ってくるのだ、と頭をひねることが多く出てくるはずだ。
このパイプを担うのが、赴任者である。赴任者は本社の語ること、重要視していることを体感した上で、現地にも身を置いている。本社からすれば、自社の「当たり前」を理解した、話の通じる相手であるし、逆に、現地の人材からすれば、 本社の意図を解釈して現地に伝え、現地の言葉を本社に翻訳して伝える「通訳」となる可能性がある。また、本社の言葉にならない文脈を、赴任者が現地の幹部に時間をかけて共有していくこともできるだろう。もちろん、赴任者が必ずしもこうしたことが得意だとは限らない。上述のとおり、日本で育ち、長く同じ会社で過ごしているだけに、自分の当たり前を自覚しているとは限らないからだ。現地従業員と深刻なコミュニケーションギャップが生じているケースも少なくないだろう。ただし、国内で長期間をかけて学んだ知識がなければ、本国-現地法人間のコミュニケーションの仲介役にはなりにくい、というのもおそらく間違いないのである。また、逆に、海外に赴任してこうした違う文脈の人々をつなぐ経験を経て、本社に帰国した人材も、 国内と現地法人をつなぐ窓口になりうるだろう。
いずれにせよ、文脈を共有した人同士のコミュニケーションに慣れた日本人が、海外の拠点と本社の間でスムーズな情報共有をしようとすれば、本社の文脈を理解した日本人を現地に置く、あるいは、そこから帰ってきた日本人を現地との窓口に置くのが、1つの有効な手段だと考えられるのだ。さらにいえば、海外から国内に逆赴任し、国内の文脈を学ぶ経験をある程度の期間もった人材も、そうした役割を果たせるかもしれない。しかし、どれだけの外国人従業員がその期間、企業内にとどまってくれるだろうか。そして、そのコストを誰が負担するのだろうか。そして、逆に期間を限ると、それだけ学べるものは限られてしまう。
世界指向の人材活用は良い結果を生むのか?
さて、ここまでの議論を振り返り、果たして、世界指向=国籍を超えて人材を活用することが日本企業において良い結果につながるのか?ということを考えてみたい。
長期雇用と社内労働市場の雇用システムの結果、その会社特有の知識や文脈を理解していることが重要になること、また、ハイコンテクスト文化の結果、言葉にしなくても、文脈や行間を補って解釈するコミュニケーションが日本人の間においては一般であることを議論してきた。そして、その結果として、社内特殊な知識や文脈を理解していることが、中核人材として機能する上で重要であること、また、国内と海外という大きく環境が異なる拠点間で、コミュニケーションをスムーズに行う上では、本社の文脈を踏まえた上で現地との仲介役を担う人材が必要である、という指摘を行ってきた。さらにいえば、こうした状況は、日本という国において広く広まっている雇用システムや文化に根ざしたものであり、それほど簡単に変わるものでもない、という点も重要な点である。
こうしたことを踏まえると、外国人を今の状況で急速に現地法人のトップや、本社の中核ポジションに据えていくことによる、ネガティブな影響が懸念されることは間違いない。コミュニケーションの効率や意思決定の一貫性が阻害される、ということだ。では、日本国内の組織のありようを大きく変えればよい、というのはどうだろうか? 長期雇用を中心にするのではなく、外部からも人材を積極的に導入し、社内特殊な知識に依存しない組織体制を作り上げていく、ということだ。しかし、それは日本国内の労働市場において、特異な企業になることを意味する。大手企業としての伝統や信頼をテコに人材を引きつけてきた企業にとっては大きなコストとなる可能性がある。社内の人材がそうした変化に適応できるか、というのも大きな懸念となるだろう。また、長期的な相互理解関係を構築してきた取引先との関係も大きく変わらざるを得ない。忘れてはならないのは、すでに国際的に活躍している日本企業の多くが、「擦り合わせ」型の産業に所属しており、従業員や取引先との長期的な関係性は、こうした産業にとって大きな強みの源泉になっている、ということだ。この変革は、そうした強みの源泉を作り替えていく、ということを意味する。
しかし、一方で、上述のとおり、海外の現地法人における人材の動機付けや採用には、おそらくポジティブな影響があるだろう。また、より重要な果実として、現地市場の開拓や、現地市場特有の状況を踏まえたイノベーション(Prahalad, 2005; Govindarajan and Trimble, 2012)が進む可能性がある。また、上記のような変革の壁を乗り越え、こうした成果を実現すれば、国内においても、ひと味違った多国籍企業として存在感を形成することもできるだろう。摺り合わせ型ではなく、国内で世界的に通用する強みを生み出しにくい産業では、特に有効かもしれない。もちろん、こうした変革を成し遂げた企業にとっては、必ずしも日本人にこだわって採用を行う必要はなく、世界中から、世界戦略に合わせて人材を採用することになると思われる。
最後に、まとめとして現時点での筆者の結論を述べたい。まず、本国指向的な人事慣行には、それなりの理由があり、現地法人におけるさまざまな問題を生んでいる半面、本社と現地法人の知識の流通、という面で生産性に貢献していると思われる、ということだ 。そして、本国指向的な人事慣行から脱却することは、さまざまなネガティブな影響を生む可能性がある。一方で、それを乗り越えて、大きく違う形の企業に変化した際には、今の、国内の制度や文化に依った強みのあり方とは大きく違うタイプの強みをもつ企業に変化できる可能性もある。そして、おそらく、国内の組織のあり方を大きく変えないままに、部分的に本国指向的な人事慣行から脱却することは、最もネガティブな影響を経営に与える可能性がある。
そこから考えられるのは、現在の本国指向的な人事慣行を維持することも、悪くはないのではないか?ということだ。部分的に本国指向から脱却するくらいであれば、赴任者を核にした仕組みを維持する方が、生産性は結果的に高い可能性がある。途中で何度か述べたように、「これからはこうあるべきだ」という言葉にのせられるのではなく、自社はどういう姿に向かうのか、どちらが自社にとって適切なのか、を判断すべき問題だ、ということでもある。このことこそ、成果主義について語られた反省から学ぶべきポイントだと筆者は考える。ただし、その方向で進むのであれば、現地法人に派遣される赴任者が、現地と本社と両方の文化や考え方を理解し、コミュニケーションのパイプ役としての役割を果たすことが非常に重要になる。そうでなければ、現地における組織不全の問題が大きな足かせとなってしまうだろう。
<参考文献>
Aoki, M. (2001). Toward a comparative institutional analysis. Cambridge, MA: MIT press.(邦訳:比較制度分析に向けて. NTT出版)
De Cieri, H., Cox, J. W., & Fenwick, M. (2007). A review of international human resource management: Integration, interrogation, imitation. International Journal of Management Reviews, 9(4), 281-302. doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00211.x
Hall, E. T., & Hall, M. R. (2001). Key concepts: Underlying structures of culture. International HRM: Managing Diversity in the Workplace, 24-40.
Hall, P., & Soskice, D. (2001). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press.
Heenan, D. A., & Perlmutter, H. V. (1979). Multinational organization development: Addison-Wesley Publishing Company.
Harzing, A., Pudelko, M., & Reiche. S. (2013) Developments in Knowledge Transfer Activities of Expatriates and Inpatriates. Presented at 2013 Annual Conference of Academy of International Business.
Koike, K. (2002). Intellectual Skills and Competitive Strength: is a radical change necessary? Journal of Education & Work, 15(4), 391-408. doi: 10.1080/1363908022000023542
Kostova, T., Roth, K., & Dacin, M. (2008). INSTITUTIONAL THEORY IN THE STUDY OF MULTINATIONAL CORPORATIONS : A CRITIQUE AND NEW DIRECTIONS. Academy of Management Review, 33, 994-1006.
Lam, A. (1997). Embedded firms, embedded knowledge: problems of collaboration and knowledge transfer in global cooperative ventures. Organization Studies, 18(6), 973-996.
Marsden, D. (1999). A theory of employment systems: micro-foundations of societal diversity. Oxford: Oxford University Press.
Perlmutter, H. V. (1969). The tortuous evolution of the multinational corporation.
Sako, M. (2004). Supplier development at Honda, Nissan and Toyota: comparative case studies of organizational capability enhancement. Industrial and Corporate Change, 13(2), 281-308. doi: 10.1093/icc/dth012
白木 (2006). 国際人的資源管理の比較分析「多国籍内部労働市場」の視点から. 有斐閣.
古沢 (2008). グローバル人的資源管理論「規範的統合」と「制度的統合」による人材マネジメント. 白桃書房.
PROFILE
吉川 克彦(よしかわ かつひこ)氏
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 客員研究員
1998年リクルート入社。
コンサルタントとして、経営理念浸透、ダイバーシティ推進、戦略的HRM等の領域で、国内大手企業の課題解決の支援に従事。
英London School of Economicsにて修士(マネジメント)取得。
現在は同校にて博士課程に所属する傍ら、リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所客員研究員を務める。
※記事の内容および所属は掲載時点のものとなります。
次回連載:『国際経営研究の現場から 第2回 自分を何者と捉えるか?~グローバル組織におけるアイデンティフィケーション~』
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










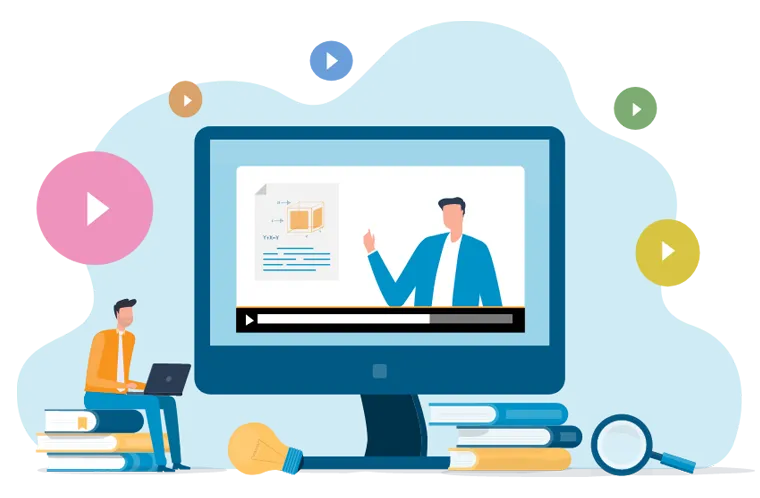 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての