インタビュー
国立精神・神経医療研究センター 伊藤 正哉氏
自分らしくないと感じたときが成長のチャンス
- 公開日:2017/10/16
- 更新日:2024/03/20

自分らしいと思える状態を、人は幸福だと感じる。そもそも、「自分らしい」とはいったいどういうことなのだろうか。自分らしくない状態が続く場合、私たちはそれに対してどう対処すべきなのか。心理学博士で臨床心理、認知行動療法にも詳しい国立精神・神経医療研究センターの伊藤正哉氏にお話を伺った。
- 目次
- AuthenticityとIdentity は違う 「自分らしさ」は Authenticity
- 年齢を重ねるにしたがい自分らしさの要素も社会的に
- 「本来感」は変化する 人間の「成長」と深い関係が
- 重要なのは感情を認めつつ、自分が決めること
AuthenticityとIdentity は違う 「自分らしさ」は Authenticity
「自分らしさ」に興味をもったのは10年以上前です。心理学の分野では当時、もっぱら「self-esteem:自尊心、自尊感情」をもつことの重要性が指摘されていました。とはいえ自尊感情にもさまざまあり、より内発的な感情も重要なのではと気になり、調べていった結果、英語のAuthenticity(オーセンティシティー)という言葉にたどり着きました。
Authenticityとは「真性の」「本物の」という意味です。分かりやすい例で言うと、世界遺産を認定する基準の1つがAuthenticityです。この場合、風土に根ざした脈々と受け継がれるものがあり、それがそのままに生かされているというニュアンスが含まれています。心理学では、Sense of Authenticityを「本来感」と訳すこともあります。
Authenticityと似た言葉にIdentity(自己同一性)がありますが、2つの意味は微妙に異なります。 Identityとは「自分は男である・日本人である」というように、自分が何者かという概念との同一性を示し、社会的な認知や意味づけと深く関係しています。
これに対して、Authenticityはあくまで「自分は自分である」という感覚。言語化する以前の、あるいは言語情報に単純化できない感覚であり、一般的に使われる「自分らしさ」の意味としては、こちらの方がより近いでしょう。
じつはこのSense of Authenticity、厳密には定義できません。Content Freeな概念ともいえるかもしれません。「おいしさ」「かっこよさ」といった感覚と同じです。私たちは「おいしいとは何か」を厳密に定義したり、知っていたりするわけではありませんが、おいしいものを食べたときには、それを「おいしい」と感じることができます。本来感もこれと同じで、普段強く意識しているわけではないけれども、何らかのきっかけで、その特定の文脈に応じて、それまでの人生経験のなかで構築されてきたセンサーが働き、「自分らしい・らしくない」という感覚が生じるものだと考えられます。
年齢を重ねるにしたがい自分らしさの要素も社会的に
では、人間はいつ頃から「自分らしさ」の感覚をもつようになるのでしょうか。小学生くらいになると、洋服の好き嫌いなど「好み」が出てきますし、思春期になればおそらく、誰もが「自分らしさ」を意識し始めるのではないかと思います。やや古いデータですが、大学生から70代以上までの男女963名を対象に、どのような要素が本来感と相関関係があるのかを調べたことがあります。測定には、自分に対してどのように感じているかについて7項目の文章を提示し、それを5段階で評価してもらう「本来感尺度」を用いました。この調査によると本来感得点はおおむね年齢と共に上昇していました。20代では恋人や友人と過ごしているときや趣味に没頭しているときなど、個人的に楽しいことと本来感の相関関係が高く、年齢を重ねるにしたがって相関関係の要素が多様かつ社会的になっていく傾向が見られました。
相関する要素の数が最も多くなるのが50代で、 70代になると、ほとんどどんな要素とも相関関係がなくなっていきます。まとめると、若いうちは個人的な生活を充実させることに自分らしさを感じますが、30代・40代ではより社会的なことと自分らしさの相関が深くなり、晩年になるにしたがい、再び個人的な趣味の世界で自分らしさを実感することが多くなっていく、といえるでしょう。
「本来感」は変化する 人間の「成長」と深い関係が
ここでいえるのは、本来感は常に変化しているということ。そして、人間の「成長」と深い関わりがあるのではないかということです。自尊感情のなかでも、他者との比較によってもたらされる優越感などは外発的で、本来感はより内発的です。健康状態が悪いと本来感は低くなりますし、環境にも影響を受けます。本来感、すなわち「自分らしさ」とは決して自分自身で「こうだ」と決められるものではなく、他者との関わり合いのなかで刺激を受けたり、情報を仕入れたりしてだんだんと輪郭が明確になったり、ぼやけたりして変化していくものでもあるのかもしれません。
多くの人は、例えば夫であると同時に父親であり、上司であるなど複数の立場をもちながら生活し、時と場合に応じて求められる役割を演じています。家庭か職場かを問わず、その演じている役割が「自分らしさ」と乖離していると、人間はつらいと感じます。つらい状態が長引くとメンタルに悪影響をおよぼしますが、短期的に乖離することは誰にでも起こり得ますし、それはむしろ、人間的に成長していくチャンスと考えることもできます。
置かれた状況が自分らしさと乖離していることを受け止めることにより、いまだ意識していない自分というものを再認識できる。同時に、「こうしたい・こうありたい」という前向きな気持ちを引き出し、そこを伸ばしていくための重要なきっかけにもなります。
したがって自分らしくあることはとても重要なことですが、ずっと自分らしくある必要があるかといえば、そうではないでしょう。むしろ、「自分らしくない」と感じた場合でも、それを受け入れることにより「自分らしさ」のストライクゾーンを広げ、楽になっていくケースもあるわけです。
重要なのは感情を認めつつ、自分が決めること
働いていれば、自分らしさに反する仕事をやらなければならない場面にも遭遇します。さまざまなつらい感情を抱くでしょう。そんなときに重要なポイントの1つは、「仕事のなかで自分で決める余地を見つけられるかどうか」という点だと思います。
自分で物事を決定できているという感覚は、本来感をもつ上で重要なものの1つです。与えられた仕事をひたすらこなすだけで自分では何も決められない状況に長期間置かれると、人間は本来感が低下します。仕事にせよ家庭生活にせよ、自分で決められる要素、それは例えばとても些細な試行錯誤であってもいいのですが、それがあった上で、それをうまくやれている感覚がもてていること。加えて、人間関係で誰かとつながっていると感じられることも、本来感をもつ上では重要です。
例えば、店頭に腹が立つ客が来て、その客に対応して疲れた部下がいるとします。上司のあなたは、部下が体験したつらい気持ちに共感し、「本人がどう考え、どうやってその難しい状況で試行錯誤しようとしたか」を聞いてあげることができるでしょう。仕事ではいつもうまくいくとは限りません。そんな状況であっても、マイナスの感情に共感し、本人の意思を丁寧にフォローすることで、職場の仲間の本来感を支えてあげることができるかもしれません。
【text :曲沼美恵】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.47 特集1「職場での「自分らしさ」を考える」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
伊藤 正哉(いとう まさや)氏
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
認知行動療法センター 研修指導部研修普及室長
筑波大学第二学群人間学類心理学専攻卒業。筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻発達臨床心理学分野博士課程。ヨーク大学心理学部心理療法研究センター客員研究員、コロンビア大学社会福祉学部客員研究員などを経て、現職。
おすすめコラム
Column
関連する
無料オンラインセミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

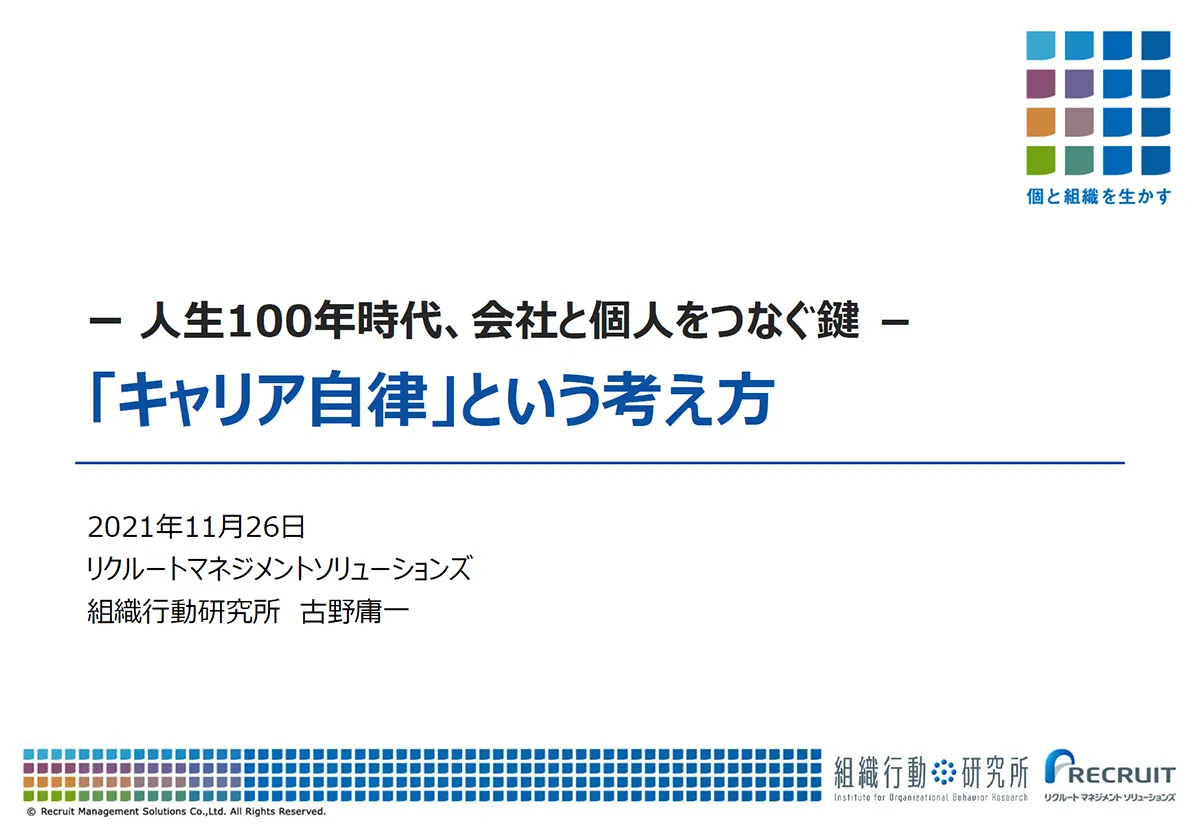
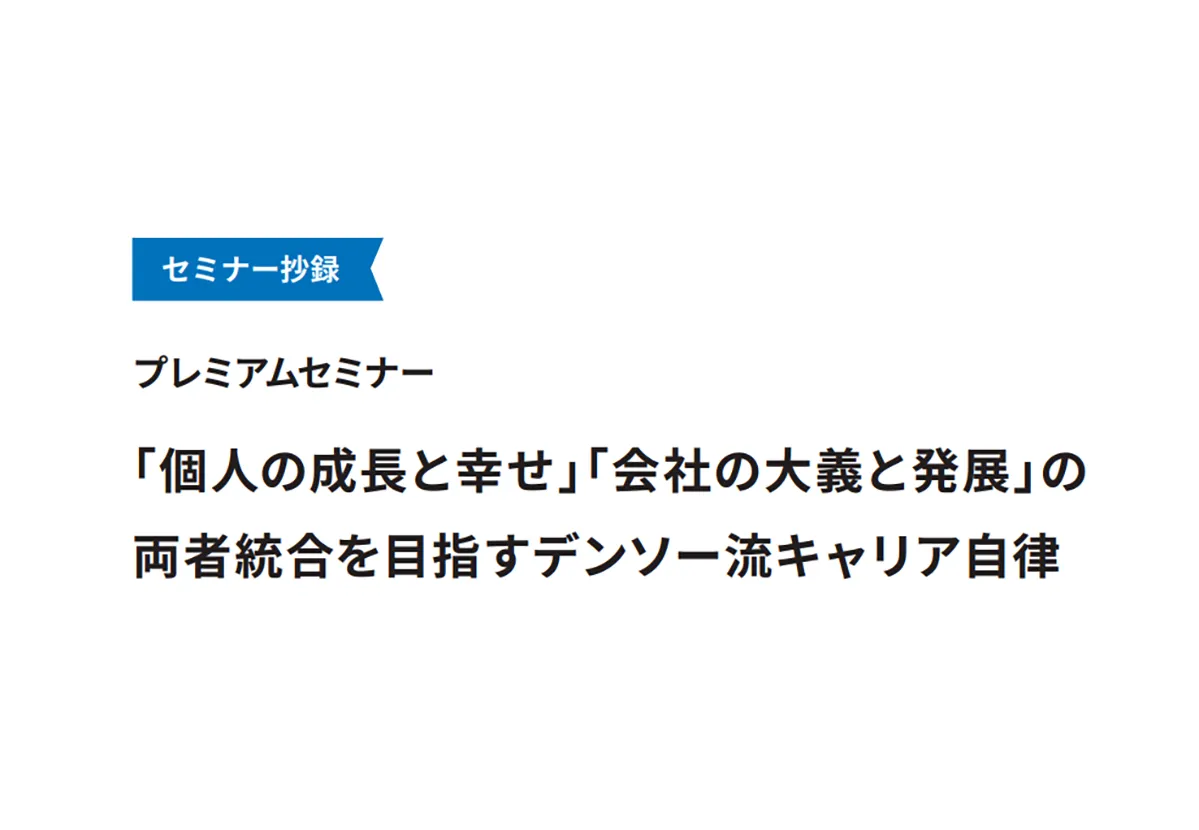









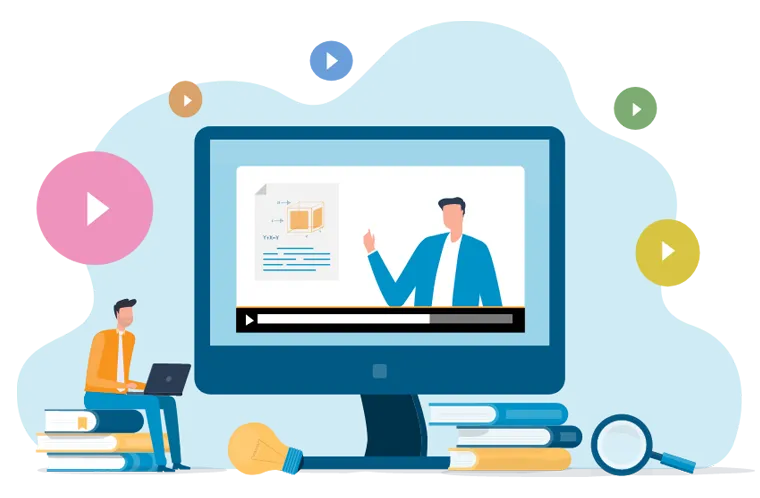 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての