- 公開日:2022/04/11
- 更新日:2024/05/16
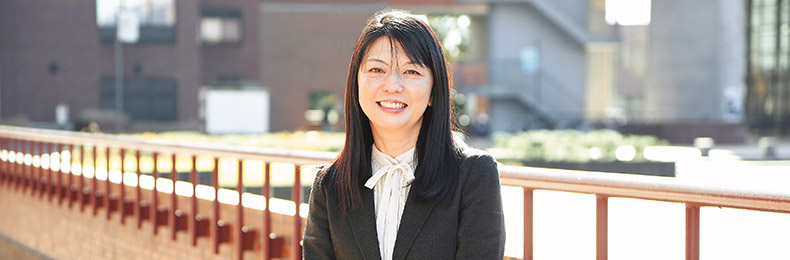
「制御焦点理論」や「制御適合理論」によれば、2 つのタイプによって、適合する目標追求の手段が異なるという。マネジャーや教師は、タイプを見て、部下・生徒への接し方を変えた方がよいのだ。筑波大学准教授の外山美樹氏に、両理論の詳細や職場実践へのアドバイスを伺った。
- 目次
- 個人は促進焦点タイプと防止焦点タイプに分かれる
- モチベーションの高め方が2 つのタイプによって異なる
- 促進焦点にはライバルが必要 防止焦点には仲間が必要
- メンバーのタイプを見極めて支援などの方針を変えてみては
個人は促進焦点タイプと防止焦点タイプに分かれる
制御焦点理論とは、目標追求の観点から、個人を「促進焦点と防止焦点」の2タイプに分ける心理学の理論です(図表1)。
<図表1>制御焦点理論(Higgins, 1997)
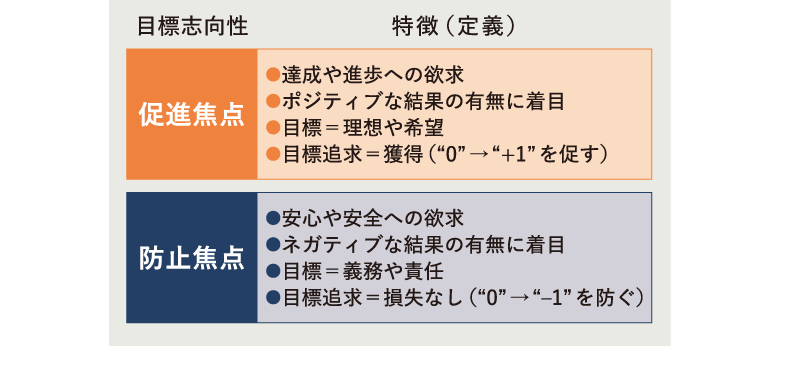
「促進焦点」タイプの人たちは、ポジティブな結果の有無に着目します。目標達成や進歩への欲求が強く、全体的に「0 →+1」を促す傾向があります。例えば、周りから好かれたり、良い成績をとったりすることを求めます。大きな成功を獲得したいのです。理想や希望を追い求めがちで、クリエイティブな課題に取り組むのが得意です。
対する「防止焦点」タイプの人たちは、ネガティブな結果の有無に着目します。安心や安全への欲求が強く、全体的に「0 →-1」を防ぐ傾向があります。例えば、周りから嫌われたり、悪い成績をとったりすることを避けようとします。損失や失敗を嫌がるのです。義務や責任を重視し、緻密な作業に粘り強く取り組むのが得意です。
誰もが、心のうちに両方のタイプをもっており、状況や環境によってタイプの表出の仕方が変わります。例えば、リーダーが「理想を考えてください」と言うだけで、メンバーの促進焦点が少し強まることがあります。また、私の場合は個人で研究しているときには促進焦点の傾向が強いのですが、研究室で他の人と一緒に研究するときには、防止焦点が強まります。場や相手が変われば、誰でもそのような焦点の変化が起こり得ます。
とはいえ、やはり多くの人は、日常的に促進焦点と防止焦点のどちらかに傾いています。そこで制御焦点理論では、ひとまず個人をおおざっぱに2タイプに分けて、その違いをさまざまな観点から研究しているのです。
なお、日本人には、防止焦点タイプの方が多いことが分かっています。これは多くの人が実感していることではないでしょうか。
モチベーションの高め方が2 つのタイプによって異なる
私が力を入れているのが、制御焦点理論を発展させた「制御適合理論」の研究です(図表2)。
<図表2>制御適合理論(Higgins, 2000)
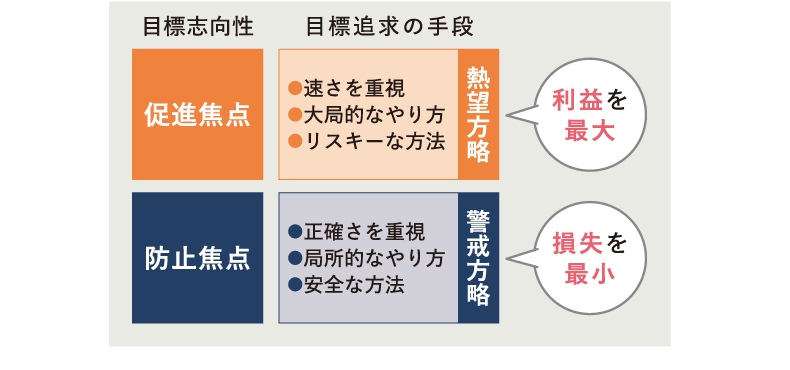
制御適合理論とは、両タイプのモチベーションやパフォーマンスを高めるにはどうしたらよいかを示す理論です。結論を言えば、促進焦点タイプは「熱望方略」をとるとよく、防止焦点タイプは「警戒方略」をとるとよいことが分かっています。そうすると、活動への従事(エンゲージメント)、課題の成績、活動に対する価値が高まるのです。
熱望方略とは、一言で言えば「ハイリスク・ハイリターン戦略」です。利益最大化のために速さを重視し、大局的なやり方を採用し、リスキーな方法を選ぶ作戦です。促進焦点タイプは、大きな目標や理想を達成しようとして、スピーディかつ大局的かつリスキーに行動するときに、大きな力を発揮できるのです。
警戒方略とは、一言で言えば「ローリスク・ローリターン戦略」です。損失を最小化するために正確さを重視し、局所的なやり方を採用し、安全な方法を選ぶ方針です。防止焦点タイプは、損失や失敗を避けるべく、正確かつ局所的かつ安全に行動するときに最も力を発揮するのです。
この制御適合理論の最大のポイントは、「適合(マッチング)」です。どちらが良いか悪いかということではありません。あくまでもタイプに適しているかどうかが大事なのです。促進焦点タイプには熱望方略が合っており、防止焦点タイプには警戒方略が合っている、というのが、この理論の眼目です。この組み合わせを逆にすると、モチベーションやパフォーマンスは下がります。
私が制御適合理論の研究に力を入れたのは、学生たちに同じように接しているのに、ある学生はモチベーションが高まり、別の学生はモチベーションが高まらない、という現象に気づいたことがきっかけでした。学生のタイプによって、接し方を変えなくてはならないのです。では、どうしたら全員のモチベーションやパフォーマンスを高められるのか。それを知るために制御適合理論を深く研究するようになったのです。
全員のモチベーションを高めるためには、各メンバーのタイプに適した方略を選び、実践する必要があります。つまり、相手によって上手に接し方を変えればよいのです。企業にも、私と同じように悩んでいるマネジャーが多くいるのではないでしょうか。参考になれば幸いです。
促進焦点にはライバルが必要 防止焦点には仲間が必要
私たちは制御適合理論の研究をさらに深めています。その結果、いくつかのことが分かりました。
第一に、フィードバックの仕方にも適合があります。促進焦点タイプは、良い働きや成果を褒めるような「ポジティブなフィードバック」を与えるとモチベーションがより高まって、課題が楽しいと感じたり、次の課題を頑張りたいと思ったりするようになります。ところが、防止焦点タイプは、失敗による損失を思い浮かべさせるような「ネガティブなフィードバック」の方が、モチベーションが高まるのです。
第二に、促進焦点の傾向が強い人ほど、切磋琢磨し合う「ライバル」がいる割合が高いことが明らかになりました。ライバルの存在によって気持ちが鼓舞され、パフォーマンスが向上するのです。対する防止焦点タイプは、協力し合う「チームメイト」の存在が重要で、チームメイトがいるとチームに対する義務・責任を果たそうとする気持ちが強まり、モチベーションが高まります。
第三に、タイプによって、適した支援の仕方が異なります。結論を言えば、促進焦点タイプにはできる限りの自由を与えて、自発的な思考を促す「自律性支援」が適合します。一方で、防止焦点タイプには、相手に興味関心をもち、共感的な態度を示す「関係性支援」が適合するのです。
つまり、促進焦点タイプには自律支援のマネジメントを行い、自由に取り組んでもらえばよいのですが、防止焦点タイプはそれではダメなのです。実際、防止焦点タイプは、自律性を求められると息苦しさを感じ、放っておかれると不安を強めるという研究結果があります。
では、どうしたらよいか。例えば、防止焦点タイプがつらそうにしていたら、「何がつらいのですか?」と声をかけたり、「それは大変ですね」と共感したりするコミュニケーションをとると効果があります。そうやって関係性を良くしていくことが、防止焦点タイプの不安を軽減し、モチベーションやパフォーマンスを高めるのです。
メンバーのタイプを見極めて支援などの方針を変えてみては
以上を踏まえて、企業の方々に対して、いくつかアドバイスできることがあります。
1つ目に、マネジャーや人事は、メンバーのタイプを見極めて、支援やフィードバックや配置などの方針を変えてみてはいかがでしょうか。
2つ目に、働く個人が、自分のタイプを見極めることにプラスの効果があるはずです。どんなときに促進焦点や防止焦点が強くなるのかを自己観察することにも、効果があるでしょう。自分のタイプが深く分かれば分かるほど、自分のモチベーションの高め方も明確になるからです。
3つ目に、組織・チームにどちらのタイプが多いとよいかは、組織・チームの機能や性質によって違うでしょう。繰り返しますが、どちらが良いか悪いかではなく、大事なのはマッチングです。一般的に言えば、クリエイティブな業務には促進焦点タイプが適しており、正確さを求められる業務には防止焦点タイプが適しています。
4つ目に、1つの組織やチームに両方のタイプがいた方がよいでしょう。いくらクリエイティビティが求められるチームであっても、全員が促進焦点タイプだと、前のめりになりすぎる可能性があります。そこに防止焦点タイプが1人でもいると、良い意味で歯止めをかける存在になってくれるかもしれません。チームメンバーの組み合わせやバランスを考えることが肝要です。
5つ目に、最近は多くの企業が、社員に「自律」を求めていると聞きますが、先ほど触れたとおり、防止焦点タイプは自律性支援に息苦しさを感じる傾向があります。防止焦点タイプが多い日本では、全社員に一律に自由を与えて自律を求めても、うまくいかない可能性が高いでしょう。
私も学生には自律性が大事だと考えていますが、自律性支援がフィットしない学生にどう接すればよいかはいまだに悩んでいます。とはいえ、防止焦点タイプでも、関係性支援に力を入れて良好な関係を築きながら、少しずつ自律性を養うサポートを行っていけば、自律性を徐々に高めていくことは可能だ、と考えています。日本人に防止焦点タイプが多いことを踏まえると、今後はこうした「防止焦点タイプの自律性養成の工夫や方法」が求められるのではないでしょうか。
【text :米川 青馬 photo : 伊藤 誠】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.65 特集1「仕事と感情」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
外山 美樹(とやま みき)氏
筑波大学人間系准教授
筑波大学大学院博士課程心理学研究科で学んだ後、鹿屋体育大学体育学部講師などを経て、2012 年より現職。『勉強する気はなぜ起こらないのか』(ちくまプリマー新書)、『実力発揮メソッド』(講談社選書メチエ)、『行動を起こし、持続する力』(新曜社)など著書多数。
おすすめコラム
Column
関連する
無料オンラインセミナー
Online seminar
サービス導入を
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・ご相談
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


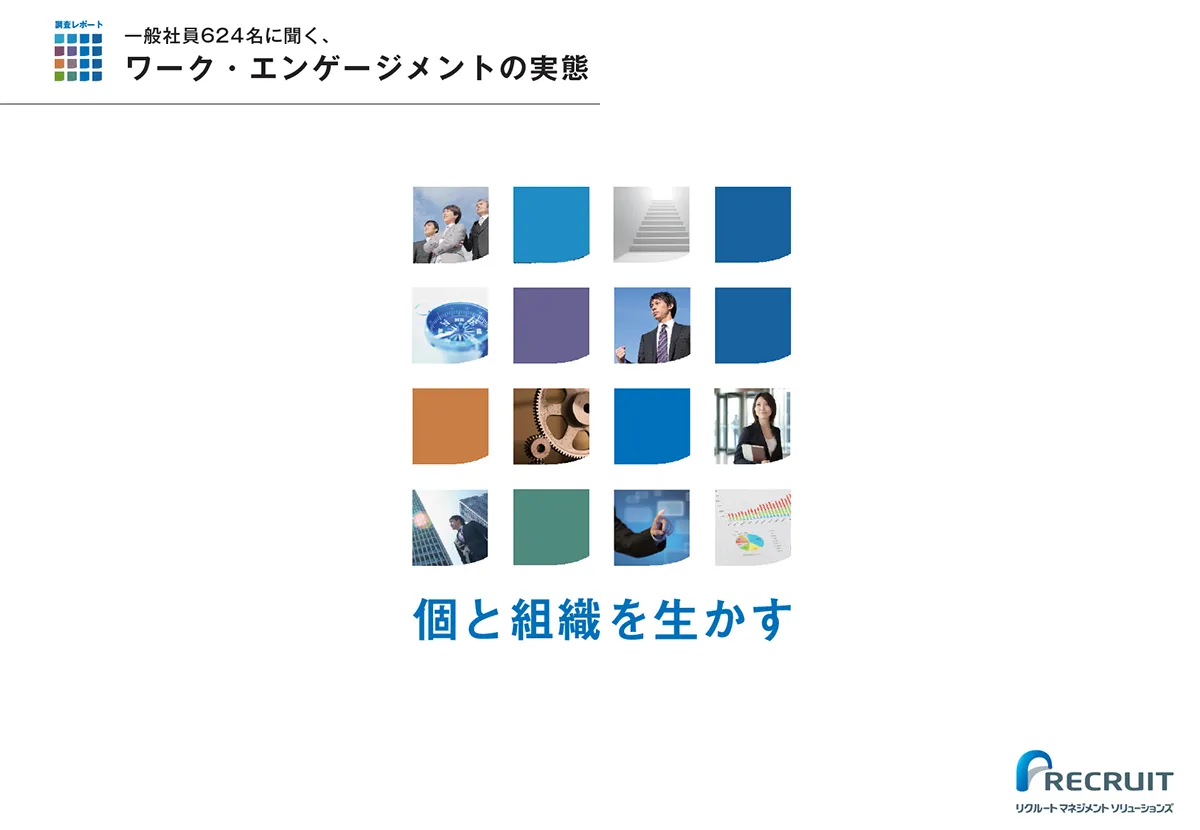
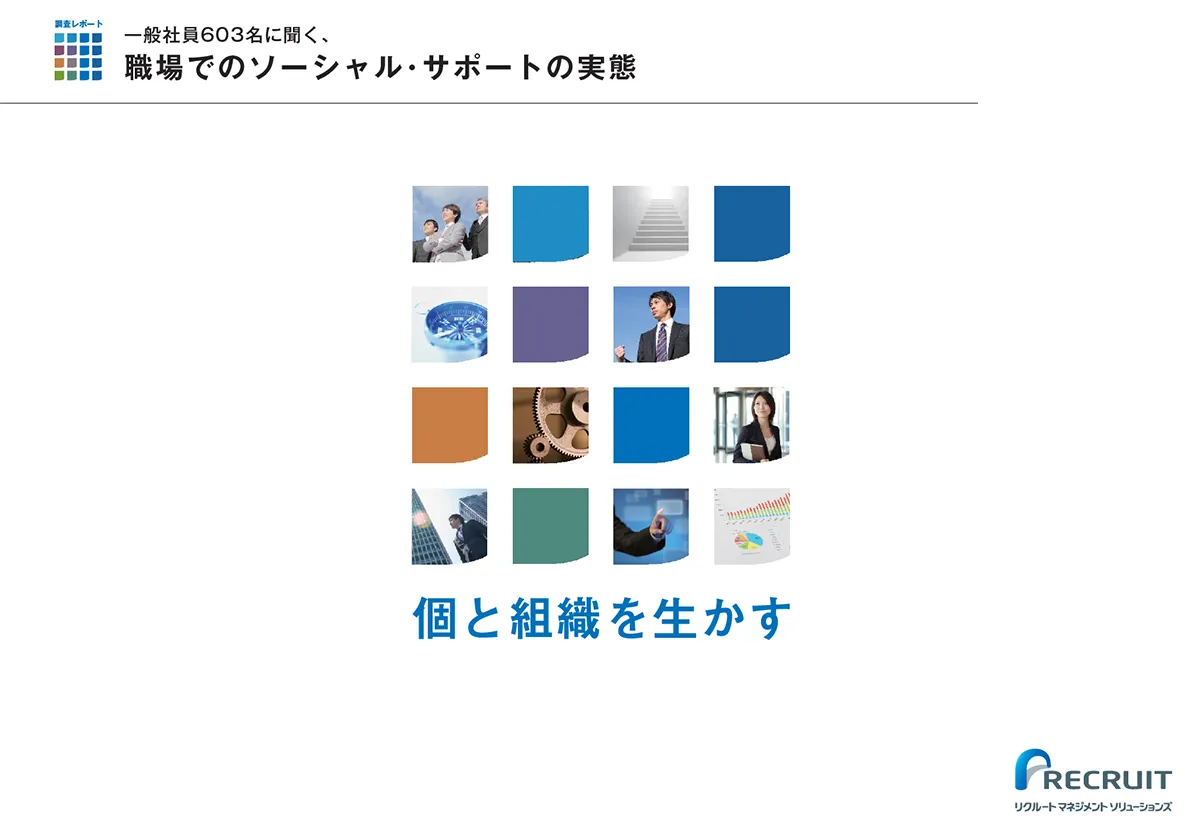
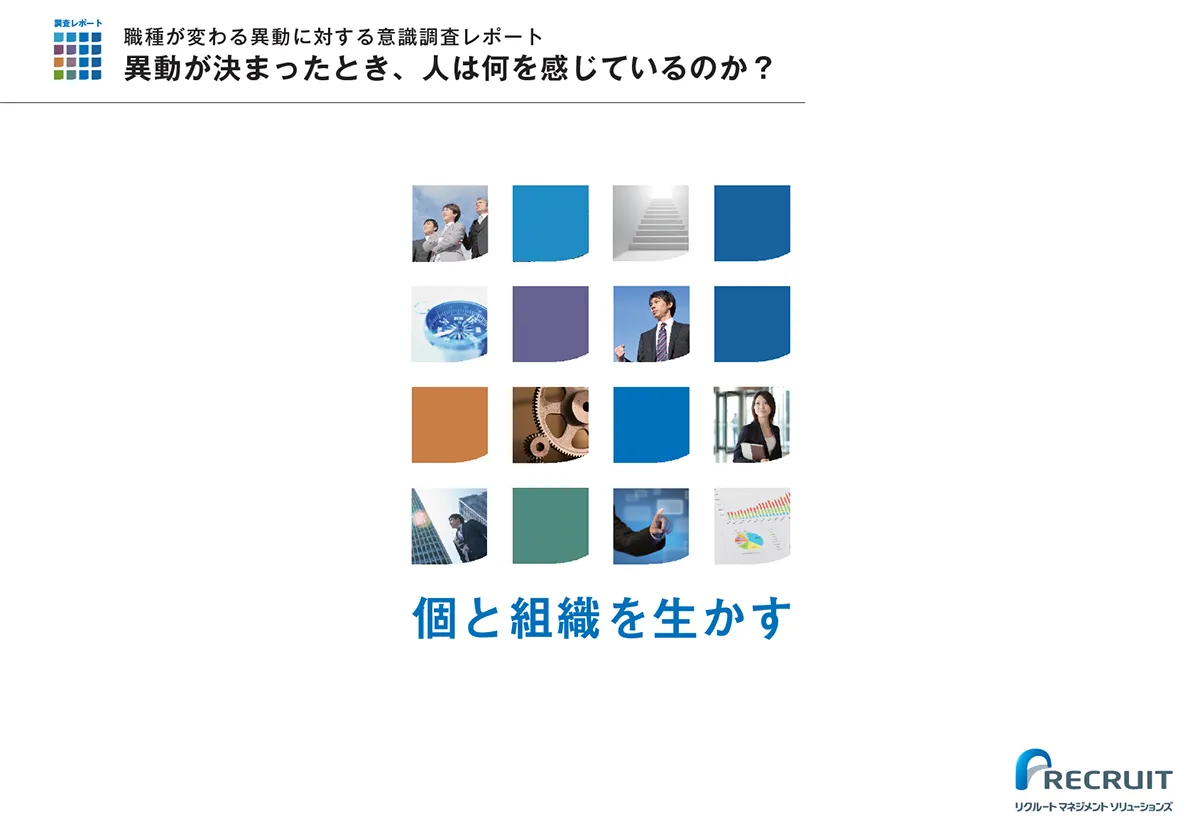









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての